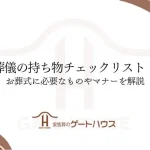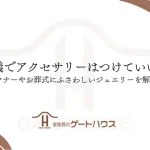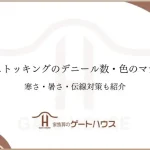葬儀に贈る供花とは?値段の相場・お花の種類・手配の仕方やマナーを紹介
葬儀や通夜で供花を目にすることはありますが、自分で手配したことがある人は少ないのではないでしょうか。
花の種類や相場、札名の書き方など、色々と決まり事があって難しいですよね。
この記事では、葬儀に贈る供花についてと、手配の仕方やマナーを紹介しています。
葬儀に贈る供花とは?何て読む?
葬儀に贈る供花は、日常生活ではあまり接することがない言葉だけに、読み方や意味、数え方の単位がわからない人も多いでしょう。
はじめに、供花の言葉の意味と読み方、数え方の単位を解説します。
供花の意味・読み方
供花の読み方は「きょうか」または「くげ」です。
言葉の意味は、故人や遺族に関係がある人が、弔意を表すために葬儀会場に贈る花のことです。
供花には、贈った人の名前を記した木札を立てて、祭壇の横や受付の辺りに飾られることが多いでしょう。
供花の由来は、釈迦が亡くなられた時に、供養のため宝石で飾られた花を意味する、宝花(ほうけ)が空から降ってきたという逸話からだと言われています。
数え方は「一基・一対」の2つ
供花の数え方の単位は「一基(いっき)」または「一対(いっつい)」のどちらかです。
供花が1つの場合は「一基」を使い、左右対称のセットになった花の場合は「一対」を使います。
葬儀に贈る際は一基の供花がいいのか、一対にするほうがいいのかは、地域によって異なります。
かつては一対で供花を贈るのが一般的でしたが、最近では一基の商品もバラエティが豊富になってきたため、一基の供花を選ぶ人が増えてきました。
葬儀に贈る供花の種類は?|宗教別
葬儀に贈る供花の種類は、一般的に白を基調とした花が使われます。
ただし、宗教によって葬儀で使う花の種類に違いがある場合があるので、注意しましょう。
続いては、葬儀に贈る供花の種類を、宗教別に紹介します。
仏式
【仏教で使われる花】
- 菊
- ユリ
- デンファレ
- カーネーション
仏教の葬儀では、白い菊やユリ、カーネーションなどを中心にした、落ち着いた雰囲気の供花が一般的です。
白色を基調としながらも、淡いピンクや黄色の花を加えたり、故人の好きだった花を取り入れたりすることもあります。
また、高級感のある供花として、デンファレや胡蝶蘭などの蘭の花を用いるスタイルも人気です。
基本的に仏式葬儀では生花が用いられますが、近年では手入れがしやすく長持ちするプリザーブドフラワーや造花を選ぶケースも増えています。
【関連記事】
浄土真宗の葬儀の流れは?お布施の相場や本願寺派・大谷派別に葬式の順序を解説
神式
【神道で使われる花】
- 菊
- ユリ
- カスミソウ
- カーネーション
神道の葬儀で供花に使うのは、穢れのない色とされる白色の菊やユリを中心にした、清楚な雰囲気の花です。
白いカスミソウや白いカーネーションを使ったり、黄色の花をミックスしたりする場合もあるでしょう。
基本的に仏教の葬儀で使われる花と同じですが、神道の場合はデンファレや胡蝶蘭といった華美な花を避ける傾向があります。
かつては榊(サカキ)をお供えしていましたが、現代は榊をお供えするのは喪主だけで、他の人は花を贈るのが一般的になっています。
【関連記事】
神式の葬儀“神葬祭”の流れとは?通夜や告別式のマナー・作法も解説
キリスト式
【キリスト教で使われる花】
- ユリ
- スプレー菊
- 小菊
キリスト教の葬儀では、供物を供える習慣がなく、贈れるのは生花のみとなります。
プリザーブドフラワーはマナー違反となるため、避けましょう。
供花としてよく選ばれるのは、聖母マリアを象徴するユリやスプレー菊、小菊を中心にした白い花です。
また、白いカーネーションや胡蝶蘭を取り入れることもあります。
ただし、仏教や神道の供花に使われるような大輪の菊は用いません。
供花は祭壇や棺の周りに飾ることが一般的ですが、花を飾らない場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
葬儀で供花以外のお花の種類は?
葬儀で使われるお花には、供花の他に「花輪・花環」「枕花」「献花」があります。
それぞれの意味や使うシーンと、供花との違いを理解しておきましょう。
次は、葬儀で使われる供花以外の花を紹介します。
花輪・花環
葬儀に贈る花輪または花環は、白色や寒色を基調とした花を円状に組んで飾る、スタンドタイプの花飾りです。
親戚一同からや、故人とつながりがあった団体の代表から贈られることが多く、供花より大型なので葬儀場の入口など屋外に置かれます。
会場の大きさによっては置けない場合もあるので、手配する際は事前に確認が必要です。
花は生花か造花を使いますが、キリスト教の場合は生花のみ使えるので、造花の花輪・花環はありません。
枕花
枕花とは、ご遺体を安置している場所に贈る、故人の枕元にお供えする花のことです。
亡くなられた直後や訃報を聞いた時から、お通夜が始まるまでの間に、親族や故人と特に深い縁があった人から贈られます。
花の種類は白を中心にした優しい雰囲気の花で、小ぶりの花籠(はなかご)にして贈ることが多いでしょう。
枕花はお通夜の会場にも飾られるため、ご遺体と一緒にお通夜の会場へ運ばれます。
コンパクトで控えめなものが、ふさわしいでしょう。
献花
献花とは、主にキリスト教の葬式で行われる習慣のことです。
参列者が花を一輪ずつ祭壇に置いたり、棺の中に入れたりする行為、またはその花を意味します。
キリスト教の葬儀では、線香をお供えする代わりに、参列者が1人ずつ祭壇や棺に花を捧げてお別れをしますので、仏式葬儀の焼香にあたる習慣といえるでしょう。
花の種類は、必ず白い生花であることとされています。
献花は葬儀会場で用意されるので、参列者が手配する必要はありません。
葬儀に贈る供花で手配してはダメな種類は?
【供花に向いていない花】
| 毒のある花 例:スズラン、彼岸花など | 仏様に毒を盛ることになるため |
| 棘のある花 例:バラ、アザミなど | 棘が「殺生」を思わせるため |
| 香りが強い花 例:バラ、カサブランカなど | 線香や抹香の匂いを消すため |
| ツルがある花 例:朝顔、スイートピーなど | ツルが絡むせいで成仏できないとされるため |
| 花が落ちやすい花 例:椿、サザンカなど | 落ちる花が「首」を連想させるため |
伝統的に、葬儀の供花にはふさわしくないとされる花も存在します。
上の表にある花は古くから縁起が悪いと言われ、葬儀では不向きとされてきた花です。
しかし、近年では葬儀のスタイルが多様化してきたため、供花の種類も変化を遂げています。
かつては「殺生」を思わせるとして、葬儀で避けられてきたバラですが、近年では使われることも増えてきました。
また、無宗教葬においては特に、故人が好きだった花を供花とするケースも増えています。
葬儀に供花を贈る時の値段・相場は?
葬儀に贈る供花の価格帯は、一基12,000円から30,000円程度で、平均的な供花の費用相場は15,000円から20,000円程度が一般的です。
2つをセットにして一対で贈る場合は値段が倍になるため、一基12,000円から20,000円程度の供花を選ばれることが多いです。
供花は他の花と並べるので、周りの花とバランスよくするために、並外れたサイズの供花を手配するのは避けましょう。
また、相場より高額な供花を贈ると、遺族が気を遣うことになります。
故人との関係性や平均的な費用を考慮して、適切な花を選びましょう。
【関連記事】
葬儀のお花代の相場は?封筒の書き方やお金の入れ方・渡すときのマナーを解説
葬儀に供花を贈る時の名前はどう書く?
葬儀に供花を贈る時は、誰から贈られた花か分かるように、札名がつけられます。
供花を頼んだ人の人数や関係性によって札名の書き方が変わりますので、手配する際は業者に正しく伝えましょう。
次は、葬儀に供花を贈る時の、名前の書き方を紹介します。
個人で贈る場合
葬儀の供花を個人で手配する場合は、札名にフルネームを記載します。
親戚が1人ずつ供花を贈るため同じ苗字の人が多くなる場合は、住んでいる地名を書き添えることもあるでしょう。
会社関係の付き合いの人で、個人名にしたい場合は「会社名、部署名、肩書、名前」を書きます。
個人的な付き合いだったため、名前だけでは遺族が誰か分かりにくい場合は、所属団体の名前を加えて、どんな関係の人からの供花か分かるようにするといいでしょう。
夫婦・家族で贈る場合
故人に夫婦でお世話になった場合や、家族ぐるみで親交があった場合など、夫婦や家族で合同で供花を贈ることがあります。
その際、札名には 夫(または世帯主)の名前のみ を書くのが一般的です。
一対の供花を贈る場合も、基本的には両方の札に 夫の名前 を記載します。
ただし、花の数のバランスを考慮し、夫と妻の名前をそれぞれ別の札に書くケースもあります。
また、札名に妻や子どもの名前を入れたい場合は、夫のフルネームの横に、妻と子どもの下の名前のみを並べて書く のが適切な形式です。
親族で贈る場合
葬儀に親族から合同で供花を手配する場合は、個人名を書く場合と「一同」とまとめる場合があります。
個人名を書く場合はフルネームを書くのですが、名前が多くなると書けるのは2名から4名程度までなので、それ以上になる時は「一同」にしましょう。
一同とする場合は「孫一同」「〇〇家親戚一同」といった書き方が一般的です。
親族からの供花をあまり多くすると、会場に入り切らないトラブルになる場合もあるため、事前に葬儀社に相談しましょう。
会社で贈る場合
会社から葬儀場に供花を贈る場合は、会社名のみを書く場合と、代表者名も一緒に書く場合がありますが、代表者名まで書くことが多いようです。
代表者名を書く場合は「会社名・役職名・代表者名」を、略さず正式なものを記載します。
会社全体からでなく、部署から供花を贈る場合は「会社名、部署名一同」と書きましょう。
有志のみで贈る場合には「会社名、部署名、有志一同」としますが、贈るのが数名程度なら会社名、部署名の後に、個人名を並べて書く場合もあります。
連名で贈る場合
同級生や友人グループなど、複数の人が連名で葬儀に供花を贈る場合、4名程度までなら個人名を並べて書きます。
書く順番は、肩書が上の人を一番右にして地位が高い順に書きますが、特にこだわらない場合もあります。
5名以上になる場合は「昭和◯年度◯◯高校卒業生一同」「◯◯サークル一同」のように、まとめて書くのが一般的です。
一部の人から贈る供花の場合は「◯◯有志一同」と書きましょう。
アルファベットが混ざる場合
葬儀に贈る供花に添える札名は、縦書きで書かれますので、アルファベットや他の外国語など、横書きにする文字が入る団体名や個人名は書けません。
アルファベットや、横書きの文字が入る名前で供花を贈る場合は、カタカナ表記にして書く必要があります。
ただし、中国語の漢字表記の企業名や個人名は、縦書きにしても問題ないため、そのままで大丈夫です。
葬儀の供花はどこに頼む?注文の仕方は?
葬儀に供花を贈る手配をする場合、頼む先は「葬儀社」「花屋」「インターネット」のどれかです。
それぞれにメリット、デメリットがありますので、自分のニーズに合うところに頼みましょう。
続いては、葬儀の供花を頼む場所と方法を紹介します。
葬儀社に頼む
葬儀社に供花を頼む場合は、喪家から聞いた葬儀社に連絡をして、名前や日時と供花を贈るのに必要な事項を伝えます。
多くの葬儀社では供花のプランが用意されているので、希望の供花を選ぶといいでしょう。
葬儀社に供花を頼むメリットは、葬儀場の大きさや宗教などの必要な情報を既に把握しているので、安心して任せられる点です。
デメリットはほとんどありませんが、あらかじめプランが決められているので、花の種類や雰囲気は葬儀社次第となります。
花屋に頼む
なじみの花屋がある、葬儀に贈る花の種類やアレンジのデザインを自分で決めたい場合は、花屋に供花の手配を頼む場合もあります。
ただし、葬儀社によっては外部からの供花を受け付けない場合もあるため、事前に確認する必要があるでしょう。
また、葬儀会場の規模や宗教、他の供花とのバランスが分からないので、手配する前に調べる手間がかかります。
急な訃報や休日が重なった場合には、手配が間に合わないケースもあるでしょう。
インターネットで頼む
葬儀に贈る供花を手配できる、インターネットサービスに頼むのも便利です。
インターネットで頼むメリットは、花の種類や価格帯などを自分で確かめてから、頼めることです。
中には葬儀会場の規模や宗教、設置時間などを、葬儀社と相談して進めてくれるところもあります。
そのため、調べたり連絡したりする手間や時間を省ける場合もあるでしょう。
ただし、葬儀会場によっては他社からの供花を受け付けないところもあるので、事前に確認が必要です。
葬儀やお通夜に供花を贈る時のマナーは?
葬儀やお通夜は、時間や場所が決められているため、供花を贈る際は決められたマナーを守る必要があります。
不用意に手配すると、遺族に負担がかかったりトラブルになったりする場合もあるため、気をつけましょう。
最後は、葬儀に供花を贈る際、気をつけたいマナーや注意点を紹介します。
遺族に確認する
葬儀に供花を贈る手配をする前に、まず遺族に花を贈っても差し支えないか確認しましょう。
葬儀会場のスペースや葬式の種類などの都合で、供花を断る場合もあります。
勝手に贈ると相手の迷惑になるのを避けるため、遺族の確認をとってから手配しましょう。
また、親戚など複数の人が合同で贈る場合は、個人で勝手に手配すると贈る人が重複する恐れがあります。
「誰と誰からは◯◯一同として贈る」など、参列者で打ち合わせをして手配しましょう。
当日中に届くようにする
一般的に供花は、通夜に間に合うように、正しい日時を指定して贈る必要があります。
供花は通夜が始まる3時間前、遅くても通夜の当日中に必ず届くように手配しましょう。
早すぎるのも遅すぎるのもNGです。
早すぎた場合は、葬儀までの間に生花が傷む恐れがあり、まるで亡くなるのを待っていたかのような、悪い印象を与えることもあります。
遅すぎる場合は、設置の時間に間に合わないからと、葬儀社に受け取りを拒否される可能性もあります。
葬儀社に確認する
インターネットや花屋で供花を手配して、葬儀社に頼まない場合でも、まず葬儀社に確認するのを忘れないようにしましょう。
葬儀社によっては、外部からの供花を受け付けない場合があります。
贈ったお花を無駄にしないためにも、手配するのは確認してからにしましょう。
また、葬儀にあった供花を準備するために、宗教や葬儀会場の規模、できれば他の供花の色やサイズなども質問して、ふさわしい花を手配する参考にしましょう。
故人とはどんな関係だったか伝える
葬儀や通夜の供花を葬儀社に頼む場合は、故人とはどんな関係だったかを、葬儀社に伝えておきましょう。
供花は、祭壇に近い場所から送り主が故人と親しかった関係順で並べられます。
故人の近親者、または親しい友人、仕事関係の付き合いの人かによって、花を置く位置が変わるので、故人との関係性をきちんと伝えておきましょう。
遺族に、送り主や故人との関係性、弔意が伝わるように、供花に添えるメッセージを依頼できる場合もあります。
葬儀に贈る供花は故人への弔意を表す花。手配する花の種類に注意
葬儀に贈る供花は、故人への弔意を表し葬儀会場を飾るという、大切な役割があります。
花の種類に気を付けたり、値段の相場や札名の書き方等のマナーを守ったりして、トラブルが起きないように、供花の手配をしましょう。
私たち家族葬のゲートハウスは、和歌山市で家族葬を最も多く手掛けている葬儀社です。
供花の選び方に関するご相談はもちろん、葬儀に関するさまざまなお悩みにも、経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施工件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。
監修者