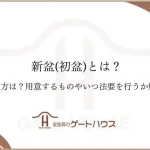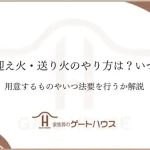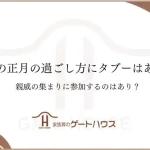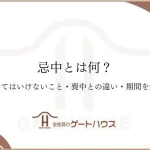四十九日が終わった報告(挨拶状)の例文|ハガキや親戚に堅苦しくない書き方を紹介
四十九日の法要を終えると、お世話になった人に報告するのがマナーです。
しかし「初めてでどう書けばいいのか分からない」「気をつけるべきポイントは?」など、書き方に悩む人も多いでしょう。
この記事では、四十九日が終わった報告をする挨拶状について、書き方や例文などを紹介します。
四十九日が終わった報告(挨拶状)の意味は?
四十九日は、故人が亡くなってから49日目に行われます。
忌明けを迎えるタイミングで、一つの区切りとなる大切な仏教儀式です。
まずは、四十九日が終わった報告をする意味について解説します。
忌明けを迎えたことの報告
四十九日が終わった報告は、つまり忌明けを迎えたことの報告となります。
故人が亡くなってから49日を過ぎるまでは「忌中」と呼ばれ、昔は外出も控えて静かに過ごすべき期間とされてきました。
現代において外出を制限するのは現実的ではありませんが、派手な遊びやお祝いごとは慎むのが一般的です。
挨拶状では無事に法要を終えたことを伝え、忌明けを報告してください。
葬儀に参列してくれたことへのお礼
四十九日が終わった報告をする挨拶状には、葬儀に参列してもらったことに対するお礼状としての意味もあります。
いつまでに送らなければいけないという決まりはありませんが、四十九日が終わったら、できるだけ早めに報告しましょう。
遅くなると失礼な印象を与えたり、相手を心配させてしまったりするかもしれません。
無事に法要が終わったことを報告し、改めてお礼を伝えましょう。
四十九日が終わった報告(挨拶状)の書き方は?
四十九日が終わった報告では、葬儀に参列してもらったお礼や香典返しの案内、直接お礼をしに出向かないことへのお詫びなどを書きます。
ここでは、挨拶状の書き方について詳しくチェックしてみましょう。
参列・香典に対するお礼
挨拶状を書くときは、最初に「拝啓」や「謹啓」などの頭語を用いましょう。
そして、葬儀に参列してもらったことや、香典をいただいたことに対するお礼を伝えます。
その際に、故人の名前の後ろに「儀」をつけて明記し、誰の葬儀であったのかを書いてください。
「儀」は「〇〇について」という意味です。
香典を受け取ったお礼は「ご厚志を賜りまして」と書くのが一般的です。
挨拶文では感謝の気持ちを伝えるため、丁寧な表現を心がけましょう。
四十九日法要が終わった旨の報告
挨拶状では、四十九日法要が無事に終わったことを報告します。
「お陰をもちまして四十九日を相営みました」など、滞りなく法要を終えた旨を記しましょう。
四十九日は、他にも「七七日」「満中陰」といった呼び方がありますが、どれを使っても大丈夫です。
スペースに余裕があれば、生前にお世話になったお礼などを書いても良いでしょう。
香典返しに関する案内
香典返しを送る場合は、一言案内を記入しましょう。
「香典返しをお送りします」ではなく「供養のお印に心ばかりの品をお届けいたします」などの文言をいれて、お返しの品について触れてください。
近年では、葬儀の当日に香典返しを用意しておくケースも増えています。
すでに香典返しを渡していて、お礼状だけを送る場合は、香典返しに関する案内は不要です。
お礼を直接言えないことへのお詫び
本来であれば直接お礼に伺うべきところを挨拶状で済ませるため、一言お詫びの言葉を入れましょう。
「早速拝趨の上お礼申し上げるべきところ 失礼ながら書中をもってお礼のご挨拶とさせていただきます」など、文面でお礼を述べることに対するお詫びを書いてください。
最後は「敬具」や「謹言」といった結語を使って締めくくり、相手に敬意を示しましょう。
このとき、頭語が「拝啓」であれば「敬具」を、「謹啓」であれば「謹白」を用います。
差出人名
四十九日が終わった報告の最後には、挨拶状を作成した日付と住所、差出人の名前を記入してください。
一般的に差出人は喪主の氏名になりますが、連名だったり、人数が多いときは「親族一同」と記載したりするケースもあります。
そのほかの場合は、故人との続柄を記載するようにしましょう。
四十九日が終わった報告(挨拶状)の例文|ハガキ・手紙
四十九日の報告をする際に「失礼な表現にならないか不安」「具体的な文章の内容が知りたい」という人も多いかもしれません。
挨拶状の書き方に悩んだときは、例文を参考にしてみてはいかがでしょうか?
ここでは、ハガキ・手紙で四十九日が終わった報告をするときの文例を紹介します。
戒名の記載・香典返しがある場合
拝啓
先般 亡母〇〇(故人の名前) 儀 永眠の際には
ご厚志を賜りまして厚くお礼申し上げます
お陰をもちまして
〇〇(戒名)
四十九日法要を滞りなく相営みました
つきましては供養の印に 心ばかりの品をお届けいたしますので
何卒ご受納くださいますようお願い申し上げます
早速拝趨の上 お礼申し上げるべきところではございますが
略儀ながら書中にて 謹んでお礼のご挨拶を申し上げます
敬具
令和〇年〇月〇日
〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇(差出人の住所)
〇〇(差出人の氏名)
戒名の記載・香典返しがない場合
謹啓
先般 亡母〇〇(故人の名前) 儀 永眠の際には
ご厚志を賜りまして誠にありがたくお礼申し上げます
お陰をもちまして 七七日忌の法要を滞りなく相営みました
早速拝趨の上 お礼申し上げるべきところ
失礼ながら書中をもって お礼のご挨拶とさせていただきます
謹白
令和〇年〇月〇日
〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇(差出人の住所)
〇〇(差出人の氏名)
戒名の記載のみの場合
拝啓
先般 亡母〇〇(故人の名前) 儀 永眠の際には
ご多用中にもかかわらず ご丁重なるご弔詞をいただき
心より厚くお礼申し上げます
お陰をもちまして
〇〇(戒名)
満中陰の法要を滞りなく相営みました
早速拝趨の上 お礼申し上げるのが本意ではございますが
略儀ながら書中にて お礼かたがたご挨拶を申し上げます
敬具
令和〇年〇月〇日
〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇(差出人の住所)
〇〇(差出人の氏名)
香典返しのみの場合
謹啓
先般 亡母〇〇(故人の名前) 儀 永眠の際には
ご鄭重なるご厚志を賜り厚くお礼申し上げます
お陰をもちまして このたび 四十九日法要を滞りなく相営みました
ささやかではございますが 供養の御印として
心ばかりの品をお贈りさせていただきます
本来であれば拝趨の上 お礼申し上げるところではございますが
略儀ながら書中をもちまして お礼のご挨拶を申し上げます
謹白
令和〇年〇月〇日
〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇(差出人の住所)
〇〇(差出人の氏名)
四十九日が終わった報告(挨拶状)の親戚に堅苦しくない例文
親しい間柄の親戚に送る挨拶状は、かしこまりすぎなくても失礼にはあたりません。
ただし、フォーマルなものであることは変わりないので、最低限のマナーは守り、砕けすぎないように気をつけましょう。
今後も変わらない付き合いを願う言葉を入れれば、気持ちが伝わる文章になるはずですよ。
拝啓
この度の葬儀では ご多用中にもかかわらず
遠方から駆けつけていただき ありがとうございました
亡母〇〇(故人の名前)も 喜んでいたことと思います
おかげさまで 四十九日の法要も滞りなく営みました
また お香典もありがとうございました
あたたかなお気遣いに 心から感謝しています
今後も変わらぬ関係で また会える日を楽しみにしています
このたびは本当にありがとうございました
敬具
令和〇年〇月〇日
〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇(差出人の住所)
〇〇(差出人の氏名)
四十九日が終わった報告(挨拶状)の例文|メール・LINE
自分(遺族側)の親しい間柄の友人に対して、とりあえずお礼を伝えたいという場合は、メールやLINEで四十九日が終わった報告をしても良いでしょう。
故人の友人や目上の人、年配者などには、メールではなく挨拶状を送るのが相応しいとされています。
メールやLINEを用いる際は、相手との関係性をふまえることが大切です。
件名:四十九日のご報告
この度 母〇〇(故人の名前)の葬儀では ご厚意を賜り心から感謝を申し上げます
お陰をもちまして 四十九日の法要を滞りなく相営みました
略儀ながら 取り急ぎメールにてお礼のご挨拶を申し上げます
令和〇年〇月〇日
〇〇(差出人の氏名)
四十九日が終わった報告(挨拶状)の注意点は?
挨拶状を書くときは、いくつか気をつけておきたいポイントがあります。
失礼な印象を与えないためにも、基本的なルールやマナーは心得ておきましょう。
それでは、四十九日が終わった報告をする際の注意点を紹介します。
縦書きにする
四十九日が終わった報告をする際は、一般的に縦書きです。
カジュアルな挨拶状は横書きにすることもありますが、四十九日などの弔事ではマナーが重んじられるため、従来通り縦書きにしましょう。
また挨拶状を手書きする場合は、横書きにすると、かえって不自然な印象を与えかねません。
特別な理由がない限り、縦書きにするのが無難でしょう。
句読点は使わない
四十九日が終わった報告をする挨拶状では、句読点を使わないようにしてください。
これは、かつて書状を作成する際に用いられた毛筆では「、」や「。」の句読点を使わないという、昔ながらの慣わしが由来しているとされています。
また句読点は文章の流れを区切るため、縁が切れることを連想させるという説も。
文章が読みにくいと感じる場合は、文と文の間にスペースを入れると良いでしょう。
忌み言葉は使わない
四十九日が終わった報告をする際には、忌み言葉を使わないように気をつけましょう。
「死(四)」や「苦(九)」などの忌み言葉や、「くれぐれも」「重ね重ね」などの不幸が繰り返されることを連想させる重ね言葉などは用いないのがマナーです。
ただし「四十九日」や日付に用いることには問題ありません。
また「ご多忙」には「亡」が入っているため、「ご多用」などの表現を使うのが好ましいとされています。
【忌み言葉】
| 重ね言葉 | くれぐれも、重ね重ね 色々、段々、引き続き …など |
| 忌み言葉 | 苦しい、終わる 辛い、消える …など |
| 生死を連想する言葉 | 死ぬ、急死 生きていたころ …など |
直筆で書く
四十九日が終わった報告をするときは、直筆が望ましいでしょう。
最近では印刷で作成されることも増えましたが、本来は毛筆で書くのが正式なマナーです。
直筆で丁寧に書かれた挨拶状からは、感謝の気持ちや温かみが伝わります。
時間に余裕があれば、濃墨の筆ペンや毛筆などで手書きしてみてはいかがでしょうか。
四十九日が終わった報告(挨拶状)はどう送る?
四十九日の法要を終えたら、封書やハガキなどで挨拶状を送りましょう。
なにかと慌ただしいかもしれませんが、できる限り早めに送るのが大人のマナーです。
最後に、四十九日が終わった報告の送り方について解説します。
手紙(封書)で送る場合
手紙(封書)で送る場合は、縦書きの便箋を使いましょう。
奉書紙という和紙を用いれば、さらに丁寧な印象になります。
四十九日を過ぎれば濃墨を使って構いませんが、地域によっては薄墨を使うこともあるため、慣習に従ってください。
封筒の宛名は、相手も自分も通常の黒色を用いて書きましょう。
また、二重の封筒だと不幸が重なることを意味してしまうため、一重の封筒を使うのもマナーです。
ハガキで送る場合
封書ではなく、ハガキで四十九日が終わった報告をする方法もあります。
手紙の方がより丁寧な印象を与えますが、すでに香典返しを済ませていたり、あまり仰々しくするのは気がひけたりする場合は、ハガキの挨拶状でかまいません。
手紙と比べて書くスペースが少ないものの、短時間で書けるので、早めに送りたいときにも向いています。
詳細な報告をするのは難しいため、できるだけ簡潔に要点をまとめて書きましょう。
法要から一か月以内に送る
四十九日が終わった報告は、法要から一か月以内に送りましょう。
挨拶状は無事に法要を執り行ったことや、葬儀の参列者に対するお礼などを伝えるものです。
そのため法要を終えたら、できるだけ早めに報告することが大切です。
ただし、年末年始やお祝い事のタイミングと重なるときは、時期をずらして送るようにしましょう。
四十九日が終わった報告(挨拶状)の例文を参考にして、マナー違反がないように
四十九日が終わった報告では、葬儀への参列やお香典のお礼なども伝えるため、失礼がないようなるべく早めに送りましょう。
書き方やマナーについて不安がある場合は、挨拶例を参考にして書くのがおすすめです。
最近は印刷で作成するケースが増えていますが、特にお世話になった人や目上の人には、心を込めて直筆で書いてみてはいかがでしょうか?
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。
監修者