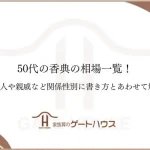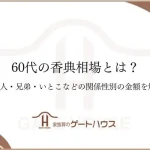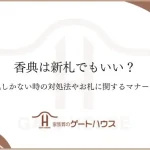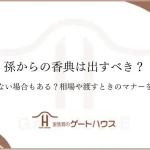家族葬|香典返しに添えるお礼状の例文6つ&挨拶状の基本マナー
家族葬後の香典返しには、心のこもったお礼状が欠かせません。
故人を偲び、参列者への感謝を伝える大切なメッセージです。
本記事では、家族葬ならではの香典返しのお礼状の書き方や例文、基本的なマナーをわかりやすく解説します。
参列の有無に合わせた例文も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
家族葬|香典返しのお礼状の基本
家族葬後の香典返しにお礼状を添えることは、故人を思い出してくださった方々への感謝の気持ちを伝えるための重要なステップです。
故人を偲ぶ大切なメッセージにもなります。
ここでは、お礼状についての基本的な考え方をご紹介します。
お礼状・挨拶状の役割
お礼状や挨拶状は、香典返しに添える手紙で、葬儀に参列してくれたことや香典をいただいたことへの感謝の気持ちを伝えるためのものです。
また、葬儀が無事に終わったことを報告する役割もあります。
特に家族葬の場合は、参列者が限られるため、参列できなかった方々への配慮として、お礼状の役割はより重要です。
お礼状と挨拶状の違い
お礼状と挨拶状は、似ているようで微妙に役割が異なります。
お礼状は、香典や参列の感謝を伝えるものであり、香典をいただいたすべての方へ送ります。
四十九日の法要の報告と、返礼品にも触れることが一般的です。
一方、挨拶状では葬儀全般に対する感謝とともに、その後の家族の状況報告なども行います。
故人と親しかった方たちへ、故人のエピソードも交えつつ、個別に感謝の気持ちを伝えましょう。
最も格式が高いのは「奉書」式
お礼状の中でも、最も格式の高いものに「奉書」式があります。
奉書は古来より用いられ、正式な文書形態として位置づけられ、特に目上の方や正式な場においては、この形式が用いられることが多いです。
奉書紙と呼ばれる和紙に、筆ペンや毛筆で手書きで文章を記し、巻物のように折り畳んで縦型封筒に収めるといった特徴があります。
ただし、近年は印刷で代用される場合も増えています。
家族葬|香典返しに添えるお礼状の例文【参列した方向け】
家族葬に参列してくださった方への香典返しのお礼状は、感謝の気持ちをしっかりと伝えることが大切です。
会葬や香典へのお礼のあいさつ、法要が無事に済んだことの報告、生前のお礼、挨拶とお礼が手紙であることのお詫び、香典返しの品物を贈ることを入れると良いでしょう。
葬儀の形式によって使う言葉や表現が異なりますので、ここでは仏教式、キリスト教式、神式それぞれの例文をご紹介します。
仏教式
用語としては「四十九日法要」「戒名」「追善」を使用してください。
特に、故人の戒名がある場合は、お礼状の文中に含めましょう。
戒名とは、仏の世界における故人の名前とされ、仏式の葬儀の際にはつけられることが一般的です。
送る時期は、四十九日法要後が一般的です。
謹啓
ご尊家益々御清祥のこととお喜び申し上げます
先般 亡父 ○○(俗名)葬儀に際しましては
ご多用の中にもかかわらずご会葬を賜り
かつご丁重なるご厚志を賜り誠に有難く厚く御礼申し上げます
おかげをもちまして この度○○(戒名)四十九日法要を滞りなく営むことができました
つきましては追善の微意を表し心ばかりの品をお届けいたしますので
ご受納くださいますようお願い申し上げます
謹白
令和○年○月○日
喪主 ○○○○○
キリスト教式
カトリックは「昇天」「追悼ミサ」、プロテスタントは「召天」「召天記念礼拝」という用語を使用しましょう。
送る時期は、カトリックでは30日目の追悼ミサ後、プロテスタントでは1か月後の召天記念礼拝後となります。
謹啓
時下ますますご清祥のことと申し上げます
過日亡き母○○昇天(召天)の際は
ご多用の中にもかかわらずご会葬を賜り
かつご丁重なるご献花を賜り誠に有難く厚く御礼申し上げます
この度 三十日目の追悼ミサ(召天記念礼拝)を滞りなく済ませました
つきましては 心ばかりの品をお贈りしましたので
御受納くださいますようお願い申しあげます
謹白
令和○年○月○日
○○(喪主名)
神式
用語としては「帰幽」「五十日祭」「御玉串料」を使用し、「供養」「冥福」は避けましょう。
また、神式では香典返しではなく「偲草(しのびぐさ)」と呼ばれます。
偲草には、故人を偲ぶ気持ちを品物に代えてお渡しするという意味が込められています。
贈る時期は、五十日祭後が一般的です。
謹啓
先般 故父 ○○儀 帰幽に際しましては
ご多用の中にもかかわらずご会葬を賜り
かつご丁重なる御玉串料を賜り誠に有難く厚く御礼申し上げます
おかげをもちまして○月○日に五十日祭を滞り無く相営みました
つきましては偲草のしるしまでに心ばかりの品をお届け致しましたので
何卒ご受納くださいますようお願い申し上げます
謹白
令和○年○月○日
喪主 ○○○○○
家族葬|香典返しに添えるお礼状の例文【参列していない方向け】
家族葬は少人数で執り行われるため、香典だけを頂いて参列していない方も多くいらっしゃいます。
参列していない方向けのお礼状では、会葬のお礼挨拶は不要です。
謝意とともに、葬儀の報告を盛り込むと、より丁寧な印象になりますので参考にしてください。
今回は仏教式の例文を紹介しますが、ほかの宗教の場合でも要点は変わりません。
仏教式
謹啓
この度 亡き(続柄)(戒名)儀 永眠に際しましては
ご丁寧なるご芳志を賜り 誠に有り難く厚く御礼申し上げます
本来であればご会葬いただき直接御礼申し上げるべきところ
家族葬のため叶わず 心苦しく存じております
おかげをもちまして 四十九日法要を滞りなく営み
忌明けを迎えることができました
つきましては 供養のしるしまでに心ばかりの品をお送りいたしました
何卒ご受納くださいますようお願い申し上げます
略儀ながら書中をもちまして 御礼申し上げます
謹白
令和○年○月○日
喪主 ○○○○○
親族一同
家族葬|香典返しに添えるお礼状の例文【参列にかかわらず使える】
参列の有無にかかわらず使える汎用性の高い例文もあります。
状況に応じて少し文言を調整するだけで、様々な場面で活用できるので、特に多くの方にお礼状を送る必要がある場合に便利です。
仏教式
謹啓
このたび 亡き(続柄)(戒名)儀 永眠に際しましては
ご丁寧なるご芳志を賜り 誠に有り難く厚く御礼申し上げます
生前には故人がひとかたならぬご厚情を賜りましたこと
改めて深く感謝申し上げます
おかげをもちまして 四十九日法要を滞りなく営み
忌明けを迎えることができました
つきましては 供養のしるしまでに心ばかりの品をお送りいたしました
何卒ご受納くださいますようお願い申し上げます
略儀ながら書中をもちまして 御礼申し上げます
謹白
令和○年○月○日
喪主 ○○○○○
親族一同
無宗教:親戚・友人向けの例文
近年増加している無宗教の葬儀や、特定の宗教色を薄めたいケースでは、宗教的な表現を避けた例文が適しています。
特に、親しい親戚や友人に対しては、より自然な言葉で心情を伝えることもできるのでおすすめです。
親しい友人間では、メールでやり取りをすることもあるかと思いますが、できれば手書き、もしくは印刷でお礼状を送りましょう。
拝啓
この度は(続柄)(故人名)の葬儀に際し
温かいお心遣いをいただき 心より感謝申し上げます
生前には(故人名)が大変お世話になり
皆様との思い出が私たちの力となっております
おかげさまで四十九日を無事迎えることができました
つきましては 感謝の気持ちを込め
ささやかな品をお送りいたしました
これからも(故人名)との絆を大切にしながら
前を向いて歩んでまいります
今後とも変わらぬお付き合いのほど
何卒よろしくお願い申し上げます
敬具
令和○年○月○日
○○○○○(差出人名)
香典返しに添えるお礼状のマナー
香典返しに添えるお礼状には、一般的な手紙とは異なる独特のマナーがあるため、難しく感じる方もいるかもしれません。
しかし、いくつかの注意点に気をつけることで、故人への敬意と受け取る方への配慮を示すことができます。
ここでは、お礼状を書く際に知っておくべき5つの基本マナーについて詳しく解説しますので、参考にしてください。
忌み言葉を避ける
お礼状を書く際は、忌み言葉を使わないようにすることが一般的なマナーです。
忌み言葉とは、不幸や死を連想させる言葉であり、葬儀に関連する場合には特に避けられます。
例えば、「重ねて御礼申し上げます」という表現が、一般的な手紙ではよく使われますよね。
しかし、弔事のお礼状では「重ね」という言葉が「不幸の重なり」を連想させるため、「あらためて御礼申し上げます」などと言い換えるのが適切です。
以下に、代表的な忌み言葉の例を挙げていますので、ご参照ください。
【忌み言葉】
| 重ね言葉 | くれぐれも、重ね重ね 色々、段々、引き続き …など |
| 忌み言葉 | 苦しい、終わる 辛い、消える …など |
| 生死を連想する言葉 | 死ぬ、急死 生きていたころ …など |
句読点は使わない
香典返しのお礼状では、基本的に句読点「、」「。」を用いないことが良しとされています。
句読点を使わない理由は諸説ありますが、文を切る=縁を切る、区切るといった言葉を連想させ、縁起が悪いと考えられているためです。
代わりに、スペースや改行を使って、読みやすい文章になるように工夫しましょう。
宗教ごとの禁句に注意する
お礼状を書く際には、宗教に合わせた言葉選びも大切です。
宗教によっては特定の言葉が禁句とされることがありますので、注意しましょう。
例えば、仏教式では「天国」という言葉は使いませんし、キリスト教式では「供養」という言葉は使いません。
普段何気なく使用している言葉が、特定の宗教では使用しないということもあるため、お礼状を書く際には例文のテンプレートを参考にし、禁句が入っていないか確認してください。
頭語・結語を用いる
お礼状には、頭語と結語を正しく使用することが基本的なマナーとして求められます。
頭語とは、手紙の冒頭に書く言葉のことで、結語とは、手紙の末尾に書く言葉のことです。文章全体を形式的に整え、丁寧さを表現できます。
迷った場合は、頭語に「拝啓」、結語に「敬具」を使用し、より格式を重んじる場合は頭語に「謹啓」、結語に「謹白」を使用すると良いでしょう。
墨の濃淡は地域のしきたりに習う
お礼状を書く際には、墨の濃淡にも気を配りましょう。
一般的に、通夜や葬儀、告別式の際には薄墨を使用するのがマナーとされています。
これは「涙で墨が薄くなった」「急いで駆けつけたため濃い墨が準備できなかった」という意味を表すためです。
お礼状の際には、濃い墨を使用するのが一般的ですが、地域によって異なりますので、事前にお相手の地域のしきたりを確認しておきましょう。
【関連記事】
香典袋は薄墨でないとだめ?書き方やいつまで濃墨を使わないべきかを解説
香典返しに添えるお礼状は例文を見ながら作るのがおすすめ。家族葬では参列の有無にも気をつけよう
香典返しのお礼状は、故人への敬意と感謝の気持ちを伝える大切なものです。
例文を参考にしながら、故人や家族の思いを込めた文面を作成しましょう。
特に家族葬の場合は、参列された方と参列されなかった方で文面を使い分けることがポイントです。
宗教や地域のしきたりにも配慮しつつ、忌み言葉を避け、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
故人を偲ぶ気持ちと、感謝の思いが伝わるお礼状を作成する参考にしていただくと幸いです。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。
監修者