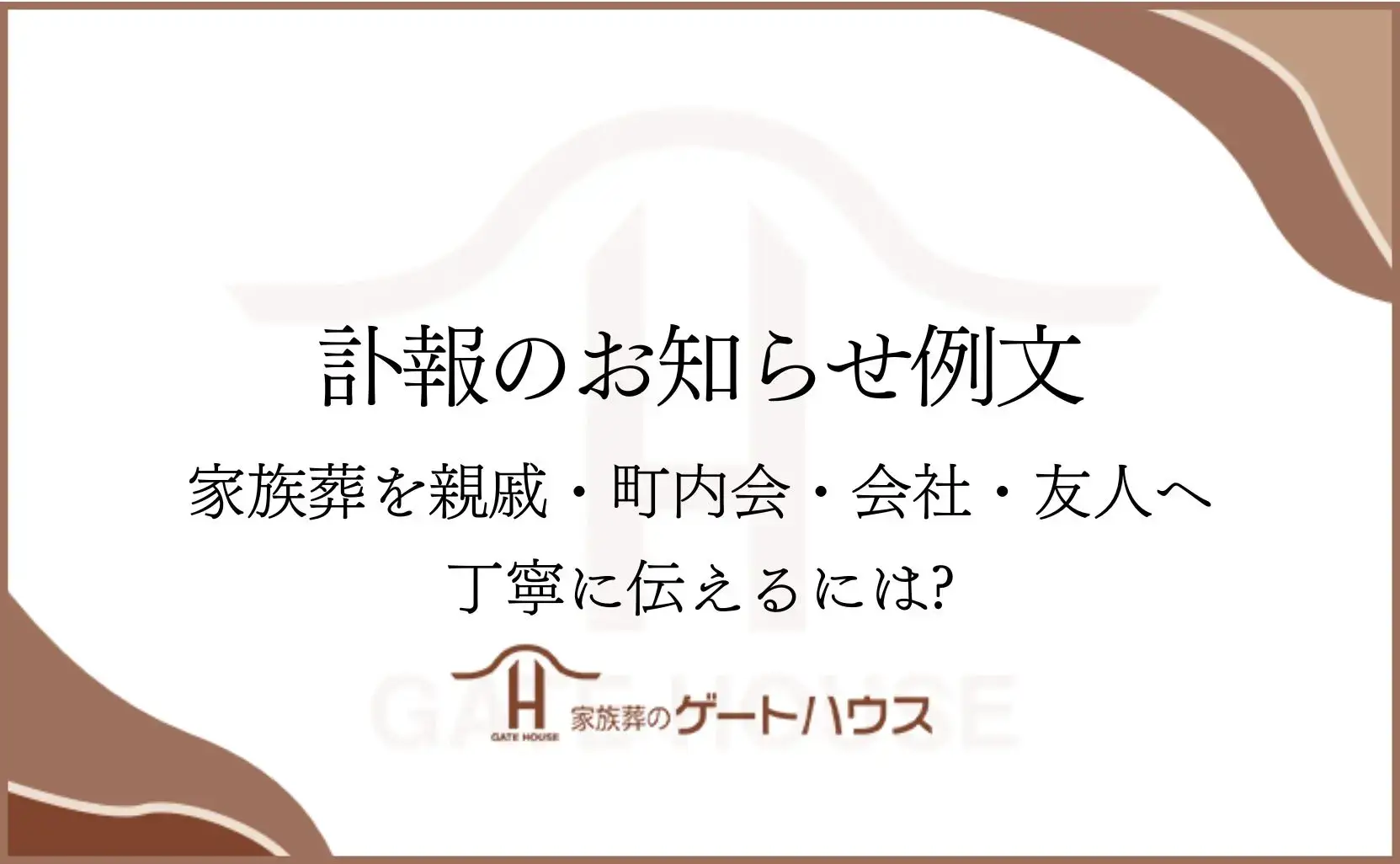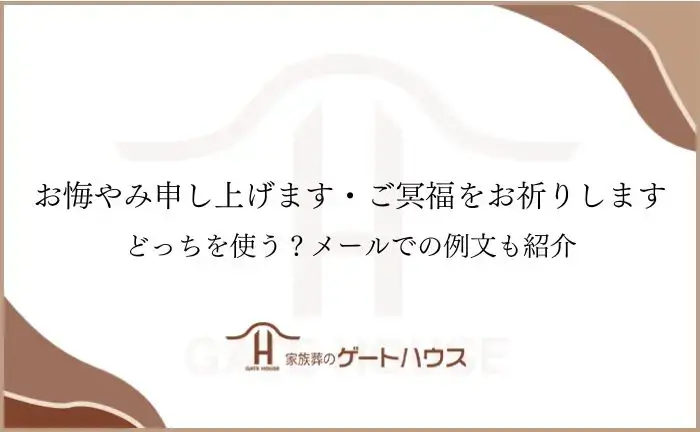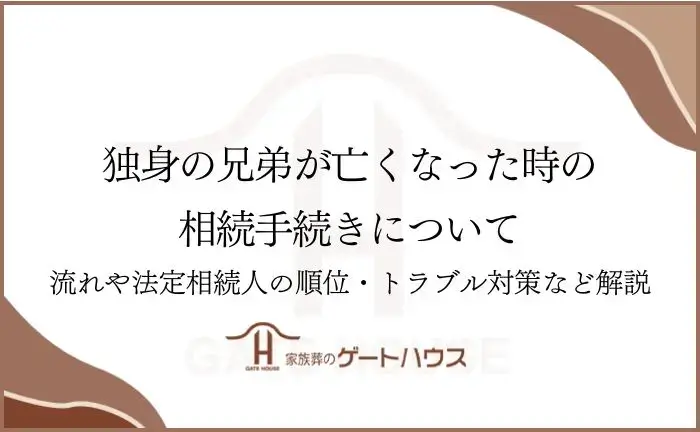お盆のお供え料理の定番メニューは?置き方・期間・基本マナーも解説
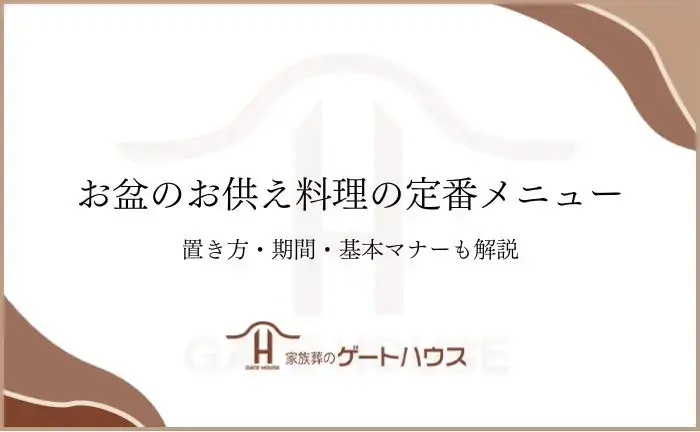
お盆には、ご先祖様や故人の霊を迎えるために、特別なお供え料理を用意します。
お盆のお供え料理とは、どのようなものなのでしょうか。
この記事では、お盆に定番とされるお供えの食品や精進料理について解説するとともに、お供えの置き方や期間など、基本的なマナーについても紹介します。
お盆のお供え料理の定番5選
お盆のお供え料理は、地方や宗派、家庭の習慣によって異なりますが、簡単に準備できるそうめんは一般的なお供え物のひとつです。
はじめに、お盆のお供え料理で定番になっている食べ物を紹介します。
そうめん
夏に人気のそうめんは、全国的にお盆のお供え料理として定番になっている食品です。
お盆にそうめんをお供えする意味は「細く長く幸せが続きますようにという願掛け」「ご先祖様が帰る際、精霊馬にお土産をくくる縄にするため」など諸説あります。
大抵は、茹でずに束のままでお皿や真菰(まこも)に乗せてお供えしますが、地域によって異なる場合もあるため、地元の慣習に従いましょう。
赤飯
北海道や東北地方などでは、お盆に赤飯を炊いてお供えします。
小豆の赤い色は邪気を払う力があり、小豆自体にも魔除けの効果があるといわれているためです。
かつては貴重な食料だった小豆に、五穀豊穣の願いやご先祖様への感謝を込めて、もち米と一緒に炊いた赤飯をお盆料理にするようになったのかもしれません。
天ぷら
東北地方や信州などの地域では、お盆に天ぷらをお供えするところもあります。
お盆のお供えは仏教の教えに則っているため、肉や魚介類を使わずにキノコやナス、れんこんなど野菜だけの「精進揚げ」をお供えします。
天ぷらの衣は水と小麦粉だけで作り、卵は殺生となるため使用しません。
団子
京都や西日本の地域では、お盆に白い団子をお供えする習慣があります。
お供えの団子は2種類あり、ご先祖様をお迎えする時の「迎え団子」と、ご先祖様を見送る際にお供えする「送り団子」です。
「迎え団子」は、旅の疲れを癒すという意味から、みたらし団子やあんこを使用した団子にすることもありますが、「送り団子」は必ず白い団子をお供えするのが決まりです。
おはぎ・ぼたもち
おはぎやぼたもちは、通常は春や秋のお彼岸にお供えしますが、お盆でもお供えすることもあります。
理由は赤飯と同じで、小豆の赤い色が邪気を払うとされているからです。
おはぎとぼたもちの違いは、以下のとおりです。
- ぼたもち:牡丹の花のように丸く、春のお彼岸にお供えする
- おはぎ:萩の花のように細長く、秋のお彼岸にお供えする
ただし、区別の仕方は地域によって異なります。
お盆にお供えする精進料理の基本
精進料理とは仏教の教えに従い、殺生につながる動物性の素材を使わないで、野菜や穀物、キノコ、海藻など植物性の素材のみを使って調理する料理です。
伝統を重んじる家庭では、お盆に精進料理をお供えする場合もあります。
続いては、お盆にお供えする精進料理の基本について解説しましょう。
食事の基本「一汁三菜」
日本人の基本的な食事となっている「一汁三菜」は、ご飯と汁物と3種類のおかずのことで、精進料理では略式の御膳(ごぜん)とされています。
おかずは焼き物、煮物、和え物などが用意されますが、漬物を添える場合はおかずにカウントしません。
汁物の出汁やおかずの調味には、鰹節など動物性の食材は使用せず、昆布や干し椎茸で味付けします。
ご飯は、ご先祖様がお腹いっぱい食べられるように、山盛りにして丸く盛り付けます。
より正式な精進料理「一汁五菜」
「一汁五菜」は、「一汁三菜」より正式な精進料理で、野菜や豆類など植物性のおかずがさらに2品増えます。
ご飯や汁物、漬物に関しては「一汁三菜」と同じです。
ただし宗派の戒律によって、正式なお供え膳の内容が異なる場合もあるため、菩提寺で自分の宗派では何が正式か確認するといいでしょう。
おかずは「煮しめ」「きんぴらごぼう」など
一般的な精進料理のおかずは、主菜が野菜の煮しめやがんもどき、高野豆腐の煮物などです。
副菜には、野菜の白和えや胡麻和え、きんぴらごぼうなどが添えられることが多いです。
本格的な精進料理を、毎回すべて調理するのは大変なので、フリーズドライや冷凍のお供え料理を利用する場合もあります。
【施餓鬼で用意するものについてはこちらをご確認ください】
施餓鬼(せがき)とは?行かないのはあり?意味・お布施の書き方マナー・宗派別の違いを解説
お盆のお供え料理の意味・目的
お盆に特別な食べ物をお供えするのには、どのような意味があるのでしょうか。
お供え料理の意味を理解した上でお供えしたほうが、より心のこもった供養ができるでしょう。
次は、お盆のお供え料理の意味や目的を紹介します。
お供え料理はご先祖への感謝のしるし
お盆のお供え料理には、ご先祖様に対する日頃の感謝のしるしという意味があります。
ご先祖様に対して、いつも見守っていてくださることへの感謝を示すため、特別なお供え料理でおもてなしします。
また、あの世から戻られた霊のため、長旅をねぎらう意味もあるでしょう。
特に新盆の場合は、故人が初めてあの世から家族のもとへ帰る機会なので、久しぶりに自宅でくつろいでもらうためという意味もあります。
地域や宗派で異なる風習にも注意
お盆のお供え料理に、厳密な決まりはありません。
精進料理をお供えする場合もあれば、そうめんなどを簡易的にお供えとする場合もありますし、故人の好物をお供えしてもいいのです。
ただし地域によって、独特な料理をお供えにする風習がありますし、宗派によっても異なります。
お盆のお供え料理は、自分の家の宗教や住んでいる地域の風習を参考にして、用意するといいでしょう。
お盆のお供え料理はいつ・どう置く?
お盆や法事などの特別な日は、御霊供膳(おりょうぐぜん)と呼ばれる5つの器と箸をセットにした、小型の御膳でお供えすることが多いでしょう。
5つの器とは、ご飯の親椀、汁物の汁椀、煮物の平椀、和え物などを盛り付ける壺椀、香の物の高坏です。
置き方は左手前がご飯で右が汁物なのは共通ですが、宗派によっておかずの器の配置が異なります。
たとえば曹洞宗・臨済宗では、左上が平椀(煮物)で右上が高杯(香の物)、中央が壺椀(和え物)となりますが、他の宗派では違う置き方をします。
続いては、いつからいつまでの期間置くのかやお供えする時間帯など、お盆のお供え料理のタイミングについて解説しましょう。
お供え期間は迎え盆から送り盆まで
お盆のお供えをする期間は、基本的に迎え盆から送り盆までの4日間とされています。
具体的には8月がお盆の地域では、8月13日から8月16日までです。
ただし、お盆が7月の地方もありますし、お盆の期間は地域によって異なる場合もあるため、自分の住んでいる地域の習慣に従いましょう。
送り盆が済んだ後は、通常のお供えに戻します。
供える場所は仏壇・精霊棚(盆棚)
お盆のお供え物は、仏壇の前に置く精霊棚(盆棚)と呼ばれる棚に載せて、お供えします。
御膳の向きは、ご先祖様が食べやすいように、仏壇のほうに正面を向けるようにします。
仏壇側から見て左が箸の先になるように置き、器の蓋をとってお供えしましょう。
お供えする時は手を合わせて、心の中で「どうぞ召し上がってください」と話しかけます。
時間帯は13日の晩から1日3食
お盆のお供えをする時間帯は、13日の夕食から1日3食お供えするのが一般的です。
かつては修行僧が朝昼の1日2食だったことから、お供えも朝昼で1日2食としていましたが、近ごろは家ごとの食習慣や地域の習慣に合わせるようになってきました。
3食のお供えが難しい場合は朝だけにしたり、親戚が集まる日だけにしたりすることもあるようです。
供えた料理は早めに下げて家族でいただく
お供えした料理は、熱いものが冷めた頃などのタイミングで、早めに下げて家族でいただきます。
家族が食事する前にお供えをして、お参りしてすぐに下げて、お下がりをいただいてもいいでしょう。
ご先祖様には、お供えした私たちの気持ちや食べ物の湯気がご馳走となりますし、家族がお供えをいただくのも供養の1つなので、長時間置いておく必要はありません。
お供えのマナー・避けたほうがいいもの
お盆のお供えに厳密な決まりはありませんが、避けたほうがいいとされている食材もあります。
お供えのマナーをきちんと守りたい場合は、次の2つの食材は避けたほうがいいかもしれません。
肉・魚など動物性食材「三厭(さんえん)」はNG
お盆のお供え料理や精進料理で禁じられているのは「三厭」と呼ばれる、動物性の食材です。
仏教の教えに不殺生戒(ふせっしょうかい)と呼ばれる、生き物の命を奪ってはいけないという戒律があるため、肉や魚を食べるのは禁じられています。
三厭とは獣、魚、鳥のことなので、お供えの食材には肉や魚、卵を避けたほうがいいでしょう。
匂いの強い野菜「五葷(ごくん)」は避ける
匂いが強く辛味のある野菜は「五葷」と呼ばれ、仏教では避けられる食材です。
お盆のお供え料理や精進料理には、植物性でも避けたほうがいいでしょう。
「五葷」とされる野菜は、ニンニクやニラ、ネギ、玉ねぎ、アサツキ、ラッキョウです。
仏教において、これらの野菜は煩悩を刺激したり、内臓に負担をかけたりするとされており、お盆のお供え料理や精進料理での使用は好ましくありません。
【関連記事】
仏壇にお供えしてはいけないものは?NGな花やお酒・ビールはダメなのかも解説
お盆のお供え料理は“心を形にする”大切な習慣
お盆のお供え料理は、そうめんや団子などをお供えするのが一般的ですが、精進料理をお供えすることもあります。
お盆に特別なお供えをするのは、ご先祖様に日頃の感謝の気持ちを表すという意味があり、あの世からの長旅をねぎらう目的もあるでしょう。
お供えは13日の夜から4日間で、お供えした料理はすぐに下げて、家族でいただきます。
お盆のお供えは、ご先祖様や故人への気持ちを形にする、大切な習慣なので、心をこめてお供えしましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要