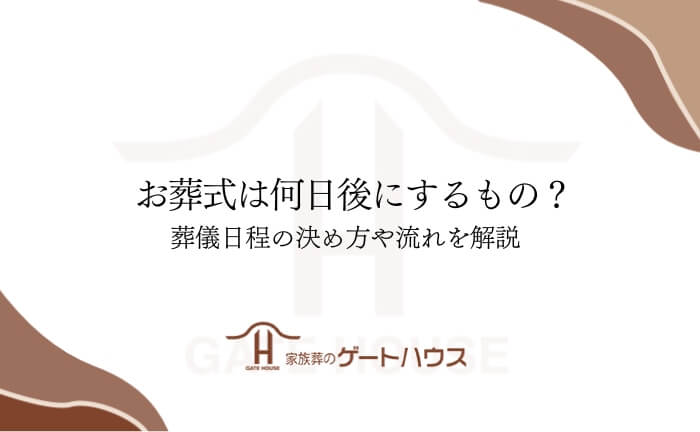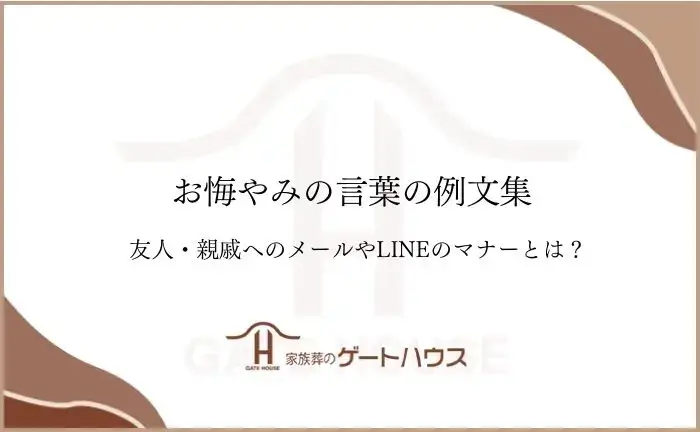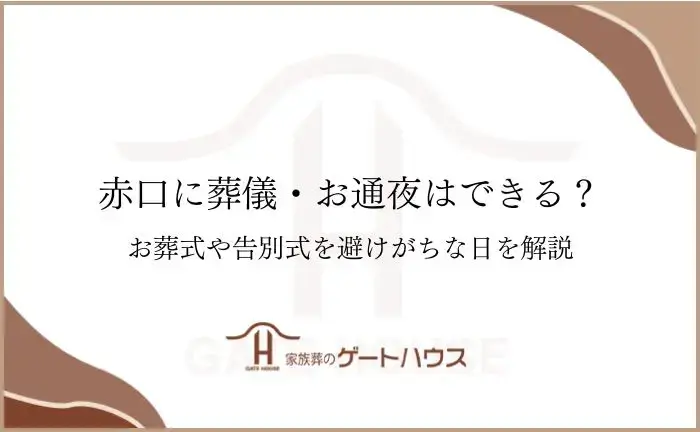新盆(初盆)の提灯は誰が買う?飾り方・選び方やいつから飾るのかを解説
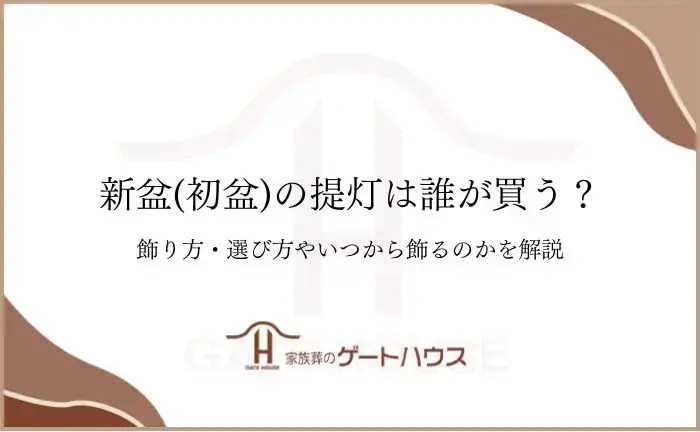
大切な人が亡くなってから、初めて迎えるお盆。
提灯を用意することは知っていても、誰が主体となって用意すべきか悩む人は少なくありません。
この記事では、提灯は誰が買うべきなのか、または提灯はどのように飾るのかなど、新盆の迎え方について解説します。
新盆の提灯は誰が買う?
提灯は新盆(初盆)を迎えるにあたって欠かせない飾りのひとつです。
基本的に新盆のときにだけ飾る白提灯と、翌年以降のお盆にも飾る絵柄入り提灯の2種類を用意します。
ただし、誰がどの提灯を用意するかについては、地域の慣習や家庭によって異なる場合があります。
まずは、それぞれの提灯を誰が購入するのかについて確認しましょう。
白提灯(白紋天)は故人のご家族が購入
新盆の年にだけ飾る白無地の提灯「白提灯(白紋天)」は、故人の家族が購入するのが一般的です。
喪主を務める故人の配偶者や子どもなどの近親者が購入するケースが多いですが、厳密な決まりがあるわけではありません。
絵柄入り提灯は特に決まりはない
新盆に限らず、毎年お盆で飾られる「絵柄入りの提灯」については、誰が購入するかについて細かな決まりはありません。
絵柄入り提灯には、故人への感謝の気持ちや「親族も故人の帰りを待っています」という意味が込められています。
そのため、兄弟や親戚など故人と近しい親族が準備することが多いです。
また近年では、住宅事情や飾るスペースの都合により、実際の提灯ではなく「提灯代(盆提灯代)」として金銭を包むケースも増えつつあります。
新盆に提灯は必要?飾る意味は?
提灯は単なる飾りではなく、故人様をお迎えするにあたって大切な役割を果たしています。
この項目では、初盆に提灯が必要な理由や、初盆用に白提灯を用意する理由について解説します。
初盆に提灯が必要な理由
「お盆」はご先祖様を自宅にお迎えし、感謝の気持ちを伝えたり、供養をしたりする行事です。
そのため、まずはご先祖様をお迎えする必要があります。
そこで必要になるのが「提灯」です。
提灯の灯りは、ご先祖様がお帰りになる際の道しるべになるとされており、特に初盆は故人にとって初めての里帰りにあたるため、迷わず辿り着けるように初盆用の提灯を飾ります。
初盆では白提灯も用意する
白提灯は、その名の通り白無地のシンプルな提灯です。
新盆で初めて自宅に帰る故人に、遺族は「迷わず帰ってこれるように」と思いを込めて飾ります。
白は仏教において「清浄無垢」を表す色とされており、白提灯を飾ることには、「清らかな気持ちで故人を迎える」という意味も込められています。
また、新盆用の白提灯は、初盆参りに来る訪問者への目印にもなるため、準備するのが一般的です。
新盆の提灯の選び方
盆提灯は、吊るすタイプと床や仏壇の前などに置いて使うタイプの2種類があります。
これまでは、吊るすタイプが一般的でしたが、近年は仏壇の前に設置できる小さな「置き提灯」を選ぶ家庭も増えています。
新盆に限らず、どちらを選んでもマナー上の問題はなく、明確な決まりもありません。
そのため、部屋の広さや予算、設置場所に応じて無理のない形で選ぶことが大切です。
なお、家紋入りの提灯を用意する場合は、製作に時間がかかることがあるため、早めに注文するようにしましょう。
新盆の提灯の飾り方
続いてはお盆提灯の飾り方について、一般的な提灯と白提灯に分け、それぞれ詳しく解説します。
新盆の白提灯の飾り方
白提灯の飾り方は、「吊るすタイプ」と「置き型タイプ」で異なります。
ご自宅の環境に合わせて、以下を参考に飾りましょう。
- 吊るすタイプの白提灯
玄関先や軒先に吊るすのが一般的です。
集合住宅の場合はベランダに飾っても良いでしょう。
また、防犯上の関係で外に飾るのが難しい場合は、部屋の窓際や仏壇の近くに吊るしても問題ありません。 - 置き型タイプの白提灯
小さなサイズであれば仏壇の前や盆棚に飾りましょう。
仏壇の前や盆棚に飾るのが難しいサイズの場合は、仏壇や盆棚の近くに飾ってください。
一般的な提灯の飾り方
盆提灯は、精霊棚(盆棚)や仏壇の前に一対、もしくは二対と並べて飾るのが一般的です。
飾る位置としては、盆棚の左右にバランスよく対で並べると整って見えます。
もし複数の提灯を飾る場合は、奥に家紋入り提灯、手前に絵柄入り提灯を配置し、扇形に広がるように並べると美しく見栄えよく仕上がります。
新盆の提灯はいつからいつまで飾る?
新盆用の提灯は、お盆の期間だけ飾るわけではありません。
地域によっても異なりますが、お盆期間前から飾るケースが多いです。
続いては、新盆の提灯はいつからいつまで飾るべきなのか、提灯に灯りをつける時間帯と合わせて解説します。
旧盆・新盆の提灯を飾る時期
| 旧盆の場合 | 8月1日~8月10日ごろ |
| 新盆の場合 | 7月1日~7月10日ごろ |
お盆の期間は、旧盆なら8月13日から16日で、新盆なら7月13日から16日です。
提灯は盆の入りである13日よりも少し前に飾るのが一般的であるため、1〜10日の間に飾ると良いでしょう。
基本的には13日までに飾れば問題ありませんが「ご先祖様に少しでも早く帰ってきてほしい」という思いを込め、月の初旬から提灯を飾り始める家庭も多いです。
旧盆と新盆では飾る時期が1ヶ月ほど異なるため、ご自分の地域が旧盆・新盆のどちらを採用しているか事前に調べてから提灯を飾りましょう。
【関連記事】
新盆(初盆)とは?やり方は?用意するものやいつ法要を行うか解説
盂蘭盆会(うらぼんえ)とは?意味やお盆・施餓鬼会との違いを解説
提灯を灯す時間帯
一般的に、提灯を灯す時間帯は日が暮れる18時ごろから深夜までの間です。
最近はLEDライトを用いた提灯も増えていますが、従来の火を灯すタイプの提灯を使用する家庭も多く、火を管理するためにも遺族の就寝に合わせて灯りを消します。
また、地域によっては「午後◯時〜午後◯時まで」と決められていることもあるため、事前に確認すると良いでしょう。
新盆の提灯は浄土真宗でも必要?
天台宗や日蓮宗など、仏教の流れを汲む宗派は基本的に新盆用の白提灯を飾ります。
しかし、浄土真宗では「故人の魂は仏様になる」と考えるため、お盆にご先祖様の霊をお迎えする風習はありません。
そのため、提灯などの盆飾り全般は用意しないのが一般的です。
ただ、一部地域の浄土真宗では、悪霊を祓う力があるとされる籠目構造を持つ多面体の火袋を用いた「切子灯籠」と呼ばれる灯籠を飾ることがあります。
【関連記事】
浄土真宗の初盆の迎え方は?お布施相場やお供え物・仏壇の飾り方など解説
新盆の提灯に関するよくある質問
新盆を迎える方にとっては、提灯の準備や扱い方に戸惑うことも少なくありません。
「提灯は使い回しても良いのか?」「処分はどうすればいいのか?」など、悩まれる方も多いでしょう。
そこでこの項目では、新盆の提灯に関してよく寄せられる疑問や不安にお答えします。
初盆の提灯は使い回しても良い?
白提灯は、故人一人につき一つ用意するのが一般的です。
使い回しはせず、初盆が終わったら処分します。
一方、絵柄入りの盆提灯は使い回しても問題はありません。
新盆やお盆が終わったら丁寧に片付け、来年もご先祖様をお迎えできるように保管しておきましょう。
ただ、絵柄入りの提灯であっても、葬儀で使用したものを使い回すのは失礼にあたります。
必ずお盆用の絵柄入り提灯を用意し、毎年お盆に合わせて飾るようにしてください。
白提灯の処分方法は?
白提灯の処分方法は、菩提寺や地域でお世話になっているお寺に納め、お焚き上げしてもらうのが一般的です。
仏具店に処分をお願いすることもできます。
また、ご先祖様を再び送り出すための「送り火」をする際に、白提灯を一緒に燃やすこともあります。
いずれも難しい場合は白提灯を塩で清めてから紙に包み、地域のゴミ出しのルールに従って処分しましょう。
新盆の提灯に関するマナーを知り、故人を偲ぶ準備を整えよう
新盆に飾る白提灯は、故人が亡くなってから初めてご自宅へ帰ってこられる際の、道しるべとなる大切なものです。
とくに浄土真宗を除く多くの宗派では、新盆を迎える前に白提灯を用意することが一般的とされています。
白提灯は、故人の配偶者やお子さまなど、ご家族が準備するのが望ましいとされます。
種類は、玄関先などに吊るす伝統的なタイプと、仏壇の前に置ける設置型タイプのいずれを選んでも差し支えありません。
ご自宅のスペースやご予算に合わせて無理のない形を選び、感謝の気持ちとともに、静かに故人をお迎えする準備を整えていきましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要