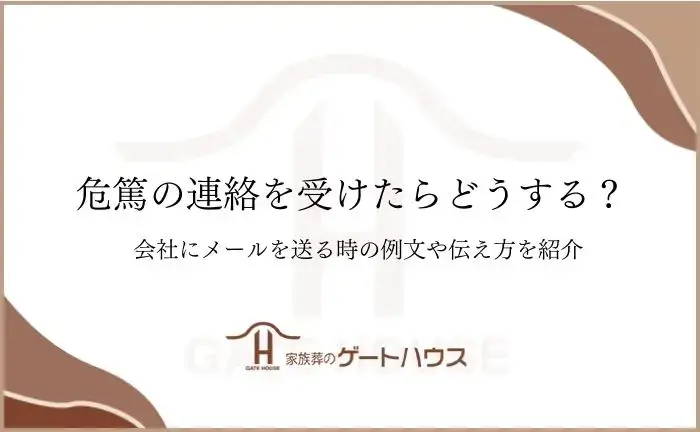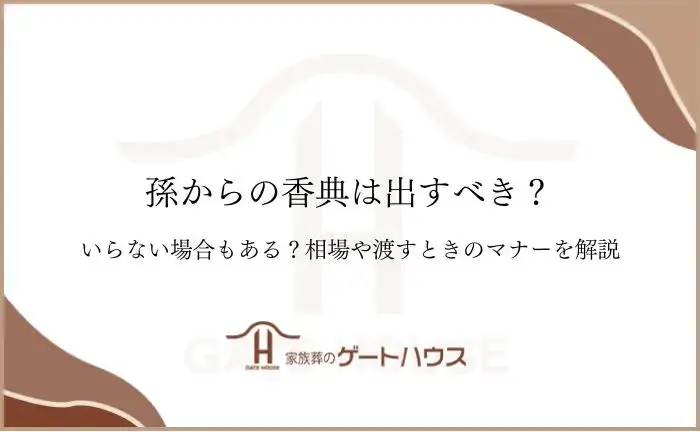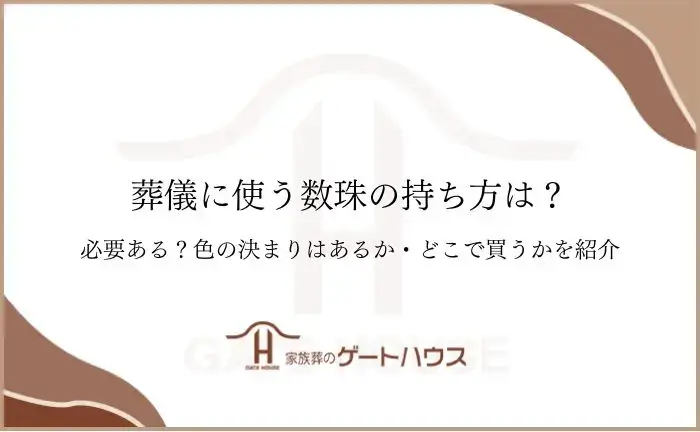お盆とお彼岸は何が違う?どちらが重要?それぞれの歴史や行事の違いを解説
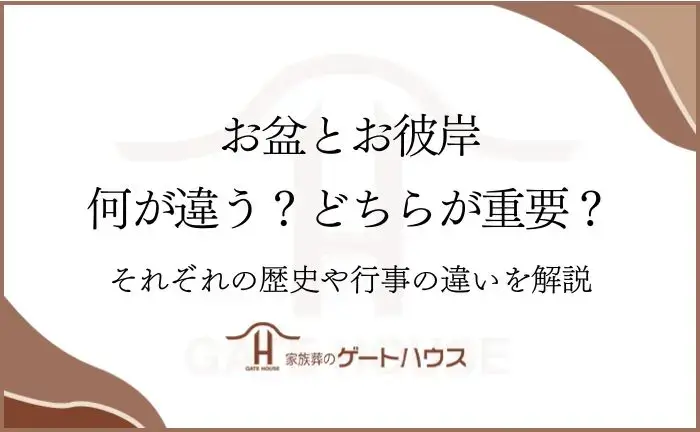
お盆とお彼岸は、お墓参りやお供えをして故人やご先祖様を供養する行事として知られています。
しかし、2つの違いについて、詳しく知らない人も多いかもしれません。
この記事では、お盆とお彼岸の違いやそれぞれの歴史、やるべきことなどについて解説します。
お盆とお彼岸の違いとは?由来や歴史を解説
お盆とお彼岸は、どちらも故人やご先祖様を供養する大切な仏教行事ですが、由来や成り立ちは異なります。
それぞれの意味を知ることで、さらに心を込めたお参りができるでしょう。
まずはお盆とお彼岸の違いについて、由来や歴史から解説します。
お盆の由来や歴史
お盆は、あの世からこの世に帰ってくるご先祖様の霊を迎え入れて供養する行事です。
日本古来の祖先崇拝や農耕儀礼などの風習と、仏教の盂蘭盆会(うらぼんえ)や儒教の考え方が混ざり合い、日本独自のお盆が生まれたと考えられています。
「お盆」の語源は、古代インドで用いられたサンスクリット語の「ullambana(ウランバーナ
)」で、「逆さに吊り下げられた苦しみ」という意味があります。
【関連記事】
新盆(初盆)とは?やり方は?用意するものやいつ法要を行うか解説
お彼岸の由来や歴史
お彼岸は、ご先祖様に日頃の感謝を込めて供養する日本独自の行事です。
昼夜の長さがほぼ同じになる春分の日と秋分の日は、あの世(彼岸)とこの世(此岸)の距離が最も近くなるため、想いが通じやすくなると考えられています。
また、お彼岸の期間に修行することで、煩悩に満ちたこの世から悟りの世界に到達できるとされています。
「お彼岸」の語源は、サンスクリット語の「paramita(パーラミタ)」。
漢訳は「至彼岸(とうひがん)」で「彼岸に至る」という意味があります。
お盆とお彼岸の時期の違いは?お墓参り・お供えはいつする?
お盆とお彼岸の違いは、お墓参りやお供えをする時期にもあります。
お盆は毎年8月が一般的ですが、7月に行う地域もあります。
一方でお彼岸は、春と秋の年2回です。
ここでは、お盆とお彼岸の時期の違いについて詳しく解説します。
お盆の時期はいつ?
お盆の期間には、7月盆と8月盆の2つがあります。
明治時代に暦が新しくなり、新暦の7月と旧暦の8月に行う地域に分かれたことが理由で、お盆の時期が異なるようになりました。
また、沖縄などの一部地域では、8月中旬~9月上旬に行う場合もあります。
2026年のお盆の時期は、7月盆は7月13日(月)~16日(木)、8月盆は8月13日(木)~8月16日(日)です。
お彼岸の時期はいつ?
お彼岸の時期は年に2回あり、春分の日と秋分の日のそれぞれ前後3日間をあわせた7日間です。
お彼岸では春分の日、秋分の日をそれぞれ中日(なかび、ちゅうにち)といい、初日を彼岸入り、最終日を彼岸明けといいます。
春分の日と秋分の日は、その年ごとに国立天文台が太陽の動きに合わせて定めるため、毎年変動します。
秋(9月)のお彼岸
2025年秋のお彼岸は、以下の時期です。
中日(秋分の日):2025年9月23日(火)
彼岸明け:2025年9月26日(金)
中日となる秋分の日は9月23日(火)です。
秋の彼岸入りは9月20日(土)、彼岸明けは9月26日(金)になります。
お彼岸にお墓参りをする場合は、この期間内に予定を立てましょう。
春(3月)のお彼岸
2026年春のお彼岸は、以下の時期です。
中日(春分の日):2026年3月20日(金)
彼岸明け:2026年3月23日(月)
中日となる春分の日は3月20日(金)です。
春の彼岸入りは3月17日(火)、彼岸明けは3月23日(月)となっています。
お墓参りの計画を立てる際の、参考にしてください。
お盆とお彼岸ではお供えものに違いがある?
仏教のお供えものは「香・花・灯明・浄水・飲食」の五供(ごく)が基本です。
お盆とお彼岸には、五供以外にもそれぞれ特有のものをお供えします。
それでは、お盆とお彼岸の違いについて、お供えものの観点からチェックしてみましょう。
お盆のお供えもの
お盆のお供えものには、以下のものがあげられます。
-
-
ろうそく
- 提灯
- 迎え団子・送り団子
- キュウリ・ナス
- 精進料理
- 素麺
- 乾物
- 故人が好きだったもの
-
お盆には、あの世から帰ってくる故人やご先祖様の目印になるように、ろうそくや提灯の明りをお供えしましょう。
迎え団子は13日に、送り団子は15日や16日にお供えするもので、個数は地域によって異なります。
キュウリを馬、ナスを牛に見立ててお供えする精霊馬・精霊牛は、あの世とこの世を行き来するご先祖様の乗り物です。
また、お盆のお供えものは、飢えや渇きに苦しむ餓鬼に対して飲食を施す「施餓鬼」の意味もあるため、普段よりも盛大に行います。
【関連記事】
お盆のナスとキュウリ「精霊馬」の向きは?意味・地域・宗派の違いや作り方も解説
お盆のお供え料理の定番メニューは?置き方・期間・基本マナーも解説
お盆のそうめんの飾り方&意味を解説!いつお供えする?正しい配置は?
お彼岸のお供えもの
お彼岸を代表するお供えものには、以下のものがあります。
-
-
おはぎ(秋彼岸)
- ぼたもち(春彼岸)
-
秋彼岸は「おはぎ」、春彼岸には「ぼたもち」をお供えしましょう。
どちらも、もち米とうるち米を混ぜて炊いたものを丸めて、あんこで包んで作った和菓子です。
同じ食べ物ですが、秋には萩に見立てて「おはぎ」、春には牡丹に見立てて「ぼたもち」と呼びます。
あずきの赤色には魔除けの効果があるとされ、古くから長寿を願って食べられてきた縁起物です。
地域によっては、彼岸団子と呼ばれるお団子をお供えすることもあります。
お盆とお彼岸では供花に違いがある?
「お盆とお彼岸では、お供えする花も変わるの?」「どんな供花を選べば良いんだろう」と悩む人もいるかもしれません。
ここでは、お盆とお彼岸の違いについて、それぞれの時期に適した供花を紹介します。
お盆に最適な供花
お盆に最適な供花には、以下のものがあります。
-
-
カーネーション
- リンドウ
- ケイトウ
- キンセンカ
-
仏花の定番といえば菊を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、カーネーション、リンドウ、ケイトウ、キンセンカなどが選ばれることも多いです。
白系の花を用いるのが多いものの、宗派や地域によっては紫や黄色、水色などの鮮やかな色の花もお供えすることもあるでしょう。
お彼岸に最適な供花
お彼岸に最適な供花には、以下のものがあります。
-
-
菊
- ヒャクニチソウ
- ストック
- キンギョソウ
- アイリス
- グラジオラス
-
お彼岸の供花には、菊のほかにもヒャクニチソウ、ストック、キンギョソウなどが選ばれています。
春彼岸にはアイリス、秋彼岸にはグラジオラスなど、季節の花を取り入れるのもおすすめです。
四十九日までは白系の花を用いるのが一般的ですが、それ以降は故人が好きだった花や思い出のある花、明るい色の花を取り入れても良いでしょう。
お盆とお彼岸で違う行事
お盆とお彼岸で共通している行事もあれば、異なる風習もあります。
それぞれの行事や意味の違いを知ることで、ご先祖様や故人をより近くに感じられるかもしれません。
それでは、お盆とお彼岸で違う行事について確認してみましょう。
お盆特有の行事
お盆には、お盆提灯やお盆飾り、迎え火、送り火、棚経を行います。
お盆は、年に一度ご先祖様の霊を家にお迎えすることが目的です。
そのため、お盆提灯を玄関先などに下げて自宅までの目印にしたり、乗り物である精霊馬(牛)を飾ったりします。
また、ご先祖様の霊をお迎えするときには迎え火を、送り出すときは送り火を玄関先やお墓の前で焚いてください。
通常のお盆では棚経といって、僧侶による読経を行いますが、故人が亡くなって初めてお盆を迎える際には新盆法要を行います。
お彼岸特有の行事
あの世とこの世が最も近くなるとされるお彼岸は、日頃の感謝を込めてご先祖様を供養するのが目的です。
お彼岸には、お寺や霊園の敷地内などで彼岸会(ひがんえ)と呼ばれる合同供養が行われます。
地域やお寺によっては、僧侶を自宅に招いて個別に供養することもあるので、確認しておきましょう。
また、お彼岸は六波羅蜜(ろくはらみつ)と呼ばれる、浄土(彼岸)に近づくための修行をする期間でもあります。
「全てのものに感謝する」という精神が基本になっているので、お供えやお参りを通して実践してみましょう。
【関連記事】
お彼岸にすることとは?お仏壇・お墓にお供えするものや仏壇飾りについて解説
お彼岸でやってはいけないことは何?してはいけないタブーな行動はある?
お盆とお彼岸でやるべきこと
お盆とお彼岸には、主にお墓やお仏壇の掃除、お参り、お供えなどを行います。
いずれもご先祖様や故人の思いを馳せながら、心を込めて行うことが大切です。
最後に、お盆とお彼岸で共通してやるべきことについて解説します。
お墓の掃除とお参り
お盆とお彼岸には、お墓の掃除とお参りをしましょう。
お盆のお墓参りは、あの世から帰ってくるご先祖様のお迎えや、お見送りのために行います。
お盆に入る前に掃除しておくのが望ましいとされていますが、難しい場合は当日お参りする際に行っても問題ありません。
一方でお彼岸は、あの世とこの世の距離が最も近く、想いが通じやすいとされる期間に、ご先祖様が眠るお墓に出向いてお参りをします。
お仏壇の掃除とお参り
お盆とお彼岸のどちらを迎える際にも、お仏壇の掃除とお参りをします。
仏具周りやお仏壇の内側、扉の裏側など、ホコリが溜まったり汚れが付きやすかったりする場所を中心に、普段の掃除よりも念入りに行いましょう。
お盆のときは、きれいになったお仏壇にお盆飾りやお盆提灯を飾って、ご先祖様をお迎えしてください。
【関連記事】
お彼岸のお墓参りはいつ行くべき?春秋別の日程・時間やマナーについて解説
お仏壇へのお供え
お盆とお彼岸は共通して、お仏壇にお供えものをあげます。
仏教のお供えは、五供(ごく)と呼ばれる「香・花・灯明・浄水・飲食」が基本です。
具体的には、お線香、お花、ロウソク、お茶やお水、食べ物を指します。
他の家庭にお供えものを贈る場合は、贈答用のお線香や、常温でも傷みにくく日持ちする食べ物などを選びましょう。
お盆もお彼岸も、お供えものにつける熨斗(のし)の表書きは「御仏前」や「御供」が一般的です。
ただし、四十九日前の場合は「御霊前」、初盆を迎える場合は「新盆御見舞」と表記します。
お盆とお彼岸はどちらも重要!それぞれの違いを知り適切な供養をしましょう
お盆とお彼岸は、ご先祖様を供養する大切な仏教行事です。
お盆は、あの世から帰ってくるご先祖様の霊をこの世にお迎えして供養します。
お彼岸は、あの世とこの世の距離が最も近くなる時期に、ご先祖様に感謝を伝え、今を生きる私たちも自分自身を見つめなおす期間とされています。
お盆とお彼岸の違いを知ると、お墓参りや期間中の過ごし方などで気持ちが変わるかもしれません。
それぞれの行事への理解を深め、ご先祖様への感謝や、家族との絆を深める機会にしましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要