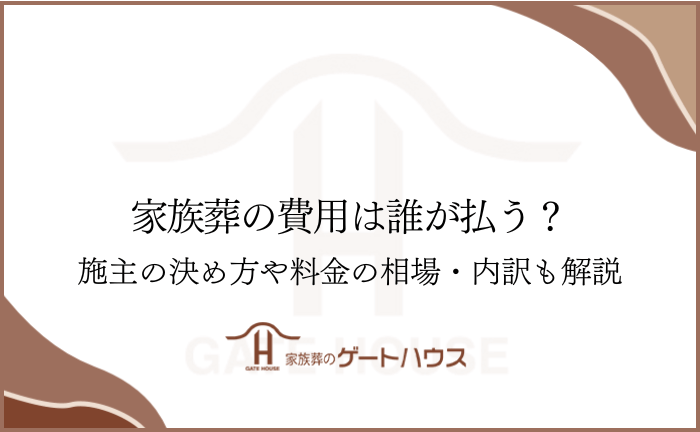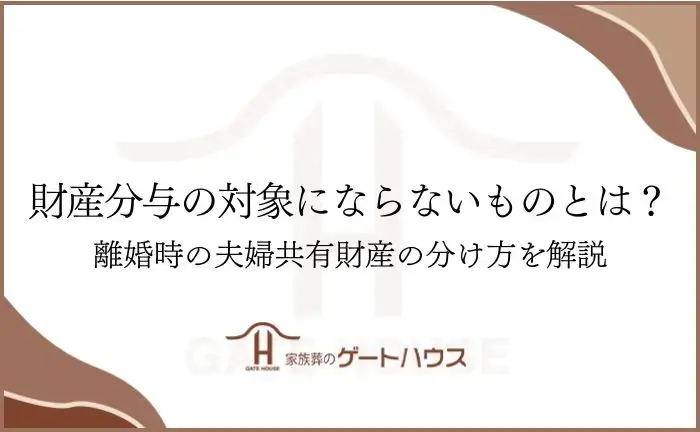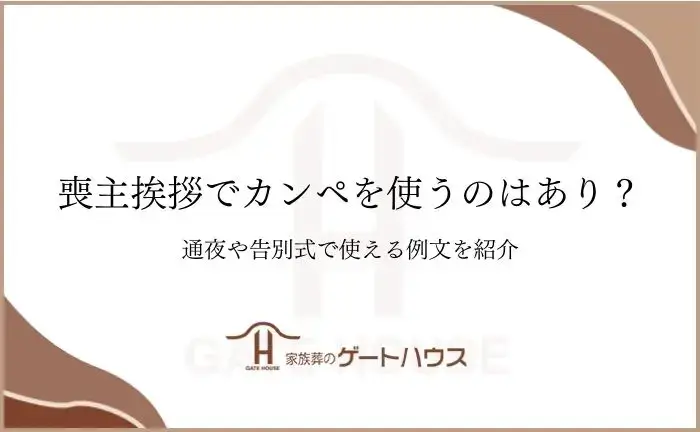遺品整理はいつから?49日前にすべき?進め方や考え方もわかりやすく解説
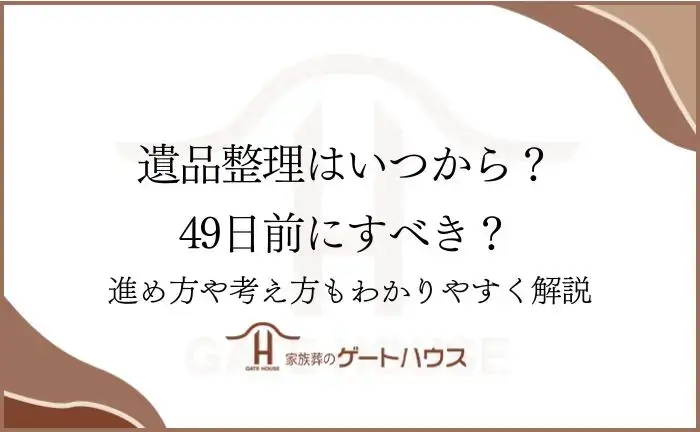
遺品整理について考え始めると「いつから取り掛かるべき?」「何から手をつければ良いのだろう」と悩む人もいるでしょう。
四十九日や相続手続きとのタイミングも気になるかもしれません。
この記事では遺品整理について、進め方や考え方などを詳しく解説します。
遺品整理はいつから?49日前にすべき?
遺品整理とは、身近な人が亡くなり、遺された物を整理して片付ける作業のことです。
始める時期は人それぞれですが、四十九日前や諸手続きの際など、区切りの良いタイミングはあります。
まずは、一般的に遺品整理を始めやすいとされるタイミングを確認してみましょう。
法律上の決まりはない
遺品整理を始める時期について、法律上の決まりはありません。
遺族の気持ちが落ち着いてから始める人もいれば、法事法要や相続税の申告手続きなどを区切りとして取り掛かる人もいます。
ただし、決まりがないからといって先延ばしにしていると、トラブルにつながる可能性も。
それぞれの状況や感情に応じて、適切な時期から始めましょう。
葬儀後すぐ|7日以内
葬儀や告別式が終わってすぐに遺品整理を行うケースです。死亡届は7日以内に提出するよう定められているため、この手続きに合わせたタイミングで遺品整理を始めるのもいいでしょう。
親族や法定相続人が遠方に住んでいても、葬儀直後であれば集まりやすいというメリットがあります。
故人が賃貸物件に住んでいて、退去手続きが必要といった事情がある場合にも、早めに取り掛かるのがおすすめです。
- 遠方の親族が集まっているうちに一部だけ整理したい
- 賃貸や施設に入所していて、住まいをすぐに明け渡す必要がある
- 孤独死など特別な事情がある
など
社会保険など諸手続きの後|1週間から1ヶ月程度
社会保険などの諸手続きの後に遺品を整理する場合は、1週間から1ヶ月程度を目安に始めます。
期限が決められている公的手続きと並行して片付けを進めたり、手続きに必要な書類を探したりしたい場合におすすめの時期です。
葬儀直後から遺品整理を始めるよりも時間的な余裕があるため、比較的自分たちのペースで取り組みやすいでしょう。
- 公的手続きと並行して、私物の片付けも少しずつ進めたい
- 手続き書類を探すために、ある程度持ち物を把握したい
- 相続人同士が遠方で集まるのが難しい
など
四十九日法要の後|2~3ヶ月程度
四十九日法要とは、故人が亡くなって49日目に執り行われる法要のことです。
親族が集まりやすいので、相談しながら遺品整理を進めたり、形見分けをしたりするのにも良いタイミングでしょう。
仏教において、四十九日は故人が亡くなってから極楽浄土に行けるかどうかの裁きを受ける日と考えられています。
遺族としても四十九日法要を区切りとして、遺品整理を始めようという気持ちになるケースが多いようです。
- 親族に相談しながら整理を進めたい
- 形見分けなども同時におこないたい
- 心の整理がついてきて、片付けに前向きになってきた
など
相続放棄の期限に合わせて|3ヶ月以内
相続放棄の期限に合わせて、遺品整理を始めるパターンもあります。
遺産相続では、遺品をすべて相続する「単純承認」、すべて相続しない「相続放棄」、一部を相続する「限定承認」の3つから選択しなければなりません。
申し立てをしなければ単純承認となりますが、その場合は借金などの負債も相続されるため、期限を迎える3ヶ月以内に資産・負債を確認しておく必要があります。
- 相続するかどうかを判断するため、資産・負債を確認したい
- 相続放棄を検討していて、物を勝手に処分できない
など
相続税の申告期限に合わせて|10ヶ月以内
相続税の申告期限に合わせるのも、遺品整理を始める目安の時期になります。
遺産が相続税の非課税額を超えている場合、相続人は相続税の申告手続きが必要です。
相続税の申告と納税は、故人が亡くなってから10ヶ月以内に行わなければなりません。
現金だけでなく土地や建物などの不動産、また貴金属や骨董品なども課税対象になる可能性があるので、申告期限に間に合うように整理しておきましょう。
- 遺産が相続税の非課税額を超えている
- 不動産など査定が必要な遺品がある
など
遺族の気持ちに合わせて
遺品整理を始める時期に決まりはないので、遺族の気持ちが落ち着いてからでも問題ありません。
故人との思い出が詰まった遺品を整理するのは、精神的な負担が大きい作業です。
無理に始めても、悲しみや喪失感が押し寄せて上手く進められないかもしれません。
相続税が心配な場合は、相続税を10ヶ月以内に概算で申告・納税をして、あとで確定したときに「更正の請求」を行うこともできます。
概算での申告は、過少申告や延滞税のリスクもあるため、判断に迷う場合は税理士など専門家に相談すると安心です。
すぐ遺品整理に取り掛かる気持ちになれないのであれば、半年や1年後など自分の中で目安となる期限を設定するのも良いでしょう。
遺品整理をいつから始めるか考えるときのポイント
遺品整理ではやるべきことが多く、手間も時間もかかります。
途中で挫折しないためには、現状を把握して計画的に取り掛かることが大切です。
ここでは、遺品整理をいつから始めるか考える際のポイントを紹介します。
遺品の量・種類は多いですか?
遺品整理を始めるにあたり、まず遺品の量や種類を確認しておきましょう。
物量や大型の家具家電が多かったりすると、整理に時間がかかることがあります。
一般的なワンルームの場合、片付けに必要な時間の目安は1週間程度です。
故人宅にある遺品の量や種類をチェックして、どれくらい作業時間が必要なのか逆算しながら計画を立てましょう。
遺品整理をする人の年齢や人数は?
遺品整理をする人の年齢や、作業者の人数も確認しておきたいポイントです。
遺品整理は体力や気力が必要なので、一般的には若い人が作業する方がスムーズに進めやすいでしょう。
また、人数が多いと手分けしながら効率的に片付けられます。
そのため整理をする人が高齢だったり、夫婦だけで行う予定だったりする場合は、作業に時間がかかるかもしれません。
時間がかかりすぎる場合は、業者に依頼するのも1つの手です。
年齢や人手をふまえて、いつからどのように始めるべきか考えてみましょう。
故人の財産・借金は把握できていますか?
故人の財産や借金を把握しているかどうかも、遺品整理をいつから始めるべきか考えるときのポイントです。
たとえば、相続放棄の期限は3ヶ月以内、相続税の申告期限は10ヶ月など、法律で期限が定められています。
このときまでに財産や借金について把握していないと、判断を誤ったり、申告漏れなどのトラブルに発展したりするかもしれません。
財産や借金について調査するには、遺品整理だけでなく、登記簿謄本の取得や金融機関への問い合わせが必要になることもあります。
把握できていない場合は、できるだけ早めに行動するのがおすすめです。
遺品整理の進め方
遺品整理を始めるにあたり「どうやって進めれば良いの?」「何から取り掛かるべき?」と悩む人は多いかもしれません。
ここでは、遺品整理の進め方について解説します。
遺言書・エンディングノートの確認
遺品整理では、まず遺言書やエンディングノートが遺されていないか確認することから始めます。
遺言書は相続財産について記した法的な書類で、財産を明らかにして分配するために重要です。
エンディングノートは、本人が自分の身に何かあったときのために、必要な情報や希望などを残すために作成されます。
本人の意志を尊重し、スムーズに遺品整理を進めるためにも、最初に確認してください。
【関連記事】
エンディングノートとは?おすすめの内容や書き方・終活ですべきことを解説
相続人の確定と役割を決める
相続人が複数人いる場合は、それぞれの役割を決めましょう。
遺品整理では遺品を片付けるだけでなく、近所の方への挨拶や親しい方への連絡、不用品回収をはじめとした専門業者の手配など、やることがたくさんあります。
相続人が確定したら分担について話し合い、協力して遺品整理を進めることが大切です。
スケジュールを立てる
遺品整理はスケジュールを立てて取り組むのがおすすめです。
故人が賃貸に住んでいて立ち退きする日が決まっている場合は、特に期限を意識して取り掛かりましょう。
ほかにも親族が集まれる日が限られる、相続税の申告期限に合わせるなど、それぞれの事情があるかもしれません。
スケジュールを立てることで優先順位が明確になり、相続人たちの間で予定を共有しながら計画的に行動できるでしょう。
遺品の仕分けをする
遺品整理では、さまざまな種類の遺品を片付けることになります。
たくさんの物をスムーズに片付けるコツは、おおまかに仕分けしながら作業することです。
重要な物、思い出の品、処分する品などに分類しながら進めると、仕分けに悩む時間を短縮できるでしょう。
重要書類・財産
重要書類には、身分証明書や健康保険証、不動産関係の書類などが該当します。
有価証券、金銭、貴金属をはじめとした経済的価値が高い物は、財産にあたります。
ほかにもクレジットカードやパスポート、年金手帳、印鑑などの貴重品も、遺品整理で見つけたらすぐに重要な物として大切に管理しましょう。
【関連記事】
遺産相続での預貯金の分け方とは?相続前の準備や分割時の注意点を解説
亡くなった人の預金をおろすには?口座凍結前・後の手続きや必要書類を解説
思い出の品
遺品整理では、写真やアルバム、手紙、日記など、故人の思い出が詰まった品も出てくるでしょう。
すべて残すのは難しいかもしれませんが、大切な物はクリアファイルや収納用品などを活用しながら保管してください。
リユース・リサイクル品
リユースやリサイクルが可能な品には、冷蔵庫やテレビなどの家電、ベッドやソファなどの家具、衣類、食器などがあげられます。
資源として再利用できる物や、リサイクルショップなどで買い取ってもらえる物を仕分けしておきましょう。
処分する品
重要書類や財産、思い出の品、リユース・リサイクルできるもの以外は廃棄します。
自治体のルールに則って分別し、処分を進めましょう。
「分別がよく分からない」「なるべく早く処分したい」という場合は、不用品回収業者や遺品整理専門業者に依頼するのも1つの方法です。
遺品の分配整理・処分を行う
遺品の仕分けをしたら、分配整理や処分を行います。
相続人で遺品の分配をしたり、家族と形見分けをしたりしましょう。
廃棄する物は適切に処分し、耐火金庫や消火器、バッテリーなど、自治体のゴミ収集では扱っていない品は個別に対処してください。
部屋の清掃
遺品整理の片付けが終わったら、部屋の清掃に取り掛かりましょう。
賃貸物件の場合は、原状回復義務として退去時の掃除を行います。
故人が住んでいた家を相続して住む場合は、リフォームや新しい家具家電を搬入する下準備としてきれいにしましょう。
洗浄力が高い洗剤や薬剤などを使うときは、素材が変色したり肌を傷めたりする可能性があるので、注意書きをよく確認して使用してください。
遺品整理を進めるための心構え
やみくもに遺品整理を始めてしまうと、途中で挫折してしまったり、思いがけないトラブルにつながったりすることもあります。
後悔しないためには、穏やかな気持ちで向き合うことが大切です。
最後に、遺品整理を進めるための心構えや注意点について解説します。
遺品整理業者などに頼むのも◎
遺品整理を専門業者に頼むのも選択肢の1つです。
プロによる遺品整理サービスを利用すると、費用はかかりますが、短時間で片付けが終了します。
「遠方に住んでいて片付ける時間が確保できない」「大量の物を処分する手間や労力を省きたい」という人におすすめです。
間違って大事な物まで捨てられるのが不安な場合は、作業前に自分で大切な遺品や形見を仕分けしておきましょう。
無理せず焦らず自分のペースで進める
遺品整理は焦らず、自分のペースで取り組みましょう。
遺品を片付けていると故人との思い出がよみがえり、悲しみや喪失感に襲われるかもしれません。
気持ちが不安定なときは無理をせず、心の準備として自分の感情と向き合いましょう。
また一人で抱え込まず、家族や友人と協力しながら進めることでも精神的な負担を軽減できるはずです。
分類に迷ったら保留にするのも◎
遺品整理で分類に迷ったら、一旦保留にするのも良いでしょう。
長時間悩んでいると、作業がスケジュール通りに進まないことも。
かといって捨ててしまうと、もう二度と同じ物は取り戻せないかもしれません。
保留用のボックスを用意しておけば、作業スピードが格段にアップします。
時間が経ってから改めて整理することで、気持ちが落ち着いて手放せる物もあれば、大切に遺しておきたい品なども判断できるでしょう。
思い出の品は写真に残すだけでも満たされることがあるので、保管したい物が多すぎる場合は試してみてください。
親族間トラブルに注意
遺品整理では、親族間のトラブルに注意してください。
たとえば遺品を処分する際に、自分にとって不要な物でも、他の人にとっては故人との思い出が詰まった大切な物かもしれません。
相続時に問題になるかもしれないので、特に自分以外にも相続人がいる場合は、親族の了承を得てから遺品整理を始めましょう。
【関連記事】
遺品整理で捨ててはいけないものは?衣類の処分時期やトラブル例を解説
遺品整理をいつから始めるかに正解はない。“どう向き合うか”を大切に
遺品整理には、いつから始めなければならないという決まりはありません。
無理に進めると気持ちが沈んでしまったり、後悔したりするかもしれないので、自分のペースで向き合うことが大切です。
始める時期に悩んだら、遺品の量や作業人数などを考えてスケジュールを立て、計画的に取り組みましょう。
時間や労力、精神的負担を軽減したい、相続や賃貸契約などの関係で急がなければならないなどの事情がある場合は、遺品整理業者に依頼するのも検討してみてくださいね。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要