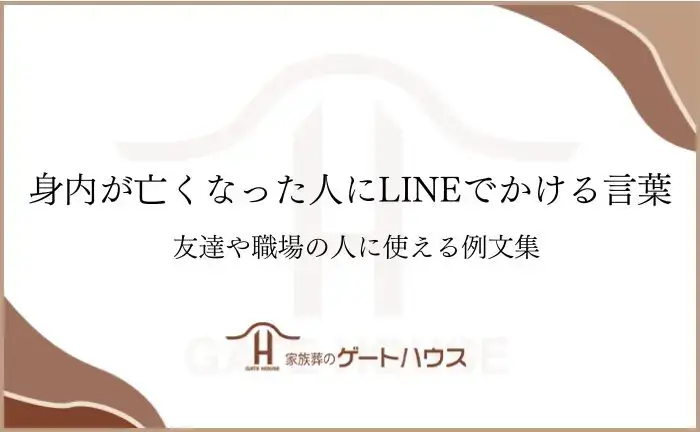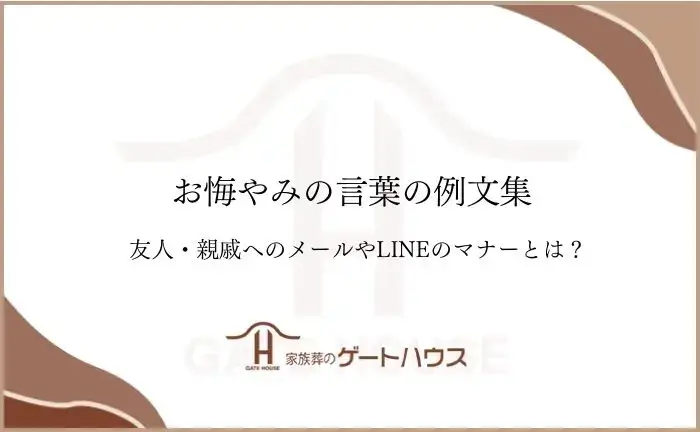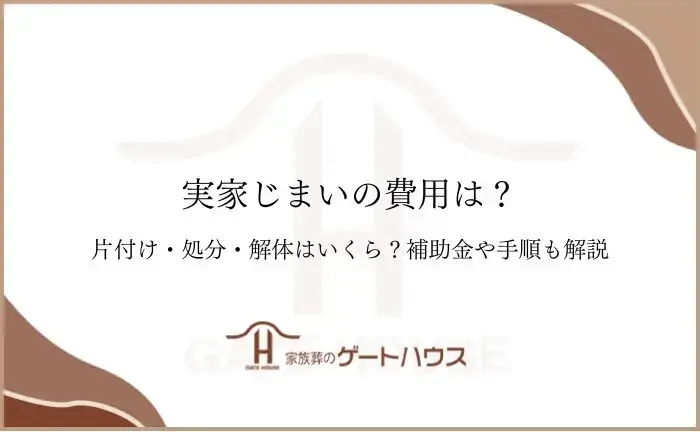財産分与の対象にならないものとは?離婚時の夫婦共有財産の分け方を解説
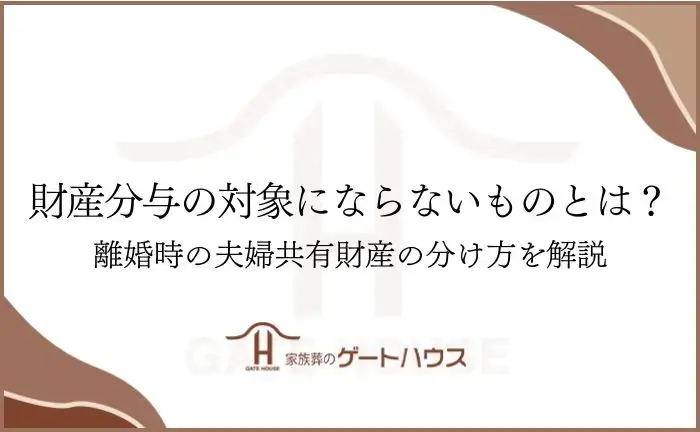
離婚の際には、財産分与を行います。
離婚後の生活を考えると、できれば財産分与で不利にならないようにしたいものです。
財産は、財産分与の対象になる共有財産と、対象にならない特有財産に分けられます。
年金や退職金など、思わぬものも共有財産とみなされる可能性があるため注意が必要です。
本記事では、共有財産と特有財産についてくわしく解説し、さらに財産分与の進め方や有利に進めるポイントも紹介します。
ぜひ、参考にしてください。
財産分与の対象にならないもの|特有財産
離婚する際の財産分与において、財産分与の対象になるものを共有財産、対象外となるものを「特有財産」と呼びます。
特有財産は3つに分けられており、主に「婚姻前から所有している財産」「婚姻後に贈与・相続によって得た財産」「夫婦間で合意して対象外にしたもの」です。
この項では、これら3つの種類とそれ以外に対象となるものを紹介します。
婚姻前から所有している財産
婚姻前から所有していた財産は特有財産です。
たとえば、結婚前に購入した不動産・株式や預貯金、結婚前に契約した保険の解約返戻金などが該当します。
結婚前に不動産をローンで購入して結婚後も支払っている場合、結婚後にローンで返済した部分は共有財産とみなされます。
結婚前に購入していた株式を結婚後に運用して得た利益は、特有財産です。
婚姻後に贈与・相続によって得た財産
婚姻後であっても自分の親族などから贈与・相続された財産は特有財産です。
ただし、財産の価値を維持・増加するために配偶者が協力した場合は、財産分与の対象になるケースもあります。
夫婦間で合意して対象外にしたもの
本来は財産分与の対象財産であっても、夫婦間で合意すれば財産分与の対象から外せます。
子どもの進学のために貯めていたお金や学資保険などは、本来共有財産とみなされますが、夫婦間の協議で親権者が引き継ぐケースが多いです。
自分専用の身の回りの品・家具
スマートフォン、趣味の品、自分が身に付ける衣類など、個人が専用で使用しているアイテムや家具などは、通常であれば財産分与の対象にはなりません。
ただしブランド品など価値の高いものは、対象となるケースがあります。
夫婦以外の名義の財産
子ども名義の財産は、原則として子ども自身のものとされ、財産分与の対象にはなりません。
ただし、名義は子どもでも実際には夫婦の収入から形成された預貯金などの場合は、実質的に夫婦の共有財産とみなされ、分与の対象となることがあります。
また、夫婦の一方が経営する会社の資産(会社名義の財産)は、会社という独立した法人の所有物であるため、通常は財産分与の対象外です。
ただし、夫婦の一方がその会社の株式を保有している場合には、その株式自体の価値は財産分与の対象となることがあります。
個人的な借金
ギャンブルや賭け事などでできた借金は、個人の責任に帰するものなので、特有財産とみなされます。
婚姻生活を営むうえで必要となる住宅や車のローンなどの負債は共有財産です。
財産分与の対象になるもの|共有財産
結婚後にできた財産は、夫婦の協力によって得られたものなので、基本的には共有財産として財産分与の対象です。
片方が専業主婦(または専業主夫)であっても、もう片方が得た収入によるものは共有財産とみなされます。
結婚後に得た預貯金
結婚後に得た収入などは、どちらか片方の給与なども含め基本的に財産分与の対象となります。
個人名義の預金も、夫婦の共有財産です。
結婚後に取得した車・株など
結婚後に取得した車や株などは、たとえ名義がどちらか片方のものであっても実質的共有財産として財産分与の対象となります。
結婚後に取得した不動産
不動産の場合、住宅ローンが残っているかどうか、不動産の査定額とローン残高のどちらが大きいかで、財産分与の方法が異なります。
住宅ローンが残っていない場合は、それぞれ1/2の権利があります。
住宅ローンの残債が不動産の査定額を下回るアンダーローンの場合、差額が財産分与の対象です。
住宅ローンの残債が不動産の査定額を上回るオーバーローンの場合、負債をどのように処理するか、夫婦で話し合わなければなりません。
年金
婚姻期間中に保険料を支払った分に相当する年金も共有財産とみなされ、年金分割という制度に基づいて分割されます。
この際、対象となるのは厚生年金の報酬比例部分のみであり、国民年金部分は分割の対象外です。
年金分割には「合意分割」と「3号分割」という2つの方法があります。
| 分割方法 | 内容 |
| 合意分割 |
婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金保険料を合算し、原則として最大1/2まで分割可能。 相手の合意または裁判所の決定が必要。 |
| 3号分割 | 専業主婦(夫)など第3号被保険者であった期間については、相手の合意がなくても自動的に1/2に分割される。 |
これにより、将来夫婦が受け取る年金が公平になります。
年金分割の請求には期限があり、離婚から2年以内に請求しなければなりません。
相手が合意してくれない場合は裁判に発展する可能性もあるので、できれば離婚協議の中で申し出ると良いでしょう。
退職金
退職金は、働いていた期間のうち婚姻期間と重複する期間が財産分与の対象です。
婚姻期間中であっても、別居していた期間は除外されます。
すでに退職金を受け取っている場合、使用したお金は夫婦共有の目的で使用されたとみなされるので、財産分与の対象にはなりません。
将来受け取る予定の退職金も、財産分与の対象として扱われる可能性があります。
積立型の保険
積立型の生命保険や学資保険など、解約返戻金を受け取れるものは財産分与の対象です。
掛捨て型の保険は、そもそも返戻金が受け取れないので財産分与の対象にはなりません。
学資保険も共有財産なので、解約して返戻金を分割できますが、子どもの将来のためにそのまま残して親権者が引き継ぐのが一般的です。
家具・家電など
婚姻期間に購入した家電や家具は、財産分与の対象です。
どのように分割するかは、夫婦が協議して決めます。
それぞれが希望する家電・家具を分け合う方法や、売却して得た金額を半分ずつ受け取る方法が考えられます。
財産分与の3つの種類
財産分与は、結婚中に築いた財産を、離婚の際に公正に分けるのが原則です。
しかし離婚の原因や離婚後の経済状況・生活環境などに応じて以下のように、3つの方法に基づいて分与を行います。
清算的財産分与
清算的財産分与は、基本的な財産分与の方法です。
婚姻中に協力して取得した財産を、貢献度に応じて分割します。
原則として、婚姻中は双方が結婚生活の維持・資産の形成に等しく貢献してきたと考え、財産を均等に分けます。
専業主婦(専業主夫)であっても、1/2の財産を得られるのが基本です。
どちらか片方の名義であっても、不動産、株式、自動車、預貯金、家財などを等分に分け合います。
扶養的財産分与
扶養的財産分与は、離婚によりどちらかが生活に困窮する可能性がある場合、もう片方が一定期間生活を支援する財産分与の方法です。
具体的には、毎月一定額のお金を困窮している側に支払うような形がとられます。
財産分与の原則は清算的財産分与なので、裁判所で扶養的財産分与が認められるケースはそれほど多くはありません。
以下のようなケースは例外的に認められる場合があります。
・長年専業主婦をしていたので、すぐには収入を得られない
・病気・高齢で仕事に就けない
・子どもの養育が必要で、フルタイムの仕事をするのが難しい
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与は、離婚の原因がどちらか片方にある場合、慰謝料に相当する部分を財産分与に含める方法です。
不倫やDVなどが原因で離婚する場合に適用されます。
本来、慰謝料は財産分与とは分けて請求する性質のものですが、財産分与に含めることで慰謝料を請求するための煩雑な手続きを省略できます。
財産分与を進める6つのステップ
財産分与の協議では、双方の主張が折り合わず解決に時間がかかったり、関係がこじれたりすることもありえるでしょう。
ここでは、財産分与を円滑に進めるための手続きの流れを紹介します。
財産分与の対象になるものをリストアップ
まず、財産分与の対象となる財産を把握しなければなりません。
婚姻前に取得した財産は本来財産分与の対象外ですが、不動産などを婚姻前に取得し婚姻後にローンを返済している場合は、財産分与の対象となります。
対象となる財産の価値を算定する
プラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などの負の財産も含めて財産の価値を算定する必要があります。
不動産の場合は評価の根拠となる資料を準備しましょう。
不動産価値の算定にはさまざまな方法がありますが、双方が合意すればどの方法を選んでもかまいません。
不動産の評価額には、固定資産税評価額、路線価、時価などがあります。
この中では時価が最も評価額が高く、固定資産税評価額は時価のおよそ5〜7割、路線価は時価のおよそ6〜7割の金額です。
離婚後もどちらかが自宅に住み続ける場合、どの評価方法を採用するかによって、それぞれのほかの資産の取り分が異なってきます。
離婚に伴って自宅を売却するのであれば、売却金額を分け合う形になるので、非常に公正・公平です。
夫婦で協議する
対象となる資産のリストアップと評価が終わったら、夫婦で協議して財産を分割します。
基本的には財産を1/2ずつ取得するのが原則ですが、双方が合意すればどのような分け方をしても問題ありません。
協議がまとまらない場合は法的手続きを行う
夫婦間の協議が合意に至らなければ、家庭裁判所での「調停」「訴訟」「審判」に進みます。
法的手続きは、離婚前と離婚後で異なります。
離婚前に協議する場合は、子どもの親権なども含めて一緒に協議すると良いでしょう。
夫婦間で話し合いが成立して離婚することを、協議離婚と言います。
日本での多くの離婚の形態は、協議離婚です。
話し合いがまとまらなければ離婚調停、それでも解決しなければ審判、裁判などの方法を選択します。
離婚後に財産分与請求をする場合は、原則として離婚後2年以内に財産分与請求調停を申し立てなければなりません。
2年を過ぎると申し立てができなくなるので注意が必要です。
合意書を作成する
協議がまとまれば、後でトラブルにならないように、できれば文書の形で残しておくと良いでしょう。
子どもの親権や他の取り決めがある場合は、離婚協議書を作成します。
後々取り決めが実行されない可能性がある場合は、公正証書を作成するのが望ましいです。
財産の移転・名義変更の手続きを実施する
取り決めに基づき、財産分与を実行に移します。
現金は協議で決められた金額を相手の口座に振り込み、不動産・自動車などは名義変更を行います。
財産分与を有利に進めるポイント
離婚後の生活のためにも、不利にならないように財産分与を進める必要があります。
ここでは、財産分与をできる限り有利に進めるためのポイントを紹介します。
不動産の評価方法はさまざま
不動産の評価方法にはいろいろあり、どの評価方法を採用してもかまいません。
自宅不動産を自分が取得したい場合は、低めの評価額が有利です。
逆に自宅不動産が必要ない場合は、高めの評価額だとそれに見合う他の財産を多めに取得できます。
婚姻前に夫婦財産契約を結ぶ
夫婦財産契約とは、民法756条に基づく規定で、婚姻前に婚姻中に発生した生活費の負担割合や離婚時の財産分与における方法を決めておくことです。
結婚前に、財産分与をしないと決めておくことも可能です。
日本ではそれほど浸透している制度とはいえませんが、海外ではよく利用されています。
相手の財産隠しをチェックする
何らかの疑いがある場合、相手が財産を隠していないかチェックすることも検討しましょう。
不自然な預金の出金があれば、預金を他の口座へ移しているかもしれません。
相手が所有するすべての預金を正確に把握する方法として、通帳開示請求があります。
専門家に相談する
弁護士であれば、財産分与に関して適切なアドバイスをしてくれます。
たとえば、上記の通帳開示請求には法的拘束力がありません。
もし拒否された場合は、弁護士照会などによって対処可能です。
弁護士には、財産分与だけでなく離婚に関する協議全般を任せられます。
特有財産は財産分与の対象外。交渉が難しい場合は専門家に相談を
財産分与を行う際には、何が共有財産で何が特有財産になるかを正確に把握することが重要です。
特有財産は財産分与の対象にはなりません。
資産の中には、預金・不動産・退職金・年金など、評価が大変難しいものもあります。
資産の算定や相手との交渉が難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要