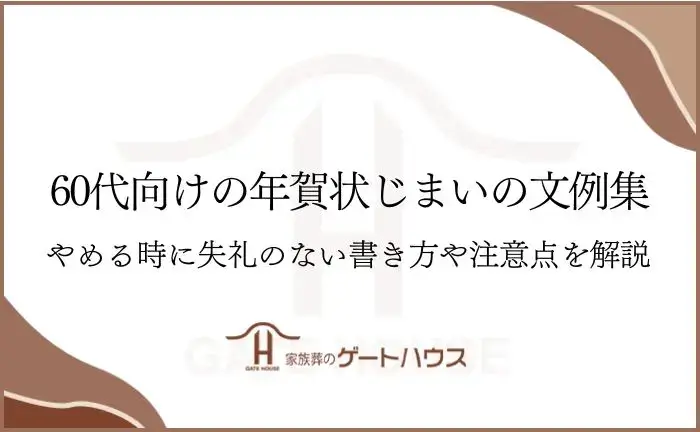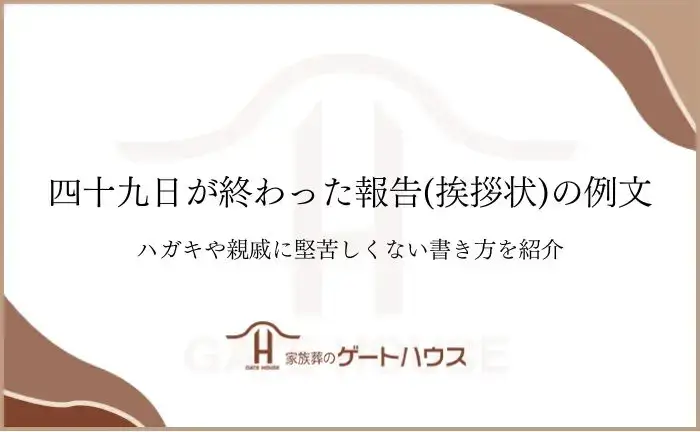高齢者が歩けなくなると余命は短くなる?食生活等の原因や予防法を解説
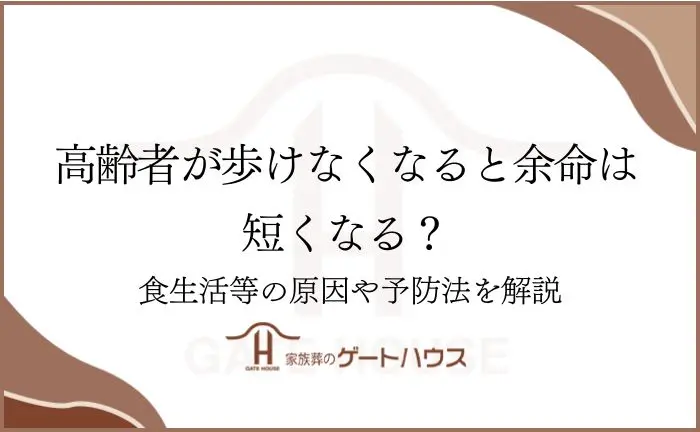
高齢者が「歩けなくなった」と聞くと、余命が短くなるのではと心配する方は多いのではないでしょうか。
本記事では、高齢者が歩けなくなった時の余命や生活への影響、歩けなくなる原因・予防のポイントを解説します。
高齢者が歩けなくなっても余命が短くなるとは限らない
高齢者が歩けなくなると、筋力や運動機能が急速に衰えることが多くあります。
歩けなくなると体力や免疫力が低下し、廃用症候群を引き起こすことで病気のリスクが高まり、結果的に健康寿命が短くなる可能性もあるでしょう。
廃用症候群とは、長期間安静状態が続き活動量が低下することで引き起こされる、様々な心身の機能低下のことを言います。
しかし、歩けなくなったからといって直ちに余命が縮むわけではなく、生活習慣や健康状態、介護者の支えなど、様々な要因が複合的に影響します。
歩けなくなった場合でも、適切な介護や医療、リハビリを受けることで健康状態を維持できるケースも多いのです。
寝たきりになった場合の余命
高齢者の寝たきり状態の余命は、平均で2~5年程度といわれていますが、個人差は大きく、数か月で亡くなる方もいれば、10年以上生活できる方もいます。
これは年齢、健康状態、介護環境、病院での治療内容などによって左右されます。
特に高齢で慢性疾患を抱えている場合、体力の限界は早まりやすいといえるでしょう。
また、寝たきりの高齢者は肺炎や褥瘡(床ずれ)などの合併症を起こしやすく、それが命に関わる場合もあります。
ただし、早期に適切なケアを行えば、廃用症候群の症状を抑え、余命を延ばすことは可能です。
歩けなくなることが余命に与える影響
歩けなくなることは、自由に移動できないということです。
これにより「移動が制限される→筋力が低下する→活動量が減る→食欲が落ちる→低栄養につながる」という悪循環が起こります。
また、外出が難しくなることで社会的孤立を招き、生活の質や精神面にも影響を与えるでしょう。
「歩行能力」は高齢者の健康状態を示す重要な指標です。
歩けなくなると体力や免疫力が低下し、最終的に老衰へとつながるリスクが高まります。
しかし、病院でのリハビリや訪問看護を活用し、介護者と共に生活を工夫することで、健康状態を維持できる可能性も十分あるでしょう。
高齢者が歩けなくなる主な原因
高齢者が歩けなくなる原因として、以下の3つが挙げられます。
-
-
1.加齢による身体機能や筋力の低下
- 2.病気や認知症の影響
- 3.栄養状態や生活習慣の影響
-
それぞれ詳しくみていきましょう。
加齢による身体機能や筋力の低下
加齢により、筋肉量や筋力は自然に低下します。
筋力が落ちると骨や関節の萎縮も進み、腰や膝の痛みで歩行が億劫になるでしょう。
結果として運動不足となり、さらに運動機能が低下するという悪循環に陥りやすくなるのです。
病気や認知症の影響
脳卒中やパーキンソン病、骨折、変形性関節症などの病気は、歩行障害を引き起こす大きな要因です。
身体の痛みがあると外出を控えるようになり、足腰の筋力が弱まっていきます。
また、認知症が進行するとバランス感覚や空間認識能力が低下し、転倒や歩行困難につながります。
栄養状態や生活習慣
加齢とともに運動量が減少する一方で、食生活の乱れや偏食が続くと栄養バランスが崩れます。
摂取カロリーが消費カロリーを上回る状態が続くと肥満につながりますし、肥満が原因で高血圧などの生活習慣病のリスクが高まります。
低栄養や偏った食生活だけでなく、慢性的な脱水、過度な飲酒、喫煙などの生活習慣も筋力低下や骨の脆弱化を進める原因です。
栄養バランスの乱れは筋肉量の維持に直接影響しますし、生活習慣病は脳の血流障害を引き起こすため、認知症の進行にもつながります。
【関連記事】
点滴のみの余命は?ご飯が食べれない終末期の高齢者はどれくらい生きられる?
高齢者が歩けなくなった後の生活
高齢者が歩けなくなると、外出や日常生活に大きな制約が生まれ、生活の質が大幅に低下するでしょう。
また、長期間寝たきりとなることで廃用症候群が進行し、老衰死につながるケースもあります。
生活上の制約
歩けなくなると、買い物・通院・友人との交流など、日常生活に必要な外出が難しくなります。
また、自分でトイレに行ったり入浴したりすることが難しくなり、日常生活に大きな支障が出るでしょう。
介護者への依存度が高まり、誰かに頼らざるをえない状況は、自尊心の低下や抑うつ状態を引き起こす可能性もあります。
認知機能への影響
高齢者は「寝たきりになると認知症になりやすい」と言われています。
活動量が減り、コミュニケーションや考える機会が減ると、脳への刺激も減少し、認知症が進行しやすくなるのです。
また、物忘れを家族から指摘されることで落ち込み、会話を控えるようになったり、本人ができることまで家族がサポートしたりすると、さらに生活意欲が低下する悪循環にも陥ります。
リハビリや治療の可能性
けがや病気が原因で歩けなくなった場合でもなるべく早くリハビリを開始するのが望ましいとされています。
なぜなら、安静にしている期間が長くなるとその分筋力も低下し、以前のように歩けるようになるまで時間がかかるからです。
ただし、けがや病気の種類、症状の重さ、手術の有無によって推奨されるリハビリの開始時期が異なりますので、必ず主治医の指示に従いましょう。
理学療法士や作業療法士のサポートによるリハビリや、適切な治療によって再び歩けるようになる可能性があります。
家庭内介護と介護施設の選択
退院後、自宅での生活に介護が必要となった場合は、訪問介護や訪問入浴介護といった、家族の負担を減らすためのサービスの利用を検討するのがおすすめです。
プロの手を借りることで、家庭内の介護において双方の負担を軽減することにつながります。
自宅の造りが介護に適していない場合は、デイサービス等を利用するのも一つです。
もし自宅での介護が難しくなったら、介護施設への入居も検討しましょう。
長期入居を前提とした特別養護老人ホーム、有料老人ホームのほか、在宅復帰を目指すための施設もあります。
介護サービス・在宅医療・訪問看護の活用
訪問介護はホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつ、衣服の着脱などの身体介護や掃除、洗濯、買い物などの生活援助を行います。
原則として、家族と同居している場合はこの「生活援助」に該当する家事支援を受けることはできません。
一方、在宅医療・訪問看護は外部の看護師や医療スタッフが定期的に訪問し、特定の医療ケアやサポートを提供します。
看護師や保健師を中心に、必要に応じて理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの医療従事者が自宅を訪問します。
医師の指示のもとに療養上の世話やリハビリ、日常生活に対する助言などを行うため安心です。
高齢者が歩けなくなる前にできる予防とケア方法
筋力や運動機能が低下すると、転倒や骨折のリスクが高まり、そのまま寝たきりにつながることも。
早期から予防をすることが、健康寿命の延伸につながります。
筋力維持と運動習慣の重要性
筋力低下を防ぐには、日常的な運動習慣が有効です。
散歩や軽い筋トレ、バランス運動など、自分に合った運動を継続することで歩行能力を維持できます。
家事や庭仕事、積極的に階段を使ったりと、日常生活でできる範囲で体を動かしたりするのもよいでしょう。
栄養管理(食事のポイント)
筋肉を維持するためには、筋肉の材料となる十分なタンパク質を積極的に摂取しましょう。
肉、魚、卵、大豆製品などをバランスよく摂ることが大切です。
また、ビタミンD、C、K、マグネシウムは筋肉の合成をサポートしますので、様々な食材を意識してとるとよいでしょう。
早期治療と定期的な検査
高齢者の歩行障害は、様々な原因によって引き起こされます。
歩行障害の原因が、脳血管疾患・神経疾患・整形外科疾患などの疾患である場合、早期の発見と治療介入が歩行機能の維持に大きく関わります。
病気やけがを早期に見つけて適切に治療することが、歩行能力の低下を防ぐための重要なポイントです。
定期的に健康診断を受け、痛みや違和感があれば早めに医療機関を受診しましょう。
高齢者が歩けなくなると余命に影響する可能性も。歩けなくなる前に予防や備えを
高齢者が歩けなくなると生活の自由度が大きく低下し、健康へのリスクが高まりますが、適切な対策を講じれば必ずしも余命が短くなるわけではありません。
大切なのは、歩けなくなる前から運動や栄養、定期的な医療チェックなどの予防に取り組むことです。
ご家族や周囲の人が一緒に支えながら、高齢者自身が「自分らしく生きる」ための準備とケアを進めていきましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要