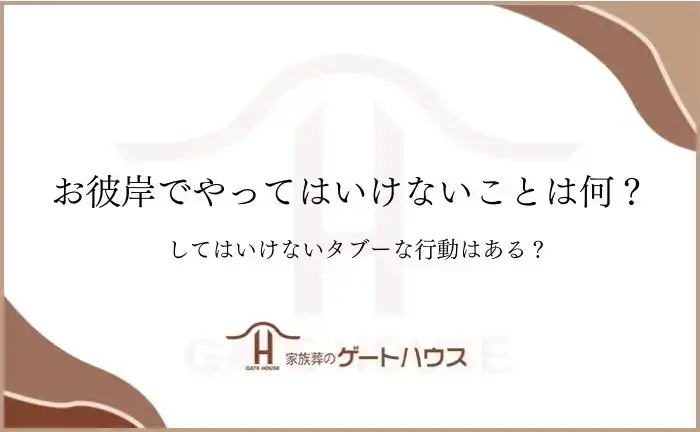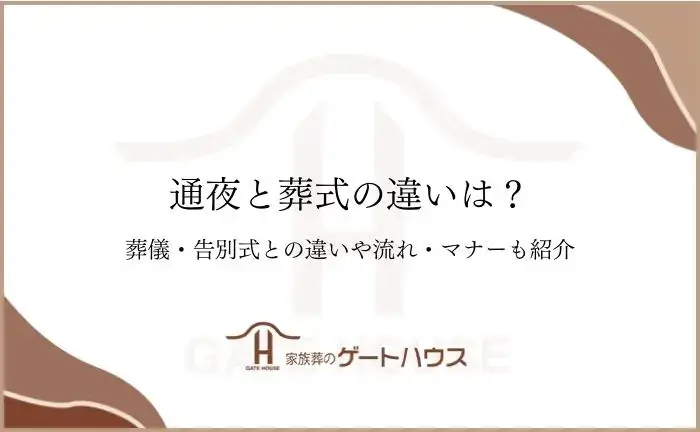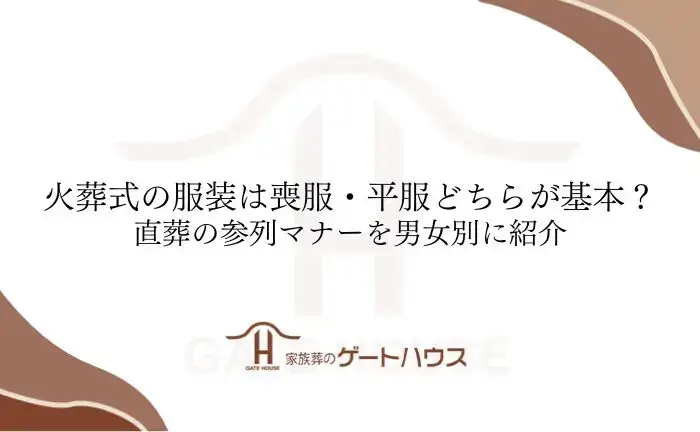子なし夫婦の遺産相続はどうなる?法定相続人・遺産の割合・対策など解説
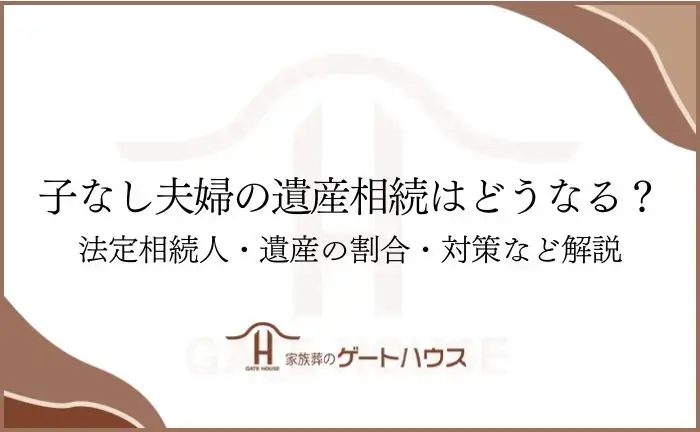
子どものいない夫婦では、一方が亡くなっても残された配偶者が全財産を相続できるとは限りません。
法律上、亡くなった方の親や兄弟姉妹も相続人となる場合があり、親族間でのトラブルに発展することもあります。
本記事では、子なし夫婦の相続の仕組みや相続割合、起こりやすいトラブルと回避策を解説。
配偶者を守るための優遇制度や今からできる対策も紹介します。
子なし夫婦の相続人は配偶者と血族相続人
子どものいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合、相続の権利がある法定相続人は、配偶者と血族相続人です。
血族相続人とは、亡くなった人(被相続人)と血のつながった親族のことで、相続する権利には以下のように順位があります。
第2順位:両親(両親が亡くなっている場合はその親(被相続人から見ると祖父母))
第3順位:兄弟姉妹(子どもが亡くなっている場合はその子(被相続人から見ると甥・姪))
上位の順位の相続人がいる場合、下位の順位の方に相続の権利はありません。
そのため、子どものいない夫婦の場合、残された配偶者が誰と遺産を分けることになるのかは、この「血族相続人の順位」によって変わります。
配偶者と親が相続人になる場合の割合
子どものいない夫婦で、亡くなった方の親が健在であれば、相続人は「配偶者と親」になります。
両親がすでに亡くなっている場合は、その代わりに祖父母が相続します。
相続の割合は、配偶者が2/3、親(または祖父母)が1/3です。
両親とも健在なら、この1/3を均等に分け合い、父と母がそれぞれ1/6ずつを受け取ります。
なお、父母の一方が亡くなっている場合は、生存している方が親の取り分(1/3)をすべて相続します。
配偶者と兄弟姉妹が相続する場合の割合
亡くなった人(被相続人)に兄弟姉妹がいて、被相続人の両親がすでに他界している場合、その兄弟姉妹が法定相続人となります。
相続の割合は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。
兄弟姉妹が複数いる場合、1/4を兄弟全員で分けます。
被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、代わりにその子どもが相続できます。
このように、相続する権利のある人が亡くなっていて代わりにその子どもが相続することを「代襲相続」と呼び、代襲相続の権利を持つ人を「代襲相続人」と言います。
たとえば、子のいない夫婦(夫Aと妻B)のうち夫Aが亡くなった場合、夫Aの両親はすでに亡くなり、その親(夫Aから見ると祖父母)も亡くなっていると、夫Aの兄弟姉妹が血族相続人となります。
夫Aの兄弟姉妹には兄Cと妹Dがいて2人とも健在であれば、相続の割合は妻Bが3/4、兄Cと妹Dがそれぞれ1/8ずつです。
もし妹Dが亡くなっていて子どもがいなければ、兄Cが1/4を相続します。
妹Dに子どもがいれば、妹Dの相続分を代わりに相続します(代襲相続)。
妹Dに子どもが複数いれば、Dの相続分1/8を均等に分けます。
なお、妹Dやその子Eがともに亡くなり、Eの子Fがいる場合、Fは相続人にはなりません。
兄弟姉妹が相続する場合の代襲相続の範囲は、亡くなった人(被相続人)から見て甥・姪までです。
【関連記事】
遺産相続での預貯金の分け方とは?相続前の準備や分割時の注意点を解説
子なし夫婦の相続の基本ルール
子どもがいない夫婦の相続に関して、民法などで定められているルールや税制面での優遇措置を紹介します。
配偶者は常に相続できる
子どもがいない夫婦の場合、他の相続人の有無にかかわらず、配偶者には常に相続する権利があります。
相続する割合は、他の相続人の相続順位によって異なります。
亡くなった人の親がいる場合、配偶者の相続分は2/3。
親はすでに亡くなっていて、兄弟姉妹がいる場合、配偶者の相続分は3/4です。
遺言書があれば遺言書を優先する
故人の遺言書があれば、法律で定められた相続分よりも遺言書の内容が優先されます。
ただし、法定相続人(兄弟姉妹をのぞく)には遺留分があります。
遺留分とは、遺言書の内容にかかわらず、法定相続人が受け取ることのできる相続分です。
遺留分は、誰が相続人となるかで割合が変わります。
遺留分の割合は、相続財産全体の1/2。
ただし、法定相続人が父母(または祖父母)のみの場合だけは、遺留分が1/3になります。
全体の遺留分を、法定相続の分割割合に基づいて遺産を分割します。
ただし、兄弟姉妹には遺留分の相続権はありません。
| 相続人 | 全体の遺留分 | それぞれの遺留分 | |||
| 配偶者 | 子ども | 父母 | 兄弟姉妹 | ||
| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | - | - | - |
| 配偶者と子ども | 1/2 | 1/4 | 1/4 | - | - |
| 配偶者と父母 | 1/2 | 1/3 | - | 1/6 | - |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | - | - | なし |
| 子どものみ | 1/2 | - | 1/2 | - | - |
| 父母のみ | 1/3 | - | - | 1/3 | - |
| 兄弟姉妹のみ | なし | - | - | - | なし |
遺言書がなければ法定相続を行う
遺言書がない場合は、相続人で遺産分割協議を行いますが、基本的には民法で定められている法定相続分に基づいて遺産を分割します。
それぞれの相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。
配偶者と親が相続人の場合は、配偶者2/3、親1/3。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。
配偶者は相続で優遇措置を受けられる
配偶者には、相続の際に以下のような優遇措置があります。
小規模宅地等の特例
配偶者が居住している住宅を相続する場合「小規模宅地等の特例」により評価額を80%減額可能です。
通常、小規模宅地等の特例を受けるには厳しい条件が必要ですが、配偶者の場合は無条件で適用されます。
たとえば、評価額5,000万円の不動産を相続する場合、特例の適用により評価額は1,000万円となり、相続税を節約できます。
ただし、特例措置を受けることのできる限度面積(住宅の場合)は、330平方メートルまでです。
330平方メートルを超える部分に対しては、通常の評価額の計算が適用されます。
参考:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
配偶者居住権
配偶者居住権は、亡くなった人が所有していた住居に配偶者がそのまま住み続けられる権利です。
所有権を相続しない場合でも、そのまま住み続けることが可能です。
たとえば、夫婦とも高齢で「妻には血縁者がいない」「夫には兄弟姉妹がいる」「夫婦が居住している住居を夫が所有している」ケースでは、以下のようなメリットがあります。
夫の亡くなった後、妻がそのまま住宅を相続すると、妻が亡くなった場合、相続人がいなければ、住居は国に所有権が移転します。
しかし、夫の兄弟姉妹に相続させて妻が配偶者居住権を取得すれば、妻は亡くなるまで住み続けることが可能です。
この場合、妻の亡くなった後は、夫の兄弟姉妹が住宅を所有できます。
参考:民法 | e-Gov 法令検索「第八章 配偶者の居住の権利」
おしどり贈与
「おしどり贈与」は、正式名称を「贈与税の配偶者控除」といいます。
結婚している期間が20年以上であれば、居住用住宅の贈与のための贈与税が2,000万円まで非課税にできる制度です。
贈与の場合、おしどり贈与による配偶者控除と基礎控除110万円を合わせて、2,110万円が非課税になります。
居住している住宅の贈与の場合だけでなく、住宅の購入資金を贈与する場合にも適用されます。
制度の適用を受けるには、以下のような条件を満たしていなければなりません。
・自宅または自宅の購入資金の贈与である
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、当該居住用不動産に住み始めている
・同一の夫婦間では一度限り
夫婦のどちらかに財産が偏っている場合、おしどり贈与を適用することで相続税を節約できます。
多くの財産がある場合、亡くなってからの相続では多額の相続税を支払わなければならない可能性がありますが、生前にこの制度を利用しておけば、2,000万円までは贈与税が非課税です。
ただし、贈与を受けた方が先に亡くなった場合、相続税がかかる場合があるので注意が必要です。
また、手続きには戸籍謄本や不動産の登記事項証明書などを添付する必要があります。
それらの書類の取得費用や、税理士・弁護士などへ依頼する場合はその報酬が必要となる点にも留意しておきましょう。
参考:国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
子なし夫婦の相続で考えられるトラブル
子どもがいない夫婦の場合、相続時に以下のようなトラブルが発生する可能性があります。
他の相続人との遺産分割協議が進まない
配偶者以外に法定相続人がいる場合、配偶者が単独で遺産の処理を進めることはできません。
他の相続人と遺産分割協議を行い、相続財産の分け方を決める必要があります。
しかし、配偶者と故人の親や兄弟姉妹などの血族相続人との関係が良好でない場合、協議がなかなか進まないことがあります。
場合によっては、兄弟姉妹と疎遠で連絡を取ること自体が難しいケースも考えられます。 それでも、相続分を決定するためには必ず遺産分割協議を行わなければなりません。
もし協議が整わない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになります。
分割が難しい不動産の相続のしかたが決まらない
不動産など、分割するのが難しい遺産の分割方法を巡って、協議がまとまらない可能性があります。
特に遺産のほとんどが自宅不動産の場合、配偶者がそのまま自宅に住み続けるためには、他の相続人に対して、相続分に相当する金銭(代償金)を支払わなければなりません。
それができなければ、自宅を売却することになってしまいます。
子なし夫婦の相続対策
子どもがいない夫婦の場合、以下のような相続対策を検討すると良いでしょう。
遺言書の作成
子どものいない夫婦の相続対策として、最も重要なのは遺言書の作成です。
遺言書を作成すれば、本人(被相続人)の希望通りに遺産を相続できます。
遺産をすべて配偶者に相続することも可能です。
ただし、法定相続人から遺留分を請求されるケースがあります。
遺留分の請求権は、第1順位(子ども)と第2順位(親または祖父母)だけで、第3順位(兄弟姉妹)には遺留分はありません。
相続手続きが複雑な場合は、遺言書の中で遺言執行者(遺言執行人)を指定しておくと安心です。
配偶者への生前贈与
配偶者に生前贈与して遺産を少なくすることで、相続のトラブルを回避でき、相続税対策にもなります。
生前贈与で贈与税をかからないようにする方法として、暦年贈与とおしどり贈与があります。
暦年贈与は、年間110万円までは贈与税が控除される仕組みで、配偶者でなくても可能です。
毎年110万円ずつ贈与することで、相当額の財産を非課税で贈与できます。
ただし、亡くなるまでの直近7年間の贈与は相続とみなされるので、節税のために生前贈与を行うのであれば、なるべく早めに始めるほうが良いでしょう。
生命保険の契約
生命保険は遺産ではないので、相続の対象にはなりません。
配偶者を生命保険金の受取人にしておくと、血族相続人に遺留分を請求された時などにも対応できます。
生命保険金にも税金がかかりますが、法定相続人であれば1人当たり500万円までは非課税です。
この適用を受けるためには、契約者(保険料を払う人)と被保険者が同じでなければなりません。
夫が契約者かつ被保険者、受取人が妻の場合、夫が亡くなると妻が受け取る保険金のうち500万円まで非課税となります。
また、夫が契約者で被保険者が妻、受取人を夫にしている場合は、妻が亡くなった時に夫が受け取る保険金の全額が所得税や住民税の対象です。
家族信託の検討
家族信託とは、財産を家族に託して管理・運用・処分してもらう制度です。
たとえば夫が自宅の所有者で妻が認知症の場合、家族信託の制度を活用することで夫の亡くなった後も、妻がそのまま自宅に住み続けられます。
夫を委託者、妻を受益者、夫の親族を受託者にして、夫が亡くなった後も希望通りに自宅を管理することが可能です。
ただし、財産の所有者自身が認知症などで判断能力がない場合は、家族信託は利用できません。
【関連記事】
終活やることリスト11選|何から始めるか・いつからがいいか解説
子なし夫婦が相続のための遺言書を作成する際の注意点
せっかく遺言書を作成しても、無効になるケースがよくあります。
遺言書を作成する際には、以下のようなポイントに注意してください。
遺留分を考慮する
法定相続人には遺留分があります。
子どもがいない夫婦でも、亡くなった人(被相続人)の親は遺留分を請求できます。
つまり、遺言書で全財産を配偶者に相続させると書いていても、遺留分を請求される可能性があるので注意が必要です。
父母の遺留分の割合は1/6、兄弟姉妹には遺留分はありません。
「全財産をすべて配偶者に相続させる」といった遺留分を侵害している条件でも、遺留分侵害請求がなければ遺言書の内容は有効です。
なお、遺留分侵害請求の時効は1年です。
公正証書遺言にする
遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は簡単に作成できますが、要件を満たしていないと無効となるケースもあるので注意しなければなりません。
公正証書遺言は公証人が作成する遺言で、公証役場で原本が保管されるため、偽造や紛失の心配がないので安心です。
費用と手間はかかりますが、できれば公正証書遺言にするのが望ましいでしょう。
家族とよく相談する
元気なうちに、どのように遺産相続をするかを家族(法定相続人)とよく相談しておくのも大切です。
自分の希望と配偶者やその他の相続人との要望をすり合わせておくと、相続トラブルが起きる心配はなくなるでしょう。
予備的遺言を検討する
遺産を受け取るべき人が先に亡くなった場合に備えて、予備的遺言を作成することもできます。
予備的遺言とは、遺言者が相続させようと考えている人(受遺者)が先に亡くなった場合に備えて、その次に相続させる人を事前に指定しておく遺言です。
夫Aに妻Bと弟Cがいるケースで、弟Cとの仲が悪いので、全財産を妻Bに相続させようと思っていても、受遺者である妻Bが自分よりも先に亡くなった場合、遺言書がなければ弟Cが法定相続人になります。
妻Bが先に亡くなった場合には、全額をボランティア団体に寄付するなどの対応をあらかじめ遺言書の中に記載しておくことで、希望通りの相続が可能です。
子なし夫婦の相続人は配偶者と血族相続人。事前対策でトラブル防止を
子どもがいない夫婦の相続人は、配偶者と親または兄弟姉妹の血族相続人です。
亡くなってから相続人同士でトラブルにならないように、遺言書を作成したり、生前贈与を行ったりして事前に対策しておきましょう。
葬儀後の相続手続きについては弁護士や税理士に依頼すると安心ですし、終活の段階から葬儀や相続のことまでまとめて相談できる専門家もいます。
早めに相談して準備を進めることで、相続トラブルのリスクを減らしましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要