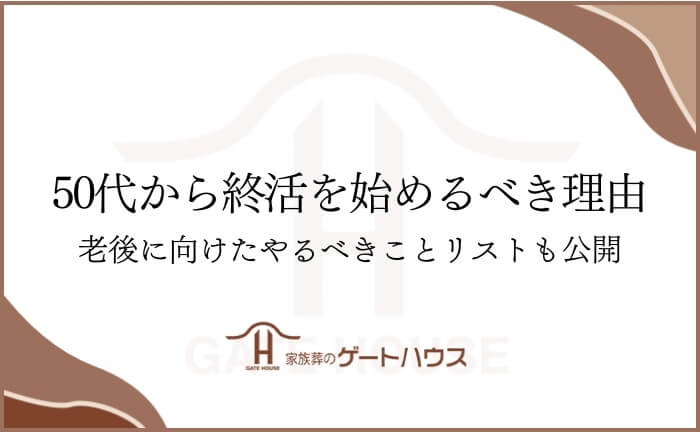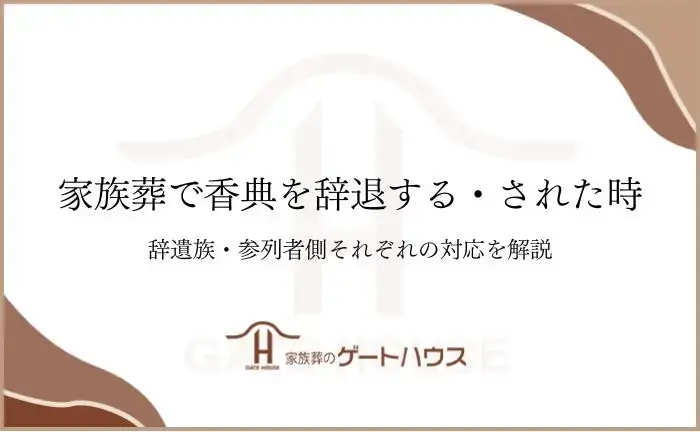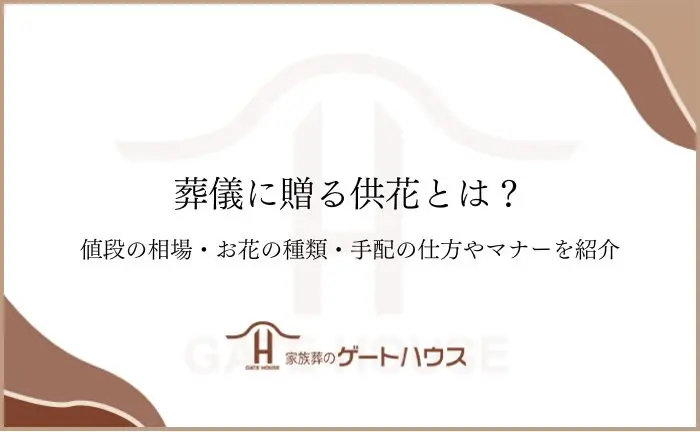墓じまいしないとどうなる?しなくていい場合やしない場合のリスクを解説
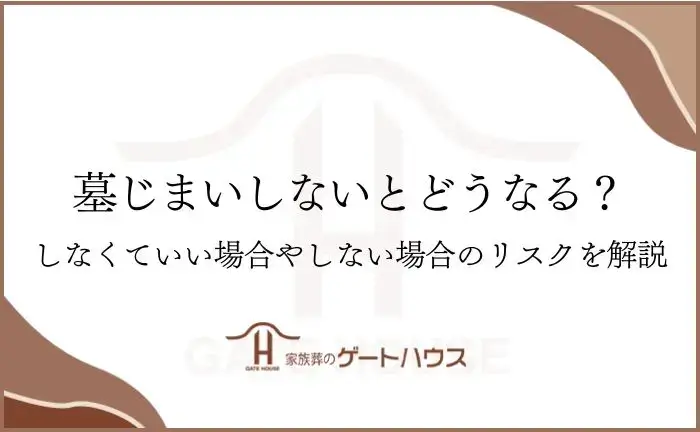
終活の一環として考えなければならないのが、墓じまいです。
しかし、費用や具体的な方法がわからず、踏み出せずにいる人も少なくないでしょう。
そこでこの記事では、墓じまいをしないとどうなるのかや、墓じまいの具体的な流れについて解説します。
墓じまいしないとどうなる?リスク一覧
墓じまいをしないまま放置してしまうと、さまざまな問題が発生する可能性があります。
【墓じまいをしないリスク】
- 管理費の督促や請求が来る
- 官報に氏名が公示される
- 墓石が撤去されご遺骨は合祀される
- お墓の管理不足によりトラブルになる
お墓の後継者がいない場合、これらの負担や責任が親戚などに及ぶこともあるため、あらかじめリスクを理解しておくことが大切です。
ここでは、墓じまいを行わなかった場合に起こりうるリスクを詳しく解説します。
【関連記事】
墓じまいとは?費用・流れや墓じまい後の手続きについて解説
管理費の督促や請求が来る
墓地にお墓があると、管理費がかかるケースがあります。
寺院・霊園など墓地を管理している場所によって金額は異なりますが、管理費用の相場は年間数千円~数万円ほど。
墓じまいをしないと永遠に管理費が発生するため、自分や家族、親族などに管理費用の請求や未納分の督促状が届く可能性が高いです。
無視すると法的な問題に発展する可能性がある他、滞納が続くと最終的にお墓は強制撤去されます。
官報に氏名が公示される
お墓の管理者が不明になり、長期間放置されていると「無縁墳墓等改葬公告」として官報に氏名が掲載される場合があります。
官報とは、内閣府が発行する国の公的な機関紙で、法律や公告が掲載される文書です。
氏名が掲載されたあと、心当たりのある人が1年以内に申し出ないと、お墓は強制撤去される可能性が高くなります。
このような掲載は、将来的に親族や関係者の間でトラブルの火種になることもあるため、早めの対処が重要です。
墓石が撤去されご遺骨は合祀される
管理費の滞納や無縁墳墓とみなされた場合、墓石は撤去され、納められていた遺骨は他の遺骨と一緒に「合葬墓(合祀墓)」へ埋葬されます。
一度合祀されると、個別に遺骨を取り出すことはできません。
また、管理者が遺骨を合祀したあとに、撤去費用などの請求が届くこともあります。
その場合、費用を請求されるのは自分自身や、関係のある親族である可能性もあります。
お墓の管理不足によりトラブルになる
墓じまいをせず、お墓の管理が長期間行われていない状態が続くと、トラブルや責任の所在を巡る問題に発展することがあります。
「後継者がいないから問題にはならない」と思われがちですが、家庭裁判所が遠縁の親族や内縁の配偶者を法的後継者と指定するケースもあります。
指定された方には、管理費や撤去費用の請求が届くほか、維持管理の責任が課せられる可能性もあります。
このような事態を避けるためにも、後継者が不在だとわかっている場合は、早めに墓じまいの検討を始めることが大切です。
墓じまいしないとどうなる?したほうがいい場合は?
墓じまいは、終活を考えはじめたタイミングで行うのがおすすめです。
その他にも墓じまいを検討したほうがいいケースはいくつかあり、この項目では具体的に5つご紹介します。
自分が高齢で管理するのが辛くなった
お墓の清掃や草むしり、遠方までの移動など、お墓の維持管理は年齢とともに負担が増していくものです。
「以前はなんともなかったことが、最近は体力的にきつい」と感じるようであれば、墓じまいを検討する時期かもしれません。
今後ますます負担が増えることを見越して、元気なうちに判断しておくことが安心につながります。
お墓を継ぐ人がいない
結婚していない、子どもがいない、あるいは子どもにお墓を託せないといった事情がある場合は、できるだけ早めに墓じまいを進めることが望ましいです。
そのまま放置すると、お墓が荒れたり、親族に管理の責任が及んだりといったトラブルにつながる可能性があります。
継承者がいないことが明らかな場合は、今のうちに次の供養先を決めておくと安心です。
子どもや孫に迷惑をかけたくない
将来的にお墓を継ぐ予定の子どもや孫がいる場合でも、できるだけ負担をかけたくないという理由から墓じまいを選ぶ方も増えています。
お墓の管理には、金銭的・時間的・身体的な負担が伴います。
もし、「自分が感じてきた大変さを、次の世代には背負わせたくない」と考えるのであれば、墓じまいも選択肢の一つです。
ただし、供養の仕方にこだわりを持つ家族もいるかもしれません。
まずは、子どもや親族としっかり話し合い、納得のうえで進めることが大切です。
管理費を負担に思っている
墓じまいをしたほうがいいケースとして、管理費が生活の負担になっている場合があげられます。
年間数千円、多ければ数万円ほどの管理費は、決して少ない金額ではありません。
また、お墓を維持するには管理費だけでなく、お墓までの交通費や清掃道具代など、諸々の雑費も発生します。
墓じまい自体にも費用はかかりますが、長期的に考えると経済的な負担は減らせるため、管理費や諸費用を負担に感じるようであれば、墓じまいを考えてもいいでしょう。
定期的に通いにくい場所にある
遠方にあるお墓の場合、移動だけで数時間〜1日かかることもあり、頻繁に通うのが難しくなってしまいます。
新幹線や飛行機を利用すれば交通費もかさみますし、乗り継ぎが多いと高齢の方にとっては体力的な負担も大きくなります。
「年に一度のお墓参りが精一杯」と感じるような場合は、アクセスのよい場所への改葬や、墓じまいを含めた見直しを検討する良い機会です。
墓じまいしないとどうなる?しなくていい場合は?
基本的には、お墓を誰かが管理し続ける必要があるため、将来的に墓じまいを検討するケースがほとんどです。
しかし、下記のような例外に当てはまる場合は、自分で墓じまいの手続きをしなくても問題ないことがあります。
まずは、ご自身の状況が以下のケースに該当するかどうかを確認してみましょう。
墓地管理者が墓じまいをしてくれる場合
お墓が有期間墓地である場合、自分で墓じまいをする必要はありません。
有期間墓地とは、墓地の使用期間があらかじめ決まっている墓地のこと。
一般的なお墓は管理費を支払い続ける限り使用できますが、有期間墓地は使用する期間を決めたうえで契約し、期限が来ると永代供養墓に埋葬されます。
つまり使用期間終了後は墓地管理者が墓じまいをしてくれるため、自分では墓じまいをしなくていいのです。
ちなみに、使用期間は必要に応じて延長できる場合もあります。
永久墓の場合
お墓が永久墓である場合も、墓じまいをしなくていいケースです。
永久墓とは、お墓の維持を親族などの関係者ではなく、墓地の管理者が行うお墓のことで、永代供養の一種です。
一般的なお墓のような墓石タイプや、他の人と一緒に埋葬される合祀タイプ、納骨堂に納めるタイプなど、様々な種類があります。
永久墓の場合は名前の通り半永久的に維持・管理されるため、親族の誰かが管理をする必要も、墓じまいをする必要もありません。
墓じまいの手続きの流れ
墓じまいは複数の手続きや関係者との調整が必要になるため、あらかじめ流れを把握しておくことがトラブル防止にもつながります。
-
-
1.他の親族・管理者の同意を得る
- 2.必要書類を用意する
- 3.新しい納骨先から受け入れ証明書を貰う
- 4.改葬許可証を得る
- 5.閉眼供養をする
- 6.墓石を撤去する
- 7.新しい納骨先に納骨する
-
他の親族・管理者の同意を得る
墓じまいをすると決めたら、まずは他の親族からの了承を得ましょう。
合意がないまま墓じまいをすると、後に大きなトラブルに発展する可能性があります。
事前に親族からの合意を得られれば、それぞれが気持ちを整理できるほか、墓じまいの手続きや費用の分担もできるかもしれません。
また、親族だけでなく管理者の同意を得ることも重要です。
寺院墓地であれば住職、公営墓地であれば管理事務所に連絡しましょう。
必要書類の用意
墓じまいを決めたら、埋葬証明書や承諾書などの各種必要書類を用意しましょう。
必要書類は地域によって異なるため、墓じまいをすると決めたら、まずは各自治体のホームページにアクセスし、必要な書類を確認してください。
また、書類は一箇所からまとめて発行できるわけではなく、これまで使用していた墓地や、新しい納骨先など、複数の箇所から発行してもらう必要があります。
墓じまいをスムーズに進めるためにも、必要書類がわかったら関係各所へ速やかに連絡を入れましょう。
受入証明書および改葬許可証の入手
自治体を問わず必要な書類が、新たな納骨先から発行してもらう「受入証明書」と、墓地がある市区町村から発行してもらう「改葬許可証」です。
受け入れ証明書に関しては新しい納骨先が見つからないと発行してもらえないため、墓じまいを決めたら、できるだけ早く納骨先を探しましょう。
改葬許可証は窓口や郵送で取り寄せられる他、ホームページからダウンロードできるケースも増えているため、自治体のホームページを確認してみてください。
閉眼供養および墓地の撤去・改葬
一般的に、墓じまいをする場合は閉眼供養を行います。
閉眼供養とは、お墓から魂を抜き出すことを目的とした供養方法の一つです。
時間と費用がかかるため「しなくてもいい」と考える人もいますが、閉眼供養を行っていないと墓じまいを受け付けない業者もいるため注意しましょう。
墓地を撤去する際、寺院墓地の場合はお墓を管理者である住職に、その他の場合は石材店や新たな納骨先の管理者に問い合わせてみてください。
墓じまいに関するよくある質問
墓じまいの経験がある人は少ないため、相談できる相手に出会う確率も少ないでしょう。
そこで、これまでに墓じまいを検討した人から挙げられた質問を紹介します。
墓じまいをご検討中の方は参考にしてください。
お墓をほったらかしにするとどうなる?
墓じまいの必要があるにも関わらずお墓をほったらかしにした場合、お墓はそのまま放置される可能性が高いです。
墓石を解体し更地にするにはそれなりの費用がかかるため、管理者に十分な予算がない場合、墓石は放置され荒れ果ててしまうでしょう。
また、お墓をほったらかして管理費を滞納している場合は、管理者から訴えられる可能性もあります。
墓じまいの費用はどれくらいかかる?
墓じまいにかかる費用は、20万〜70万円程度が一般的な相場です。
内訳としては以下のようなものがあります。
-
-
墓石の撤去費用:10〜15万円前後
- 閉眼供養のお布施:3〜10万円程度
- 離檀料(寺院墓地の場合):5〜20万円程度
-
お布施や離檀料は地域や寺院の慣習によって異なりますし、墓地の立地や墓石の大きさによっては費用が高くなることもあります。
また、寺院によっては離檀料がかからない場合もあるため、事前に問い合わせて確認するのがおすすめです。
墓じまいをするタイミングはいつがいい?
墓じまいをするタイミングとしておすすめなのは、お墓の管理を負担に感じた時です。
高齢になるにつれてお墓へ出向くことや、お墓を掃除をすることが、体力的に辛く感じることでしょう。
墓じまいをするのも体力的・金銭的な負担になる可能性が高いため、お墓の管理が辛くなった時点で墓じまいをするとスムーズといえます。
墓じまいのタイミングに明確な決まりはないため、家族・親族と話し合ったうえで、最適な時期を決めてください。
墓じまいをしないと様々なリスクがある。迷ったら放置せずにご相談を
お墓を放置したままにすると、お墓が荒れ果てるだけではなく、管理費を滞納して金銭的なトラブルに発展したり、官報に名前が公示されたりと、様々なリスクがあります。
墓じまいを行うタイミングに決まりはありませんが、体力的に余裕があるタイミングで行うとスムーズです。
お墓をどうすべきか迷ったらそのまま放置するのではなく、早いうちに墓地の管理者や行政など、関係各所に相談しましょう。
【終活についてはこちら】
終活やることリスト11選|何から始めるか・いつからがいいか解説
50代から終活を始めるべき理由とは?老後に向けたやるべきことリストも公開
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要