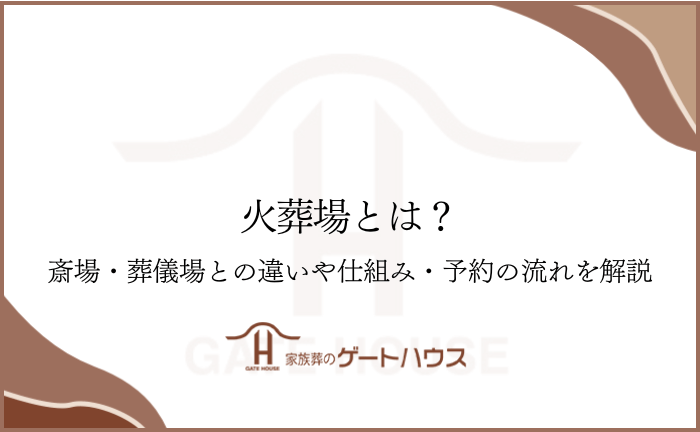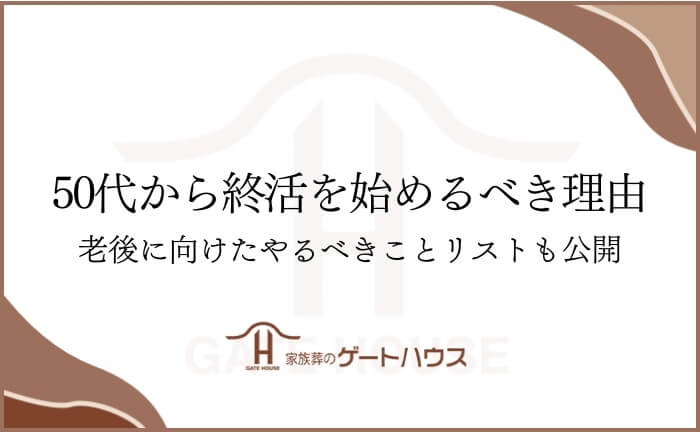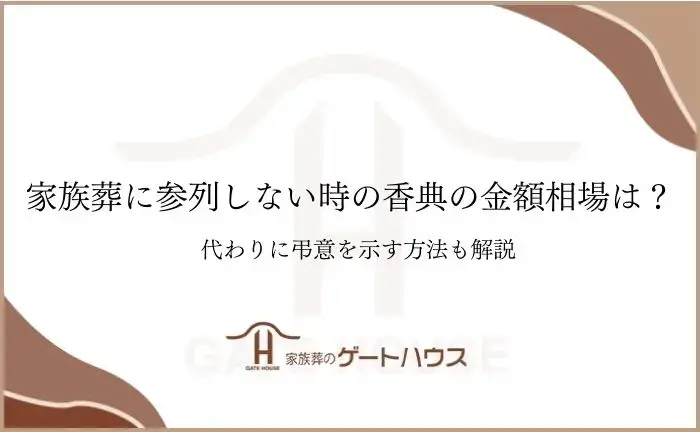亡くなった人の預金をおろすには?口座凍結前・後の手続きや必要書類を解説
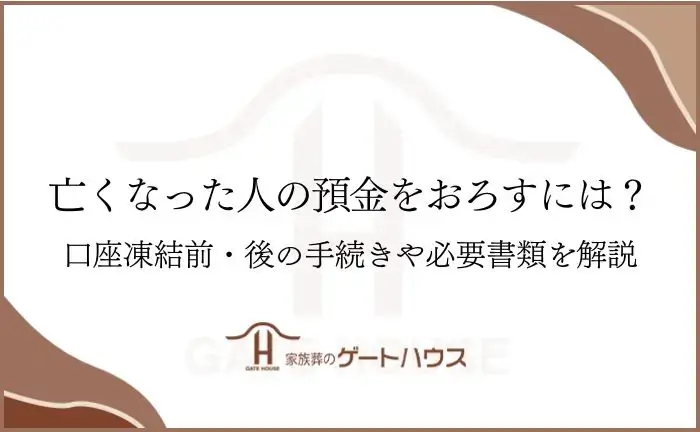
口座の名義人が亡くなったことを銀行が知ると、口座は凍結されて入出金ができなくなります。
とはいえ、やむを得ない事情で故人の口座のお金が必要になるケースもあります。
しかし、凍結口座の預金をおろすには、十分注意しなければなりません。
戸籍関係の書類をそろえる必要があり、むやみに引き出すと後でトラブルになる可能性もあります。
本記事では、亡くなった人の口座預金をおろす方法を、口座凍結時と凍結解除時に分けて詳しく解説します。
亡くなった人の預金をおろすには手続きが必要
預金口座の名義人が亡くなると、遺族は銀行に連絡しなければなりません。
銀行が死亡を確認した時点で、口座は凍結され、引き出しや振込などの取引ができなくなります。
「銀行に連絡しなければ引き出せるのでは」と考える方もいるかもしれませんが、そのような行為は後に遺産の使い込みや相続トラブルにつながる可能性があるため、避けるべきです。
凍結された口座から預金を引き出すには、相続人による手続きが必要です。
遺産分割協議が済んでいるかどうかにかかわらず、戸籍・通帳・印鑑・本人確認書類などをそろえたうえで、銀行所定の書類を提出する必要があります。
亡くなった人の預金をおろす方法|遺産分割前(口座凍結中)
相続人の間で遺産分割協議がまとまっていない場合、亡くなった人の口座から預金をおろすのは簡単ではありません。
とはいえ、故人が生計の主な担い手であった場合などは、どうしてもお金が必要となるケースも考えられます。
このような場合のために、遺産分割協議がまとまっていなくても、凍結されている口座から預金をおろす方法があります。
預貯金の仮払い制度を利用する
預貯金の仮払い制度によって、遺産分割協議がまとまる前でも、一部の預金の引き出しが可能です。
引き出せる金額は「相続開始時の預金残高×1/3×法定相続分」で、最大150万円まで。
それぞれの金融機関ごとに、限度額まで引き出せます。
引き出しに必要な書類は、主に以下の3種類です。
・相続人全員の戸籍謄本あるいは全部事項証明書
・預金の払い戻しを希望する人の印鑑証明書
参考:民法 | e-Gov 法令検索「(遺産の分割前における預貯金債権の行使)第九百九条の二」
家庭裁判所に払い戻しを申し立てる
上記の払戻し制度よりもお金が必要な場合、家庭裁判所に「預貯金債権の仮分割の仮処分」を申し立てることで、より多額のお金を引き出せます。
預貯金債権の仮分割の仮処分は、どうしても凍結口座のお金が必要な場合、必要な条件を満たしていれば、家庭裁判所に申請することで口座のお金を引き出せる制度です。
この制度を利用してお金を引き出すには、以下の要件を満たしていなければなりません。
・生活費の支払いや相続財産に含まれる債務の返済など、仮処分の必要性がある
・他の共同相続人の利益を害する恐れがない(原則として引き出しを希望する相続人の法定相続分が上限金額)
申し立てには、遺産の全体がわかるような書類や戸籍関係の書類など多くの書類が必要です。
申し立てがあると、裁判所はすべての共同相続人に対して陳述を聴取しなければなりません。
そのため、仮処分が認められるまでに最低でも1〜2ヵ月程度の期間が必要です。
亡くなった人の預金をおろす方法|口座凍結の解除
遺言書があったり、遺産分割協議がまとまったりした場合は、手続きを行うことで口座の凍結を解除できます。
解除手続きに必要となる書類は、遺言書の有無などによって異なります。
また、銀行によっても手続きの方法や必要書類は異なるケースがありますが、一般的に必要となる書類は以下のとおりです。
遺言書あり・遺言執行者ありの場合
遺言執行者とは、遺言の執行に必要となる権利と義務を有する人です。
遺言の内容を実現するために、相続財産の適切な管理などを行います。
相続人のひとりが遺言執行者になっているケースも珍しくありません。
遺言書があり、遺言執行者がいる場合に必要となる書類を以下に示します。
| 遺言書 | 原本が必要 |
| 通帳 | キャッシュカード、貸金庫の鍵なども含む |
| 検認済証明書 | または検認調書が必要 |
| 戸籍謄本など | 被相続人とすべての相続人を確認できる書類(法務局が発行する法定相続情報一覧図の写しなどでも可) |
| 印鑑証明書 | 遺言執行者と預金を相続する人の印鑑証明書 |
| 遺言執行者の選任審判書謄本 | 遺言執行者が家庭裁判所によって選任されている場合に必要 |
相続人に遺言書の存在とその内容を知らせること
「検認済証明書」は、遺言書が家庭裁判所により検認済であることを証明する書類です。
検認手続きでは、まず相続人に対して遺言書の存在とその内容が通知されることが目的です。
これにより、相続人は遺言の存在や内容を把握することができます。
遺言書の形状や署名の有無などを確認し、偽造・変造を防ぐこと
検認手続きでは、遺言書の状態(形状・日付・署名の有無など)を裁判所が確認し、 偽造や変造の可能性がないかを確認します。
検認済証明書は、遺言書のコピーとともにホチキス留めされて発行され、銀行はこれを見て遺言書の正当性を判断します。
なお、遺言書が公正証書遺言である場合や、自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、検認手続きは不要です。
また、以下のようなケースでは「検認調書」や「遺言執行者の選任審判書謄本」が必要になることもあります。
-
遺言書の原本を紛失した場合:裁判所に申請すれば「検認調書謄本」の交付が受けられます。
- 遺言書に遺言執行者の指定がない場合:家庭裁判所に申し立てることで、遺言執行者を選任してもらうことが可能です。
遺言執行者の選任審判書謄本は、遺言執行者が法的に選任されたことを証明する書類であり、
金融機関での手続き時に提出が求められることがあります。
ただし、遺言書内で遺言執行者が明記されている場合は、改めて審判書を提出する必要はありません。
遺言書あり・遺言執行者なしの場合
遺言書があり、遺言執行者がいない場合に必要となる書類は以下のとおり。
上記の「遺言書あり・遺言執行者あり」の場合とほとんど同じですが、遺言執行者の選任審判書謄本と遺言執行者の印鑑証明書は必要ありません。
| 遺言書 | 原本が必要 |
| 通帳 | キャッシュカードや貸金庫の鍵なども含む |
| 検認済証明書 | または検認調書 |
| 戸籍謄本など | 被相続人とすべての相続人を確認できる書類(法務局が発行する法定相続情報一覧図の写しなどでも可) |
| 印鑑証明書 | 預金を相続する人の印鑑証明書 |
遺言書なし・遺産分割協議書ありの場合
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合、口座の凍結を解除するために提出する書類は以下のとおり。
凍結口座の資金を、誰にどれくらい支払うかを確認するために、遺産分割協議書が必要です。
| 遺言分割協議書 | 原本が必要 |
| 通帳 | キャッシュカードや貸金庫の鍵なども含む |
| 戸籍謄本など | 被相続人とすべての相続人を確認できる書類(法務局が発行する法定相続情報一覧図の写しなどでも可) |
| 印鑑証明書 | 相続人全員の印鑑証明書 |
遺言書なし・遺産分割協議書なしの場合
遺言書も遺産分割協議書もない場合、一般的には以下の書類が必要です。
ただし、この場合に必要となる書類は、金融機関によって大きく異なる傾向にあります。
詳しくは、金融機関にご確認ください。
| 通帳 | キャッシュカードや貸金庫の鍵なども含む |
| 戸籍謄本など | 被相続人とすべての相続人を確認できる書類(法務局が発行する法定相続情報一覧図の写しなどでも可) |
| 印鑑証明書 | 相続人全員の印鑑証明書 |
参考:裁判所「遺言書の検認」
民法 | e-Gov 法令検索「第四節 遺言の執行」
亡くなってからすべての預金をおろすまでの手続き・必要書類
亡くなった直後から、最終的に口座の預金を相続するまでの手続きを順に解説します。
手続きの方法や必要となる書類は金融機関によって多少異なりますが、大手銀行の一般的な流れは以下のとおりです。
亡くなったことの連絡
家族が亡くなった場合、亡くなったことを速やかに銀行に連絡する必要があります。
連絡は、銀行ごとに行わなければなりません。
ただし、同じ銀行の複数支店に口座がある場合は、1つの支店に連絡すればすべての口座が凍結されるので、すべての支店に連絡する必要はありません。
連絡手段は銀行によって異なり、電話やWebでも可能な場合もあります。
連絡すると、銀行から相続手続きの案内書などが送られてきます。
必要な書類の準備
各銀行の手続き方法に従い、必要書類を準備しましょう。
相続確認表は、窓口での取得、もしくはネットからダウンロードできます。
たとえば、ゆうちょ銀行の場合「相続確認表」の準備・提出を行い、その後必要書類を提出する流れになります。
必要となる書類は、遺言書の有無や相続人の数などによって異なるので注意しましょう。
必要な書類の提出
必要な書類を準備し、銀行の窓口または郵送で書類を提出します。
なお、遺言書・戸籍謄本などは原本での提出を求められることが多いため、注意してください。
郵送の場合は、銀行がコピーをとって、原本が送り返されてきます。
また、相続税の申告などをする際には、残高証明書や預金入出金取引証明が必要となるケースがあります。
銀行に必要書類を提出する時に、これらの書類の発行を依頼しておくと良いでしょう。
預金の払い戻し
書類に不備がなければ、指定した銀行口座に相続預金が振り込まれます。
書類の提出からおおむね2〜3週間で払い戻しされ、手続き完了です。
亡くなった人の預金をおろす際に注意すべきポイント
亡くなった人の預金をおろす際には、様々な点に注意する必要があります。
銀行への連絡時期は慎重に
家族が亡くなったことを銀行に伝えると、その時点で故人名義の預金口座は凍結されます。
凍結されると、預金の引き出しだけでなく、入金や公共料金の引き落とし・年金の振り込みなどもできなくなるため注意が必要です。
故人の口座から公共料金などを引き落としていた場合、口座を凍結する前に引き落とし先を変更する必要があります。
預金を引き出すと相続放棄できない
相続する財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどマイナスの財産も含まれます。そのため、負債の方が多い場合には、相続放棄という選択肢を検討することもあります。
しかし、故人の預金を引き出してしまうと「相続財産を処分した」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。これは民法上「単純承認」と呼ばれ、一度でも相続の意思を示したと判断されると、放棄の手続きができなくなってしまいます。
相続放棄を希望する場合は、遺産に手を付けず、亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で正式な手続きを行いましょう。
他の相続人に無断で引き出さない
たとえ葬儀費用や生活費のためであっても、他の相続人に無断で故人の口座からお金を引き出すのは避けましょう。
相続財産は法的に「相続人全員の共有財産」となるため、一部の人が単独で使うことは、相続トラブルの原因になります。
どうしても故人の預金を使う必要がある場合は、あらかじめ相続人全員で話し合い、同意を得てから引き出すようにしましょう。
また、一定の条件を満たせば「預貯金の払戻し制度(民法909条の2)」を利用して、遺産分割協議が終わる前でも法定相続分に応じた金額を一部引き出すことができます。
ただし、その範囲を超えての引き出しは認められません。
民法 | e-Gov 法令検索「第四章 相続の承認及び放棄」
亡くなった人の預金に関するよくある疑問
亡くなった人の預金相続に関してよくある疑問にお答えします。
亡くなったことは役所から銀行へ連絡される?
亡くなったことは個人情報なので、役所が無断で銀行に連絡することはありません。
基本的に、家族が連絡しない限り口座は凍結されませんが、銀行員が新聞のお悔やみ欄で亡くなったことを知って、口座を凍結する場合もあるようです。
死亡を連絡しないで故人の口座からお金を引き出すのは罪になる?
口座の名義人が亡くなったことを銀行に連絡せずにお金を引き出しても、刑事事件になる可能性は低いでしょう。
しかし、他に法定相続人がいる場合、トラブルになって民事訴訟を起こされる可能性があります。
どうしてもお金が必要な場合は、他の相続人とよく相談し、預貯金の払戻し制度などの正当な手続きで引き出すようにしましょう。
故人の預金をおろす際は十分注意を。必要な場合は仮払い制度の利用を
故人の預金口座は、凍結されて入出金ができなくなります。
とはいえ、どうしても必要な場合は、仮払い制度を利用して一定限度額までは引き出せます。
引き出す際には、後でトラブルにならないように注意しなければなりません。
口座の凍結を解除して預金を相続する際には、様々な書類が必要で、手続きが完了するまでに1〜2ヵ月の期間が必要です。
なるべく早く相続するためには、他の相続人とよく相談することが重要です。
【相続や遺品整理についてはこちら】
親が亡くなった時の手続き一覧表|家族や身内の死亡後にすることを順番に解説
遺産相続での預貯金の分け方とは?相続前の準備や分割時の注意点を解説
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要