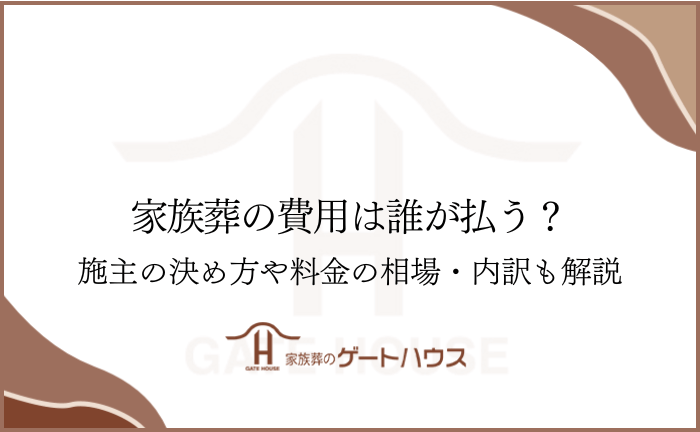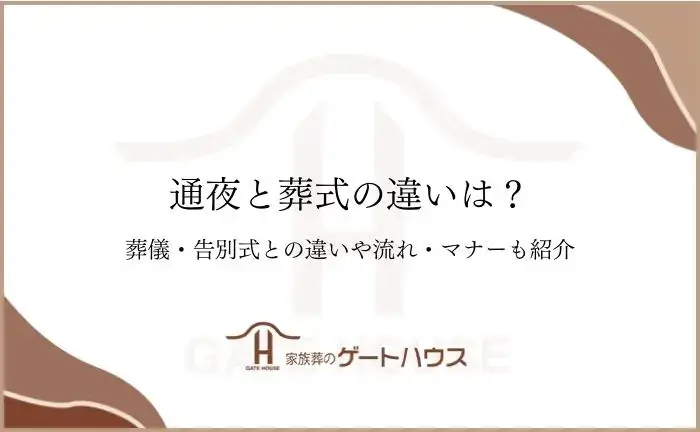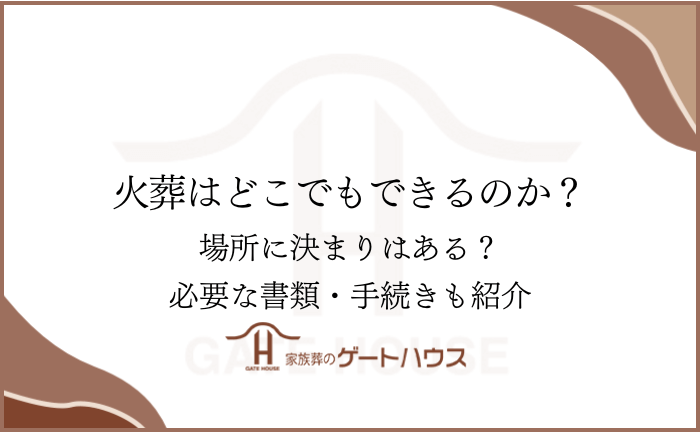喪中はがきが届いたら返事はどうする?マナーや状況別の文例などを解説
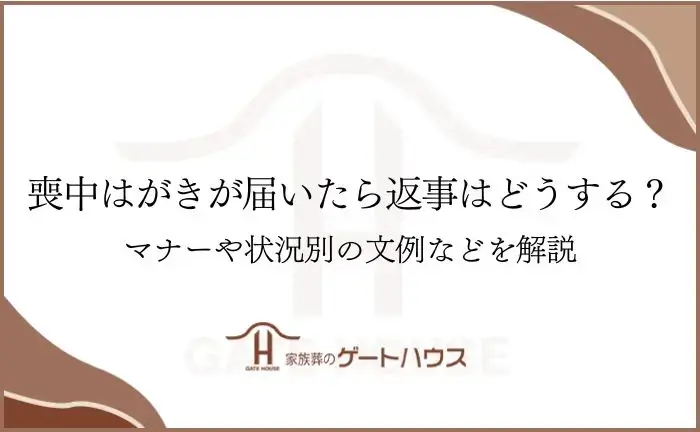
知人から喪中はがきが届いたら「返事はどうすればいいのかな」と悩む人も少なくありません。
心を痛めているご遺族を傷つけることのないよう、マナーを守ってお悔やみの言葉を伝えたいものですよね。
この記事では、喪中はがきが届いた時の返事のマナーや、状況別の文例などをご紹介します。
喪中はがきが届いたらどうする?
喪中はがきが届いたら、その人には年賀状を出さないのが慣習となっています。
喪中はがきには、ご遺族が「新年のご挨拶を控えます」というお知らせの意味があり、年賀状を受け取るだけなら問題ありません。
しかし、家族を亡くして悲しみに暮れ、新年を喜ぶ気にもなれない人に祝いの言葉が入った年賀状を送るのは、相手を不快にさせてしまう可能性があります。
相手の心を気遣うという意味でも、喪中の人には年賀状を送るのを控えましょう。
喪中はがきが届いたら返事はどうする?
一般的に「喪中はがきが届いたら返事を出さなければいけない」という決まりはありません。
ご遺族との関係性によっては、喪中はがきへの返事を送ることで、余計に気を遣わせてしまう可能性もあります。
故人やご遺族との関係性があまり親しい間柄ではない場合は、返事は控えておくことが多いです。
しかし、相手との関係性が親しい場合は、哀悼の意を表すとともにご遺族の心に寄り添うという意味を込めて、返事を送った方がいいでしょう。
ここでは、喪中はがきが届いた時の返事の仕方を解説します。
寒中見舞い
寒中見舞いは、喪中はがきが届いた場合の返事として、多く選ばれている方法です。
本来、寒中見舞いとは、年末年始の慌ただしさが落ち着いた時期に、相手の健康を気遣うために送る挨拶状のことをいいます。
送る時期は地域によってやや異なりますが、基本的には松の内が明ける日(1月8日または1月15日)から立春までに出すのが一般的です。
通常の寒中見舞いでは、文章内に自分の近況報告を添えることが多いですが、喪中の人に送る場合は控えましょう。
主に故人へのお悔やみの言葉や、ご遺族への気遣いを込めた文章を送ります。
喪中見舞い
喪中はがきが届いた後、すぐに故人への哀悼の意を伝えられるのが喪中見舞いです。
基本的には、喪中はがきを受け取ってからすぐに用意するのが一般的で、年内までには相手に届くよう送りましょう。
また、年末に年賀状を出した後、行き違いで喪中はがきが届いてしまった場合も喪中見舞いを出します。
その場合、お悔やみの言葉に加え、年賀状を出してしまったことへのお詫びの気持ちを添えて、年内には喪中見舞いが届くように急いで準備するのがマナーです。
年始状
年始状は、新年の挨拶のみを伝えるために出す挨拶状です。
本来は自然災害などで被災した人に向けて出すものでしたが、近年では喪中はがきが届いた時の返事としても使われるようになりました。
年始状には、お世話になったことへのお礼や、引き続きお付き合いをお願いする言葉を添えるのが一般的です。
年始状を送る相手に決まりはありませんが、ご遺族との関係性が親しい場合が多いでしょう。
送る時期は、元旦から松の内までの日(1月7日または1月15日)までに届くように送ります。
【関連記事】
喪中はがきはいつ出す?文例や書き方・誰に出すかも解説
喪中はがきが届いたら?返事のマナーは?
喪中はがきへの返事を送る場合は、受け取るご遺族の気持ちを十分に考え、言葉やマナーに注意することが大切です。
ここでは、喪中はがきが届いた時の返事のマナーを解説します。
返事に関するマナーは、寒中見舞い・喪中見舞い・年始状のいずれにも該当するので、よくチェックしてから送りましょう。
祝い事を表す言葉は使わない
喪中は、ご遺族が喪に服す期間とされています。
当然ではありますが、喪中はがきへの返事で、祝い事を表す言葉を使うのは避けましょう。
返事で年頭の挨拶を述べる場合も「明けましておめでとうございます」「謹賀新年」など、新年を祝う言葉はNG。
年頭の挨拶を控える旨を記載したり、新年の挨拶のみを伝えたりするようにしましょう。
【関連記事】
喪中にあけましておめでとうは言わない?言われたらどう返す?代わりの挨拶も紹介
喪中の人に「良いお年を」と言って良い?年末の挨拶マナーや過ごし方を解説
句読点をつけない
喪中はがきへの返事に限らず、正式な挨拶状には句読点をつけないのがマナーです。
日本で句読点が使われるようになったのは明治時代からといわれており、文章をわかりやすく区切るために句読点を用いるようになりました。
句読点をつける文化の歴史は浅いため、正式な挨拶状には句読点をつけずに送るのが昔からの決まりとなっています。
また、句読点は文章を区切るという役割から「縁を切る」という意味を連想させてしまうので、避けましょう。
読みやすくしたい場合は、句読点ではなくスペースを入れてください。
はがきや切手のデザインに注意する
喪中はがきが届いた際の返事では、切手にあたる部分が胡蝶蘭になった郵便はがきを使います。
年末年始の時期に送る場合でも、年賀はがきを使うのは絶対に避けましょう。
また、弔事用の切手は、基本的にご遺族側が喪中はがきを出す時に使うものです。
返事のはがきに使う切手は、普通切手を使いましょう。
はがきのデザインにも注意し、華美なものではなく優しい色合いのはがきを使うのがマナーです。
数字は漢数字を使う
寒中見舞いや喪中見舞い、年始状は、いずれも正式な挨拶状です。
日付や住所など、数字を使う文章では必ず漢数字を用いるようにしましょう。
なお、横書きはカジュアルな印象になってしまうので、縦書きで書くのが基本的なマナーです。
忌み言葉を使わない
喪中はがきの返事では、忌み言葉を使わないように注意しましょう。
忌み言葉とは、不幸や不吉な出来事が続くことを連想させる言葉のことで、弔事のシーンではタブーとされています。
無意識に使ってしまいそうな言葉もあるので、文章が出来上がったら再度読んで確認することが大切です。
| 重ね言葉 | くれぐれも、重ね重ね 色々、段々、引き続き …など |
| 忌み言葉 | 苦しい、終わる 辛い、消える …など |
| 生死を連想する言葉 | 死ぬ、急死 生きていたころ …など |
喪中はがきが届いた時に送る返信の文例
ここでは、喪中はがきが届いた時に送る返事の文例を紹介します。
寒中見舞い・喪中見舞い・年始状に分けて文例を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
寒中見舞いの文例
寒中見舞いは、松の内が明ける日(1月8日または1月15日)から立春までに出す挨拶状です。
また、松の内が明ける日は地域によって異なるので、ご遺族が住んでいる地域に合わせるようにしましょう。
寒中見舞いでは、故人への哀悼の意を表すと同時に、ご遺族の健康を気遣う文章を入れて送ります。
寒中お見舞い申し上げます
寒い日が続いておりますが お元気でお過ごしでしょうか
◯◯様がご逝去されてから◯ヶ月がたちましたね
ご家族皆さまの寂しさが少しずつ和らいでおられますことをお祈り申し上げます
厳しい寒さが続きますので どうぞお身体を大切にご自愛くださいませ
寒中お見舞い申し上げます
ご服喪中と存じ 年頭のご挨拶はご遠慮させていただきました
お葉書を拝見して初めて◯◯様のご逝去を知り 驚きとともに大きな悲しみでいっぱいです
遅ればせながら ◯◯様のご冥福を心よりお祈り申し上げます
寒さが一段と厳しくなります折柄 何卒お身体を大切にお過ごしください
喪中見舞いの文例
喪中見舞いは、喪中はがきを受け取ってすぐ〜年末までにご遺族に届くように送ります。
まずは喪中はがきを送ってくれたことへのお礼を述べ、お悔やみの言葉とともに、新年の挨拶を控える旨を伝えるのが一般的です。
また、故人やご遺族との関係性によっては、香典やお供え物を一緒に送る場合もあります。
ご丁寧なご挨拶状をいただき ありがとうございました
〇〇様のご逝去から◯ヶ月になりますね
ご家族様におかれましては寂しい日々をお過ごしのこととお察し申し上げます
何かお役に立てることがありましたら いつでもご連絡ください
服喪期間中でいらっしゃいますので新年のご挨拶は控えさせていただきますが ◯◯様には穏やかな新しき年をお迎えになられますよう心よりお祈り申し上げます
喪中はがきで初めて知った場合の文例:
喪中お見舞い申し上げます
ご丁寧なご挨拶状をいただき ありがとうございました
年賀欠礼のお知らせをいただき 大変驚いております
遅ればせながら 〇〇様のご冥福を謹んでお祈り申し上げます
ご服喪中と存じ 年頭のご挨拶はご遠慮させていただきます
どうぞお身体を大切に新しい年をお迎えになられますよう 心よりお祈り申し上げます
香典やお供え物を一緒に送る場合の文例:
喪中お見舞い申し上げます
このたびはご丁寧なご挨拶状をいただき ありがとうございました
お手紙を拝見してご家族のご不幸を初めて知り お悔やみも申し上げず大変失礼いたしました
遅ればせながら 〇〇様のご冥福を心よりお祈り申し上げます
心ばかりのものではございますが どうぞご霊前にお供えいただければと存じます
ご家族様のご心痛のほど いかばかりかとお察しいたします
どうぞお身体を大切に 新しい年をお迎えください
年始状の文例
年始状は、元旦から松の内までの日(1月7日または1月15日)にご遺族に届くタイミングで送ります。
なお、年賀はがきの場合は12月に投函しても元旦を迎えるまで相手に届くことはありませんが、年始状は普通の郵便はがきを使います。
よって、12月に投函すると年内に届いてしまうため、年始に届くように大晦日や元旦に投函しましょう。
謹んで年頭のご挨拶を申し上げます
〇〇様のご冥福を心よりお祈り申し上げるとともに ご家族様にとって新しい年が穏やかな一年となりますことをお祈りいたします
本年もどうぞよろしくお願いいたします
新年のご挨拶を申し上げます
昨年は大変お世話になりました
また このたびはご丁寧なご挨拶状をいただき ありがとうございました
お葉書を拝見して〇〇様のご逝去を知り 大変驚いております
遅ればせながら 〇〇様のご冥福を心よりお悔やみ申し上げます
さぞかしご心痛のことかと存じますが どうぞお身体を大切に新しい一年をお過ごしになられますよう心よりお祈り申し上げます
喪中はがきが届いたら香典は送った方がいい?
喪中はがきが届いて故人の訃報を知った場合、香典を送ることを検討する人もいるかもしれません。
しかし、香典を送ると、ご遺族に対して過度に気を遣わせる可能性があります。
香典へのお礼状の作成や香典返しの準備などで、負担をかけてしまうことにもつながるので、香典を送るのは避けたほうが無難です。
とはいえ、故人やご遺族との関係性が深く、弔意を示したい人もいるでしょう。
その場合は、香典の代わりにお供え物を送るのがおすすめです。
お供え物を選ぶ際は、ご遺族に気を遣わせないくらいの金額に抑えましょう。
喪中はがきが届いたらお供えは何を送る?
喪中はがきが届いた際、喪中見舞いと一緒に送るお供え物の相場は、3,000〜5,000円といわれています。
どんなに相手との関係性が深い場合でも、相場を無視した贈り物はご遺族の負担になってしまうので、高額すぎるものは避けましょう。
最後に、喪中はがきが届いた時に送るお供え物に適した品物を紹介します。
線香・ろうそく
線香・ろうそくは、喪中見舞いのお供え物として定番の商品です。
お供え物向けの線香は、上質な香木を使っているものや灰の飛び散りが少ないものなど、通常のものとは異なります。
また、ろうそくも美しいデザインやお花が描かれているものがあり、お供え物に選ぶとご遺族にも喜ばれやすいです。
故人の雰囲気に合うものを選ぶと、心からの哀悼の意を表せるでしょう。
ただし、相手がキリスト教の場合は、線香を送るのはマナー違反なので選ばないようにしましょう。
お花
お花は故人を偲ぶとともに、ご遺族の心を落ち着かせてくれるという意味があり、お供え物としてよく選ばれています。
故人が亡くなられてから四十九日を迎えていない場合は、白色を基調としたお花のアレンジメントが最適。
四十九日を迎えているなら、淡い色が入ったお花を贈っても問題ないとされています。
ただし、毒やトゲのある花・香りが強い花はお供えにはタブーなので、選ぶ際には注意しましょう。
また、自分で花を選ぶのではなく、お供え物である旨を花屋に伝えて選んでもらったり、ネットのフラワーギフト店でお悔やみ用の商品を探したりするのもおすすめです。
お茶
仏教では、お仏壇に供えるお茶やお水のことを浄水と呼び、心を清めるという意味があるお供え物の定番となっています。
喪中見舞いに添える贈り物として選ぶ場合は、日本茶を選ぶのが無難です。
紅茶などもありますが、好みが分かれにくい日本茶を送る方が、ご遺族を困らせずに済むでしょう。
また、賞味期限に余裕のあるものを重視し、飲み比べできるものやお菓子付きのものを選ぶと、ご遺族に喜んでもらえるかもしれません。
お菓子
お菓子も、喪中見舞いと一緒に送るお供え物としてよく選ばれる品物です。
お菓子は、お供え後はご遺族に召し上がってもらえるため、気軽に送りやすいでしょう。
お菓子を選ぶ際は、日持ちするかどうか・個包装になっているかを確認することが大切です。
また、パッケージも華美なデザインではないものを選びましょう。
ネットではお供え専用のお菓子も販売されていますので、直接お店に買いに行く時間がない人は、これらを利用するのもいいかもしれません。
カタログギフト
近年では、お供え物の贈り物にカタログギフトを用いる方も増えています。
豊富な商品の中から、ご遺族が必要としているものを自分で選んでもらえるので、確実に喜んでもらえるのがメリットです。
また、お供え用のカタログギフトもあり、予算によってコースが選べるので、お供え物の相場に合ったものを送れます。
ただし、ご遺族の年代によってはカタログギフトに馴染みがない可能性があるので、相手によって送るかどうかを選ぶようにしましょう。
喪中はがきが届いたら状況にあった返事の方法を選び哀悼の意を表そう
喪中はがきが届いたら、故人・ご遺族との関係性や状況に合わせて、返事の方法を選びましょう。
基本的には、喪中はがきへの返事は出さなくてもマナー違反にはなりません。
ただし、故人との関係が深く、哀悼の意を表したい場合や、ご遺族を気遣いたい場合は、返事を送るのが思いやりのある方法でもあります。
その場合、返事のマナーに十分に注意しつつ、故人へのお悔やみの言葉を丁寧に伝えましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要