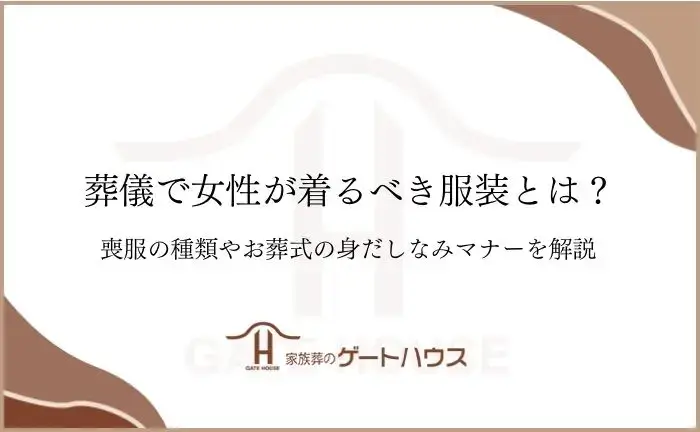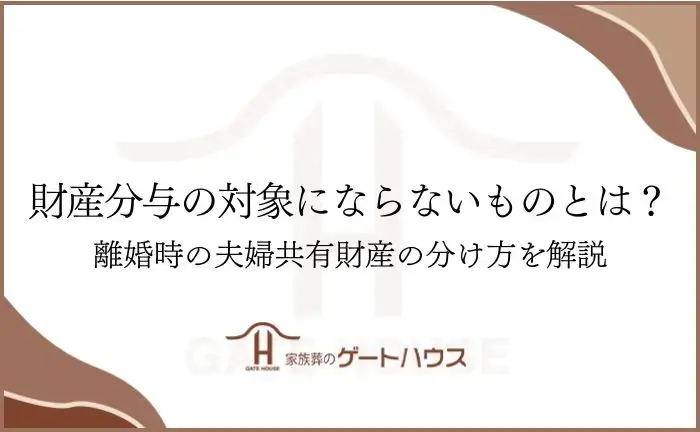遺産相続での預貯金の分け方とは?相続前の準備や分割時の注意点を解説
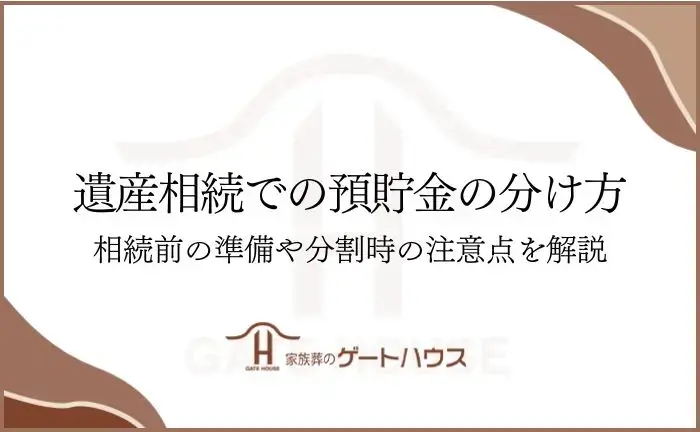
家族が亡くなった場合「遺産相続で預貯金をどのように分ければいいかわからない」「すぐに現金が必要だけれど、故人の口座からお金を引き出していいかどうかわからない」というケースがよくあります。
どのように対処すべきかは、それぞれの状況によって異なるので注意しましょう。
この記事では、遺産相続での預貯金の分け方や分ける際の準備の仕方、必要書類などをわかりやすく解説します。
遺産相続での預貯金の分け方|事前準備
遺産相続で預貯金を分ける前に「遺言書の有無」を調べ「相続人を確定」し「遺産総額を確定」する必要があります。
それぞれのステップを解説するので、参考にしてみてください。
遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合、基本的には預貯金を含めたすべての遺産を、遺言書に基づいた方法で分割しなければなりません。
ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には、法律で定められた遺留分があります。
遺留分とは、相続人に認められた遺産の最低保証金額です。
もし、遺言書の内容が遺留分を侵害するようであれば、侵害された相続人は遺留分を請求できます。
遺言書がなければ、相続人同士で遺産分割協議を行って、どの遺産を誰が相続するかを決定します。
相続人を確定する
遺言書がない場合、相続できるのは民法で定められている相続人(法定相続人)です。
配偶者は、必ず相続人になります。
配偶者以外にも、以下の順位に当てはまる人がいる場合、相続する権利があります。
| 順位 | 対象者 |
| 第1順位 | 子ども(または孫などの直系卑属) |
| 第2順位 | 親(または祖父母などの直系尊属) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(またはその子どもなどの代襲相続人) |
上位の順位の相続人がいる場合、それより下位の順位の人は相続できません。
つまり、亡くなった人に子どもがいる場合は、親や兄弟姉妹は相続の対象外です。
相続人がすでに亡くなっている場合は、その子どもが代わりに相続する権利を持ちます。
その子どもも亡くなっている場合は、孫が相続人となります。
これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
相続財産を確定する
最後に、相続の対象となる財産を確定します。
登記簿や預金通帳なども全部チェックしましょう。
亡くなった人が個人事業主だった場合、売掛金なども相続の対象です。
また、プラスの財産だけ相続して、負債を相続しないということはできません。
住宅ローンや借金などの負の財産も把握する必要があります。
さまざまな種類の遺産がある場合や、不動産などの評価額を決めなければならないものが含まれる場合は、専門家に相続財産調査を依頼すると良いでしょう。
どの専門家に頼むかは状況によりますが、税理士、弁護士、司法書士、行政書士などが候補として挙げられます。
遺産相続での預貯金の分け方|分割方法の決定
遺言書があれば、遺言書の内容にしたがって遺産を分割します。
相続人全員が合意すれば、遺言書とは異なる分割方法も可能です。
遺言書がなければ、相続人で話し合って(遺産分割協議)、各自の取り分を決定しなければなりません。
遺産に、不動産や会社の株式など分割できないものが含まれていると、協議がなかなかまとまらないケースもあります。
相続人同士の話し合いで決着がつかなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。
遺産相続での預貯金の分け方|実践
預貯金を分ける方法には、以下の3つがあります。
口座を解約して現金にする
最も公平かつ一般的な方法は、故人の預金口座をすべて解約して現金化し、決められた相続割合に応じて分割する方法です。
口座の解約・払い戻し手続きのやり方は、相続の方法や金融機関によって異なります。
詳しくは、次項の「預貯金相続時に用意する書類」をご覧ください。
通常払い戻したお金は相続人の口座に振り込んでもらいますが、それぞれの相続人の口座に分けて振り込む方法と、代表相続人の口座にまとめて振り込む方法があります。
金融機関によっては、代表相続人の口座にしか振り込まれないので注意しましょう。
口座ごとに引き継ぐ
複数の預金口座がある場合、各口座をそれぞれの相続人に割り当てて相続することも可能です。
この方法の場合、それぞれの口座を引き継ぐ相続人が個別に対応できるので、前項で解説した口座をすべて解約する方法よりも、手続きが比較的簡単です。
しかし、口座ごとに残高が異なる場合は不公平が生じるので、預貯金以外の遺産で調整する必要があります。
口座の預貯金を引き継ぐ場合、口座を解約して相続人名義の口座にお金を振り込む方法と、口座の名義を書き換える方法の2つがあります。
被相続人(故人)の口座で公共料金の引き落としなどを行っていた場合、名義変更をするとそのまま引き落とし口座として使えて便利です。
しかし、口座名義人の変更に対応していない金融機関もあるので、詳しくは銀行にお問い合わせください。
代償分割で精算する
「代償分割」とは、1人の相続人が遺産を(すべて、あるいは多めに)相続し、残りの相続人に「代償金」を支払って、相続する財産を調整する遺産分割の方法です。
代償分割は、遺産に不動産や家業の株式などが含まれる場合によく用いられます。
たとえば合計4,000万円の遺産があり、Aが評価額3,000万円の不動産を相続し、Bが預金1,000万円を相続した場合、AがBに現金1,000万円を支払うことで、相続財産の調整を図ります。
なお、代償分割には、相続人間での合意や代償金の準備が必要であるため、手続きが複雑になることや、資金的負担が生じる可能性がある点には留意が必要です。
【関連記事】
親が亡くなった時の手続き一覧表|家族や身内の死亡後にすることを順番に解説
預貯金相続時に用意する書類
預貯金を相続する時に必要な書類は、遺言書の有無などによって異なります。
さらに、銀行によって手続き方法や必要な書類はさまざまです。
預貯金の相続手続きを始める前には、必ず銀行に連絡して手続き方法や必要書類を確認してください。
ここでは、一般的に相続時に必要とされる書類を、それぞれのケースごとに紹介します。
【関連記事】
亡くなった人の預金をおろすには?口座凍結前・後の手続きや必要書類を解説
遺言書があるケース
遺言書がある場合、以下の書類などを準備します。
①遺言書
②検認調書または検認済証明書(遺言書が公正証書遺言以外の場合)
③被相続人の戸籍謄本または全部事項証明
④相続人の印鑑登録証明書
⑤その他(預金通帳、キャッシュカード、貸金庫の鍵など)
遺言執行者がいる場合は、さらに以下の書類が必要
⑥遺言執行者の印鑑証明書
⑦遺言執行者の選任審判書謄本
①の遺言書は、原本が必要です。
銀行は遺言書が原本であることを確認し、コピーをとってその場で返却してくれます。
②は、遺言書を保管、あるいは発見した相続人が裁判所に届け出て「検認」を受けることによって発行される書類です。
検認とは、遺言書の偽造・変造を防ぐために裁判所が遺言書の内容を確認し、保管する手続きです。
公正証書遺言の場合、検認調書(または検認済証明書)は必要ありません。
③は、口座の名義人が亡くなっていることを確認するために必要となる書類です。
遺言書がないケース
遺言書がない場合は、おおむね以下の書類などが必要です。
遺産分割協議書がある場合は、他の書類と一緒に提出します。
①被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
③相続人全員の印鑑登録証明書
④本人確認書類
⑤その他(預金通帳、キャッシュカード、貸金庫の鍵など)
遺産分割協議書がある場合は、さらに以下の書類が必要
⑥遺産分割協議書
①は、口座の名義人が亡くなっていることと、法定相続人の確認のために必要となる書類です。
②も、法定相続人の確認のために必要です。
⑥の遺産分割協議書によって、銀行に預けている預金を誰が受け取るかを確認します。
遺言書と同様に原本を提出しなければなりません。
【遺言書・エンディングノートについてはこちら】
エンディングノートとは?おすすめの内容や書き方・終活ですべきことを解説
預貯金を遺産相続で分ける際の注意点
預貯金を遺産相続で分ける際には、以下のような点に注意してください。
亡くなった人の預貯金口座は凍結される
口座の名義人が亡くなったことを銀行が把握すると、ただちに口座は凍結されてその口座からの出金はできなくなります。
これは、一部の相続人が不正に故人のお金を引き出すのを防止するためです。
ひとつの銀行に複数の口座があると、その銀行の口座はすべて凍結されますが、他行の口座は凍結されません。
故人の銀行口座を凍結する場合は、それぞれの銀行に対して凍結の手続きをする必要があります。
役所に死亡届を提出すれば自動的に銀行口座が凍結される、ということはありません。
預貯金だけを先に遺産分割できる
どうしても現金が必要な場合などは、遺産分割協議が成立する前であっても、一部の遺産だけを先に分割できます(一部分割)。
遺産分割協議がなかなかまとまらず、相続税の支払い期限が迫っている場合などにこの制度を利用すると便利です。
一部分割は、相続人全員の合意があり、他の相続人の利益を侵害する恐れがない時に認められます。
また、預貯金だけでなく、不動産などの一部分割も可能です。
たとえば、故人が所有する不動産の売却手続きを進めていて、契約直前に亡くなった場合は、一部分割によって契約を完了できます。
故人の口座から預金を引き出すのはトラブルのもと
現金が必要だからといって、口座凍結前に故人の口座から預金を引き出すのはトラブルのもとです。
とはいえ、故人が生計の主な担い手であった場合は、葬儀の費用などを故人の口座にあるお金で支払わなければならないこともあります。
このような時は、相続預金の仮払い制度を利用しましょう。
「仮払い制度」とは、遺産分割協議が成立する前であっても、法定相続人が一定の金額を被相続人の口座から引き出せる制度です。
しかし、同一金融機関からの払い戻しには限度額があります。
限度額の計算は、以下のとおりです。
たとえば、預金額が600万円、法定相続人が妻、子ども2人で子どもが払い戻しを行う場合。
子ども1人の法定相続分は1/4なので【600万円 × 1/3 × 1/4 = 50万円】となります。
つまり、法定相続分の1/3までの金額を仮払い制度によって受け取ることが可能です。
ただし、150万円を超える金額は払い戻しできません。
限度額は銀行ごとに設定されているので、それぞれの銀行の預金額に応じて法定相続分の1/3までの金額(または150万円)を受け取れます。
仮払い制度を利用する場合に必要となる主な書類は、以下のとおりです。
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・預金の払い戻しをする人の印鑑証明書
故人の預貯金は勝手に引き出せない。速やかな遺産相続の手続きが必要
故人の預貯金の分け方には3種類あります。
それぞれの状況に応じて適切な方法を選択し、スムーズに遺産相続の手続きを進めてください。
亡くなった人の預貯金口座は凍結されるので、勝手には引き出せません。
遺言書がなかったり、遺産分割協議がなかなかまとまらなかったりする場合は、預貯金の仮払い制度を利用すると良いでしょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要