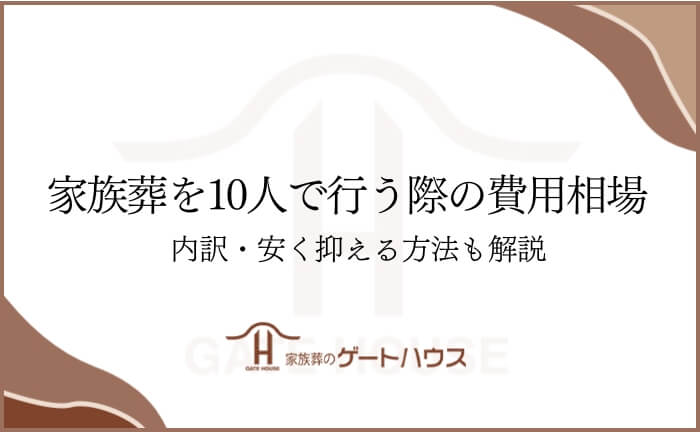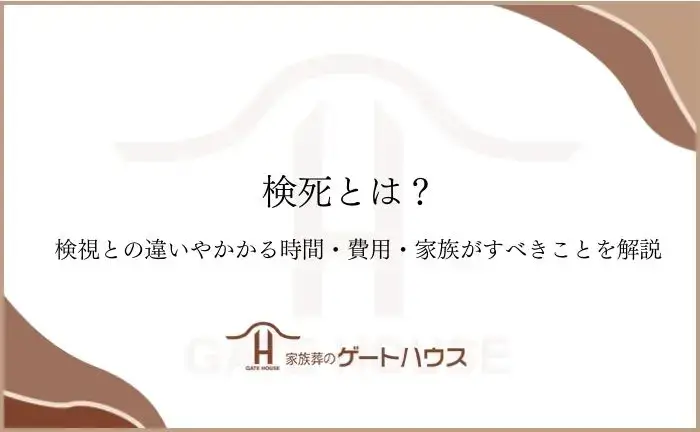新盆(初盆)はお坊さんを呼ばなくてもいい?家族だけの供養で準備する物などを解説
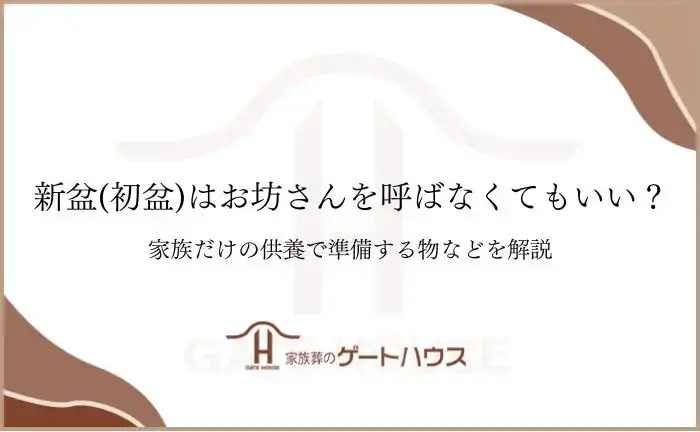
新盆(初盆)を迎えることになり、お坊さんを呼ばないという選択肢はあるのかと、疑問を感じたことはないでしょうか。
もし呼ばなければ非常識になるのでは、と不安になる人も珍しくありません。
この記事ではお坊さんを呼ばずに、家族だけで新盆供養をする際の注意点や、供養の方法を解説しています。
新盆にお坊さんを呼ばないのは非常識?
故人が亡くなってから初めてのお盆となる新盆には、お坊さんを呼んで新盆法要をするのが一般的でした。
しかし、現代ではすべての人がそうするとは限りません。
お盆の目的は、故人を思い出したり感謝したりして供養することなので、お坊さんを呼ばないことが非常識とは言えないのです。
個人の価値観が多様化した現代、宗教観も人それぞれなので、新盆法要のために僧侶を呼ばないという選択する人も増えてきています。
遺族が満足する供養ができるなら、形式にこだわる必要はないでしょう。
新盆にお坊さんを呼ばない時の注意点
新盆にお坊さんを呼ばない場合は、関係者の了承を得ることが大切です。
続いては、新盆にお坊さんを呼ばない時の注意点を紹介します。
親戚には事前に相談する
新盆にお坊さんを呼ばずに家族で供養する際は、事前に親戚と相談してから決めましょう。
親族が新盆法要にお坊さんを呼ぶべきだと考えている場合、トラブルになる恐れがあります。
地域によっては新盆法要の慣習が強く残っている場合もあるため、お互いの理解が必要です。
双方が納得できる過ごし方を選び、不満が残らないようにしましょう。
菩提寺がある場合は事前に連絡する
先祖代々の菩提寺がある場合は、新盆法要にお坊さんを呼ばない意向を事前に連絡しましょう。
新盆なので、お寺側は法要に呼ばれると想定しているかもしれません。
何も知らされないままお盆が過ぎ、後から呼ばれなかったと知った場合、今後お寺との関係性が悪くなる恐れがあります。
お寺にとって、お盆はとても忙しい時期なので、早めに連絡しておいたほうがいいでしょう。
新盆にお坊さんを呼ばない時の過ごし方
新盆にお坊さんを呼ばないで、家族だけで供養する場合も、自宅に故人や先祖の魂をお迎えする準備をしましょう。
供養の内容は宗派や地域によって異なるため、新盆を迎える前にどう過ごすのか確かめておくといいでしょう。
次は、新盆にお坊さんを呼ばない時の過ごし方を紹介します。
お供え物を準備する
新盆にお坊さんを呼ばなくても、故人や先祖のために仏壇へのお供え物を準備しておきましょう。
基本的には、お線香・花・浄水・ロウソク・飲食の「五供(ごくう)」と呼ばれるものを供えます。
五供や故人が好きだった食べ物などを仏壇にお供えして、お盆の間は毎日取り替えるようにします。
お供え物の決まりごとは、宗派や地域によって異なる場合もあるため、自分の宗派や地域の慣習に従うようにしましょう。
【関連記事】
お盆のお供え料理の定番メニューは?置き方・期間・基本マナーも解説
お盆のそうめんの飾り方&意味を解説!いつお供えする?正しい配置は?
白提灯や盆棚などのお盆飾りを準備する
お坊さんを呼ばずに家族だけで新盆供養する場合も、お盆飾りの準備をしておきましょう。
お盆飾りには、故人の魂が迷わずに帰ってくるための白提灯や、故人の魂が滞在する盆棚の用意などがあります。
白提灯は玄関先に吊るすものが多いですが、仏壇の前に設置するタイプもあります。
盆棚には位牌やお供え物だけでなく、精霊馬やほおずきなどを飾ることもあるでしょう。
必要な場合は会食を準備する
新盆にお坊さんを呼ばずに会食の場を設ける場合は、葬儀の際に喪主を務めた人が中心となって会食を準備します。
人数が少なければ、自宅で準備したり仕出し弁当を手配したりしてもいいでしょう。
ある程度の参列者が予想される場合や、自宅でのもてなしが難しい場合には、レストランなどの飲食店を予約します。
いずれにせよ、新盆法要の会食であることを伝えて、慶事ではなく必ず法事用のメニューを手配しましょう。
新盆にお坊さんを呼ばない時の供養方法
続いては、新盆にお坊さんを呼ばない場合の、流れと供養方法を解説します。
また、自宅で新盆法要をしない場合に、新盆を迎える家族が集まって行われる合同法要についても紹介します。
迎え火を焚く
お盆の初日(13日)の日暮れには、自宅の玄関やお墓などで迎え火を焚きます。
迎え火とは、故人や先祖の魂が迷わずに戻って来られるように焚く火のことで、魂は迎え火の煙に乗って来ると言われています。
本来は、幹(おがら)を燃やして焚いた迎え火を白提灯に灯すのですが、現代では住宅事情もあるため、LED型の提灯にする家庭も多いでしょう。
【関連記事】
お盆の迎え火・送り火のやり方は?いつやる?マンションでできる代用方法も解説
墓参りをする
お盆の14日か15日に墓参りをすることが多いですが、迎え火を焚いた日に墓参りをする場合もあるため、家族と相談して日程を決めましょう。
まず、墓石や墓の周りをきれいに掃除して花やお菓子を供え、線香やロウソクに火をつけてお参りします。
お参りした後は、墓を汚さないようにロウソクや線香を片付け、お供えした食べ物は持ち帰るようにします。
お坊さんを呼ばない場合でも、あの世から帰ってきた故人や先祖の魂を迎えるために、忙しくても墓参りはできるよう日程を調整しましょう。
送り火を焚く
お盆の最終日(16日)には、故人の魂を見送るために送り火を焚きます。
迎え火は日没後にすぐ焚きますが、送り火は名残惜しいため、時間にゆとりを持たせて焚くのがいいとされています。
火を使えない場所では、LED提灯を使用する場合もあるでしょう。
送り火の後は白提灯を燃やしますが、お寺でお焚き上げをしてもらうこともあります。
最後にお盆飾りを片付けると、お盆の終了です。
合同法要に参加する
お盆はお坊さんが忙しくなるため、複数の檀家が集まって合同法要を行う場合もあります。
合同の新盆法要に参加すれば、お坊さんを家に呼ばなくても、新盆法要をしてもらえます。
合同法要の流れは、僧侶の読経から始まり、参列者の焼香、僧侶の法話というのが一般的です。
法要に行く際はお布施・数珠・位牌などを持参する場合もあります。
また、お寺によっては準喪服を着用する場合や、平服で構わない場合があるので事前に服装マナーを確認しておきましょう。
【関連記事】
初盆法要をお寺で行うには?お布施や持ち物など合同法要について解説
新盆に関するよくある質問
新盆は通常のお盆とは異なり、特別な意味を持つ行事ですが、初めてお盆を迎える場合は、どうするべきか戸惑うことも多いでしょう。
最後は、新盆に関するよくある質問を紹介します。
新盆は親戚に声かけするもの?
日本ではお盆に親戚が集まって過ごす伝統があるため、新盆は親戚にも声をかけるのが一般的とされています。
新盆法要にお坊さんを呼ばないで、家族だけで供養する場合には、その旨を親戚にも伝えたほうがいいかもしれません。
ただし、誰に声をかけるべきかという明確な決まりはないので、連絡する範囲は家族で相談して決めましょう。
遠方の親戚や高齢者に連絡する際には「参列は、くれぐれもご無理のない範囲で」と付け加えると親切です。
新盆にやってはいけないことは?
新盆にやってはいけないとされるのが、ロウソクの火を息で吹き消したり、海や水辺に立ち寄ったりすることです。
他にもお供えしてはいけない食べ物があり、昔からの決まり事がいくつか存在します。
また、宗派によってはお盆に対する考え方が異なるため、新盆の過ごし方も変わる場合もあるのです。
新盆にやってはいけないことについては、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】
初盆(新盆)にやってはいけないことは?言葉遣いや浄土真宗などでタブーな行為を紹介
新盆はお墓参りだけでも良いって本当?
かつては新盆にお坊さんを呼んで法要を行ったり、親族が集まって墓参りや会食をしたりするのが一般的でした。
しかし、近年では新盆の過ごし方が厳密ではなくなってきており、家族だけで過ごしたり、お墓参りだけしたりしても問題ありません。
宗教観や価値観の多様性がある現代では、新盆はこうするべきというのではなく、故人を思う気持ちを忘れないことが大切です。
新盆のお墓参りについては、以下で詳しく解説しています。
【関連記事】
新盆はお墓参りだけでも良い?お坊さんを呼ばない場合や持ち物・服装を解説
新盆にお坊さんを呼ばない場合も故人を思いやり、心のこもった供養を
新盆の過ごし方に厳密な決まりはないため、お坊さんを呼ばないで家族だけで過ごすのも珍しくなくなりました。
ただし、人によっては僧侶を呼ぶべきと考える人もいるので、関係者とは事前に話し合いましょう。
菩提寺がある場合も、事前の連絡が必要です。
お坊さんを呼ばなくても、故人の魂を供養する方法があるので、自分たちの宗教や考え方に合った方法で、新盆供養しましょう。
どんな形でも、故人を思いやり心のこもった新盆供養をするのが大切です。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要