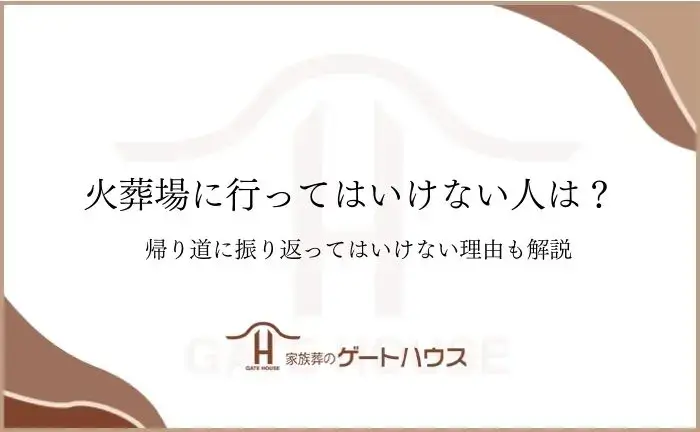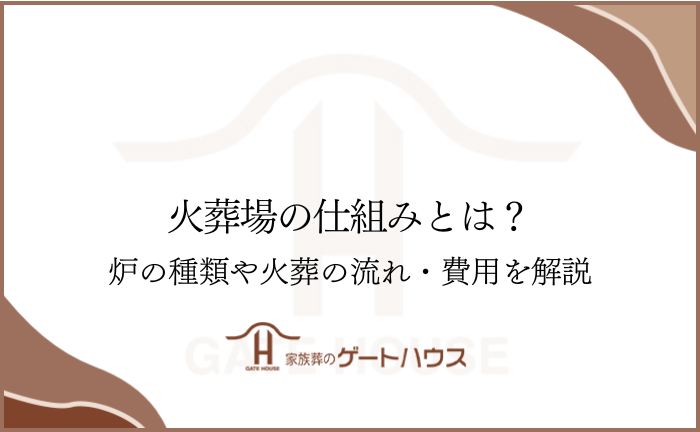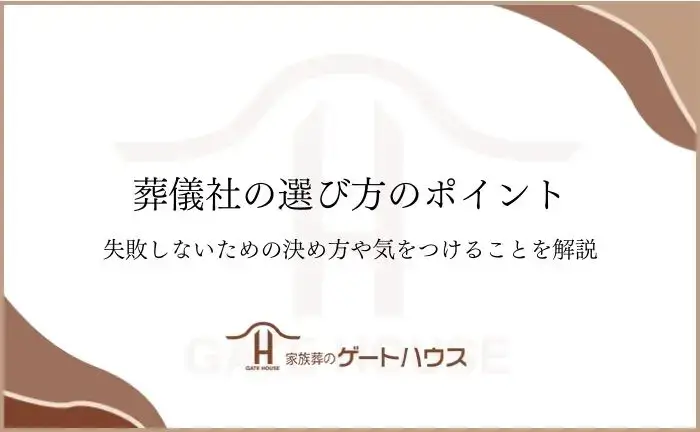死亡後の手続きの優先順位は?身近な人が亡くなった時~葬儀後に行う手続き一覧
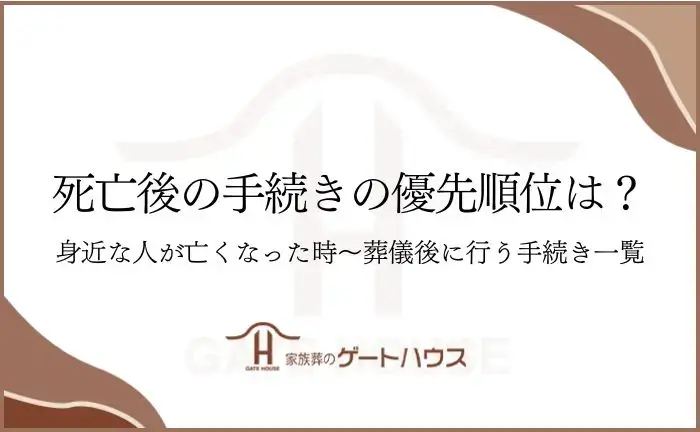
家族が亡くなると、役所への届出や各種契約の解約など、多くの手続きを行わなければなりません。
なかには期限が定められているものもあるため、計画的に対応することが大切です。
しかし、葬儀の準備や関係者への連絡に追われながら、数多くの手続きをこなすのは容易ではありません。
本記事では、身近な方が亡くなった際に必要となる手続きを、優先順位や期限とともにわかりやすく解説します。
死亡後の手続きの優先順位はどう決める?
家族が亡くなるとさまざまな手続きがあります。
公的な手続きのなかには、期限が決められているものもあるので特に注意が必要です。
家族が亡くなった場合、最初に行うべき最も重要な手続きは、死亡届の提出です。
医師の死亡診断書を添えて死亡届を提出することで本人の死亡が確認され、その他の手続きが進みます。
役所へ提出するその他の書類は期限が決められているものが多数あります。
なかには死亡後2週間以内に提出しなければならないものもあります。
まずは役所関連の手続きを優先して進め、次に公共料金や各種契約の解約、さらに相続・税金関連の手続きの順番で行うのが一般的な流れです。
死亡後の手続き一覧
死亡後に行う手続きを、葬儀までに行うものと葬儀後に行うものに分けた一覧表を紹介します。
【死亡直後から葬儀までの間に行う手続きの一覧】
| 手続きの種類 | 取得先・提出先 |
| 死亡診断書の取得 | 医師・医療機関から取得 |
| 死亡届の提出・埋火葬許可証の取得 | 市区町村の窓口に提出および取得 |
| 葬儀社への連絡 | 葬儀社 |
| 訃報の連絡 | 関係各所 |
【葬儀後に行う主な手続きの一覧と期限】
| 手続きの種類 | 取得先・提出先 | 期限 | |
| 健康保険の資格喪失届の提出 | 年金事務所または故人の勤務先に提出 | 5日以内 | |
| 年金受給停止手続き | 厚生年金 | 年金事務所に提出 | 10日以内 |
| 国民年金 | 市区町村窓口に提出 | 14日以内 | |
| 国民健康保険・後期高齢者医療制度資格喪失届の提出 | 市区町村窓口に提出 | 14日以内 | |
| 介護保険資格喪失届の提出 | 市区町村窓口に提出 | 14日以内 | |
| 世帯主変更届の提出 | 市区町村窓口に提出 | 14日以内 | |
| 葬祭費・埋葬料などの申請 | 市区町村窓口などに提出 | 2年以内 | |
| 未支給年金の請求 | 年金事務所または市区町村窓口に申請 | 5年以内 | |
| 遺族年金の請求 | 年金事務所または市区町村窓口に申請 | 5年以内 | |
| 公共料金の解約・名義変更 | 各サービス会社に申請 | 随時 | |
| 各種契約の解約 | 各サービス会社に申請 | 随時 | |
| 死亡保険金の請求 | 生命保険会社に申請 | 3年以内 | |
| 相続・故人の税金関連の手続き | 税務署等に提出 | 3カ月〜10カ月以内 | |
死亡直後から葬儀までに行う手続き
死亡直後から葬儀までに行う手続きを流れに沿って詳しく解説します。
死亡診断書の取得
家族が亡くなったとき、最初に必要となるのが死亡診断書です。
死亡の事実は法律上、医師の診断によってのみ確認されます。
死亡診断書がなければ死亡届の提出もできず、葬儀社も正式に対応できません。
死亡診断書は、生前に診療を受けていたかかりつけ医や、亡くなった際に立ち会った医療機関の医師が作成します。
費用は医療機関によって異なりますが、おおむね3,000円〜1万円程度です。
なお、突然死や事故死など死因が不明な場合は「死体検案書」が必要です。
死体検案書は死因の調査や遺体の運搬・保管の費用が発生するため、3~10万円程かかります。
死亡届の提出
死亡届は、死亡地・本籍地・届出人のいずれかの市区町村役場に提出します。
提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。
死亡届の用紙は、医師が作成する「死亡診断書」と一体になっていることが多く、病院などの医療機関から交付されます。
片面または左右で構成されており、死亡診断書欄は医師が記入し、死亡届欄には届出人が故人の氏名・本籍・住所、届出人との関係、届出人の氏名・住所などを記入します。
埋火葬許可証の取得
遺体を火葬または埋葬するには、市区町村が発行する「埋火葬許可証」が必要です。
これは法律で義務付けられており、許可証がないと火葬場や墓地での手続きができません。
通常、死亡届を役所に提出すると、その場で埋火葬許可証が発行されます。
発行された許可証は火葬場などに提出する必要があるため、葬儀まで大切に保管してください。
なお、多くの自治体では夜間や休日にも「死亡届の仮受付」が可能ですが、この場合は埋火葬許可証の交付が翌開庁日以降となることがあります。
急ぎで火葬を行う必要がある場合は、自治体の受付時間を事前に確認しておくと安心です。
葬儀社への連絡
死亡診断書の取得と並行して、できるだけ早めに葬儀社に連絡しましょう。
葬儀の段取りや火葬場の予約などはスピードが求められるため、事前に葬儀社を決めておくと安心です。
多くの葬儀社では、遺族に代わって市区町村への死亡届の提出や、火葬場の予約申請、埋火葬許可証の受け取りなどを代行してくれます。
死亡届の提出は遺族以外の代理人でも可能ですが、必要書類が整っていないと受理されないこともあるため、専門家に任せるのが一般的です。
葬儀社への連絡とあわせて、葬儀の日程・場所・形式(通夜や告別式の有無、宗教形式など)についても早めに相談・決定しておくことをおすすめします。
訃報の連絡
葬儀の日程が決まれば、親族・知人・会社関係者などに亡くなったことを連絡します。
家族葬や直葬など、参列者を限定する葬儀を行う場合は、誰に連絡するかも慎重に検討しましょう。
葬儀に呼ばない人には、葬儀が終わったあとに書面で連絡する方法もあります。
葬儀後に行う手続き①|公的手続き
葬儀が終わったあと、速やかに行わなければならない手続きがいくつかあります。
同じ手続きでも、届出先によって手続きの方法や必要書類が異なる場合があるので注意が必要です。
詳しくは、窓口にお問い合わせください。
健康保険の資格喪失届の提出
健康保険は、3つの種類に分かれています。
会社員や公務員が加入する「被用者保険」、自営業者が加入する「国民健康保険」、75歳以上の高齢者が加入する「後期高齢者医療保険」の3つです。
それぞれの種類によって、期限や手続き方法が少し異なります。
| ・被用者保険 【期限】 死亡日の翌日から5日以内 【手続き先】 勤務先(勤務先に連絡すると手続きを行ってくれます) 【必要書類】 健康保険証など ・国民健康保険 【期限】 死亡日の翌日から14日以内 【手続き先】 市区町村役場 【必要書類】 健康保険証など ・後期高齢者医療保険 【期限】 死亡日の翌日から14日以内 【手続き先】 市区町村役場 【必要書類】 後期高齢者医療保険証など |
年金受給停止手続き(厚生年金・国民年金)
手続きを行わないとそのまま年金が振り込まれるので、あとで返還しなければなりません。
長期間放置すると年金の不正受給を疑われかねないので、速やかに手続きを行いましょう。
| 【期限】 ・厚生年金の場合:死亡日から10日以内 ・国民年金の場合:死亡日から14日以内 【手続き先】 ・厚生年金の場合:社会保険事務所 ・国民年金の場合:住所地の市町村役場 【必要書類】 年金証書、亡くなったことを証明する書類など |
介護保険資格喪失届の提出
亡くなった人が介護保険の被保険者の場合、資格喪失手続きが必要です。
| 【期限】 死亡日の翌日から14日以内 【手続き先】 市区町村役場 【必要書類】 介護保険被保険者証など |
世帯主変更届の提出
故人が世帯主で、同居している家族が世帯主になる場合は、世帯主変更届の提出が必要です。
世帯主が亡くなり残った家族がひとりだけの場合や、15歳以上の家族がひとりしかいない場合は自動的に世帯主が変更されるため届出は不要です。
| 【期限】 死亡日の翌日から14日以内 【手続き先】 市区町村役場 【必要書類】 届出人の本人確認書類など |
葬祭費・埋葬料などの申請
健康保険の被保険者が亡くなると、各健康保険組合から葬儀費用に対して給付金が支給されます。
給付金の名称は健康保険組合によって異なります。
国民健康保険と後期高齢者医療保険の場合は葬祭費、社会保険(組合けんぽや共済組合など)の場合は埋葬料が申請可能です。
埋葬料の金額は法令で定められており、一律に5万円となります。
葬祭費は市区町村によっては3~7万円と金額が異なりますが、埋葬料と同じ金額である5万円のケースが多いようです。
| ・葬祭費 【期限】 葬祭を行った日の翌日から2年以内 【手続き先】 市区町村役場 【必要書類】 被保険者証、届出者の本人確認書類、葬儀の領収書、振込先口座が確認できるもの(銀行の通帳など) ・埋葬料 【期限】 亡くなった日の翌日から2年以内 【手続き先】 勤務先の健康保険組合、または社会保険事務所 【必要書類】 被保険者証、届出者の本人確認書類、亡くなったことを証明する書類など |
未支給年金の請求
亡くなった人が年金を受給していた場合、故人と生計を同じくしていた3親等以内の親族は、未支給の年金を受けとれます。
| 【期限】 故人が亡くなった日の翌日から5年以内 【手続き先】 年金事務所または街角の年金相談センター 【必要書類】 年金証書、故人と請求者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本など)、 故人と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類(故人の住民票の除票および請求する人の世帯全員の住民票の写し) 振り込みを希望する金融機関の通帳 |
遺族年金の請求
亡くなった人が生計維持していた遺族がいる場合、国民年金・厚生年金から遺族年金を受け取れます。
受け取れる年金の種類は2つあり、国民年金に加入している場合は遺族基礎年金、厚生年金に加入している場合は遺族厚生年金です。
| 【期限】 5年以内 【手続き先】 市区町村役場または年金事務所 【必要書類】 戸籍謄本 世帯全員の住民票の写し 死亡者の住民票の除票など |
葬儀後に行う手続き②|公共料金・各種契約
故人が契約していた公共料金や各種契約をそのままにしていると、銀行口座やクレジットカードから自動で料金が引き落とされる可能性があります。
なるべく早めに契約の解除や名義変更を行いましょう。
公共料金の解約・名義変更
電気・ガス・水道などの公共料金の解約を行います。
契約した故人に同居家族がいる場合は、名義変更をしなければなりません。
電気とガスに関してはそれぞれ契約している会社に連絡し、水道料金は市区町村で手続きを行います。
【関連記事】
亡くなった人の預金をおろすには?口座凍結前・後の手続きや必要書類を解説
各種契約の解除
公共料金以外にも、故人が契約していたクレジットカードや携帯電話(スマートフォン)、各種サブスクリプションサービスなどの契約解除が必要です。
なかでも注意が必要なのがクレジットカードです。
放置しておくと、不要なサービス料金が継続して引き落とされる可能性がある一方、必要な支払いがある状態で解約すると、あとから別途支払いの手続きが必要になることがあります。
家族も利用している契約が停止されてしまうおそれもあるため、引き落とし内容を確認しながら慎重に解約を進めましょう。
近年では動画配信サービスや音楽配信サービスなど、定額制の契約(サブスク)が増えています。
故人が何を契約していたか、家族が把握できていないことも少なくありません。
クレジットカードの利用明細や銀行口座の取引履歴を確認し、契約中のサービスをリストアップした上で、ひとつずつ解約の手続きを行いましょう。
なお、生前のうちにこうした契約情報を家族間で共有しておくと、手続きが格段にスムーズになります。
運転免許証・パスポートなどの返納
亡くなった人の運転免許証に関しては、家族に返納義務はありません。
ただし、そのままにしていると運転免許証更新の通知などが来るので、通知の停止を希望する場合は手続きが必要です。
| 【返納先】 警察署、運転免許更新センター、運転免許試験場 【必要書類】 故人の運転免許証 亡くなったことを証明する書類(死亡診断書の写し、住民票の除票など) 申請者の本人確認書類(運転免許証など) |
パスポートは旅券法の定めにより、すみやかに返納することが義務付けられています。
思い出として故人のパスポートをそのまま持っていたい場合は、旅券事務所で無効処置をしてもらったうえで手元に保管できます。
| 【返納先】 各都道府県の旅券事務所 【必要書類】 故人のパスポート 亡くなったことを証明する書類(死亡診断書の写し、住民票の除票など) 申請者の本人確認書類(運転免許証など) |
マイナンバーカードには、返納義務はありません。
死亡届の提出によって自動的に失効しますが、死亡保険金の請求や相続手続きなどで必要になるケースがあるので、大切に保管しましょう。
悪用される心配などがある場合は、返納することも可能です。
死亡保険金の請求
故人が生命保険に加入していた場合、保険金の受取人(被保険者)であれば手続きをしましょう。
受取の期限は保険会社によって異なりますが、おおむね3年以内です。
必要書類は、契約している保険会社に確認してください。
葬儀後に行う手続き③|税金・相続関連
公共料金や各種サービスの解約手続きを終了したら、次は税金と遺産相続の手続きを行いましょう。
税金・相続関連で最も期限の早いものは3カ月ですが、専門的な知識が必要で準備に時間がかかるので、早めに取り掛かることをおすすめします。
相続の放棄
故人の残した財産よりも負債のほうが多ければ相続放棄を検討しましょう。
相続を放棄するときは、相続開始から3カ月以内が期限です。
さまざまな事情がある場合期限を延長できますが、延長の申請も3カ月以内に行わなければなりません。
所得税の準確定申告
故人がすべき確定申告を相続者が代わりに行う必要があります。
相続者が故人に代わって確定申告を行うことを「準確定申告」といいます。
相続開始から4カ月以内に申告と納税を行わなければなりません。
相続税の申告
相続税が発生する場合、逝去を知った日から10カ月以内に申告・納税が必要です。
相続税は「基礎控除」を超える場合に発生します。
基礎控除は「3,000万円+法定相続人数×600万円」です。
期限内に申告しないと、延滞税などのペナルティが発生する可能性があります。
遺産分割協議が10か月以内にまとまらないようであれば、いったん法定相続分で申告し、同時に「申告後3年以内の分割見込書」を提出します。
相続手続き(遺産分割協議・名義変更など)
相続人が複数いて遺言書がない場合は、遺産分割協議によって財産の分け方を相続人全員で話し合って決定する必要があります。
協議に法的な期限はありませんが、相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内)を考慮し、それまでに終えるのが望ましいでしょう。
また、不動産を相続する場合は、所有権移転登記(相続登記)の手続きが必要です。
2024年4月の法改正により、相続登記は義務化され、相続の開始および取得を知った日から3年以内に名義変更を行わなければなりません。
正当な理由なく期限を超えると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、過去の相続で名義変更をしていない不動産がある場合でも、2027年4月1日までに相続登記をすれば過料の対象にはなりません。
その他、株式などの金融資産や自動車などについても、必要に応じて名義変更の手続きを行いましょう。
死亡後の手続きをスムーズに進めるポイント
死亡後には、さまざまな手続きを期限内に終了させる必要があります。
手続きをスムーズに進めるためのポイントを紹介します。
やるべき手続きをリストアップする
まずは、漏れがないようにやるべき手続きをすべてリストアップしましょう。
手続きに必要となる書類や期限、行くべき場所なども把握する必要があります。
役所関係の手続きだけでなく、電気・ガス・水道などの公共料金やインターネット・スマホの契約なども解約・名義変更が必要です。
それ以外にも、故人のクレジットカードの明細や預金通帳の取引履歴を確認しましょう。
家族が知らないサブスクの料金引き落としが見つかるかもしれません。
株式や生命保険などの金融資産の洗い出しとともにローンや借金などの負債についてもチェックする必要があります。
リストアップを終えてから、優先順位をつけて計画的に手続きを進めましょう。
必要書類を保管する
死亡に伴うさまざまな手続きの多くには、死亡を証明する書類が必要です。
死亡届を提出する前に、死亡診断書(死亡届)のコピーを複数枚取っておきましょう。
死亡届を提出すると、埋火葬許可証が交付されます。
火葬とお墓への埋葬には必須の書類なので、必ず大切に保管してください。
葬祭費・埋葬料の請求には、葬儀社の請求書や領収書などの葬儀に要した費用を確認する書類が必要です。
これらの書類も紛失しないように注意しましょう。
役所の手続きはまとめて行う
年金や健康保険など、役所の手続きは14日以内を期限とするものが多いので葬儀後すぐに着手しましょう。
葬祭費の請求は2年以内ですが、他の手続きとまとめて済ませるのが効率的です。
故人の銀行口座の扱いは慎重に
口座の名義人が死亡すると銀行への連絡が必要ですが、慎重に行わなければなりません。
銀行へ連絡すると口座はただちに凍結されて、相続手続きが完了するまで預金の払い戻しはできなくなります。
故人の口座から公共料金を引き落としていたり、生活費を賄っていたりする場合は預金の払戻し制度を利用すると良いでしょう。
なお、亡くなったからといって、役所から銀行に直接連絡が入り自動的に口座が凍結されることはありません。
デジタル遺産に注意
近年の死亡後手続きでは、デジタル遺産にも注意が必要です。
デジタル遺産とは、デジタル形式で保管していた財産を指します。
たとえば、暗号資産(仮想通貨)や電子マネー、さらにはネット証券やネット銀行で管理されている口座もデジタル遺産と考えて良いでしょう。
これらのデジタル遺産は、本人のスマホやパソコンで管理されているので、家族が把握するのは簡単ではありません。
デジタル遺産も、現金や有価証券などと同様に手続きをして相続する必要があります。
デジタル遺産には該当しませんが、故人が契約していたサブスクも本人が亡くなったあとの処理には注意しましょう。
契約していることを知らずに放置していると、そのまま引き落としが継続する可能性があります。
【関連記事】
遺産相続での預貯金の分け方とは?相続前の準備や分割時の注意点を解説
生前の準備が重要
死亡後の手続きを円滑に進めるために最も重要なのは、生前に家族間でよく話し合っておくことです。
保有しているすべての資産を洗い出し、家族で共有しておきましょう。
特にデジタル遺産は、家族が気づかない可能性があります。
いざという時に備えて、関連するアカウントとパスワードなどの情報を適切な形で保管しておくことをおすすめします。
エンディングノート(終活ノート)の活用や遺言書の作成も検討しましょう。
自分が亡くなったあとの手続きだけでなく、延命治療するかどうかや葬儀・埋葬方法の希望なども記録しておくと家族の負担も軽減できます。
【関連記事】
エンディングノートとは?おすすめの内容や書き方・終活ですべきことを解説
死亡後の手続きには期限がある。優先順位をつけて計画的に進めよう
家族が亡くなると、葬儀の準備に加えてさまざまな手続きが必要です。
健康保険や年金の手続きは14日以内に行う必要があるので、葬儀が終了するとすぐに取り掛からなければなりません。
手続きを滞りなく進めるために、やるべきことに優先順位をつけて計画的に進めましょう。
生前に、亡くなったときの対応を家族と話し合っておくのも、スムーズに手続きを進める上で重要です。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要