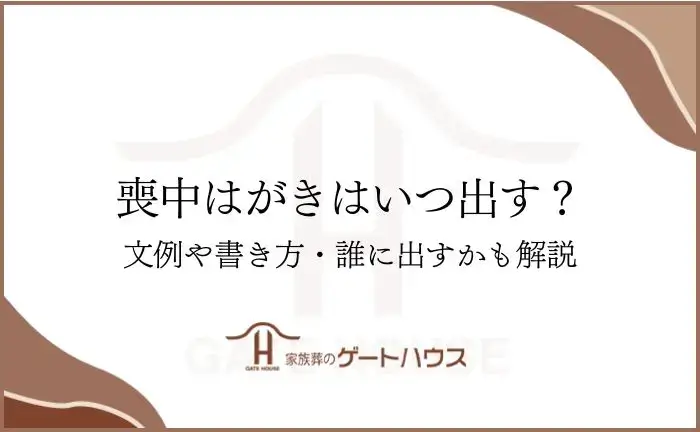墓じまいとは?費用・流れや墓じまい後の手続きについて解説
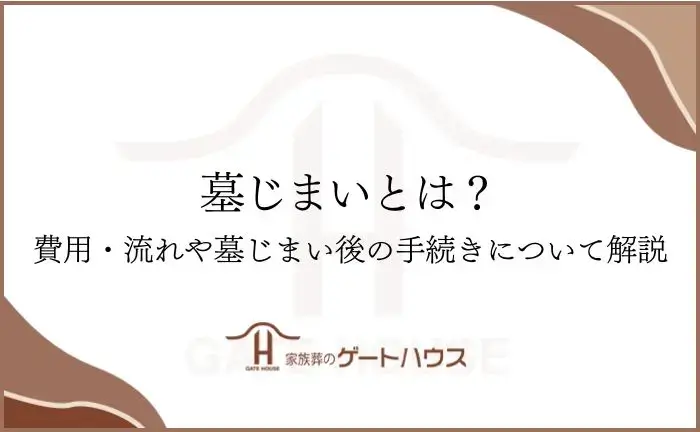
近年、少子高齢化や核家族化が進む中で、「お墓を継ぐ人がいない」「遠方で管理が難しい」といった理由から、墓じまいを検討する方が増えています。
いざ墓じまいを考え始めると、「本当に墓じまいをするべきなのか」「費用はどれくらいかかるのか」など、不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、墓じまいを検討している方に向けて、墓じまいの意味や必要な手続き、費用の相場、トラブルを避けるためのポイントなどをわかりやすく解説します。
墓じまいとは?
墓じまいとは、現在あるご自身やご先祖のお墓を撤去して更地に戻し、墓地の管理者(寺院や霊園など)に返還することを指します。
また、墓石を撤去するだけでなく、納められていたご遺骨を他の場所へ移して供養することも含まれます。
墓じまいの時期に明確な決まりはなく、ご家庭の事情に応じて進めることができます。
ただし、役所への申請や石材店・管理者との調整などに一定の時間がかかるため、早めの準備が大切です。
また、寺院や霊園はお盆や春・秋のお彼岸などの繁忙期に対応が立て込むことがあるため、これらの時期を避けて動き出すと、よりスムーズに進められるでしょう。
墓じまいが近年増加している背景
厚生労働省『衛生行政報告例』によると、2023年度の改葬(墓じまい)件数は年間166,886件にのぼります。
これは、2018年度の115,384件と比較しても大幅に増加しており、墓じまいは年々増えている傾向にあります。
では、なぜ墓じまいをする人が増えているのでしょうか。
主な理由は以下の3つです。
少子高齢化による後継者不在
一つ目は少子高齢化による、お墓の跡継ぎがいないという問題です。
たとえば、子どもがいない夫婦や、娘が結婚して別の姓になった場合など、自分たちの代でお墓を守る人がいなくなる状況が多く見られます。
将来的に無縁墓になることを避けるため、早めに墓じまいを検討する人が増えているのです。
地方の過疎化と都市集中
二つ目の問題は、地方の過疎化です。
若い世代の多くが都市部へ移住する中で、地方に残されたお墓の管理が困難になるケースも少なくありません。
「実家のお墓が遠方にあって、なかなか通えない」と悩む方は多く、 自分たちの生活圏に近い場所へ改葬したいと考える人が増加しています。
お墓に対する価値観の多様化
三つ目は、お墓に対する価値観が多様化していることです。
近年では、お墓を持たずに『永代供養・納骨堂・樹木葬・散骨』といった選択肢を選ぶ人も増えています。
「子どもに負担をかけたくない」「維持費がかからない形で供養したい」といった考えが広まり、 従来のお墓にこだわらず、墓じまいを機に新たな供養方法を選ぶ傾向が強まっています。
参考:厚生労働省『衛生行政報告例|厚生労働省』
墓じまいのメリット・デメリット
墓じまいをすることで、現在・未来の悩みが解消される方にとっては大きなメリットもあります。
ただし、自分達以外の親族にも影響があることなので、気を付けなければならないポイントもあります。
メリットとデメリットの両方を確認したうえで、墓じまいの検討を進めると良いでしょう。
墓じまいのメリット
墓じまいをしてどんな部分がメリットになるかは、現在抱えている懸念事項によって違います。
墓じまいの5つのメリットを見て、現在の状況と比べてみましょう。
①お墓の維持に関する金銭的な負担の軽減
お墓を維持するには、以下のような費用が発生します。
-
- 定期的な清掃と墓石の修繕費
- 寺院や霊園に支払う年間管理費(護持会費や檀家料など)
- お寺が遠方にあればお墓参りの際の交通費
こうした費用が長期的にかかることを考えると、将来の負担を見越して墓じまいを選び、永代供養墓・納骨堂・樹木葬・海洋散骨などへ移行する人が増えています。
これにより、継続的な費用や精神的負担の軽減につながるのです。
②お墓の継承者不在の問題解決
お墓を継ぐ人がいなければ、供養を親戚や業者に依頼する必要があります。
管理を依頼できる親族がいたとしても、その方の負担になってしまいますし、業者に依頼すれば金銭的負担がかかります。
どちらにしても永久的に供養をお願いすることは難しいでしょう。
お墓の継承者がいないのであれば墓じまいをして、永代供養にすることで懸念は解消されます。
③無縁墓となってしまう可能性がなくなる
お墓の継承者や管理者がいなくなり、管理料の支払いが滞ると、そのお墓はやがて無縁墓として扱われるようになります。
無縁墓になると、墓石の劣化や雑草の繁茂によって荒れた状態となり、ご先祖様への供養が行き届かなくなってしまいます。
周囲のお墓に悪影響を及ぼすこともあり、他の利用者の迷惑になる恐れもあるでしょう。
さらに、無縁墓はすぐに撤去できるわけではなく、墓地の管理者や自治体が手続きを経たうえで対応する必要があります。
撤去が完了するまでその区画を他の人に貸し出すこともできず、管理側の負担は少なくありません。
将来的に継承者がいなくなるとわかっている場合は、早めに墓じまいを行い、適切に供養を済ませておくことが望ましいと言えるでしょう。
無縁墓化を防ぐことで、供養の責任もきちんと果たせます。
④供養がしやすくなる
お墓が遠方にあったり、ご自身が高齢で移動が困難になったりすると、思うようにお墓参りができないこともあります。
その場合は、墓じまいをして自宅近くの納骨堂や永代供養墓へ改葬することで、供養しやすくなります。
また、短期的な選択肢として「手元供養(自宅で遺骨や遺灰を安置する形)」を選ぶ方も増えています。
「お墓参りに行けていない」という心理的負担も解消され、供養をより身近に感じられる環境を整えることができます。
⑤自分の遺骨の行く先を自分で決めることができる
以前は、「亡くなったらお墓に入る」のが一般的でしたが、現代では供養の選択肢が多様化しています。
「海が好きだったから海洋散骨をしてほしい」「自然が好きで自然に還りたいから樹木葬にしてほしい」など、生前に自分の意向を家族に伝えることで、遺骨の行く先を決めることができます。
墓じまいのデメリット
墓じまいには多くのメリットがありますが、一方で注意すべきデメリットも存在します。
トラブルを防ぐためにも、事前に考えられる課題を理解しておくことが大切です。
①墓じまい自体に費用がかかる
墓じまいには、墓石の撤去費用や墓地管理者へのお礼、行政手続きに関わる費用などが発生します。
さらに、ご遺骨の移転先によっては永代供養料や納骨堂の使用料なども必要です。
金銭的な理由で墓じまいを考える場合には、現状の維持費と、墓じまいにかかる費用・改葬後の供養費を比較したうえで、総合的に判断することが大切です。
②申請や手続きの手間がかかる
墓じまいを進めるには、「改葬許可申請書」や「埋蔵証明書」などの書類をそろえる必要があります。
また、霊園や寺院、石材店、改葬先などとのやりとりも発生するため、準備から完了までに3か月〜数年かかるケースもあります。
短期間で終わるものではないため、時間と手間がかかることをあらかじめ理解したうえで取り組むことが必要です。
③親族や菩提寺とトラブルになってしまう可能性がある
お墓には多くの場合、複数のご遺骨が納められており、代々続く家族の供養の場となっています。
そのため、自分たちだけで判断して墓じまいを進めてしまうと、お墓に対する思いが異なる親族とのトラブルに発展することがあります。
改葬先や費用負担の分担、今後の供養の方針について、事前に丁寧に話し合い、納得を得ることが重要です。
また、長年お世話になった菩提寺との関係性にも配慮が必要です。
離檀にあたっては「離檀料」を求められることもあり、突然の墓じまい申請は寺院側の反発を招く可能性もあります。
お寺や親族への説明を省略せず、感情面と事務面の両方で丁寧にコミュニケーションをとることが、トラブルを防ぐ最大のポイントです。
墓じまいの流れと手続きについて
墓じまいには手間や時間がかかることがありますが、具体的にどのような作業が必要で、どれほどの期間がかかるのでしょうか。
①親族や墓地管理者(菩提寺や霊園)に相談する
まずは、親族に墓じまいを検討していることを伝え、納得を得ることが第一歩です。
反対する親族がいる場合は、話を急がず、しっかりと意見をすり合わせましょう。
親族間で意見がまとまったら、現在の墓地の管理者(寺院や霊園)に墓じまいの意思を伝えます。
場合によっては、菩提寺や管理者との対話に時間がかかることもあるため、丁寧な説明を心がけることが大切です。
管理者から許可を得たら、「埋蔵証明書」の発行を依頼します。これは後の行政手続きに必要な書類です。
②墓じまい後の改葬先を決める
親族と墓地管理者の合意が得られたら、ご遺骨の改葬先を決めます。
継承者がいない場合は「永代供養墓」や「樹木葬」、費用を抑えたい場合には「手元供養」や「散骨」などの選択肢もあります。
改葬先が決まったら、「受け入れ証明書」を発行してもらいましょう。
改葬先がすぐに見つからない場合は、先に墓じまい業者を探し、業者を通じて紹介を受けることも可能です。
人気の霊園や納骨堂では空きがなく、数ヶ月〜数年待ちとなることもあるため、余裕を持ったスケジュールを立てると安心です。
③必要な書類と行政手続き
業者と改葬先が決まったら、お墓のある自治体で行政手続きを行います。
必要書類は次の3点です。
- 現在の墓地が発行する「埋蔵証明書」
- 改葬先が発行する「受入証明書」
- 自治体で記入する「改葬許可申請書」
これらを自治体窓口に提出し「改葬許可証」の発行を受けます。
書類が揃っていれば、通常はその日のうちに改葬許可証を発行してもらえます。
④閉眼供養と墓石撤去
行政手続きが完了したら、現在のお墓で「閉眼供養(へいがんくよう)」を行います。
閉眼供養とは、お墓に宿っている魂を抜く宗教的な儀式です。
通常は、菩提寺の住職などに依頼して執り行います。
供養を終えたら、遺骨を取り出し、墓じまい業者や墓地管理者によって墓石を撤去します。
その後、あらかじめ決めた改葬先にて納骨し、必要に応じて「開眼供養(かいげんくよう)」を行えば、一連の墓じまいの手続きは完了です。
墓じまいにかかる費用の目安
墓じまいの依頼先は、大きく4つに分けられます。
-
- ①寺院や霊園などの施設に依頼
- ②寺院や霊園が提携している業者に依頼
- ③代行業者に依頼
- ④自治体に依頼
それぞれ費用や対応範囲が異なるため、比較検討しながら最適な依頼先を選ぶことが大切です。
今のお墓にかかる費用
現在のお墓の墓じまいにかかる費用相場は以下のとおりです。
| 墓石撤去費用 | 約8~15万円 前後/ ㎡ |
| 閉眼供養のお布施 | 約3~15万円前後 |
| 離檀料(寺院のみ) | 約5〜20万円程度 |
| 洗骨 | 約2万円前後 / 霊位 |
| 書類の発行手数料 | 数百円~1,500円程度 |
墓石撤去費用は、墓石の大きさや工事機械の入りやすさによっても変動します。
また、寺院の墓じまいでは、檀家をやめることで離檀料がかかることがあるのが特徴です。
離檀料を請求されなかったとしても、今までお世話になったお礼としてお布施を多めに包む場合もあります。
補助金が出る可能性も
一部の自治体では、公営墓地に限り墓じまいの費用に対して補助金制度を設けています。
これは、無縁墓の増加を防ぐことを目的としたもので、すべての墓地が対象になるわけではありません。
補助金の上限額は自治体によって異なりますが、最大で20万円程度の支援が出るケースもあります。
補助対象・条件・申請方法などは、必ず各自治体の窓口で確認しましょう。
墓じまい後の改葬先(納骨先)の選択肢と費用
墓じまいのあとは、遺骨をどのように供養するかを決める必要があります。
選択肢は多岐にわたるため「なぜ墓じまいをするのか」という理由に応じて適した改葬先を選びましょう。
一般的な供養方法は、一般墓所、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨、手元供養の6種類です。
| 墓じまいを検討している理由 | 選択肢 |
| 跡継ぎがいない | 永代供養・散骨・樹木葬 |
| 今あるお墓が遠い | 一般墓所・納骨堂・手元供養 |
| お墓に入る以外の選択肢を考えている | 散骨・樹木葬・手元供養 |
一般墓所
改葬先が一般墓所の場合は、新しい墓石代や施工費、土地の永代使用料(区画料)、管理費等が新たにかかります。
- 墓石代・施工費:約50~150万円
- 永代使用料:約30~100万円
- 管理費:年間1万円程
さらに、新しく墓石を建てて納骨する場合には、開眼法要のお布施も必要になります。
開眼供養のお布施は、約3~5万円程度が相場となります。
納骨堂
納骨堂の費用は、20万~150万円程度ですが、施設の種類や立地、設備によって大きく異なります。
| 納骨堂の種類 | 相場 | ポイント |
| ロッカー型納骨堂 | 20~150万円程度 |
・一時預かりもできる ・区画の大きさが選べる ・低価格から契約可能 |
| 自動搬送式納骨堂 | 50~150万円程度 |
・アクセス良好な立地 ・機械を使用するため管理費が高くなる傾向 |
| 仏壇型納骨堂 | 100~200万円程度 |
・立派な装飾が施されている仏壇ほど高くなる ・初期費用の他に施設利用料や管理料がかかる |
| 位牌型納骨堂 | 約20~30万円程度 | ・遺骨を合葬にすると低価格に |
| 合祀型納骨堂 | 約20~30万円程度 | ・一般合祀にすると低価格に |
永代供養墓
永代供養墓とは、お墓の継承者がいなくても、寺院や霊園が責任を持って供養・管理を行ってくれるお墓のことです。
個別に納骨するか、ほかの遺骨と一緒に合祀するかで費用に大きな違いがあり、相場は約5〜150万円と幅があります。
個別の永代供養墓
個別の永代供養墓では、一定期間ご遺骨を個別の区画に安置したのち、期間終了後に合祀墓へ移す形が一般的です。
個別安置のため土地代がかかり、合祀タイプよりも費用は高めです。
| 開眼供養のお布施 | 3~5万円前後 |
| 埋葬料・納骨料 | 1〜5万円 / 霊位 |
| 年間管理料(永代供養料) | 約1万円~ |
| 区画料(土地代) | 30万円〜130万円前後 |
埋葬料とは、ご遺骨を新しい区画に埋葬するための費用で、ご遺骨ごとに埋葬料がかかるケースがほとんどです。
年間管理料とは、契約期間中のお墓を維持・管理してもらうための費用です。
通常はご遺族がお墓参りや清掃を行いますが、永代供養墓の場合は施設に依頼をするために費用がかかります。
合葬墓・合祀墓(集合墓)の永代供養墓
永代供養墓には、ご遺骨を共同のスペースにそのまま埋葬する合葬墓や、ご遺骨を骨壷に入れた状態で共同のスペースに埋葬・安置する合祀墓(集合墓)があります。
合葬墓は、ご遺骨を骨壷に入れずスペースも取らないため安価です。
合祀墓は骨壷に入れるので、合葬墓よりは費用がかかります。
いずれも、個別の永代供養墓に比較すると費用は1/3ほどに抑えられます。
| 埋葬料(合葬墓) | 5〜15万円 / 霊位 |
| 埋葬料(合祀墓) | 20〜50万円 / 霊位 |
樹木葬
樹木葬とは、通常のお墓のように墓石を目印とするのではなく、樹木や草花を目印としたお墓です。
樹木葬の費用相場は、20万円~80万円程度になります。
多くの樹木葬は、共通のスペースにご遺骨をそのまま埋葬する合葬型、または、ご遺骨を骨壷に入れた状態で埋葬する集合型の2種です。
樹木葬では、墓じまいに加えて以下の費用がかかります。
| 埋葬料(合葬型) | 5〜15万円 / 霊位 |
| 埋葬料(集合型) | 20〜50万円 / 霊位 |
個別の区画がある永代供養墓のように土地代(区画料)がかからず、埋葬料のみなので比較的安価に改葬可能です。
散骨
散骨とは、ご遺骨を粉状にし、そのご遺灰を海や山などの自然に撒いて供養する方法になります。
散骨の費用相場は、約5万円~70万円程度です。
散骨の方法は、海洋散骨や山林散骨などがありますが、代理で散骨してもらうのか、自分達も一緒に行って散骨するのか(個別か合同か)によっても費用が変わってきます。
手元供養
手元供養とは、ご遺骨の一部を自宅にある仏壇等で供養する方法です。
手元供養の相場は、数百円~300万円程度です。
遺骨をどのように供養するかによって、金額が変わります。
取り出した遺骨をそのまま骨壺等に入れて供養するのであれば、費用はほとんどかかりませんが、ペンダント等に入れられるよう粉骨するには1~3万円程度の費用が追加でかかります。
また、遺骨をダイヤモンドに加工する場合の費用は、数十万~300万円程度です。
墓じまいを進める際の注意点とトラブル対策
お墓やご先祖様の供養には、絶対的な正解があるわけではありません。
ご遺族それぞれの価値観や思いが関わってくるため、意見が分かれるのは自然なことです。
しかし、独断で進めてしまうと、親族や菩提寺とのトラブルに発展する可能性もあります。
以下のポイントに注意しながら、墓じまいを丁寧に進めましょう。
親族での話し合い
先祖代々のお墓であれば、自分たちだけで判断せず、関係する親族全体への配慮が欠かせません。
お墓参りをしている親族がいれば、感情的な反発を受けることも考えられます。
いきなり「墓じまいを決めた」と伝えるのではなく、まずは「検討している」段階で相談するのが望ましいです。
また、費用負担や管理の問題を共有することで、話し合いによって解決の道が見つかることもあります。
菩提寺との交渉
菩提寺との関係も慎重に進めるべきポイントです。
突然「墓じまいをします」と伝えてしまうと、住職の心象を損ね、結果として高額な離檀料を請求されたというケースも報告されています。
離檀料に法的根拠はありませんが、閉眼供養や墓石の撤去に協力が得られないなど、実務に支障が出る可能性もあります。
そのため、早い段階で事情を丁寧に説明し、理解を得ながら進めることが大切です。
業者選びや日程調整などは、できれば菩提寺との話し合いが済んでからにしましょう。
業者選定
墓じまいの工事を請け負う石材店は、地域によっては数が限られており、かつて依頼した業者が廃業している場合もあります。
最近ではインターネット経由で業者を探す方も増えていますが、 「見積もりが極端に高額」「安価だったが手抜き工事だった」といったトラブルも少なくありません。
依頼前には、以下の点を必ず確認しましょう。
-
-
作業範囲と費用に含まれる内容
- 追加料金の有無
- 現地調査の有無
- 撤去証明の発行有無
-
どこまでの作業が含まれていくらなのかなど具体的な内容を確認するだけでなく、見積もりは必ず複数の業者から取って選定することをおすすめします。
墓じまいを後悔しないために
墓じまいをするには時間も労力もかかります。
苦労して手続きを進めたのに、親族との関係が悪化してしまったり、心残りのある形になってしまったりするのは避けたいところです。
後悔のない墓じまいにするためには、手続きだけでなく、心の整理や供養のあり方についても事前によく考えておくことが大切です。
墓じまい後のメンタルケア
合葬墓や永代供養墓に納骨する場合、遺骨を後から取り出すことは基本的にできません。
そのため、墓じまいを進める前に、「本当にお墓がなくなっても大丈夫か」「新しい供養のかたちに納得できるか」を、自分の気持ちと丁寧に向き合って確認することが大切です。
特に、これまでお墓参りを大切にしてきた方にとっては、精神的な影響が大きいこともあります。
新しい供養先で気持ちが落ち着けるかどうか、不安な場合は一度立ち止まって考えてみましょう。
法要や供養の継続方法
墓じまいをしたからといって、供養そのものをやめなければいけないわけではありません。
むしろ、今後どのように供養を続けていくかを考えることが、墓じまいの大切な一部です。
たとえば、納骨堂や永代供養墓に改葬した後でも、法要を行いたい場合は、以前の菩提寺や信頼できる寺院に相談すれば、対応してもらえることが多くあります。
墓じまいをしないという選択肢
話し合いを進めるなかで、意見がまとまらなかったり、タイミングが合わなかったりすることもあるかもしれません。
そのようなときは、「墓じまいを見送る」という判断も、選択肢のひとつです。
「今はできない」と決めることで、無理に進めるよりも、家族関係や気持ちを守れることがあります。
時間をかけて納得のいく形を探すことが、後悔のない墓じまいにつながります。
墓じまいをする際は事前準備がトラブル回避のカギ。何が最善なのか家族でしっかりと話し合いを
墓じまいは自分一人の意志だけではできず、親族やお墓のある霊園・墓地などの管理者からも同意を得る必要があります。
検討段階で周囲に相談すれば、自分だけでは見えてこなかった最善策が出てくる可能性もありますし「早く相談してくれれば良かったのに」という感情から生まれるトラブルも防ぐことにもつながります。
話し合う・相談するという事前準備が、トラブル回避のカギです。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要