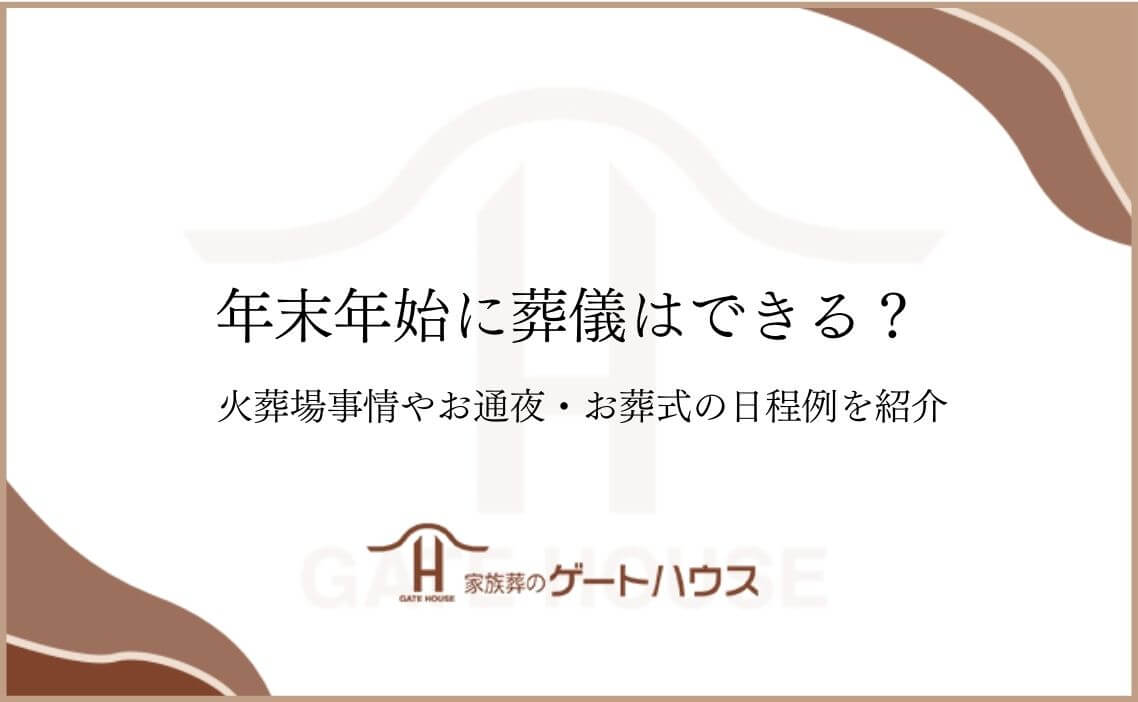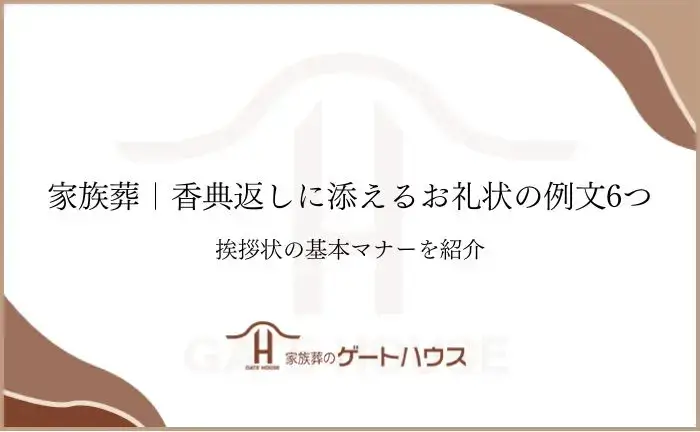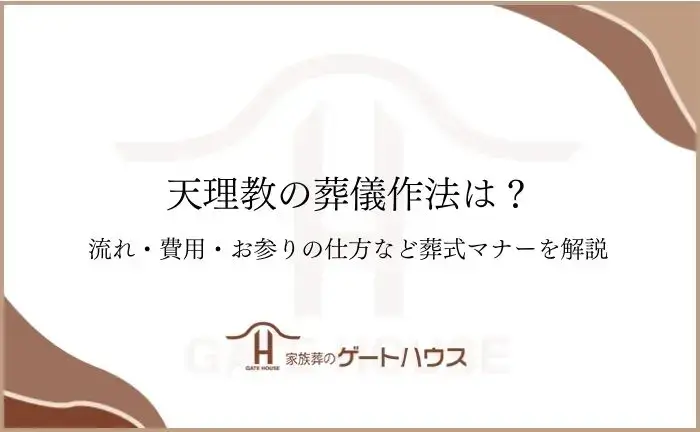喪中はがきはいつ出す?文例や書き方・誰に出すかも解説
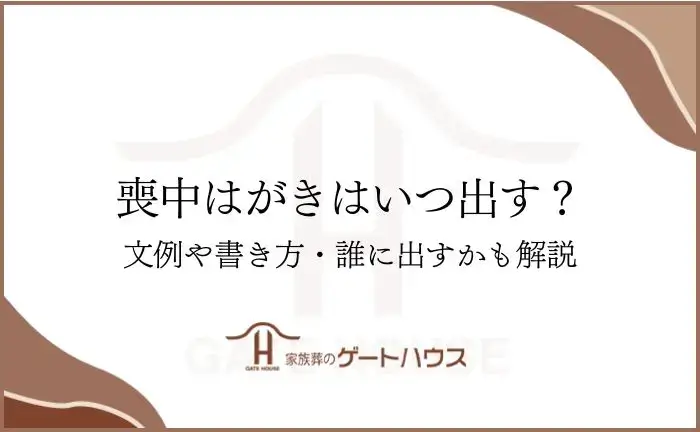
年賀状を出す習慣がある人は、大切な家族を亡くした年には、新年の挨拶を控える「喪中はがき(年賀欠礼状)」を出す必要があります。
しかし「いつ出すのが正しいのか」「誰に出せばいいのか」など、疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、喪中はがきを出すタイミングから、正しい書き方や文例、マナーまで詳しく解説します。
喪中はがきはいつ出す?タイミングは?
喪中はがきは、年賀状の準備が始まる前に相手へ届いていることが大切です。
タイミングを間違えると、相手が先に年賀状を出してしまい、お互いに気まずい思いをするかもしれません。
ここでは、喪中はがきの最適な発送時期について解説します。
遅くとも12月10日までに出す
一般的に、喪中はがきは11月中旬から12月上旬までには届くように出すのが望ましいとされています。
遅くとも12月10日頃までに相手へ届くようにするのがマナーです。
これは、相手が年賀状や年始状の準備を始めるタイミングまでに間に合うよう配慮するためです。
しかし、9月や10月など連絡をする時期が早すぎると、相手方も忘れてしまうので早ければ良いという訳でもありません。
12月中に不幸があった場合は?
12月15日の年賀状引受開始までに間に合わないなら、喪中はがきは出さない方が良いとされています。
相手の方が既に年賀状を投函してしまっている場合「どうしよう、出してしまった」と気を遣わせてしまうからです。
この場合、喪中はがきや年賀状は出さず、松の内が明けてから年賀状をくださった方に「寒中見舞い」を出します。
年賀状へのお礼と、連絡が遅れた事情を兼ねた文面で返事を出すと良いでしょう。
年賀状を手配済みの12月末に不幸があった場合は?
年賀状の投函後に不幸があった場合、配達前であれば、郵便局に取戻し請求を行い、配達を取りやめることができます。
差出地の集配局を出ていなければ無料で取り戻せますが、出てしまっている場合は取り戻し請求手数料がかかります。
喪中はがきとは?意味や定義
喪中はがきは、身内の不幸により年賀状を出せないことを知らせる挨拶状で、正式には「年賀欠礼状」といいます。
新年をともに祝えないお詫びを相手に伝える大切なマナーであり、日本では古くから続く習慣です。
「どなたの喪に服しているか」を記すことで、葬儀を知らなかった方への死亡報告の役割を担う側面もあります。
【関連記事】
喪中の正月の過ごし方にタブーはある?親戚の集まりに参加するのはあり?
喪中はがきは誰が出す?喪中の範囲
喪中はがきは、基本的に故人の家族や配偶者が出します。
一般的には、父母、配偶者(夫・妻)、子、祖父母、兄弟姉妹の二親等以内までが喪中の範囲とされています。
ただし、故人との関係性や個人の考え方によっても異なりますし、同居・同世帯かどうかを判断基準とする人もいるため、親戚やそれぞれの地方の慣習に従うようにしましょう。
喪中はがきは誰に出す?送る相手は?
喪中はがきは、普段年賀状を交換している相手に出します。
親しい友人、親戚、仕事関係の人など、新年の挨拶が必要な相手には必ず送りましょう。
また、年賀状のやりとりがあれば、葬儀に参列して頂いた方にも送ります。
逆に、普段やり取りのない人には、無理に送る必要はありません。
相手も喪中で、先に喪中はがきを受け取った場合でも、送るのが礼儀です。
しかし、ビジネス関係の相手や、それほど親しくなく余計な気遣いをさせたくない人には、通常どおりの年賀状を出す人も少なくありません。
喪中はがきを出し忘れた場合の対応
忙しさや準備不足で、喪中はがきを出し忘れてしまうこともあります。
その場合でも、落ち着いて適切に対応すれば大丈夫です。
ここでは、年賀状が届いてしまった場合の対処法も含めて説明します。
相手から年賀状が届いてしまった場合
喪中はがきを出せなかった場合、相手から年賀状が届くことがあります。
この場合は「寒中見舞い」として返事を送り、喪中である旨を伝えましょう。
寒中見舞いは1月7日から立春(2月4日頃)までに送るのが一般的なマナーです。
【関連記事】
喪中はがきが届いたら返事はどうする?マナーや状況別の文例などを解説
喪中はがきの購入方法
喪中はがきは、郵便局や文具店、コンビニ、オンラインの印刷サービスなどで購入・注文できます。
最近では、パソコンやスマホから簡単にデザインを選んで注文できる「喪中はがき印刷サービス」もあります。
自分で私製はがきを購入して手書きする方法もありますが、印刷サービスを使うと短期間で多くの枚数を用意できるので手間を省けるでしょう。
デザインと印刷の選び方
喪中はがきのデザインは、落ち着いた色合いでシンプルなものが基本です。
文字の色は黒か薄墨で、印刷等する場合はフォントを「楷書体」「明朝体」のいずれかにするのが主流です。
絵柄のカラーに関してはモノクロ・淡い青・紫などが一般的ですが、近年では故人が好きだったものをモチーフにしたり、モダンなデザインで赤や黄色を使う方も珍しくありません。
私製はがきと官製はがきの違い
官製はがきは郵便局で販売されている切手付きのはがきで、追加の切手は不要ですが、ある程度デザインが限られています。
一方、私製はがきはオリジナルの印刷・デザインが自由に選べますが、自分で切手を貼らなければなりません。
喪中はがきを出す際はどちらを使っても問題ありませんが、官製はがきを使うと切手の貼り忘れなどのミスを防げます。
こだわりたい場合は、私製はがき+弔事用切手の組み合わせがおすすめです。
喪中はがきの書き方
喪中はがきは通常の挨拶状とは異なり、特別なマナーや注意点があります。
故人との関係や喪中期間を伝えつつ、失礼のない丁寧な表現が必要です。
以下では、基本的な構成やポイントを紹介します。
| ①年賀欠礼の旨を伝える挨拶文 前文や時候の挨拶などは必要なく「新年」「年始」「年頭」などを使用します。 ②故人について 故人の名前と命日(大半の場合は月のみ)、享年を記載します。 ③感謝の言葉 先方への感謝の言葉、先方の無事を祈る言葉を記載します。 ④結びの挨拶 今後も変わらぬお付き合いをお願いするための言葉を添えます。 ⑤日付 喪中はがきを出す日付を書きます。 ⑥差出人の情報 喪中はがきの差出人の氏名・住所・連絡先を書きます。 夫婦連名で喪中はがきを出す場合は、右から夫の氏名、夫の名前の左側に妻の名前のみを記すのが基本です。 |
喪中はがきの文例
喪中はがきでは、故人の逝去を知らせるとともに新年の挨拶を控える旨を簡潔に伝える必要があります。
ここでは実際の文例を紹介します。
「喪中につき年末年始のご挨拶を謹んでご遠慮申し上げます
本年〇月に母 〇〇(享年〇歳)が永眠いたしました
生前に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに
明年も変わらぬご交誼を賜りますようお願い申し上げます
令和〇年〇月〇日
東京都千代田区〇〇〇〇
山田太郎
花子」
このように、喪中はがきはシンプルかつ礼儀正しい文章が求められます。
特に忌み言葉や祝いの表現は避け、句読点も使わないのがマナーです。
喪中はがきの書き方マナーや気を付けるポイント
喪中はがきには通常の手紙やはがきの書き方とは違うルールがあります。
細かいポイントを守ることで、相手に対して誠意を伝えられるでしょう。
ここでは、特に注意しておきたい書き方のポイントを紹介します。
数字は漢数字で表記
喪中はがきは縦書きで文章を記述しますので、年号や日付、年齢などの数字は「一、二、三」といった漢数字で表記しましょう。
これは日本語の伝統的な表記法で、格式を重んじる意味があります。
句読点をつけない
正式な挨拶状や喪中はがきでは、句読点を使わないのが一般的です。
文章を区切らずに続けることで、途切れのない気持ちを表現するとされています。
代わりに空白のスペースを空けて、読みやすい文体に整えましょう。
毛筆を使用していた時代では、句読点を用いると「学のない人」という認識を与えていた名残があり、句読点を使用しない書き方がマナーとして残っています。
差出人の情報
差出人として夫婦を連名で記す場合、故人は夫からみた続柄で書き、夫から妻の順に記します。
子の名前は一般的に記載しませんが、家族ぐるみでお付き合いがあった方へ送られる場合であれば、子を含む家族を連名で入れても問題ありません。
頭語や結語を避ける
喪中はがきでは、前文を省略します。
「拝啓」「拝呈」「啓上」などの頭語や「敬具」「敬白」「拝具」などの結語、時候の挨拶を入れることは基本的にありません。
あくまで簡潔かつ端的に欠礼の挨拶を伝えます。
忌み言葉を避ける
「死ぬ」「切れる」「終わる」などの不幸や不吉を連想させる忌み言葉は使用しないようにしてください。
また「度々」「重ね重ね」などの重ね言葉も不幸が重なることを連想させるため、使用を避けます。
祝いを表す言葉を避ける
「おめでとう」や「祝う」などの言葉は、新年の挨拶ではよく使われますが、喪中はがきには相応しくありません。
「年賀」という言葉は避け「年始」「新年」「年頭」と記しましょう。
文章全体を通して、慎ましく落ち着いた表現にします。
【関連記事】
喪中にあけましておめでとうは言わない?言われたらどう返す?代わりの挨拶も紹介
喪中の人に「良いお年を」と言って良い?年末の挨拶マナーや過ごし方を解説
近況報告を書かない
喪中はがきは弔事に関してのみ記載するものなので、通常の年賀はがきのように個人的な近況報告や、自分や家族の近影を載せることは控えます。
近況報告を行いたい場合は寒中見舞いで伝えましょう。
あくまで欠礼の挨拶と故人の報告に留め、別の機会に改めて近況を伝えるのがマナーです。
喪中はがきは11月中に出すと安心!マナーを守って心のこもった挨拶を
新年の挨拶を欠礼する旨を丁寧に伝える「喪中はがき」は、単なる形式的なものではなく、相手への思いやりと故人への敬意を表す大切な挨拶状です。
マナーを守ることで、相手に無用な心配や手間をかけず、誠意を伝えることができますので、相手が年賀状を用意する前の11月中に手配しておくと良いでしょう。
郵便局やオンラインサービスも活用して、デザインや印刷を早めに準備し、家族や関係者と相談しながら、心のこもった一枚を作りましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要