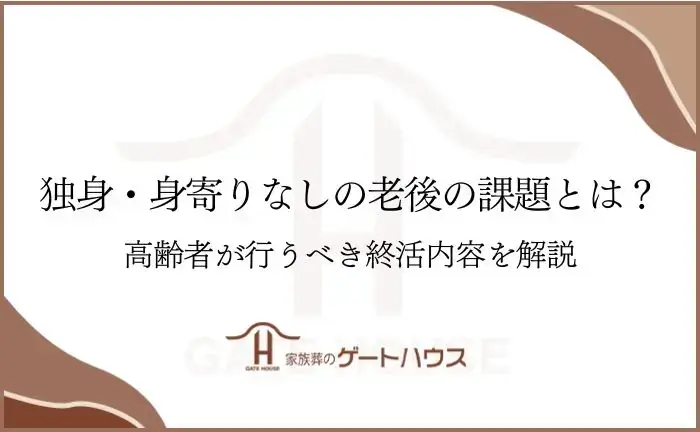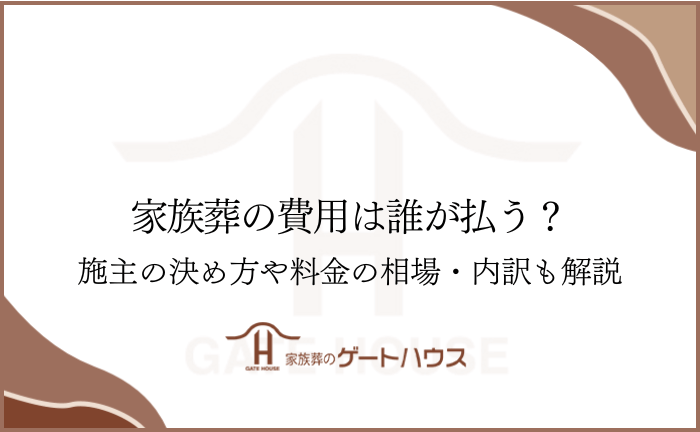お盆に葬儀や火葬はできる?葬儀までご遺体を管理する方法や注意点なども解説
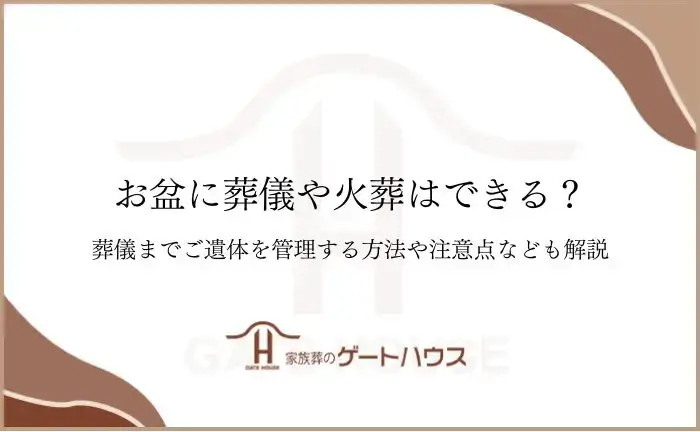
「お盆」は、ご先祖様を現世にお迎えし、供養する期間です。
そのため、お盆に葬儀や火葬はできるのか、疑問に思う方も多いでしょう。
この記事では、お盆に葬儀・火葬はできるのか、お盆に葬儀・火葬を行う場合の注意点などを詳しく解説します。
お盆に葬儀はできる?
一般的に、お盆の期間とされているのは、8月13日〜8月16日です。
ただし、一部の地域や宗教・宗派によっては、7月13日から16日に行われることもあります。
それでは、お盆の時期に葬儀を行うことができるのか、詳しく見ていきましょう。
お盆でも葬儀はできる
基本的に、お盆の期間でも葬儀は執り行えます。
12月31日〜1月3日の年末年始に当たる期間は、葬儀場や火葬場など葬儀に関わる施設が休業することが多いものの、お盆の期間は通常通り対応していることが多いです。
「お盆に葬儀を行ってはいけない」というルールも特にないため、各施設の予約さえできれば、お盆であっても葬儀・火葬ともに行えます。
火葬場の休業日は葬儀ができない
たとえ葬儀社が営業していても、火葬場が休業している場合は葬儀を執り行うことができません。
お盆に限らず、一般的に葬儀を執り行えるか否かは火葬場の営業状況によって決まります。
前述の通り、火葬場はお盆の期間中も開いていることが多いですが、六曜の「友引」と重なる日は縁起が悪いとされているため、休業するケースが多く見られます。
また、友引は斎場も休業になることが多く、お盆に関わらず葬儀を行うのは難しいでしょう。
お盆に葬儀をする時の注意点
お盆は、ご先祖様の霊を迎え、丁重に供養する大切な期間です。
そのため、お盆に葬儀を行う場合は、いくつか注意すべき点があります。
続いては、お盆に葬儀をする時の注意点について解説します。
僧侶の都合がつきにくい
お盆の時期になると、僧侶は檀家をまわってお盆の法要を行います。
多い時は一日に十数軒の檀家をまわることもあるなど、お盆は寺院・僧侶が一年のうちでもっとも忙しい時期です。
そのためお盆期間は僧侶の都合がつかず、葬儀ができない可能性も少なくありません。
ただ、お寺によっては複数の僧侶がいたり、または時間を工面してくれたりするケースもあるため、お盆に葬儀をする必要がある場合は、相談してみると良いでしょう。
参列者が集まりにくい
お盆は各家庭で法要を行っているほか、帰省や旅行など様々な予定を入れているケースも多く、葬儀に参列者が集まりにくい可能性が高いです。
また、参列したくても新幹線のチケットやホテルの予約などが取れない、渋滞に巻き込まれて葬儀に間に合わないなども考えられます。
故人を一人でも多くの人にお見送りしてほしい場合や、故人が生前関わった人を葬儀に呼ぶことを希望している場合は、叶いにくいかもしれません。
お盆で葬儀ができない場合ご遺体はどうする?
お盆の期間に葬儀ができない場合、ご遺体をどうすべきか悩む人は非常に多いです。
気温も湿度も高い時期であるため、保存状態が心配な人も少なくないでしょう。
続いては、お盆に葬儀ができなかった場合、ご遺体の安置はどうすべきかについて解説します。
自宅でご遺体を安置する
ご遺体の安置場所の一つとして挙げられるのが、故人または喪主が暮らしている自宅です。
ただ、お盆の時期は気温も湿度も高いため、棺の中にドライアイスを置き、ご遺体が腐敗しないようにケアする必要があります。
加えてエアコンなども駆使して室温を低く保つことができれば、ある程度ご遺体の腐敗を防止できるでしょう。
しかし、自宅での安置期間が長引く場合はご遺体の状態を保つことが難しいため、できるだけ早く葬儀社に連絡しましょう。
遺体安置施設を活用する
ご遺体を自宅に安置するのが難しい場合は、遺体安置施設の利用がおすすめです。
遺体安置施設は保冷設備が整っているため、ご遺体の状態を心配する必要はなく、安心して任せられます。
ご遺体の状態を保ちながら葬儀当日を迎えられるのはもちろん、場所によっては葬儀までに面会をすることも可能です。
遺体安置施設は葬儀社に併設されていることが多いほか、民間の安置施設などもあるため、事前に調べておくと良いでしょう。
エンバーミングも検討する
「エンバーミング」とは、ご遺体の腐敗を防いで衛生的に保存する技術のことです。
日本語では「遺体衛生保全」と呼ばれ、葬儀をするまでに長い期間がかかる場合に行われます。
具体的には、ご遺体を殺菌消毒し、血液を抜いて防腐溶液を注入することで腐敗を防ぎ、修復処理や化粧を施すことで生前の姿に近づけます。
ご遺体を綺麗な状態で保全できる点は大きなメリットですが、費用相場は15〜20万円ほどと決して安くはないため、費用を含め検討するのがおすすめです。
お盆の葬儀に関するよくある質問を紹介
お盆に葬儀を行う場合、葬儀の準備や流れは一般的なケースと同じなのか、それとも違いがあるのかなど、疑問に思う人も多いかもしれません。
そこでこの項目では、お盆に葬儀を行う場合のよくある質問をご紹介します。
葬儀の準備はいつからするべき?
葬儀の準備を始めるタイミングは、大きく分けて三つあります。
一つ目は終活を考え始めた時、二つ目は葬儀社による葬祭関連のイベントに参加した時です。
これらは、周りではなくご本人が葬儀の準備を始めるタイミングといえるでしょう。
もう一つ葬儀の準備を始めるタイミングとして挙げられるのが、ご本人の病状が思わしくない時です。
こちらは本人だけでなく、周りが葬儀の準備を始めるタイミングといえます。
詳しくは以下の記事でご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
【詳しくはこちら】
葬儀の準備はいつからする?チェックリスト付きで事前にすべきことを解説
そもそも喪主って誰がする?
喪主は誰が務めても良いとされていますが、一般的には故人と血縁関係が近い人が行うことが多いです。
故人に配偶者がいる場合は配偶者、いない場合は子供、子供もいない場合は兄弟姉妹や親族が行います。
また、故人の血縁関係に適当な人がいない場合、故人の友人や知人が喪主を務めることもあります。
喪主の決め方など、より詳しい情報は以下の記事でご紹介していますので、合わせてご覧ください。
【詳しくはこちら】
喪主は誰がやると良い?続柄の優先順位や決め方・葬儀でやることを解説
亡くなった後から葬儀までの流れは?
ご逝去後、まずは葬儀社の手配を行います。
次に葬儀のプランや日程を決め、その後僧侶の手配や関係各所への連絡を行うのが一般的です。
また、同じタイミングで死亡診断書の受け取りや死亡届の提出など、各種手続きも行います。
また、お葬式はお通夜から始まり、翌日に告別式と火葬・収骨を行うケースが多いです。
より詳しい流れは以下の記事でご紹介しておりますので、万が一に備えてご確認ください。
【詳しくはこちら】
お葬式は何日後にするもの?亡くなってから葬儀までにかかる日数を解説
お盆でも葬儀はできる!事前の相談はゲートハウスへ
お盆に当たる時期も、葬儀は執り行えます。
しかし、お盆に関係なく友引が重なる場合は火葬場が休業のケースが多いので注意しましょう。
また、お盆期間中は僧侶の都合がつきにくい、または参列者が集まりにくいといった注意点もあります。
遺体安置施設を利用したり、エンバーミングを行なったりすれば、お盆が明けるのを待って葬儀を執り行うこともできます。
家族葬のゲートハウスでは事前のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要