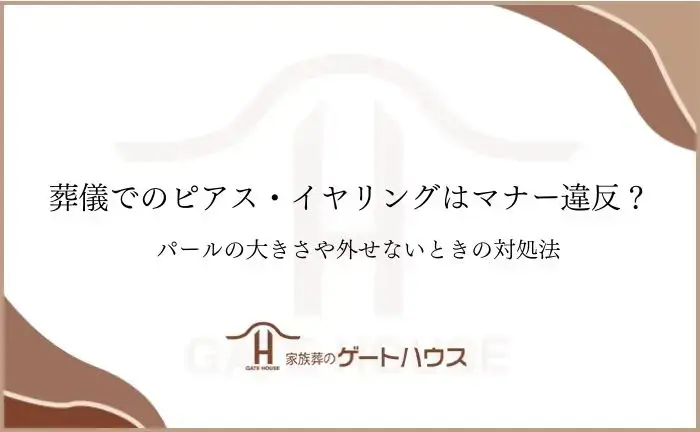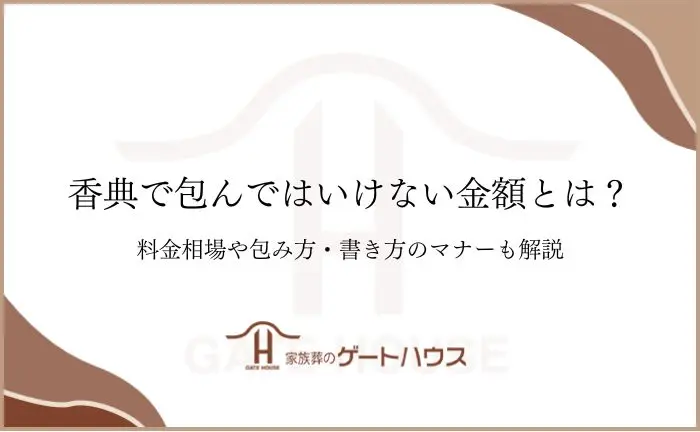お彼岸のお墓参りはいつ行くべき?春秋別の日程・時間やマナーについて解説
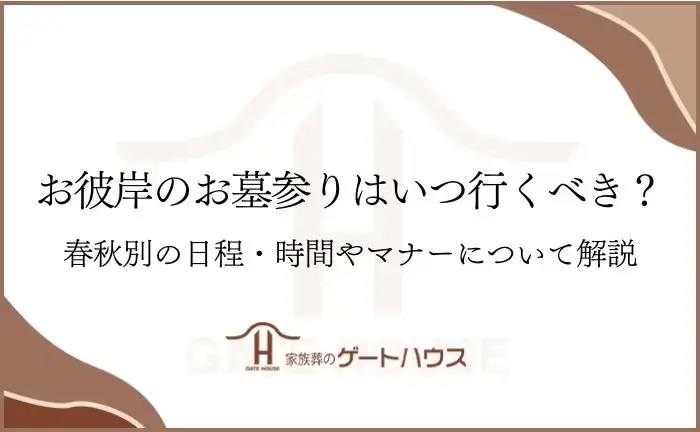
春と秋のお彼岸には、お墓参りをする風習があります。
しかし、いつ行くのが正しいのか、どのタイミングが一般的かなど、日程や時期について悩んでいる人は多いかもしれません。
また、都合がつかず行けない場合や、お参りのマナーなども気になるところです。
この記事では、お彼岸のお墓参りについて詳しく解説します。
お彼岸とは?お墓参りをする意味は?
お彼岸になると、家族でお墓参りに行く人も多いでしょう。
しかし、名前は知っていてもお彼岸自体の意味や、なぜこの時期にお墓参りをするのかは知らない人もいるかもしれません。
まずはお彼岸について、お墓参りをする意味も解説します。
お彼岸とは
そもそもお彼岸は日本独自の風習で、毎年「春分の日」と「秋分の日」を中日とした前後3日間、合計7日間にご先祖様や仏様に感謝の気持ちを込めて供養する仏教行事のことです。
「彼岸」は仏教用語で「あの世」を意味し、悟りの境地とされています。
一方で「此岸(しがん)」と呼ばれる「この世」は、煩悩や迷い、苦悩が溢れる世界だといわれます。
彼岸期間は供養だけでなく、仏教の教えに従って自分自身を見つめなおし、修行する時期でもあるのです。
お彼岸にお墓参りをする意味
昼と夜がほぼ同じ長さになるお彼岸の時期は、あの世とこの世が近くなると考えられています。
したがって、あの世に想いが通じやすくなるとされているため、この時期にお墓参りへと出向き、ご先祖様に会いに行くという意味があるのです。
また、仏教の西方浄土(さいほうじょうど)の考えから、真東から昇った太陽が真西に沈む時期は、浄土への道しるべができるとされるため、供養を行ったという説もあります。
同じくお盆にもお墓参りをしますが、それはあの世から戻ってくるご先祖様を迎えに行くためです。
お彼岸のお墓参りは、こちらからご先祖様に会いに出向くため、お盆のお墓参りとは意味合いが異なります。
お彼岸のお墓参りはいつ行くべき?時間帯は?
お彼岸のお墓参りは、期間中であればいつ行っても問題ありません。
しかし、地域や家庭によっては六曜を気にすることもあるため、心配な場合は親族に相談してみましょう。
ここでは、お彼岸のお墓参りの時期や、時間帯について紹介します。
※六曜:先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口
秋(9月)のお彼岸のお墓参りはいつ行く?
2025年秋(9月)のお彼岸は、以下の時期です。
| 彼岸入り | 2025年9月20日(土) |
| 中日(秋分の日) | 2025年9月23日(火) |
| 彼岸明け | 2025年9月26日(金) |
秋のお彼岸は、2025年9月20日(土)~9月26日(金)です。
六曜の日取りとしては、20日(土)大安・23日(火)先負・24日(水)仏滅・25日(木)大安がお墓参りに適しています。
春(3月)のお彼岸のお墓参りはいつ行く?
2026年春(3月)のお彼岸は、以下の時期です。
| 彼岸入り | 2026年3月17日(火) |
| 中日(春分の日) | 2026年3月20日(金) |
| 彼岸明け | 2026年3月23日(月) |
春のお彼岸は、2026年3月17日(火)~3月23日(月)です。
お墓参りに適している六曜の日取りは、17日(火)大安・19日(木)友引・20日(金)先負・21日(土)仏滅・22日(日)大安なので、お墓参りに行く際の参考にしてみてください。
お彼岸のお墓参りに行く時間帯は?
お彼岸のお墓参りに行く時間帯は、午前中がおすすめです。
日が出ている朝の清らかな空気は邪気を払うといわれるため、午前中か午後の早い時間に行くのが望ましいでしょう。
日が沈んでからのお墓参りは、無縁仏や餓鬼などを連れて帰るといわれています。
また、足元が悪く転倒の恐れがあるほか、お墓掃除がしにくいこと、霊園や寺院によっては閉園時間があることから、できるだけ明るいうちに行きましょう。
お彼岸はお墓参りに行かないとダメ?時期を早めるのは?
お彼岸だからといって、必ずしもお墓参りに行く必要はありません。
供養において最も大切なのは、故人やご先祖様を想う気持ちです。
お墓参りに行けない場合は、お仏壇にお参りしたり、お墓がある方向に向かって手を合わせたりなど、できる範囲で感謝の気持ちを表現するだけでも供養になります。
お墓参りをするのは、お彼岸の時期以外でもかまいません。
お彼岸はお墓参りに最適な機会ではありますが、無理せず都合がつくタイミングでお参りしましょう。
お彼岸のお墓参りのお供え物に関するマナー
お彼岸にお墓参りに行くときは、お供え物を用意します。
特別なものをお供えする必要はありませんが、基本的なマナーは心得ておきたいものです。
それでは、お彼岸のお墓参りのお供え物に関するマナーについてチェックしてみましょう。
五供を用意する
お彼岸のお墓参りのお供え物には、五供(ごく)を用意しましょう。
五供は仏教において基本的なお供え物とされ「香・花・灯明・浄水・飲食」の5つを指します。
具体的には、お線香・仏花・ロウソク・水・飲食物を用意しましょう。
故人が好きだったものをお供えしてもかまいませんが、春彼岸にはぼたもち、秋彼岸にはおはぎをお供えするのが定番になっています。
供花以外は持って帰る
お彼岸に限らず、お墓参りの際にお供えしたものは、供花以外を持ち帰るのも大切なマナーです。
特に飲み物や食べ物などは、カラスが荒らしたり、害虫を寄せ付けたりしてお墓を汚す可能性があります。
周囲にも迷惑となるため、お参りが終わったら必ず持ち帰ってください。
霊園や寺院によっては、供花の持ち帰りを推奨していることもあるので、それぞれの方針に従いましょう。
【関連記事】
お彼岸にすることとは?お仏壇・お墓にお供えするものや仏壇飾りについて解説
お彼岸のお墓参りの供花に関するマナー
お彼岸のお墓参りでは、どのような花をお供えすれば良いのか悩む人もいるでしょう。
「こうしなければならない」というルールはないものの、季節にふさわしい花やお供えしてはいけない花などについては知っておきたいですね。
ここでは、お彼岸のお墓参りの供花に関するマナーについて解説します。
お墓に供える花の選び方
お彼岸でお墓参りの際にお供えする際は、
-
- キク
- ユリ
- カーネーション
- リンドウ
など日持ちしやすい花が定番として選ばれています。
お墓に供える花に決まりはないので、故人が好きだった花や思い出の花などをお供えしても良いでしょう。
また、春にはスイートピーやフリージア、秋にはケイトウやコスモスなど、季節を感じさせる花を取り入れるのもおすすめです。
色にも決まりはありませんが、白や黄色、ピンク、青、紫など、淡いカラーの花がよく用いられています。
お墓に供えてはいけない花はある?
お墓参りで供えてはいけない花には、毒がある花や香りが強い花、トゲがある花、ツルがある花などがあげられます。
また、ツバキやサザンカなどの花が落ちるものは死を連想させるため、お供えするのは控えましょう。
稲穂やアワなどの食べられる植物も、動物や虫に荒らされる可能性があるため、お墓の供花には不向きです。
造花やプリザーブドフラワーも供えられますが、仏教では綺麗な花が枯れていく様子が諸行無常の教えを表すと考えられています。
さまざまな事情がありますが、無理のない範囲で生花をお供えしたいものですね。
お墓に花を供える正しい方法
お墓参りでは、ご先祖様が空から私たちを見ていることを意識して、花がまっすぐ立つようにお花を供えます。
上から見たときに、茎を束ねたビニール紐や輪ゴムなどが見えていないか確認しながらお供えしましょう。
お墓や仏壇に飾る仏花は、左右対称にするものと思うかもしれませんが、必ずしも対にする必要はありません。
左右対称でなくても気持ちを込めて整えれば、きっと故人やご先祖様に喜んでもらえるはずですよ。
お彼岸のお墓参りの服装に関するマナー
お彼岸のお墓参りには、どのような服装がふさわしいか迷うかもしれません。
お墓参りだけなのか、彼岸法要にも参列するのかによって好ましい服装は異なります。
最後に、お彼岸のお墓参りの服装に関するマナーをチェックしてみましょう。
お墓参りだけの場合
お彼岸にお墓参りだけ行う場合は、普段着で問題ありません。
墓掃除や草むしりをするので、スニーカーにパンツスタイルなど、動きやすく汚れても良い服装がおすすめです。
ただし、故人やご先祖様に挨拶をする場なので、派手な色や露出の多い服は控えましょう。
また、本堂にご挨拶する必要がある場合は、失礼がないように落ち着いた服装を心がけてください。
法要にも参加する場合
お墓参りだけでなく、彼岸会や法要に参加する場合は、落ち着いた色味のスーツやワンピースなどの平服を着用しましょう。
霊園や寺院によっては、お墓までの道のりが舗装されておらず歩きにくいこともあるので、ピンヒールやハイヒールなどは避けたほうが無難です。
殺生を連想させる毛皮や革製品、華美なアクセサリーなどを身に着けるのも控えてください。
【関連記事】
お彼岸でやってはいけないことは何?してはいけないタブーな行動はある?
お彼岸のお墓参りは中日が基本!正しいマナーを知り心を込めて供養しましょう
お彼岸のお墓参りは、中日とよばれる「秋分の日」や「春分の日」が基本ですが、期間中であればいつ行っても良いでしょう。
供養において最も大切なのは、故人やご先祖様を想う気持ちなので、彼岸入り前や彼岸明けなど時期がずれても問題ありません。
あくまでお彼岸はお墓参りに最適なタイミングとして考え、無理のない範囲でお参りしてください。
お供え物や供花、服装に関するマナーをおさえ、心を込めて供養しましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要