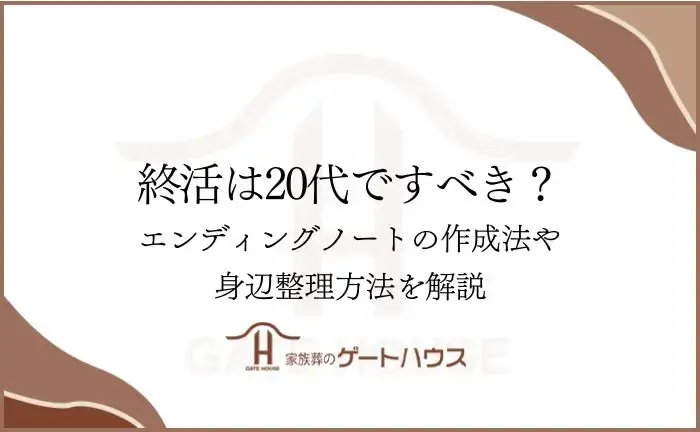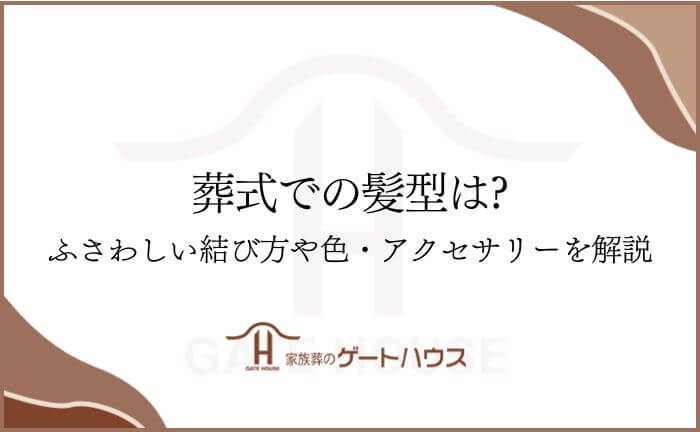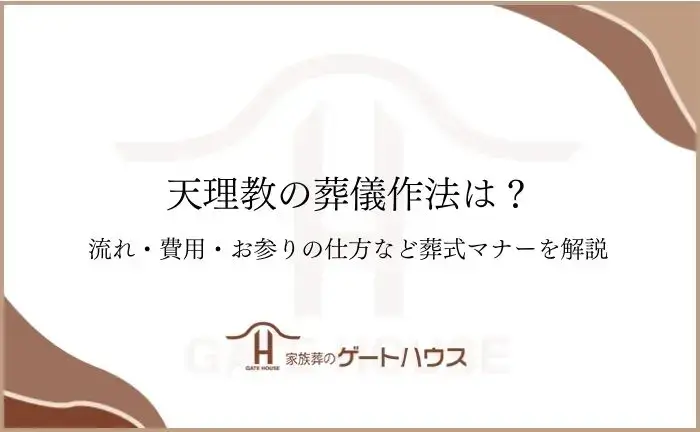無宗教葬儀とは?お坊さんは必要?流れ・香典や服装のマナー・その後の供養を解説
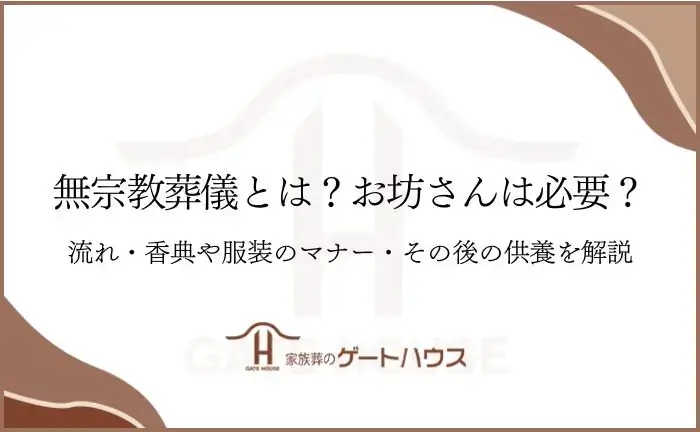
近年では特定の宗教にとらわれず、自由な形式で執り行う無宗教葬儀を選択する人が増えています。
しかし、自由度が高い分、どのような流れで葬儀を進行するべきか悩みますよね。
この記事では、無宗教葬儀の詳細やお坊さんを呼ぶかどうか、メリット・デメリットなどを紹介します。
無宗教葬儀とは?お坊さんは必要?
無宗教葬儀とは、宗教儀式を行わず、自由なスタイルで進行する葬儀のことです。
宗教者を呼ばずに執り行うのが一般的で、焼香や読経などの儀式も行いません。
故人の希望や好みに沿って執り行えることから「自由葬」とも呼ばれています。
決まった流れや形式も一切ないため、故人が好きだった音楽の生演奏を依頼したり、故人との思い出をビデオで流したりと、思い思いの形で故人と向き合える葬儀スタイルです。
ここでは、無宗教葬儀の詳細について解説します。
必ずしもお坊さんを呼ぶ必要はない
宗教儀式を行わない無宗教葬儀では、仏教やキリスト教など特定の宗教との関わりがない葬儀となるため、宗教者を呼ぶ必要はありません。
お坊さんを呼ばないからといってマナー違反にはならないので、安心していいでしょう。
ただし「無宗教葬儀=お坊さんを呼んではいけない」という決まりも存在しません。
「一般的な葬儀と同じように故人を偲びたい」という親族の希望がある場合は、無宗教葬儀でもお坊さんを呼ぶことが可能です。
近年は認められつつある
あまりなじみのない「無宗教葬儀」ですが、葬儀の多様化により、近年では認められつつある葬儀形式の一つです。
現代においても、日本では仏式での葬儀が大多数ではあるものの、昔に比べると少しずつ無宗教葬儀の割合が増えてきています。
宗教にこだわらない人が増えた背景としては、核家族化により宗教に触れる機会がなかったり、そもそも宗教への関心が低かったりすることが要因といえるでしょう。
昔に比べて宗教観の自由化も進んでいるため、無宗教葬儀に抵抗を感じない人も増えています。
参考:全日本冠婚葬祭互助協会HP「Ⅲ.葬儀に関するアンケート結果」
無宗教葬儀の費用相場は?
無宗教葬儀は内容を自由に決められる分、はっきりとした費用相場がありません。
どの規模の会場を選ぶかや、飾りつけ、演出など、葬儀内容によって費用は大きく上下します。
目安としては、無宗教葬儀の一つである直葬(火葬式)の費用相場を参考にするのがおすすめです。
ご遺体を自宅・病院などから直接火葬場へ搬送し、火葬のみを行うシンプルな見送り方で、費用相場も通常の葬儀よりも安いといわれています。
この金額に、会場使用料やセレモニー費用が加算されると考えましょう。
また、宗教者を呼ばない場合はお布施がいらないため、一般葬と比べると葬儀費用は抑えられます。
無宗教葬儀のメリットは?
特定の宗教にとらわれない無宗教葬儀は、決まった流れがないからこそ、故人の人生を反映させたオリジナリティあふれる葬儀が可能です。
ここでは、無宗教葬儀で得られるメリットを解説します。
自由な葬儀の内容にできる
無宗教葬儀は、決まった形式が一切ない葬儀となるため、内容を自由に計画できる点が特徴です。
故人が生前好きだった音楽を流したり、趣味のコレクションを展示したり、故人らしさが詰まった空間で故人とゆっくり向き合えます。
仏式や神式などの葬儀では行えない演出ができる自由度の高さが、メリットの一つです。
【関連記事】
自由葬とは?流れ・葬儀例や香典・服装マナーを紹介
信仰している宗教に問わず参列できる
信仰している宗教が家族間で異なる場合や、他宗教の葬儀への参列が難しい人でも、無宗教葬儀であれば問題なく参列できるのもメリットです。
また、宗教によっては、そもそも葬儀を執り行わないところもあります。
しかし「お葬式で故人を見送りたい」と親族が希望した場合、宗教の縛りがない無宗教葬儀を行うことが可能です。
宗教者の費用が抑えられる
無宗教葬儀では、宗教者を呼ばずに葬儀を執り行うのが一般的です。
葬儀・告別式でのお布施の相場は20万〜50万円といわれており、その分の費用が発生しないため、経済的な負担を抑えられます。
ただし、無宗教葬儀でも、故人を偲ぶために宗教者を呼ぶことは可能です。
その場合は、一般的な葬儀と同様のお布施が必要となる可能性があります。
無宗教葬儀のデメリットは?
無宗教葬儀は多くのメリットがありますが、まだまだ少数派の葬儀形式である分、理解されるのが難しい部分もあります。
メリットだけでなく、デメリットもしっかりと理解しておくことで、より無宗教葬儀への知識が深まるでしょう。
ここでは、無宗教葬儀のデメリットを解説します。
親族から反対される可能性がある
無宗教葬儀は近年増えてはいるものの、多くの人に浸透しているとはいえない葬儀形式の一つです。
仏式などの葬儀に比べると一般的ではないので、昔からのしきたりや宗教儀式を重んじる親族から反対されるケースも考えられます。
無宗教葬儀のメリットや検討している理由を明確にして、事前に親族に伝えると、トラブルを防げるでしょう。
菩提寺との関係が悪化する恐れがある
先祖代々お世話になっている菩提寺がある場合、無宗教葬儀を選ぶと、納骨を断られるなどの問題が生じるかもしれません。
「先祖のお墓に納骨したい」と考えているなら、宗教に沿った従来の葬儀で故人を見送るほうが無難です。
ほかの納骨方法を検討している場合は無宗教葬儀でも問題ありませんが、何も知らせずに執り行うと、菩提寺との関係が悪化する恐れがあります。
菩提寺には、葬儀の前に伝えておくのを忘れないようにしましょう。
葬儀の準備が大変になる
一般的な葬儀と比べて決まった儀式や流れがない分、葬儀内容を全て考える必要があります。
故人らしさを反映させた葬儀を行えるのは魅力的ですが、大切な故人を亡くされたばかりのご遺族にとっては、大きな負担になるかもしれません。
無宗教葬儀を検討し始めたタイミングで、どんな葬儀にしたいか、取り入れたい演出はあるかなどを考えておくと、準備の負担を軽減できます。
無宗教葬儀の流れは?
宗教にとらわれない無宗教葬儀は、一般的な葬儀と比べて決まった形式がありません。
葬儀内容や流れを自由に決められるほか、故人の希望や好みを反映させられるのが選ばれる理由です。
しかし、一から葬儀を計画するのは負担が大きいため、仏式の葬儀から宗教的な儀式を除いて、故人らしさを取り入れる形が多くなっています。
以下では、それらを踏まえた一例を紹介します。
| 無宗教葬儀の流れ<一例> |
|
①入場 ・参列者が入場する ・会場の入口に参列者席の確認係を設けるといい ・入場の間は故人の好きだった曲を流したり生演奏をしたりする |
|
②開会の辞 ・司会者が葬儀の始まりを宣言 ・長すぎないようにまとめる |
|
③黙とう ・無宗教葬儀では僧侶が読経しない ・読経の代わりに黙とうを捧げる |
|
④献奏やビデオ上映 ・故人の好きだった曲を流したり、スライドを流して思い出を振り返ったりする |
|
⑤弔電の読み上げ ・届いた弔電を読み上げる |
|
⑥感謝の言葉 ・遺族の代表者が参列者に感謝の言葉を述べる |
|
⑦お別れの言葉 ・参列者が故人に最後の別れを告げる ・一般葬の弔辞にあたる |
|
⑧献花 ・焼香の代わりに花を供える ・喪主→遺族→親族→参列者の順で供える |
|
⑨閉会の辞 ・司会者が葬儀の終わりを宣言 ・挨拶後に出棺するが、別室で会食をする場合もある |
|
⑩出棺 ・故人の遺体を葬儀場から火葬場へと移す |
|
⑪会食 ・火葬後に故人を偲ぶ会食を行う |
無宗教葬儀の香典や服装などの注意点は?
メリット・デメリットを理解したうえで無宗教葬儀を希望する場合、事前にしておくべきことがあります。
ここでは、無宗教葬儀を執り行う際の注意点や、服装・香典などのマナーについても解説します。
菩提寺や親族と相談する
古くからお世話になっている菩提寺がある場合、無宗教葬儀を行った遺骨は、先祖のお墓に納骨できない可能性があります。
事前に菩提寺に相談しても理解は得られにくいかもしれないので、納骨方法や今後の法要についても考えておくようにしましょう。
また、親族に無宗教葬儀を検討していることを伝えておくのも大切です。
葬儀の直前での報告はトラブルのもとになりやすいため、必ず事前に相談し、無宗教葬儀を行いたい理由を明確にして伝えましょう。
事前にしたいことを決めておく
無宗教葬儀は全てが自由である分、行いたい演出や会場の装飾などについて悩んでしまい、直前では決めきれない可能性も。
葬儀は先延ばしにはできないので、内容の選択を迫られ、終わってから「やっぱりこうすればよかった」といった後悔が残るかもしれません。
一度しかない故人の葬儀を悔いのないものにするためにも、事前にしたいことを細かく決めておきましょう。
葬儀内容の希望を親族間で共有しておくと、全員が納得した状態で故人を見送れます。
服装は略喪服にする
無宗教葬儀の場合、服装についても決まりはありません。
しかし、故人を偲ぶという意味でも、普段着ではなく略喪服を着用するのが一般的です。
男性は無地の黒スーツ・白ワイシャツを着用し、ネクタイ・ベルト・靴などの小物は黒でそろえます。
女性は黒のワンピースやアンサンブルを着用し、30デニール程度の黒ストッキング・黒パンプスを合わせましょう。
香典は宗教と無関係な表書きにする
無宗教葬儀に参列する場合、ご遺族から香典辞退の申し出がないのであれば、一般葬と同様に香典を準備します。
白無地の封筒・白黒の水引の一般的な香典袋を選び、表書きは宗教と関係のない表記にしましょう。
無宗教葬儀では「御霊前」や「御香料」と書くことが多いです。
無宗教葬儀のその後でよくある質問
宗教にとらわれない無宗教葬儀は、宗教的要素がないため、葬儀後の法要や供養の仕方に悩むかもしれません。
最後に、無宗教葬儀のその後についてのよくある質問を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
四十九日法要や一周忌はどうする?
無宗教葬儀の場合、四十九日法要や一周忌などは必要ありません。
しかし「葬儀後に何もないのは寂しい」と感じるご遺族もいるでしょう。
その場合は、法要の代わりに、近親者で食事会を開くこともあります。
納骨の時期も自由に決められるため、故人との思い出の日にしたり、ご遺族の都合のいい日に合わせたりするのもおすすめです。
仏壇や位牌は用意してもいい?
無宗教葬儀では、仏壇や位牌も特に必要ありませんが、故人を偲ぶ何かが欲しいなら代わりになるものもあります。
無宗教葬儀の場合は、仏壇の代わりに「モダン仏壇」を検討することが多く、インテリアにマッチするものもあります。
位牌は、戒名ではなく俗名(本名)を記し、開眼供養(魂入れ)は行わない場合がほとんどです。
葬儀後の供養方法は何がある?
無宗教葬儀を選ぶ場合でも、納骨は行います。
菩提寺が管理する先祖のお墓には納骨できない可能性があるため、別の供養方法を考えておきましょう。
以下では、無宗教葬儀後の供養方法の種類について紹介します。
【無宗教葬儀後の供養方法】
- 【手元供養】遺骨の一部を身近に保管する供養方法(自宅・ペンダントなど)
- 【永代供養】寺院や霊園が遺族の代わりに遺骨を管理する供養方法
- 【海洋散骨・樹木葬】遺骨を海に撒いたり、樹木を墓代わりにしたりする供養方法
- 【公営墓地への納骨】宗教・宗派を問わず、予算も抑えられる供養方法
無宗教葬儀は宗教的要素がない葬儀。行う際はよく相談すること
無宗教葬儀は、特定の儀式など宗教的要素に縛られず、自由な形式で故人を見送れる葬儀スタイルです。
自由度が高く故人らしさを反映した葬儀が行える一方で、まだまだ認知度は低く、伝統を重んじる親族からは反対される可能性もあります。
無宗教葬儀を検討する際は、親族や菩提寺に必ず相談し、理解を得るようにしましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要