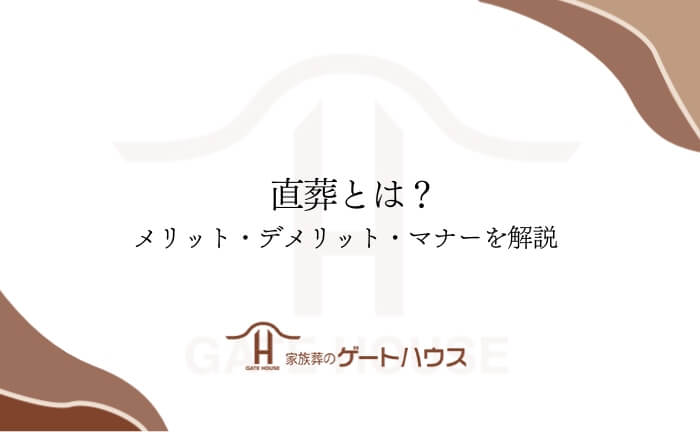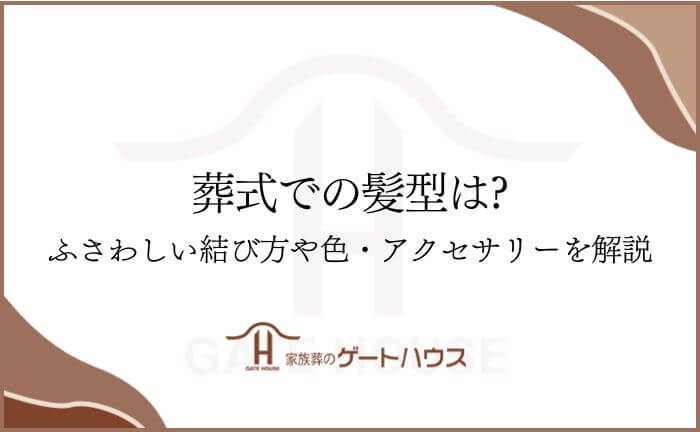独身の兄弟が亡くなった時の相続手続きについて┃流れや法定相続人の順位・トラブル対策など解説
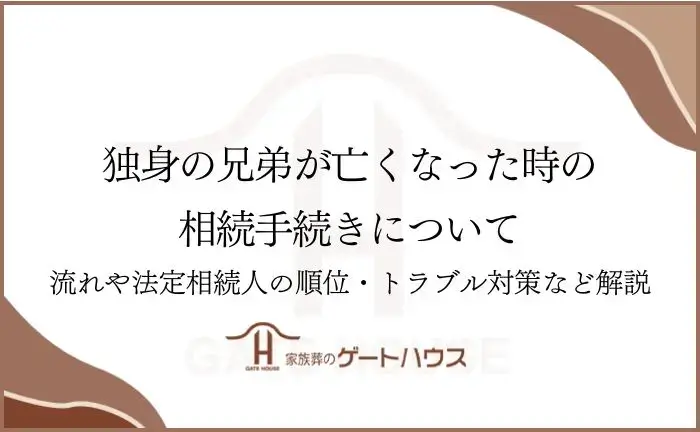
独身の兄弟が亡くなった場合の相続手続きも、一般的な相続手続きと同じ流れです。
しかし、配偶者や子どもなど近しい親族がいないケースでは、財産や相続人の調査に時間がかかることが多く、手続きの進め方に悩む人も少なくありません。
そのうえ、相続の承諾や放棄を判断する期間は短いので、注意が必要です。
本記事では、兄弟が亡くなった場合の相続順位や必要な手続き、トラブルを防ぐための注意点などについて、分かりやすく解説します。
独身の兄弟が亡くなった時の相続手続きとは
独身の兄弟が亡くなった場合でも、相続手続きの基本的な流れは一般の相続と同じです。
ただし、配偶者や子どもなどの近親者がいないケースでは、相続人の特定や財産調査に時間がかかることが多く、注意が必要です。
相続税の申告・納付には期限があり、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などが発生する恐れがあります。
また、相続放棄や限定承認の判断は「死亡を知った日から3か月以内」と定められています。
実子や養子の有無によって、兄弟姉妹が相続に関係するかどうかも変わってきますので、法定相続人の順位や状況を早めに確認することが大切です。
独身の兄弟が亡くなった時の相続手順
独身の兄弟が亡くなり相続を考えたとき、どのような手順で相続人を特定し、手続きをすればいいのか解説します。
①遺言書の有無を確認し相続人を特定
相続の手続きにおいて、最初に確認すべきは遺言書の有無です。
遺言書があれば、その内容が法定相続分よりも優先され、指定された人が遺産を受け取ることになります。
一方で、遺言書が無い場合や、法的に無効とされた場合には、民法に基づく法定相続人が財産を相続します。
遺言書がある場合
遺言書には主に2つの種類があります。
-
自筆証書遺言:本人が自筆で書いた遺言。自宅や貸金庫で保管されていることが多い。
- 公正証書遺言:公証役場で作成された遺言。原本は公証役場で保管。
自筆証書遺言が見つかった場合は、開封せずに家庭裁判所で「検認」の手続きを行う必要があります。
検認前に勝手に開封しても遺言書の効力に影響はありませんが、5万円以下の過料となる恐れがあるので注意が必要です。。
検認には通常1〜2か月程度かかりますが、内容が法的に有効であれば、遺言に従って相続が行われます。
一方、公正証書遺言は公証人によって作成されているため、家庭裁判所での検認手続きは不要で、法定相続分とは異なる内容であっても有効です。
公正証書遺言については、全国どこの公証役場でも検索可能となっています。
遺言書が無い場合
遺言書がない場合は、法定相続人を確定させる必要があります。
そのために、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集し、相続関係を明らかにします。
特に、独身の兄弟が何度も転籍している場合や、親が既に他界している場合、戸籍収集に時間がかかるケースがあります。
戸籍がそろうまでに数週間から数か月かかることもあるため、早めに手配することが重要です。
②法定相続人を確認
独身であっても子ども(実子または養子)がいる場合、その子どもが法定相続人の第一順位となります。
一方、子どもがいない場合には、相続の順位が次のように変わります。
-
- 第二順位:父母(または祖父母などの直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子ども=甥や姪が代襲相続)
たとえば、独身で子どもも両親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
なお、兄弟姉妹には遺留分(最低限相続できる権利)が認められていないため、遺言書で他の人物や団体に財産を譲る旨が記されていれば、基本的にはその内容が優先されます。
遺留分とは、配偶者・子・親などに対して法律上保障されている最低限の相続分のことを指します。
③財産を確認
相続するか放棄するかの判断、あるいは遺産分割の協議を行ううえで、財産の全体像を把握することは非常に重要です。
財産には、預貯金・不動産・車両・株式・投資信託などの「プラスの財産」だけでなく、借金やローン・保証債務などの「マイナスの財産」も含まれます。
遺言書やエンディングノートが見つからない場合は、遺品の中から通帳やキャッシュカード、請求書、郵便物などを確認し、どのような資産・負債があるのかを調査する必要があります。
また、クレジットカード会社や金融機関からの引き落とし状況、通知メールなども参考になります。
特に、独身で一人暮らしだった兄弟の場合、財産の管理状況を把握している人がいないことも多く、調査に時間がかかるケースも少なくありません。
【関連記事】
亡くなった人の預金をおろすには?口座凍結前・後の手続きや必要書類を解説
④相続放棄・限定承認の検討
相続人は、相続の方法として以下の3つの選択肢から選ぶことが可能です。
| 相続の方法 | 内容 | 詳細 |
| 単純承認 | すべての財産を相続。 | 単純承認は手続きが必要なく、相続開始から3か月経過すると自動的に成立する。 |
| 相続放棄 | すべての相続を完全に放棄。 | 3か月以内に家庭裁判所の手続きが必要。相続放棄した場合、他の相続人に権利が移る。 |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ。 | 3か月以内に家庭裁判所に手続きが必要。相続した財産の範囲内で負債を弁済する方法。 |
財産と負債を調査した結果、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合は、相続放棄を検討した方がよいでしょう。
現時点ではプラスの財産が多いものの、将来的にマイナスの財産が上回る可能性がある場合は、限定承認をするという選択もあります。
相続放棄・限定承認は、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申請しなければなりません。
また、3か月間に相続財産を使い込んだ場合、単純承認が自動成立します。
使用用途が葬儀費用であれば問題ありませんが、生活費や私的なことに使ってしまった場合は、相続放棄が認められなくなる可能性もありますので注意してください。
期限内にすべての財産(負債)の確認が難しいときは、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申請することもできます。
⑤遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員で「誰がどの財産を、どの割合で相続するか」を話し合って決める手続きです。
法定相続分を参考にしながらも、各家庭の事情に応じて柔軟に分けることができます。
遺言書がない場合や、遺言書に財産の分け方が明記されていない場合に、原則としてこの協議が必要です。
協議の結果は「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名・押印します。
この協議書は、不動産の相続登記や銀行口座の解約・名義変更などで必要となります。
協議がまとまらない場合
話し合いで協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能です。
調停でも解決しない場合は、審判(裁判)に移行し、裁判所が遺産の分割方法を決定します。
⑥相続税の申告・納付
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。
基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」と定められています。
相続税の申告と納付は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があり、遅れると延滞税や加算税が課される可能性もあり、注意が必要です。
また、兄弟姉妹が相続する場合は、相続税が2割加算されます。
相続税の2割加算は、被相続人との関係性が遠い相続人に対する税負担の調整を目的としています。
独身の被相続人のケースでいうと、子や親は生活を支える立場にありますが、兄弟姉妹や甥姪が経済的に支援しているケースは多くないため、公平性の観点から設けられた制度です。
【関連記事】
死亡後の手続きの優先順位は?身近な人が亡くなった時~葬儀後に行う手続き一覧
独身の兄弟が亡くなった時は誰に相続する?法定相続人の順位について
独身の兄弟が亡くなった場合は、子どもがいるのかどうかや、父母・祖父母が存命なのかどうかによっても相続人が変わります。
法定相続人の順位と、様々なケースについて確認していきましょう。
法定相続人の順位と相続分の割合について
法定相続人の順位と法定相続分は、以下のように定められています。
| 相続順位 | 相続人 | 関係 | 遺留分 | 備考 |
| 第一順位 | 直系卑属 | 子・養子 | あり | 子どもが死亡している場合は孫に、孫も死亡している場合はひ孫に代襲相続 |
| 第二順位 | 直系尊属 | 父母 | あり | 父母が死亡している場合には祖父母に代襲相続 |
| 第三順位 | 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹 | なし | 兄弟姉妹が死亡している場合は甥姪に代襲相続 |
優先順位の高い相続人が1人でもいれば、優先順位の低い人物は相続人にはなれません。
優先順位が同列の人が複数人いる場合は、その人数で等分して相続します。
子や養子がいる場合
兄弟が独身者であっても、子どもや養子がいる可能性があります。
-
-
離婚や死別によって別れた配偶者との間に子がいる場合
- 婚姻関係を結ばなかったものの認知している子がいる場合
- 養子縁組をしている場合
-
これらの場合、法定相続人は子や養子のみです。
実子と養子の間に相続順位や相続分の違いはなく、特別な遺言がなければ遺産は均等に分けられます。
たとえ親子が長年会っていなかったとしても、法律上の親子関係がある限り、相続権は有効です。
また、遺言書に「すべての財産を第三者に相続させる」と書かれていた場合でも、子や養子には遺留分の請求権があります。
遺留分とは?
法定相続人が最低限受け取ることのできる相続分で、相続財産の1/2(親・祖父母のみの場合は1/3)が全体の遺留分となります。
例:子が1人、養子が1人いる場合
それぞれが全体の1/4ずつ遺留分を請求可能です。
さらに、子や養子がすでに亡くなっている場合は、孫やひ孫が代襲相続人となり、元の相続人と同じ権利を持ちます。
親が存命の場合
独身の兄弟に子どもがおらず、親が健在であれば、親が法定相続人として財産を相続します。
両親が健在な場合は1/2ずつ、どちらか一方だけの場合はその親が全額を相続することになります。
両親が存命の場合は祖父母に相続権は発生しませんが、両親が死亡していて祖父母が存命の場合は代襲相続人となり、遺留分を請求することが可能です。
子や養子がいない場合
被相続人に子、養子、親、祖父母がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。
-
- 兄弟姉妹が複数いる場合は、遺言書がなければ遺産を等分します。
- 故人の兄弟姉妹のうち、すでに亡くなっている人がいる場合は、その人の子(甥・姪)が代襲相続人となります。
- 甥・姪は、他の兄弟姉妹と同等の割合で相続することができます。
※ただし、代襲相続は一代限りのため、甥・姪がすでに亡くなっている場合、その子どもには相続権はありません。
また、兄弟姉妹や甥・姪が相続する際は、以下の点にも注意が必要です。
-
- 相続税が2割加算されます。
- 遺留分は認められていないため、遺言書で「すべてを第三者に譲る」と記されている場合、相続権は主張できません。
【関連記事】
子なし夫婦の遺産相続はどうなる?法定相続人・遺産の割合・対策など解説
内縁関係には相続権は発生しない
法律上の婚姻関係が無い内縁の配偶者には、相続権がありません。
内縁の夫・妻が財産を相続するためには、有効な遺言書を作成する必要があります。
ただし、遺言書なしで生命保険の受取人を事実婚の相手や内縁者に指定することは可能ですし、金額によっては贈与税がかかりますが生前贈与も可能です。
独身者が亡くなった時に法定相続人がいない場合について
独身の兄弟に法定相続人がいない場合、もしくは相続人全員が相続放棄をした場合は、相続財産清算人の選任を申し立てるのが一般的です。
ただし亡くなった故人が財産をほとんど残していない場合は、財産の処分・清算をする必要がなく、申立てをせずに済ませることもあります。
相続財産清算人の選任の申立てができるのは「利害関係人」または「検察官」と定められています。
利害関係人とは、債権者や特定受遺者、特別縁故者などです。
申し立てがあった場合は、家庭裁判所により弁護士などの相続財産清算人(相続財産管理人)が選任され、以下のような手続きが行われます。
債権者への弁済にあてる
被相続人に金銭や住居などを貸していた人が、債権者に当たります。
相続財産清算人は相続債権者に対して、請求の申し出をするよう公告しますが、期間内に申し出なければ遺産を受け取ることはできません。
債権者がわかっている場合には、個別に請求を申し出てもらうようにします。
公告の期間が終了後、相続財産の中から借金や未払い金など、債権者への弁済を行います。
弁済に充当できる預貯金が無い場合、相続財産清算人は、相続財産の売却などをしなければなりません。
特定受遺者が受け取る
特定受遺者とは、遺言により財産を受け取る人のことをいいます。
債権者への公告と同時に、請求申出の公告を行います。
債務の支払いが済んだあと、遺言書に特定の個人や団体に財産を遺贈する旨が記載されていれば、特定受遺者が相続財産を受け取ることが可能です。
この時点で相続財産をすべて使い切ってしまっていれば、手続きは終了します。
特別縁故者が受け取る
特別縁故者とは、療養看護をしていた人、内縁者、親代わりだった人のことです。
相続債権者・受遺者の請求申出の公告と並行して相続人の捜索の公告を行いますが、期間内に相続人が見つからなかった場合、故人の生前の生活を支えていた人は、家庭裁判所の判断で相続財産を受け取れる可能性があります。
財産分与を受けたい特別縁故者は、相続人捜索の公告期間終了後3か月以内に、家庭裁判所へ財産分与を申し立てなければなりません。
財産の共有者に帰属する
相続人も特別縁故者もいない場合で、共有名義の不動産などがあるケースでは、その不動産の共有持分は他の共有者に帰属することがあります。
相続人がいない場合の遺産は最終的に国庫に納められる
債権者、特定受遺者、特別縁故者、財産共有者(不動産など)がいずれもいないか、それぞれへの清算・分配が済んでも余る場合、残った財産は最終的に国庫に納められます。
独身の兄弟が亡くなった時に相続トラブルを避ける対策とは
独身の兄弟が亡くなった場合、遺産相続の手続きが複雑になる可能性があります。
特に兄弟姉妹間では、普段の交流が少ない・疎遠であるなどの理由から、相続分を巡ってトラブルに発展しやすい傾向があります。
もしもの場合に備えて、以下の具体的な相続対策を知っておきましょう。
遺言書
以下のようなケースでは、相続トラブルやなかなか手続きが進まないケースがあります。
-
-
相続人が複数いる場合
- 兄弟の数が多い場合
- 疎遠な親族がいる場合
-
遺言書を作成し、誰にどの財産を相続させるか明記することで、遺産相続の混乱を防げます。
例えば特定の兄弟と仲がよかったり、介護などの貢献があったりした場合、その対象者に財産を遺したいと考えるのであれば、遺言書は必須です。
遺言書の作成方法には厳格なルールがあり、わずかなミスでも無効になるリスクがあるので注意しましょう。
自筆証書遺言よりも公証人に依頼して公正証書遺言を作成する方が、法的効力と安全性が確保されます。
家族信託
家族信託とは、信頼できる家族に自分の財産の管理や運用、処分を任せる制度で、認知症などの発症後も、家族が財産を管理・運用できます。
不動産の売却や賃貸、預金の払い戻しなどを家族ができるので、認知症になった後、施設入所が決まったときに自宅を売却し、入所費用や介護利用に充てることも可能です。
家族信託と遺言書を組み合わせることもできますので、より柔軟な相続対策となります。
任意後見制度
任意後見制度とは将来自分の判断能力が不十分になったときに備えて、支援してくれる人と支援してもらう内容を事前に契約しておく制度です。
成年後見制度と異なり、後見人になってくれる人物や後見内容を自分で決められるのが特徴で、自分が信頼できる人に後見人を依頼できます。
独身の兄弟が認知症になった場合、任意後見人を立てると、介護施設の入所手続きや医療費の支払いなどを代行してもらえます。
死後事務委任契約
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の事務作業(葬儀、埋葬、遺品整理など)を、第三者(受任者)に生前契約で依頼しておくことです。
一般的には、人が亡くなった後の葬儀や各種手続きは遺族が行いますが、親族がいない・親族がいても疎遠で負担をかけたくない場合に有効です。
死後事務委任契約を活用すれば、遺族に葬儀や手続きを任せる必要がないので負担を減らせます。
そのうえ、自分の希望通りの内容で葬儀の形式、埋葬場所、遺品整理の方法、医療費の精算など、詳細な内容を契約で定めることが可能です。
生前贈与
生前贈与は、受贈者(贈与を受ける人)が限定されないため、法定相続人以外にも財産を残すことが可能です。
贈与税には年間110万円の非課税枠もあるので、早めにスタートすれば1,000万円以上の財産でも非課税贈与が可能で、相続税対策にもなります。
【関連記事】
生前整理とは?いつから始めるのか・生前整理をやるメリット&デメリットなど解説
こまめに兄弟と連絡を取り、相続について話し合うことが大切
独身の兄弟が亡くなったときの法定相続人の順位は「子・養子 → 親 → 兄弟姉妹」の順番で、兄弟姉妹には遺留分がありません。
独身の兄弟に子どもがおらず、両親や祖父母もすでに他界している場合は、亡くなった人の兄弟姉妹や甥・姪が遺産を受け継ぐこともあります。
そのため、遺産相続手続きや遺産分割協議が難航する可能性も少なくありません。
万が一のときに兄弟の意思を尊重するためにも、日頃から兄弟姉妹と相続について話し合い、遺言書の有無や内容など相続財産管理の準備をしておくことが非常に大切です。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要