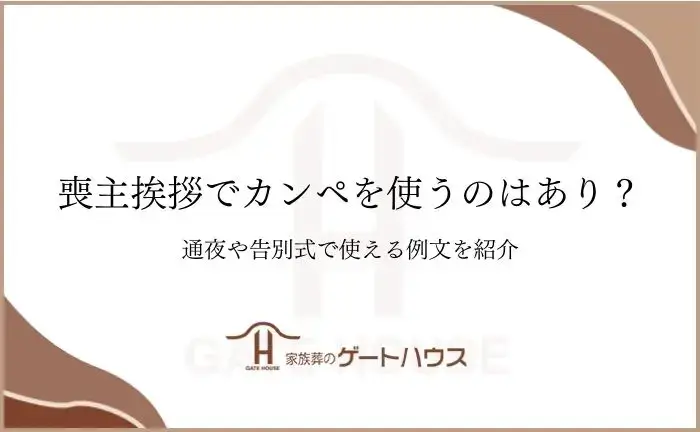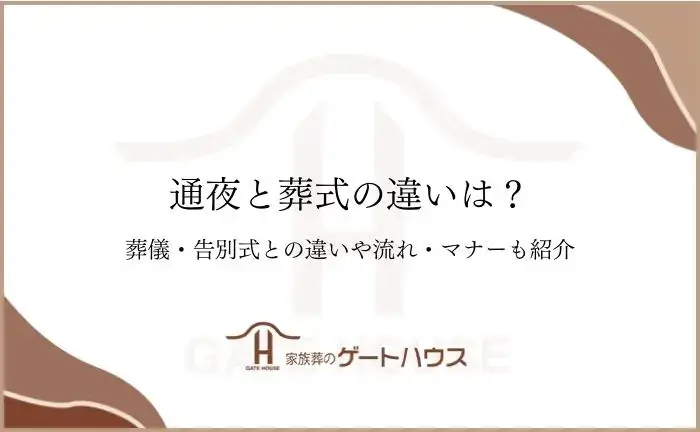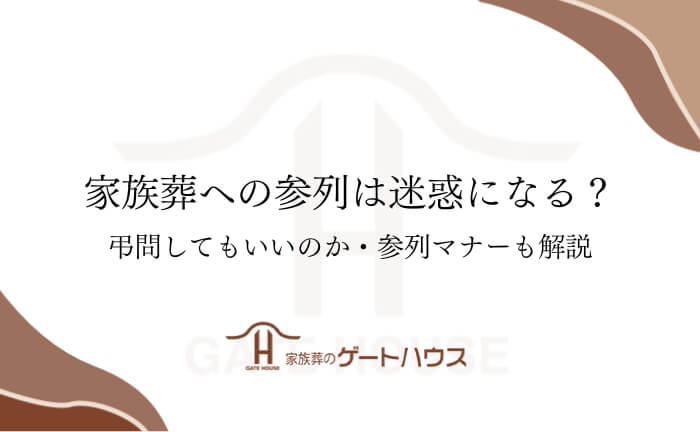訃報のお知らせ例文|家族葬を親戚・町内会・会社・友人へ丁寧に伝えるには?
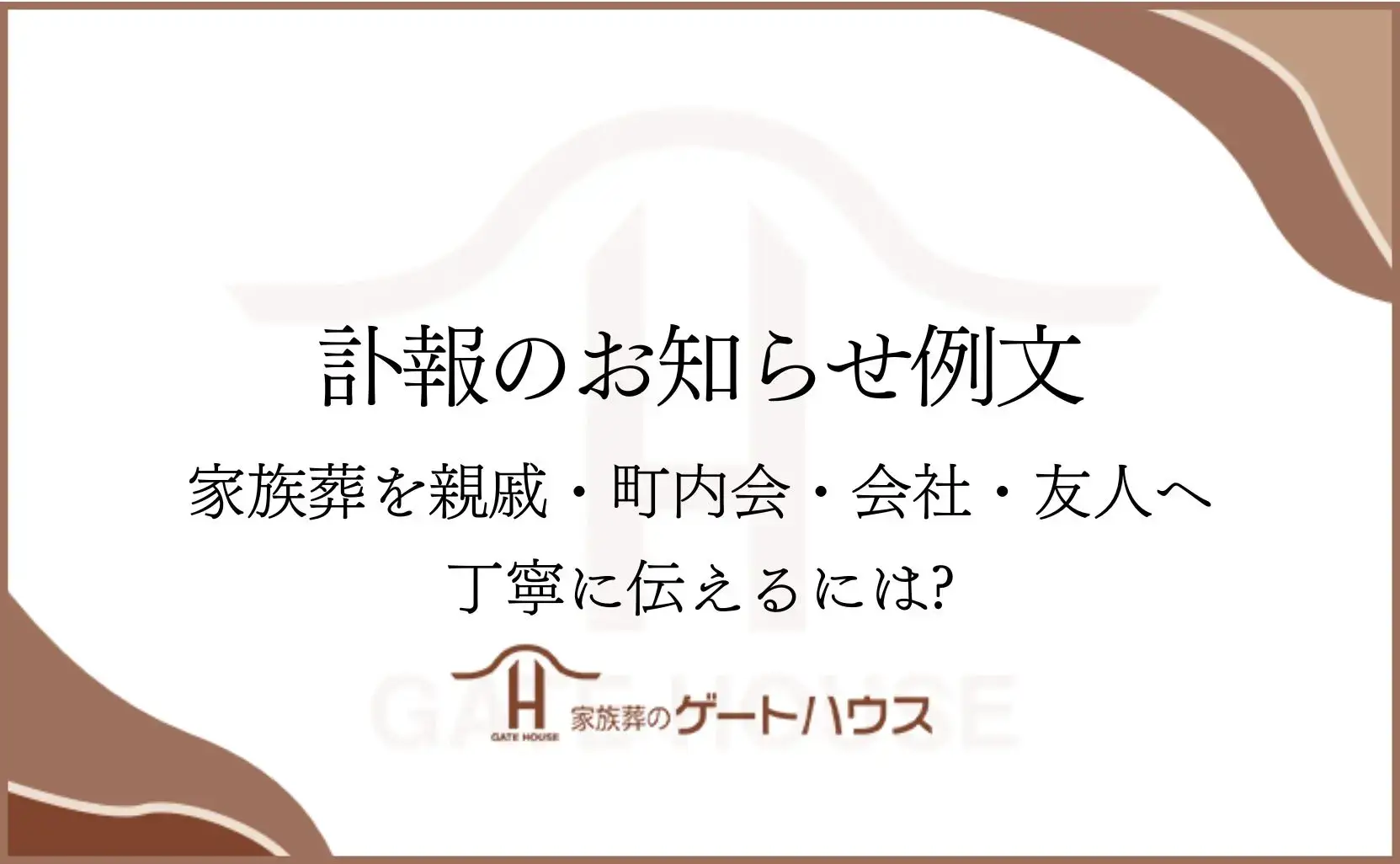
家族葬の訃報連絡は、適切なタイミングで必要な情報を簡潔に伝えることが大切です。
この記事では、親戚や友人、町内会などの相手別に適した訃報の例文を紹介します。
また、押さえておくべきポイントや伝えるタイミング、訃報の基本マナーについても解説していますので、参考にしてみてください。
家族葬の訃報|お知らせ例文【親戚・友人】
家族葬は一般葬と異なり、参列者を限定する葬儀です。
訃報のお知らせは、葬儀に出席するべきかどうかが、相手にわかるように伝えましょう。
まず、家族葬に出席をお願いする親戚・友人宛の例文と、お断りする相手へのお知らせ例文を紹介します。
出席をお願いする親戚
家族葬に出席をお願いする親戚に、訃報のお知らせをする時は、緊急の用事なのでなるべく電話で連絡しましょう。
深夜や早朝で電話をするのが難しい場合や、葬儀まで日数がある場合は、手紙やメールで連絡することもあります。
例文1.電話で伝える場合
突然の電話で、失礼します。◯◯の息子(娘)の◯◯です。
父(母)が闘病中だったのですが、昨夜◯時に永眠しました。
家族葬で葬儀を執り行いますので、参列をお願いします。
葬儀の詳細が決まり次第、改めて電話しますのでよろしくお願いします。
今かけている私の携帯で連絡がとれますので、何かありましたら電話してください。
電話番号は◯◯です。
例文2.手紙やメールで伝える場合
◯◯病院にて療養中でした父(母)◯◯が 令和◯年◯月◯日に永眠しました
生前の父(母)へのご厚誼に対し 心よりお礼申し上げます
葬儀につきましては故人の希望により 家族葬を執り行います
ぜひ ◯◯様にもご参列をお願いしたく ご案内申し上げます
日時 通夜式 日付と時間 告別式 日付と時間
場所 会場名 住所 電話番号
喪主 氏名 電話番号
出席を頼みたい友人・知人
家族葬でも、故人と特に親しかった友人、お別れをしてもらいたい知人や関係者に、出席を頼むケースは珍しくありません。
続いては、出席を頼みたい友人・知人に訃報のお知らせをする際の例文を紹介します。
例文1.手紙やメールで伝える場合
突然の連絡、失礼致します
◯◯の息子(娘)の◯◯です
療養中の父(母)◯◯が 令和◯年◯月◯日に永眠しました
ここに生前のご厚誼に感謝し 謹んでお礼申し上げます
通夜・告別式は家族葬にて執り行います
また 故人の遺志により ◯◯様にもご参列いただきたくご案内申し上げます
1.日時 通夜式 日付と時間 告別式 日付と時間
2.場所 会場名 住所 電話番号
3.喪主 氏名 電話番号
出席をお断りする親戚・友人・知人
家族葬を理由に出席をお断りする人への訃報は、相手が勘違いして参列するなどのトラブルを避けるため、事後報告が一般的です。
次は出席をお断りする親戚や友人・関係者に、訃報を知らせる電話・メールの例文を紹介します。
例文1.電話での事後報告
突然のお電話失礼いたします。◯◯の息子(娘)の◯◯です。
闘病中だった父(母)が、◯月◯日に永眠しました。
葬儀は故人の生前の遺志により、家族葬になりました。
誠に申し訳ありませんが、供花、供物、香典等のご厚志は辞退させていただきます。
生前は父(母)が大変お世話になり、ありがとうございました。
この番号で連絡がとれますので、何かありましたらご連絡ください。
電話番号は◯◯です。
例文2.手紙やメールでの事後報告
令和◯年◯月◯日に 父(母)◯◯が永眠いたしました
父(母)が生前に賜りましたご厚意に対し 心より御礼申し上げます
故人の遺志を尊重して、近親者のみで家族葬を済ませました
誠に恐縮ながら 供花 供物 香典は謹んで辞退させていただきます
故人の冥福を祈りつつ ここに謹んでご通知申し上げます
喪主 氏名 住所 電話番号
家族葬の訃報|お知らせ例文【町内会・ご近所】
故人が生前居住していた地域の町内会や、ご近所の方に訃報を知らせる時は、葬儀の前に連絡する場合と、葬儀後にお知らせする場合があります。
次は、町内会やご近所の方に家族葬の訃報を知らせる際の例文を紹介します。
町内会の回覧板でお知らせする場合
町内会の回覧板で一斉に訃報のお知らせをする際、生前に故人がお世話になったことへの感謝を伝えることが大切です。
また、家族葬を執り行う場合は、家族以外は参列できない件を明記し、相手が勘違いして参列しないようにしましょう。
例文1.葬儀前にお知らせする場合
お世話になります、〇町◯丁目に住む〇〇でございます。
このたび 父(母)の◯◯が 令和◯年◯月◯日に永眠いたしました
故人の遺志により 葬儀は親しい家族による家族葬を執り行います
誠に恐縮でございますが 供花 供物 香典等は 謹んで辞退させていただきます
町内会の皆様より頂いた 生前の◯◯へのご厚情に深謝いたします
◯◯家 親族一同
例文2.葬儀後にお知らせする場合
お世話になります、〇町◯丁目に住む〇〇でございます。
令和◯年◯月◯日 父(母)の◯◯が 〇歳をもって永眠いたしました
本人の希望で 葬儀は近親者が家族葬にて済ませましたことを ご報告申し上げます
故人が生前に賜りましたご厚誼に対しまして 心よりお礼申し上げます
◯◯家 親族一同
ご近所向けにお知らせする場合
故人が生前に交流があったご近所の方に家族葬の訃報を知らせる際は、故人との関係性により、電話かメール・挨拶状で伝えます。
その際、家族葬で香典やお参りを辞退したい件や、今後の連絡先も伝えましょう。
例文1.電話で伝える場合
突然の電話で申し訳ありません。
◯◯の息子(娘)の◯◯です。
◯月◯日に父(母)が息を引き取りました。
通夜や告別式は、本人の希望で家族葬にする予定です。
失礼ですが、香典・弔電・供花・供物などはお断り申し上げます。
生前は父(母)が大変お世話になりました。
何かありましたら、この番号までご連絡ください。
電話番号は◯◯です。
例文2.葬儀後にお知らせする場合
令和◯年◯月◯日に 父(母)◯◯が永眠いたしました
本人の遺志で 近親者のみの家族葬を行いましたことを ご報告します
誠に勝手ながら 香典・弔電・供花・供物などはお断り申し上げます
故人が生前に賜りましたご厚誼に対しまして 心よりお礼申し上げます
何かありましたら 下記までご連絡ください
喪主名 電話番号
家族葬の訃報|お知らせ例文【会社関連】
遺族が勤めている会社や取引先、故人が勤務していた職場に訃報を伝える際は、できるだけ早く連絡して、迷惑をかけないように配慮しましょう。
その際、家族葬を執り行う・香典や供花をお断りするなどの意思表示が必要です。
遺族が勤めている会社への連絡
遺族が勤める会社に家族葬の連絡をする際は、直属の上司に電話で一報を入れ、休暇の希望や連絡手段を知らせます。
必要に応じて、メールなどで仕事の引き継ぎを相談することもあります。
休暇中に影響がありそうな取引先には、メールで概要を伝えておくといいでしょう。
例文1.勤め先への連絡
お疲れ様です。◯◯です。
療養中だった父(母)が、昨夜亡くなりました。
葬儀は〇月〇日に家族葬で執り行う予定です。
そのため、〇日から〇日まで、忌引き休暇をいただけないでしょうか。
その間の業務や詳細については、後で改めてメールします。
何かありましたら、私の携帯まで連絡してください。
また、香典や供花等は、失礼ながら辞退させていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。
例文2.取引先への連絡
いつもお世話になっております。
私事で恐縮ですが、父が〇月〇日に他界し、家族葬にて葬儀を執り行うこととなりました。
つきましては◯月◯日より◯月◯日まで不在となり、ご迷惑をおかけいたしますことお詫び申し上げます。
私が不在の間は◯◯が担当いたしますので、何かありましたら以下にご連絡をお願い致します。
代理担当者の氏名 メールアドレス 携帯番号
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い致します。
故人の勤めていた会社への連絡
故人が会社員として勤務していた場合は、遺族が勤務先に連絡を入れ、訃報と今後の連絡手段、家族葬を行う件を知らせましょう。
なるべく早めに、直属の上司か担当部署に伝えるのが望ましいです。
例文1.
〇〇課〇〇の息子(娘)の〇〇と申します。
〇〇は病気療養中でしたが、昨晩他界しました。
生前は父(母)が大変お世話になり、深く感謝しております。
葬儀は◯月◯日に、近親者のみの家族葬で執り行う予定です。
参列や香典などのご厚志は、勝手ながら辞退させていただきます。
今後の連絡先は、私の携帯電話となりますので、何かありましたらご連絡ください。
電話番号は◯◯です。
家族葬の訃報|お知らせ時に押さえておくべきポイント
家族葬の訃報をお知らせする時には、押さえておくべきポイントがあります。
必要な情報が欠けていた場合、相手が困って問い合わせが来たり、誤解を招いたりする可能性があります。
連絡する前に、次の内容が記載されているかチェックしましょう。
故人が亡くなったこと
訃報であることがすぐ分かるように、まずは亡くなったことを明記します。
病死や老衰以外の場合は、死因は省略しても構いません。
故人の氏名・逝去日・年齢
誰の訃報か分かるように、故人の氏名と亡くなった日を必ず伝えます。
訃報の場合、亡くなった年齢は数え年を表記するのが一般的です。
家族葬を執り行うこと
家族葬を執り行う前に連絡する場合は、一般葬と誤解されないように家族葬であることを明確に伝えましょう。
事後報告では、家族葬が済んでいることを伝えます。
参列・香典・供物などの辞退について
家族葬で参列や香典、供物を辞退したい場合は、相手が理解できるように明記しましょう。
葬儀後の事後報告でも、挨拶状に書いて知らせましょう。
生前のご厚情への感謝
生前に故人が受けたご厚情への感謝の言葉は、訃報のお知らせに必ず添えるのがマナーです。
家族葬への参列をお断りする場合でも、忘れないように気持ちを伝えましょう。
喪主(差出人)の情報
訃報には、喪主(差出人)の氏名や故人との関係性を伝えることも必要です。
今後連絡を取り合う可能性があるなら、住所や電話番号、メールアドレスなども知らせましょう。
メールの場合は明確な件名
メールで家族葬のお知らせをする際は、訃報だとわかるような件名をつけ、内容が分かるようにして送りましょう。
家族葬の訃報|お知らせを出すタイミング
家族葬は参列者を限定する葬儀なので、お知らせのタイミングが一般葬とは異なります。
故人との関係性などを考慮して、適切なタイミングで連絡するようにしましょう。
次は、家族葬の訃報を出すタイミングを解説します。
葬儀後に送るのが一般的
家族葬の訃報は、葬儀後に送るのが一般的です。
相手が家族葬とはどういうものか理解していないと、一般葬と同じように葬儀に参列する可能性があるからです。
事後報告になった相手には、ハガキや挨拶状などで失礼がないように伝えるといいでしょう。
葬儀前に知らせておくべき相手
葬儀に参列を頼む人には、なるべく早く訃報と家族葬のお知らせをする必要があります。
まずは電話で一報を入れ、詳細な情報はメールなどで伝えてもいいでしょう。
一般的に故人の三親等以内の親族には、参列をお断りする相手でも、葬儀前にお知らせするのがマナーとされています。
家族葬の訃報|お知らせ・挨拶状の基本マナー
訃報のお知らせや挨拶状には、基本的なマナーがあります。
家族葬の場合でも決まり事を守り、失礼がないように心がけましょう。
最後は、訃報のお知らせや挨拶状の基本マナーと注意点を紹介します。
最初の文字を下げない
手紙などを書く時は、最初の文字を一字下げてから書き始めますが、訃報のお知らせや挨拶状は、同じ高さから書き始めます。
句読点を使わない
訃報のお知らせや挨拶状では、句読点を使わないで書くのが一般的です。
必要な箇所にはスペースを入れましょう。
時候の挨拶を入れない
ビジネスでの連絡では時候の挨拶から始めますが、訃報のお知らせや挨拶状では省略し、用件から書き始めます。
忌み言葉を使わない
不幸の連鎖を想像させる「追って」などの忌み言葉や「ますます」などの重ね言葉は、訃報や挨拶状では避けるのがマナーです。
薄墨で書くのが一般的
弔事に関わる挨拶状や訃報は、薄墨で書くのが一般的です。
ハガキや手紙を自分で印刷する場合は、インクの色に気をつけましょう。
家族葬の訃報は相手に合わせて。伝え方と例文選びで心を届けよう
家族葬の訃報は、相手に合わせた適切なタイミングで通知しましょう。
葬儀に参列してもらいたい相手にはなるべく早く連絡し、お断りする相手には事後報告するのが一般的です。
また、訃報の内容には押さえるべきポイントがあり、内容を吟味することが大切です。
訃報の例文を参考に、マナーやタイミングを守って連絡しましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要