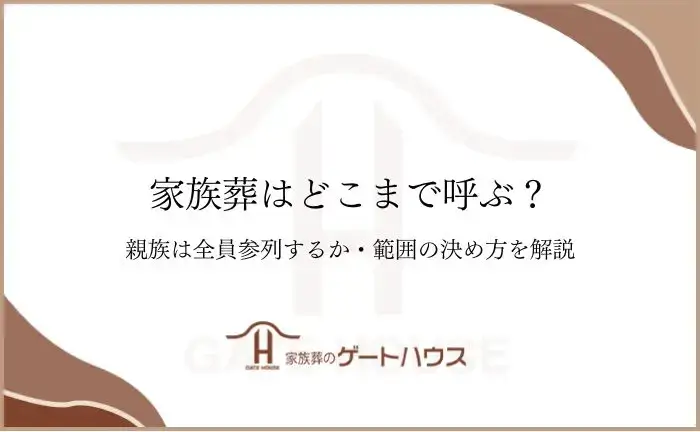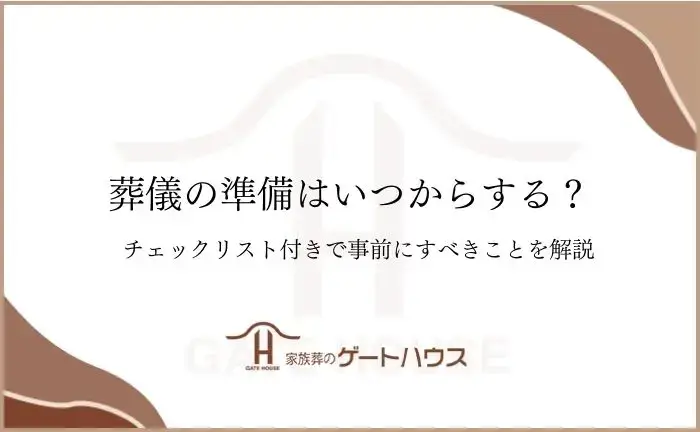お焼香とは?あげる意味は?作法・回数やマナーも解説
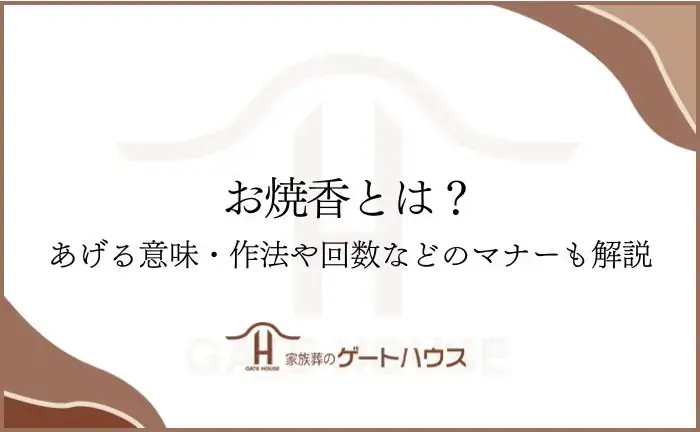
お焼香とは、仏式の葬儀や法要などで拝む前に香を焚くことですが、どのような意味があるのでしょうか。
参列者が順に行う所作なので、作法も一通りチェックしておきましょう。
この記事では、お焼香をあげる意味や作法、回数の意味について解説しています。
お焼香とは?
「焼香」とは、仏教の儀式の1つである香を焚く行為で、特に葬儀や法事の場で香を焚いて、故人や仏を拝むことを目的としています。
また、通夜、葬儀などで焚かれるのは、白檀や樒(しきみ)などの香木を細かくした「抹香」が多いです。
お焼香をあげる時は、抹香を指でつまみ、火のついた炭を置いた香炉にパラパラと振り入れた後、両手を合わせて拝むのが一般的です。
ただしお焼香の作法は、宗派によって異なるので注意しましょう。
お焼香の由来
お焼香の由来は、古代インドだといわれています。
気温が高いインドでは、体臭を抑えたり殺菌したりする目的で、香木を焚く習慣がありました。
そしてお焼香には鎮静効果があり集中力を高める効果もあるので、宗教行事や瞑想で使われるようになりました。
また、お釈迦様が説法をする際も、香を焚いたとされています。
一方、日本ではもともと香を焚いて、香りを楽しむ習慣がありました。
その後、仏教が伝来した時に焼香が仏教行事として伝えられると、葬式や法要でも行われるようになったのです。
線香との違い
仏壇やお墓などであげる線香は、香木や香料を練って棒状にしたものです。
お焼香と線香の違いは使うシチュエーションにあり、お焼香は通夜や葬儀、法要など特別な機会にあげることが多いでしょう。
一方、線香は日常的に仏壇を拝んだりお墓参りしたりする時に使います。
そして、線香とお焼香の目的は、香を焚き、芳香を拝む相手にお供えするという点です。
線香をあげる時もお焼香と同じで、宗派ごとに本数や置き方など作法に違いがあります。
お焼香をあげる意味とは?
拝む前にお焼香をあげることには、さまざまな意味があります。
儀礼的に行うだけでなく、意味を理解して行うと、より心のこもったお焼香があげられるでしょう。
続いては、お焼香をあげる意味や目的を解説します。
故人と仏に香りを供えるため
前述で説明したとおり、お焼香をあげることには、香を焚いて良い香りを故人や仏にお供えするという意味があります。
お供えといえば、食べ物や飲み物、花などを思い浮かべるかもしれませんが、良い香りというのも相手を尊ぶ気持ちを込めたお供えの1つです。
亡くなって身体がなくなった方は、香りと煙を好んで食べるといわれています。
お焼香の良い香りや煙は、食べ物や花の香りと同様に、故人の食べ物となるのです。
心身についた穢れを払うため
お焼香をあげるのは拝む対象のためだけでなく、拝む人の心身についた穢れを払う意味もあります。
葬式や法要の場は、亡くなった方をお見送りしたり仏をお迎えしたりするための、神聖な場所です。
お焼香で生まれる香りや煙は、人が日常生活を送る中で身につけた穢れを払い、周りの空気を浄化させる効果があるといわれています。
拝む前にお焼香をあげることで、心身ともに清らかな状態になり、故人や仏と向き合う準備が整うでしょう。
仏の教えを表現するため
焼香炉から静かに煙が立ち上り、良い香りが四方へと広がっていく様子は、仏の教えを表現しているといわれています。
香炉から漂う芳しい香りは、故人が浄土に導かれることを意味しています。
お焼香の香りや煙は、その場にとどまらず徐々に離れた場所まで拡散して、仏の慈悲が誰にでも平等に届くさまを体現しているようです。
また、抹香の材料としてよく使われている白檀の木は、仏陀が荼毘(だび)に付された時に使われた木で、香り高く高貴な木です。
気持ちを落ち着かせるため
お焼香をあげるのには、香りの力で気持ちを落ち着かせる意味もあります。
お焼香から立ち上る煙を前に静かに手を合わせる瞬間は、慌ただしい葬儀の中で心の静寂が訪れます。
お焼香から立ち上る香りによって、日常生活の忙しさや雑念を忘れさせてくれて、真摯な気持ちで死を悼むことができるでしょう。
お焼香の作法や回数の意味とは?
お焼香の種類は、一般的な立礼焼香の他に、座礼焼香、回し焼香があります。
お焼香のつまみや押しいただきの回数は宗派によって異なり、数にもそれぞれ意味があります。
次は、お焼香の作法や回数の意味を紹介しましょう。
立礼焼香
立礼焼香は、椅子席がある一般的な斎場や葬儀会場で行われるお焼香の形式で、席を立って焼香台に行き、お焼香をあげて席に戻ります。
お焼香の順番は、通常は喪主、その次に遺族が席順にお焼香をあげていき、最後に参列者がお焼香をあげます。
葬儀社のスタッフがいる場合は、指示に従って順に焼香台に向かいましょう。
お焼香をする前は遺族・僧侶に一礼、遺影に合掌して一礼し、お焼香の後は遺族に一礼して席に戻ります。
【立礼焼香の流れ】
-
-
- 1.焼香台の前で遺族・僧侶に一礼する。
- 2.遺影に合掌して一礼する。
- 3.焼香台に進んでお焼香を行い、合掌する。
- 4.遺族に一礼した後、席に戻る。
-
座礼焼香
お寺や自宅など和室で行われる葬儀や法要では、座礼焼香が行われます。
また、焼香台に向かう時は腰を落としたまま移動する「膝行・膝退(しっこう・しったい)」を行い、立ち上がらないようにするのが特徴です。
膝行・膝退は、親指だけを立てて握った手を両脇から少し前につき、両腕で身体を支えながら軽く膝を浮かせ、足の甲をすべらせるイメージで移動します。
回し焼香
香炉と抹香が載った台やお盆(焼香セット)を隣の席に回しながら、自分の席でお焼香をあげるのが回し焼香です。
回し焼香は、焼香台を設置する必要がなく、参列者全員が立って移動する時間を短縮できます。
回し焼香の手順は、焼香セットが回って来たら会釈して受け取り、立礼焼香などと同じ仕方でお焼香をします。
お焼香が済んだら、遺影に向かって手を合わせた後、次の人に焼香セットを回して終了です。
お焼香のつまみ・押しいただきの回数
お焼香をあげる時は、右手の親指と人差し指、中指の3本を使って、抹香をつまみ焼香炉に落とします。
焼香炉に落とす前に、つまんだ抹香を額の高さに上げる所作を「押しいただき」といいます。
お焼香のつまみと押しいただきの回数は宗派によって異なり、押しいただきがない宗派もあるので、下記の表を参考にしてください。
| 【お焼香のつまみ・押しいただきの回数|宗派別】 | |
| 天台宗 |
・つまみ:決まりはない ・押しいただき:決まりはない |
| 臨済宗 |
・つまみ:1回 ・押しいただき:決まりはない |
| 真言宗 |
・つまみ:3回 ・押しいただき:同じ回数 |
| 曹洞宗 |
・つまみ:2回 ・押しいただき:1回目あり・2回目なし |
| 日蓮宗 |
・つまみ:1回または3回 ・押しいただき:同じ回数 |
| 浄土宗 |
・つまみ:1~2回 ・押しいただき:同じ回数 |
| 浄土真宗本願寺派 |
・つまみ:1回 ・押しいただき:なし |
| 浄土真宗大谷派 |
・つまみ:2回 ・押しいただき:なし |
| 浄土真宗高田派 |
・つまみ:3回 ・押しいただき:なし |
※地域やお寺の考えによっては異なる場合があります。
回数の意味
お焼香の回数は1回から3回で、宗派によって異なります。
なぜ宗派によって回数が異なるかというと、宗派ごとに大切にしている数字が違うからです。
例えば、お焼香を3回とする宗派の教えでは「身・口・心の三業」「仏・法・僧の三宝」など、3という数字を重要視しています。
このように宗派の教えの違いが、お焼香の回数に影響を与えました。
ただし、参列者が多くお焼香に時間がかかる場合は、会場からの要請があり、お焼香を1回にする場合もあります。
| 【お焼香の回数に込められた意味】 | |
| 3回 | 仏教において「3」は重要視しているため |
| 2回 |
1回目を主香(しゅこう)、2回目は従香(じゅこう)という考えに沿っている。 ・主香:仏や故人の冥福を祈って香をたくこと ・従香:香はその火が消えないようにすること |
| 1回 | 死を「一に帰る」と捉える宗派の教えに沿っている。 |
【関連記事】
お焼香のやり方は?基本的な手順や宗派別の作法など解説
お焼香のマナーで気を付けることは?
お焼香をあげる時は、マナーを守って正しい方法で行うよう心がけましょう。
お焼香に慣れないと緊張するかもしれませんが、正しい作法を知っていると落ち着いてお焼香をあげられるでしょう。
次は、お焼香のマナーで気を付けることを紹介します。
手荷物を少なくする
手荷物を持ったままだと、お焼香をあげたり手を合わせたりする時に邪魔になるので、できるだけ手荷物は少なくしましょう。
葬儀会場に持ち込むバッグは、必要最小限な物が入る小型のものを選ぶようにします。
大きな荷物がある場合は、クロークなどに預けて小さな手荷物だけで着席するか、足元に置きましょう。
会場によっては、焼香台の横に荷物を置く場所が設置されているので、焼香の際はそこに荷物を置いて、お焼香をあげることができます。
数珠を持参するようにする
お焼香をあげる時は、自分の数珠を持参します。
まだ数珠を持っていない人は、これから必要になる可能性があるので、自分の数珠を用意しておきましょう。
どの宗派でも使える略式数珠と、宗派ごとに決められた形状の本式数珠がありますが、初めて購入する場合は、どの宗派でも使える略式数珠がおすすめです。
略式数珠の値段相場は5千円から1万円程度です。
数珠がないからといって、人から数珠を借りるのはマナー違反なので避けましょう。
なお、数珠の持ち方は宗派によって異なります。
【関連記事】
葬儀に使う数珠の持ち方は?必要ある?色の決まりはあるか・どこで買うかを紹介
服装・身だしなみのマナーを守る
葬式や法事に参列してお焼香をあげる時は、服装や身だしなみのマナーを守りましょう。
喪主や遺族は正喪服または準喪服を着用し、参列者の男性はブラックフォーマルのスーツ、女性はブラックフォーマルのアンサンブルやスーツを着用します。
汚れやシワ、ほころびがない清潔感がある服装を心がけ、華美なアクセサリーやメイクは避け、肌の露出を抑えるようにしましょう。
急な知らせで通夜にかけつける場合は、平服でも派手な配色を避けるなど、配慮が必要です。
喪主や遺族への挨拶は簡潔にする
お焼香をあげる時に喪主や遺族へ挨拶をする場合は、他の人の邪魔にならないように、簡潔に済ませることが大切です。
親しい間柄の人が亡くなった場合、いろいろ話したくなってしまうかもしれませんが、喪主や遺族は他の参列者も応対しなくてはならないため、長話はマナー違反です。
「この度はご愁傷様です」といったシンプルな挨拶のみとして「重ねがさね」など不幸が連続することを連想させる、不吉なイメージの言葉は避けましょう。
【Q&A】お焼香でよくある質問
普段の生活ではあまりお焼香をあげる機会は多くないので、お焼香をするうえでどうするか迷うこともあるでしょう。
最後は、お焼香に関するよくある質問を紹介します。
お焼香の作法は自分の宗派でもいい?
お焼香の作法は宗派によって異なりますが、故人の宗派と自分の宗派が異なる場合は、どちらに従っても、マナー違反になることはありません。
ただし、相手の宗派のお焼香のやり方に合わせた場合は、相手に対する敬意を示すことができるでしょう。
相手の宗派で、どのようにお焼香をするか不明な場合は、喪主や遺族のやり方を見て参考にしましょう。
ただし、自分の宗派にこだわりがあるなら、自分の宗派の作法通りにお焼香をあげても、失礼には当たりません。
通夜・告別式ではお焼香をして帰ってもいい?
通夜は急な知らせで駆けつけることもあるため、最後まで残らずお焼香だけあげて帰ってもマナー違反にはなりません。
しかし、告別式は日時が決まっているため、お焼香だけで途中退場することはなるべく避けた方がいいでしょう。
どうしても外せない用事がある場合は、事前に遺族に伝えておき、最初から後ろの席や隅の席に座って、退席しても目立たないようにします。
その際改めてきちんとお別れがしたい場合は、遺族と相談して後日弔問に伺いましょう。
自宅でのお焼香の仕方は?
葬儀が斎場ではなく自宅で行われる場合や、葬儀に参列できず弔問に行く場合は、自宅でお焼香をあげることもあります。
自宅でのお焼香の仕方として、足つきの台に載った焼香炉の場合は、立礼焼香または座礼焼香でお焼香をあげましょう。
お盆や台に載った焼香炉が回ってくる回し焼香の場合は、通常の葬儀での回し焼香と同様に行います。
また、仏壇でお焼香する場合は、線香を使うことが多いです。
線香の火はマッチなどで直接つけるのではなく、必ずろうそくの火からつけましょう。
仏教以外にお焼香はある?
お焼香は仏式の葬式だけの儀式なので、他の宗教の葬式では違った形で祈りを捧げます。
神道の葬儀では、榊の枝に紙垂(しで)や木綿(ゆう)を麻で結んだ「玉串」を祭壇に捧げて祈る「玉串奉奠」が行われます。
また、キリスト教の葬儀でお焼香に該当するのは、献花です。
参列者が1輪ずつ献花台に花を置き、黙祷をして亡くなった方に別れを告げます。
無宗教の葬儀の場合、基本的に決まりはないのですが、仏教の葬儀と同じように、お焼香をあげるケースが多いようです。
お焼香とは仏事で香を焚くこと。穢れを払う・故人・仏に香りを供えるなどの意味がある
お焼香とは、仏教の葬式や法事で香を焚き拝むことで、故人や仏に香りを供えたり、参拝者の穢れを払ったりする意味があります。
また、焼香には3つの形式があり、抹香をつまむ回数、押しいただきの回数、お焼香をする回数は宗派によって異なります。
お焼香の意味ややり方、気を付けるマナーを理解して、心を込めてお焼香をあげましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要