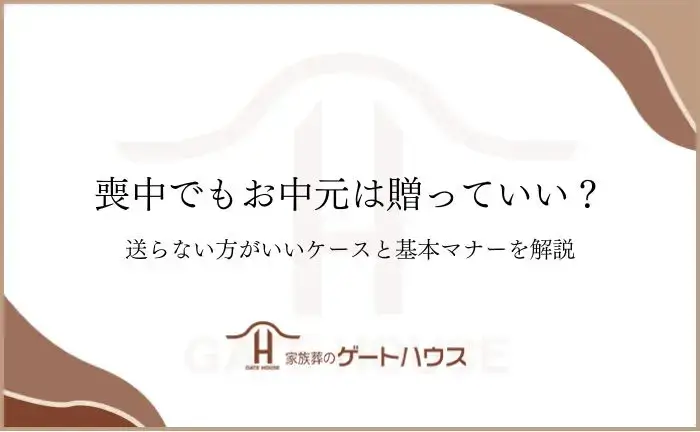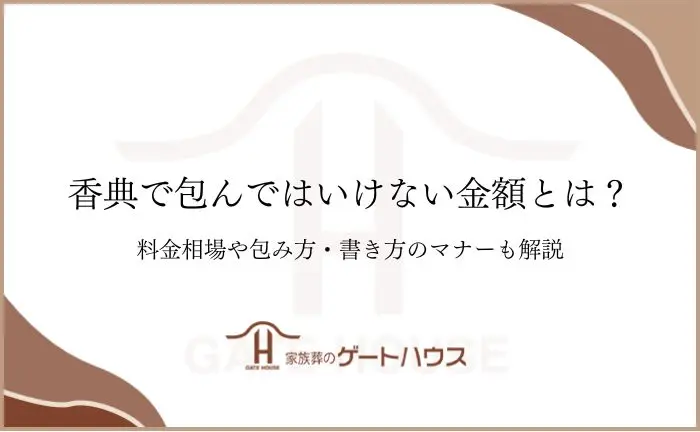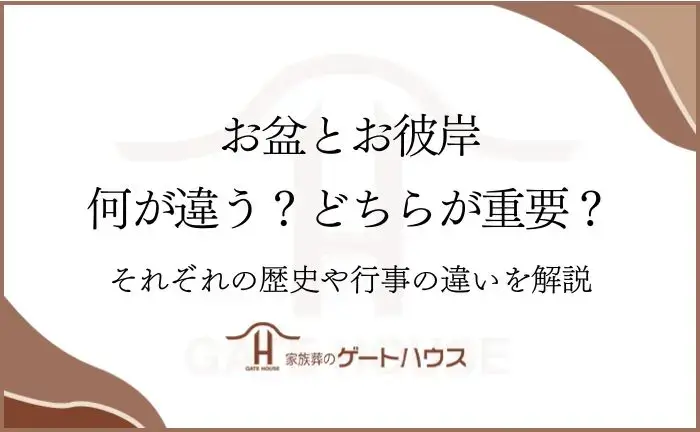【葬儀のお礼状】親戚向けの堅苦しくない例文6つ!基本のマナー&よくある質問
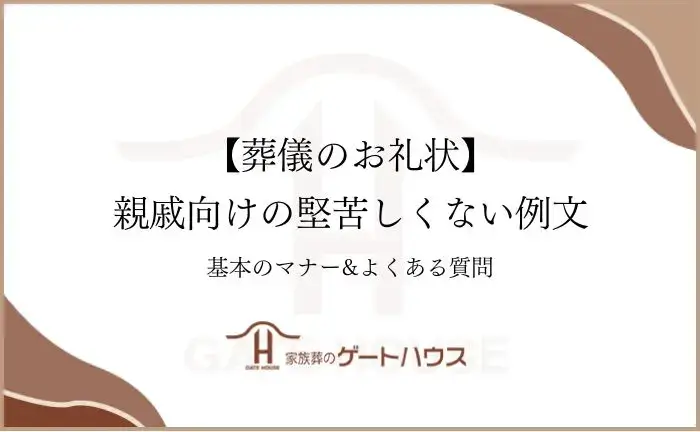
葬儀のお礼状を出す際、書き方やマナーに悩む人もいるでしょう。
また参列してくれた親戚との関係性によっては、堅苦しくない文章にしたいと思われるかもしれません。
この記事では葬儀のお礼状について、親戚向けの堅苦しくない例文や基本のマナーなどを解説します。
葬儀のお礼状|親戚向けの堅苦しくない例文集
葬儀のお礼状は定型文ではなく、故人を思い出してもらえるようなエピソードや、相手に合わせた内容を書きましょう。
「親戚へのお礼状で何を書いていいか分からない」「堅苦しくない表現が知りたい」という場合は、例文を参考にしてみてください。
生前故人がお世話になった親戚向け
この度 亡父〇〇儀 葬儀に際しましては過分なお心遣いを賜り誠にありがとうございました
お陰様をもちまして無事四十九日の法要を相営むことができました
父は年に数回△△さんのお宅にお世話になり 一緒にゴルフへ行くことを何よりも楽しみにしておりました
生前父がお世話になりましたこと 心からお礼申し上げます
親しい皆様に見送って頂き さぞ喜んでいることと思います
本来ならば拝眉の上お礼を申し上げるべきところ 略儀ながら書中にてご挨拶申し上げます
これからも変わらぬお付き合いのほど よろしくお願い申し上げます
敬具
令和〇年〇月〇日
住所
喪主 〇〇(喪主の名前)
外 親戚一同
香典や供花をくださった親戚向け
この度 亡母〇〇儀 葬儀に際しましては ご香料と立派な供花を賜り誠にありがとうございました
謹んでお受けし 霊前(四十九日以降は「仏前」)に供えさせて頂きました
病床の母にお花を差し入れてくださった時も 母はお花を眺めては綺麗ねと微笑み その美しい花姿に癒されておりました
△△さんの優しいお心遣いと かぐわしい花の香りに包まれ 母も心安らかに旅立って行ったことと存じます
ご厚情に心からお礼申し上げますと共に 失礼ながら書面にてご挨拶申し上げます
これからも変わらず 親しくお付き合いいただけますと幸いです
敬具
令和〇年〇月〇日
住所
喪主 〇〇(喪主の名前)
外 親戚一同
弔辞を引き受けてくれた親戚向け
この度 亡父〇〇儀 葬儀に際しましてご多用中にも関わらず 弔事をお引き受け頂き誠にありがとうございました
遺族を代表しまして 厚くお礼申し上げます
弔事を拝聴しながら 毎年親戚が集まり賑やかに過ごしていたお盆を思い出しました
父にとって△△さんと飲むビールは 格別だったことと思います
お陰様をもちまして 四十九日の法要も 滞りなく執り行うことができました
本来であれば直接お伺いしてお礼を申し上げるべきところ 略儀ながら書面にてご挨拶申し上げます
近くにいらっしゃる際は ぜひ足をお運びいただけますと嬉しく思います
敬具
令和〇年〇月〇日
住所
喪主 〇〇(喪主の名前)
外 親戚一同
葬儀の準備・片付けを手伝ってくれた親戚向け
この度 亡母〇〇儀 葬儀に際しましてご丁寧なお心遣いを頂き 誠にありがとうございました
葬儀では お茶出しの準備や片付けなどを手助けして頂き 家族一同とても心強く感じておりました
母は料理上手な△△さんから頂く手作りのお菓子が大好きで いつも紅茶と一緒にティータイムを楽しんでおりました
あの時の嬉しそうな笑顔が 今でも目に浮かびます
本来であれば 拝趨の上お礼申し上げるべきところ 失礼ながら書中でのご挨拶となりますことをご容赦頂きますようお願い申し上げます
今後とも変わらぬご厚誼を賜りますよう 心よりお願い申し上げます
敬具
令和〇年〇月〇日
住所
喪主 〇〇(喪主の名前)
外 親戚一同
故人と趣味が一緒だった親戚向け
この度 亡母〇〇儀 葬儀に際しましてご会葬とご香料を頂きありがとうございました
母は△△さんと趣味のガーデニングを通し 交流を楽しんでいることをよく嬉しそうに話しておりました
今年も庭に美しく咲き誇るバラを 母もきっと空から見ていることと思います
亡き母にかわりまして 生前のお気遣いにお礼申し上げますとともに 今後とも変わらぬお付き合いをお願いしたく存じます
直接お会いしてお礼をすべきところではございますが 略儀ながら書中をもちましてお礼申し上げます
敬具
令和〇年〇月〇日
住所
喪主 〇〇(喪主の名前)
外 親戚一同
思い出深いエピソードがある親戚向け
この度 亡父〇〇儀 葬儀に際しましてはご会葬くださった上 ご弔意を賜り誠にありがとうございました
父からは学生時代に△△さんと旅行に行った際の話を よく聞かせてもらいました
少年のように目を輝かせながら話す姿を見て 子どもながらに父にとって大切な思い出なのだなと思ったものです
生前は父への多大なるご厚情を頂き ありがとうございました
今後とも変わらぬお付き合いを賜りますよう お願い申し上げます
略儀ながら書中を持ちまして お礼申し上げます
敬具
令和〇年〇月〇日
住所
喪主 〇〇(喪主の名前)
外 親戚一同
親戚向けの葬儀のお礼状に入れたい内容
親戚に送るお礼状は、堅苦しくない表現にしたいと思われるかもしれませんが、葬儀に参列していただいたお礼や挨拶など、盛り込んでおきたいこともあります。
親戚に向けた葬儀のお礼状として入れたい内容をチェックしてみましょう。
故人の名前(俗名・戒名でも可)
親戚に送る葬儀のお礼状には、故人の名前を入れましょう。
故人の名前は、生前の名前である俗名を書き、戒名があれば合わせて記入してください。
お礼状には故人の名前を入れて、受け取る人が誰の葬儀に関連するお礼状なのかが分かるようにしましょう。
参列や香典に対するお礼
葬儀のお礼状には、参列してもらったり、香典をいただいたりしたことに対するお礼の言葉も添えてください。
供花や弔電などへのお礼も書きましょう。
相手の温かい心遣いに触れてどのように感じたのか、送ってもらったものがどのように役立ったのかなど、感謝の思いが伝わる表現を文章に含めます。
故人と親戚の思い出
堅苦しくない印象のお礼状にしたい場合は、故人と親戚の思い出を入れるのがおすすめです。
誰にでも使いまわせる定型文ではなく、自分の言葉でエピソードを綴ることで、より気持ちが伝わるお礼状になるでしょう。
手紙で済ませることへのお断り
葬儀のお礼状では、挨拶を手紙で済ませることへのお断りをしてください。
本来は「挨拶回り」といって、直接会ってお礼を伝えるのがしきたりですが、近年ではお礼状を送ることが増えています。
親しい親戚にも、きちんとお断りを入れるのがマナーです。
今後の親戚付き合いに対する挨拶
親戚向けの葬儀のお礼状には、今後も変わらぬ付き合いをお願いする旨を入れましょう。
葬儀を終えると、親戚と疎遠になってしまうこともあります。
しかし、これからの親戚付き合いについて一言入れておくと「法要で手伝えることがないか尋ねてみよう」「近くに行く機会があれば挨拶しよう」など、良い関係を続けるきっかけになるでしょう。
お礼状の基本の書き方&マナー
葬儀のお礼状は、堅苦しくない内容にしたい場合にも、正しい書き方を心がけてください。
基本的なマナーをおさえて、参列してくれた親戚に失礼がないようにしましょう。
ここでは、お礼状の書き方とマナーについて解説します。
故人の呼び方に気をつける
葬儀のお礼状では、故人の呼び方に気を付けてください。
お礼状では、喪主と故人の関係性によって呼び方が変わります。
たとえば、喪主の父親が亡くなった場合は「亡父」、喪主の母親であれば「亡母」です。
また、亡くなった人の名前の先頭に「故」を付けて「故〇〇」と表現することもあります。
敬語で統一する
葬儀のお礼状は、送る相手に関わらず敬語で統一します。
相手の立場や年齢、普段から仲が良いなどの関係性によらず、きちんとした表現を心がけましょう。
敬語表現として「御礼」「御挨拶」などの「御」を用いますが、漢字が続くと読みにくくなるため「お礼」「ご挨拶」と表記すると堅苦しさも和らぎます。
句読点を入れない
葬儀のお礼状には、句読点を入れないのもマナーです。
筆を使って字を書いていた時代には「、」や「。」などの句読点を使っていなかったので、その名残だとされています。
また、葬儀や法要が滞りなく済むようにという意味も込めて、文章を区切る句読点を使わないという説もあります。
ほかにも、文章を読みやすくするために用いられる句読点は、読み手を子ども扱いしていて失礼と受け取られるという説もあるそうです。
時候の挨拶を入れない
葬儀のお礼状には、時候の挨拶を入れません。
一般的に丁寧な文章には、季節や気候を表す言葉を用いた挨拶を入れますが、葬儀のお礼状は香典のお礼や忌明けの報告などを目的としているため、時候の挨拶は不要です。
葬儀のお礼状は「拝啓」や「謹啓」ではじめ「敬具」や「敬白」で締めましょう。
忌み言葉に気をつける
葬儀のお礼状には、忌み言葉を使わないように気を付けましょう。
「くれぐれも」「重ね重ね」などの重ね言葉は、不幸を繰り返すことを連想させてしまいます。
「苦しい」「終わる」などの忌み言葉や「死」「生」などの生死を連想させる言葉も、参列者や遺族を不快な気持ちにさせてしまうため、使用を控えてください。
【忌み言葉】
| 重ね言葉 | くれぐれも、重ね重ね 色々、段々、引き続き…など |
| 忌み言葉 | 苦しい、終わる 辛い、消える…など |
| 生死を連想する言葉 | 死ぬ、急死 生きていたころ…など |
墨の濃さは地域のしきたりに合わせる
親戚へのお礼状に用いる墨の濃さは、地域のしきたりに従いましょう。
葬儀の香典や引き出物では薄墨を使うのが一般的ですが、香典返しのお礼状に使用するのは通常の濃い墨で問題ないとされています。
しかし、地域によっては薄墨を用いることもあるため、あらかじめ家族や親戚などに確認しておきましょう。
送るタイミングに気をつける
葬儀のお礼状を送るタイミングにも配慮が必要です。
一般的には四十九日法要を終えてからお礼状を送るケースが多いですが、宗教や宗派によって忌明けの概念や期間が違うため注意してください。
たとえば、キリスト教には忌明けの概念が存在せず、一か月後に行われる追悼式のタイミングでお礼状を送ります。
宗教や宗派の慣習に従って、お礼状を送りましょう。
親戚への葬儀のお礼状はメールでもOK?
親戚への葬儀のお礼状を、メールで済ませようと思っている人もいるかもしれません。
葬儀のお礼状をメールで送るのは、マナー違反にはならないのでしょうか?
略式ではあるがメールでもOK
葬儀のお礼状をメールで親戚に送るのは、略式ではあるものの問題ないとされています。
昨今では、手紙や電話、お礼メールなど、訪問以外の方法で挨拶をする方が一般的かもしれません。
なかでもメールやLINEはカジュアルな手段ですが、普段からやりとりしている親戚であれば問題ないでしょう。
奉書式・カード式がおすすめ
親戚に送る葬儀のお礼状は、奉書式やカード式が良いでしょう。
お礼状の形式にはいくつか種類がありますが、和紙に縦書きで文章を書き、封筒に入れて渡す奉書式は、最も丁寧な形式です。
親しい親戚に対して堅苦しさを感じる場合は、カード式のお礼状もあります。
カードのデザインや字体を工夫すれば、丁寧かつ堅苦しくない印象で、相手に感謝の気持ちを伝えられるでしょう。
親戚向けの葬儀の御礼状は堅苦しくない文例でもOK。ただし最低限の礼儀は忘れずに
葬儀のお礼状を親戚に送る時は、堅苦しくない表現で問題ありません。
ただし、基本的なマナーや言葉選びの配慮などは忘れないようにしましょう。
相手に対する感謝の思いや、故人との思い出などを綴ることで、形式ばらずに気持ちが伝わるお礼状になるはずです。
「親しい親戚に対して、どんな表現が適切なのか分からない」「具体的な文例を知りたい」という場合は、例文を参考にしながら書いてみてくださいね。
【四十九日の報告をするときの例文はこちら】
四十九日が終わった報告(挨拶状)の例文|ハガキや親戚に堅苦しくない書き方を紹介
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要