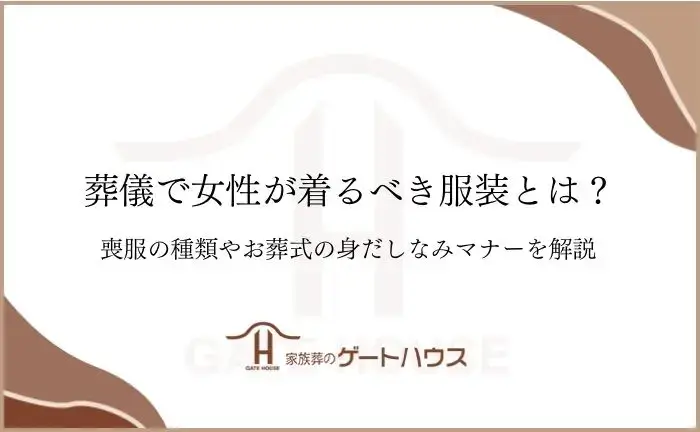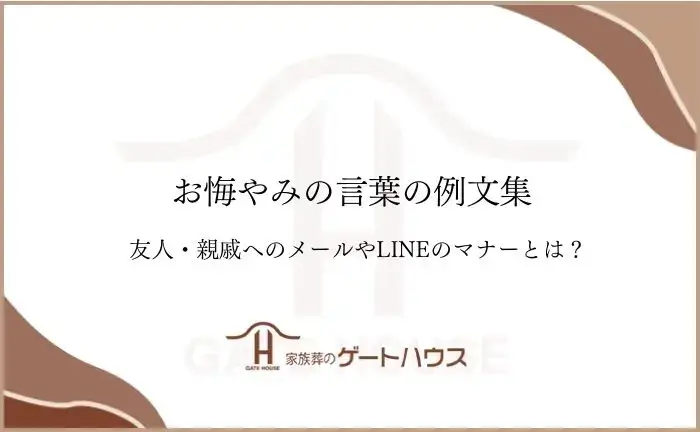家族葬のお布施の相場はいくら?地域・宗派別の金額や渡し方のマナーを解説
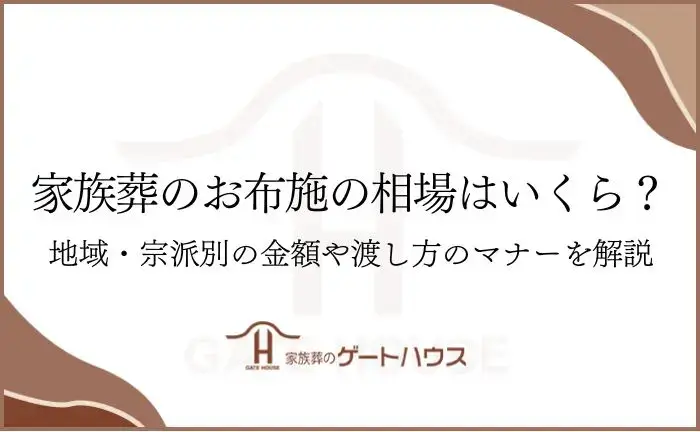
家族葬を行う際には、葬儀社に支払う葬儀費用のほか、僧侶などの聖職者へ支払うお布施・お礼も必要になります。
仏教のお布施は金額がはっきりと決まっていないことが多く、僧侶に対して金額を聞きづらかったり、金額を聞いても「お気持ちで」といわれるケースもあったりするため、困ってしまう方も多いのではないでしょうか。
そんな方のために本記事では、地域や宗派別の家族葬におけるお布施の相場やマナーについて解説します。
家族葬のお布施の相場は?
家族葬におけるお布施の相場は15〜50万円程度です。
また、お布施の金額は下記によって決まるとされています。
- 地域での慣例・宗派・寺院での違い
- 戒名のランク
- お寺とのこれまでの関係性
菩提寺がなく、葬儀社などでお寺を紹介される場合よりも、お寺と古い付き合いがある方がお布施は高くなるといわれています。
寺院によって違いますが、檀家は一律の金額の場合もあります。
家族葬のお布施は一般葬と相場はほとんど変わらない
お布施の相場は、一般葬であっても家族葬であっても違いはほとんどありません。
戒名をつける、読経をするなどの行為は一般葬・家族葬問わず行いますし、宗派やお寺の考え方にもよりますが、お布施はサービスに対しての対価ではなく、僧侶へのお礼なのです。
ただし、一日葬の場合はお通夜の読経がない分、お寺によっては多少減額される場合もあります。
【関連記事】
お布施とは?金額の相場やお金の入れ方・渡し方のマナーを徹底解説
家族葬のお布施の相場【地域別】
お布施の相場は、地域によっても違いがあり、西日本より東日本の方が高い傾向にあります。
| 地域 | 相場 |
| 北海道地方 | 30万円前後 |
| 東北地方 | 50~60万円前後 |
| 関東地方 | 20~80万円前後 |
| 中部地方 | 40~80万円前後 |
| 近畿地方 | 40~50万円前後 |
| 中国・四国地方 | 20~40万円前後 |
| 九州地方 | 20~35万円前後 |
家族葬のお布施の相場【宗教・宗派別】
お布施の費用相場は、地域のほか、宗教・宗派によっても違いがあります。
仏教の浄土真宗は、庶民を中心に広がってきた背景もあって、お布施は比較的低価格です。
一方で曹洞宗や臨済宗などの禅宗は、葬儀の読経の際に複数の僧侶を伴うのが作法となっており、その分高額です。
| 宗教 | 宗派 | 相場 |
| 仏教 | 浄土宗 | 10~30万円前後 |
| 日蓮宗 | 30~90万円前後 | |
| 曹洞宗 | 30~60万円前後 | |
| 真言宗 | 50~80万円前後 | |
| 天台宗 | 30~50万円前後 | |
| 臨済宗 | 30~50万円前後 | |
| 浄土真宗 | 10~35万円前後 | |
| 神道 | 10~20万前後 (2人の時は15~30万前後) | |
| キリスト教 | 5~20万程度 | |
※仏教は戒名料を含む相場
【関連記事】
浄土真宗の葬儀の流れは?お布施の相場や本願寺派・大谷派別に葬式の順序を解説
神道
神道の場合、葬儀の際に渡すお金はお布施ではなく祭祀料といいます。
祭祀料として渡す封筒の表書きは「御礼」「御祭祀料」「御榊料」「玉串料」などと書きます。
神道では、仏教でいうところの戒名の代わりに諡(おくりな)がありますが、諡をつけるための費用はかかりません。
また、仏教の場合と同様に、御車料と御膳料もお渡しするのが一般的です。
【関連記事】
神式の葬儀“神葬祭”の流れとは?通夜や告別式のマナー・作法も解説
キリスト教
キリスト教の場合は、お布施ではなく献金となります。
「御礼」として神父・牧師宛に渡すか、教会宛の場合は「献金」「御ミサ料」などと封筒に記載します。
家族葬ではあまり大規模な演出は行わないかもしれませんが、オルガン奏者や聖歌隊をお願いする場合は、その方たちにもお礼が必要です。
1人当たり5,000円~2万円が相場だといわれています。
家族葬のお布施の相場【戒名】
お布施は修行の一種であり、本来金額が決まっているものではありませんが、時代の流れとともに、読経料や戒名料などとして値段がついてしまっているのも事実です。
実際、戒名料の相場は戒名のランクによって大幅に金額が違うため、葬儀の際に渡すお布施は、戒名料として考えている方も多いかと思います。
| 宗派 | 信士・信女 | 居士・大姉 | 院信士・院信女 | 院居士・院大姉 |
| 浄土宗 | 10~20万円 | 30~60万円 | 80~100万円 | ー |
| 日蓮宗 | 30~50万円 | ー | 50~80万円 | 100万円~ |
| 曹洞宗 | 30~50万円 | 50~70万円 | ー | 100万円~ |
| 真言宗 | 30~50万円 | 50~70万円 | ー | 100万円~ |
| 天台宗 | 30~50万円 | 50~70万円 | 80万~ | 100万円~ |
| 臨済宗 | 30~50万円 | 50~80万円 | ー | 100万円~ |
| 浄土真宗 |
(釋・釋尼※) 20~40万 |
(院釋※) 50万~ |
ー | ー |
※浄土真宗は戒名ではなく法名となります。「釋(しゃく)+ 法名(2文字)」の合計3文字
浄土真宗では、戒名に対するランクがなく法名が自動的に貰えるので、比較的金額が低いのが特徴です。
一般的に、浄土真宗以外の宗派でご先祖様がいる場合は、特別なことが無ければご先祖様に合わせた戒名となります。
費用を払うのが難しければ、戒名のランクを下げる相談を先に菩提寺にしておくといいでしょう。
また、その一家で人が初めて亡くなった場合は、どのランクの戒名をつけて頂きたいのか相談しておくと安心です。
【関連記事】
戒名とは?法名との違いや宗派別のつけ方・値段の相場を解説
戒名はいらない?必要?つけないとどうなるのかも解説
家族葬のお布施の内訳は?
お布施の内容は、基本的には戒名と読経に対してのお礼となります。
お車代と御膳料は実費として考えるため、袋を分けて渡すのが望ましいです。
それぞれの内訳の内容をみていきましょう。
読経料
読経料は、故人が亡くなってからの一連の儀式の中で、僧侶が行った読経に対してお渡しするお礼となります。
基本的には枕教・通夜・葬儀・告別式・炉前読経・初七日までの読経が含まれますが、地域やお寺によっては、初七日は別で執り行う場合もあります。
葬儀の際に四十九日法要まで繰り上げて行う場合には、お布施の袋を分けるのが一般的です。
戒名料
故人に授けられた戒名に対して支払うお金です。
戒名料は前述のとおり、戒名のランクによって相場が異なるのが一般的で、10万円~100万円が相場と、金額にも幅があります。
金額は、宗派やお寺によって変わりますが「居士・大姉」や「院号」がつく戒名ほど高くなると考えておきましょう。
明確にお寺の住職から、戒名のランクごとの金額が提示される場合もあります。
御車料
御車料は自宅や葬儀場まで、僧侶の移動にかかる交通費です。
5,000円~10,000円ほどが相場ですが、遠方から来て頂く場合は、それに相応しい金額をお渡しします。
僧侶が交通機関やタクシーを利用した場合は、実費で渡す、もしくはチケットなどを手配する形でも構いません。
僧侶の住居が隣接しているお寺で葬儀をする場合や、施主が送迎タクシーを手配した場合などは僧侶に渡す御車料は不要と考えて問題ありません。
宿泊が必要な場合はさらに+1万円と考えておきましょう。
御膳料
御膳料は簡単にいうと、葬儀当日の食事代です。
御膳料の相場は5千円~1万円です。
僧侶が葬儀後の通夜振る舞いや精進落としの会食に参席されなかった場合に渡します。
近年は通夜振る舞い・精進落とし自体が省略される傾向にあり、行ったとしても身内だけで僧侶が参加するケースは少なくなっています。
折詰め(弁当)などを用意している場合、御膳料は不要と考えて問題ありません。
もし御車料と御膳料を一つの袋で渡す場合には、切りのいい金額にしましょう。
家族葬で菩提寺がない場合でもお布施は必要?
菩提寺が無かったとしても、読経をお願いするために僧侶を呼ぶ場合、お布施は必要になります。
菩提寺が無い場合は葬儀会社に手配してもらうか、近年では僧侶の派遣サービスがありますので、そちらを利用しましょう。
僧侶の派遣サービスは金額が決まっていますし、菩提寺以外のお寺に依頼する場合ははっきり金額を伝えられることも多くあります。
菩提寺以外ではっきりとした金額がわからない場合は、相場とされる金額の用意をしておきましょう。
直葬や自由葬(無宗教葬)で僧侶の読経を必要としない場合は、不要です。
【関連記事】
お布施が少ないと言われたらどうしたらいい?金額相場・マナーについても解説
家族葬でのお布施の渡し方・マナー
お布施は感謝の気持ちですので、できれば新札を用意しましょう。
また、新札を用意しない、新札の場合は折り目をつけるなどのマナーは、喪家に対してお渡しする香典のマナーになりますので、勘違いしないように気をつけてください。
その他にも、お布施の渡し方にはマナーがありますので、確認していきましょう。
白無地の封筒か奉書紙に包む
お布施は、まず半紙でお札を包み、その上から奉書紙で包むのが正式なマナーです。
白無地の封筒でも構いませんが、水引は付いていないものを使用します。
表書きは「お布施」または「御礼」と濃墨で書きます。
喪家にとってお葬式は不幸事ですが、僧侶にとっては不幸事ではないので、薄墨は使用しません。
渡すタイミングは開式前
お布施を渡すのは開式前が望ましいとされていますが、僧侶の到着が開式ギリギリになってしまった場合など、渡すタイミングが無ければ終了後でもマナー違反ではありません。
防犯上の観点から、葬儀終了後をおすすめされる場合もあります。
葬儀前に打ち合わせなどで顔を合わせることがあれば、その際に渡してしまっても構いません。
タイミングがわからない場合は、葬儀社スタッフへ確認するといいでしょう。
その際、僧侶へのお声がけや渡す際のサポートをして頂ける場合もあります。
葬儀前にお渡しする時は「本日はよろしくお願いいたします。」、開式後の場合は「本日はありがとうございました。どうぞお納めくださいませ。」などと一言添えてお渡しするようにしましょう。
切手盆に載せて渡す
お布施を渡す際、直接手渡しするのは失礼になります。
切手盆か袱紗の上にお布施袋を載せて渡しましょう。
切手盆とは、黒塗りの20cm程度のお盆のことです。
葬儀が葬儀会社の斎場で行われるのであれば、貸して貰えることがほとんどです。
お布施をいくら包めばよいかわからない場合は直接僧侶にたずねても失礼ではない
お布施には金額の相場があるといっても、地域や宗派、お寺ごとに異なります。
「どれくらい包んだらよいのだろう」「僧侶に金額を尋ねるのは失礼ではないだろうか」と戸惑ってしまうこともあるでしょう。
わからない場合は、僧侶にお布施の金額を聞いてしまっても失礼ではありません。
もしはっきりとした金額の回答を頂けなかったり、聞きづらかったりする場合など、葬儀以外にもお布施の金額やマナーに関するお悩みもご相談ください。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要