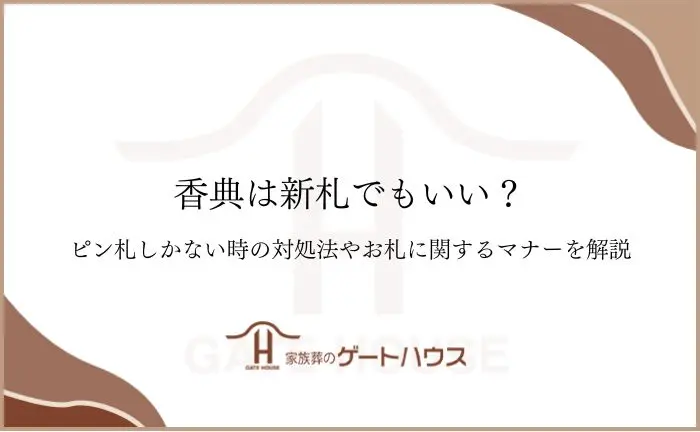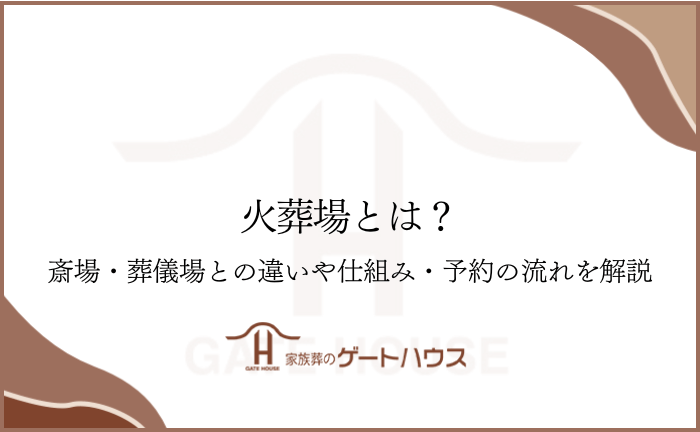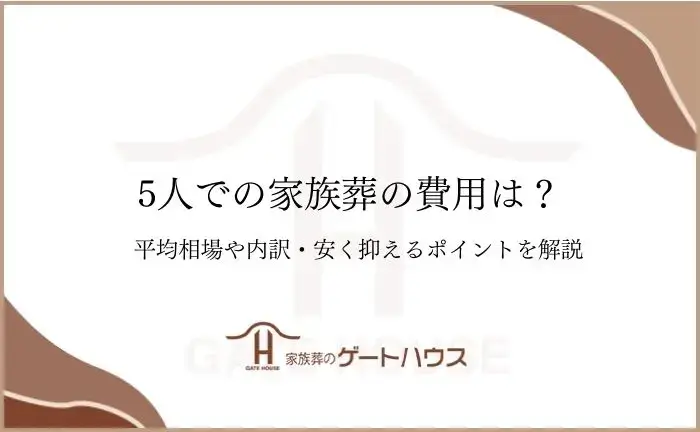独身・身寄りなしの老後の課題とは?高齢者が行うべき終活内容を解説
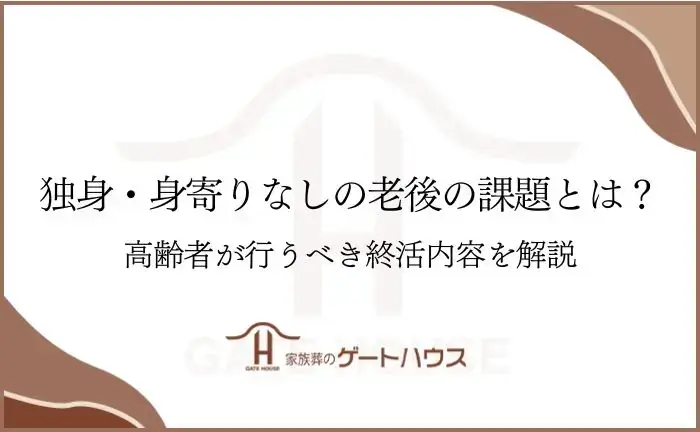
少子高齢化が進む現代社会では、「独身で身寄りがない」という高齢者が増加しています。
結婚歴がなく、子どもや兄弟もいない、あるいは疎遠になっているなど、老後の不安を抱える人は少なくありません。
独身で身寄りがない高齢者は、家族の支援がない中で、入院や介護施設への入所、財産管理や葬儀に関することまで自分で備えていく必要があります。
本記事では、独身で身寄りのない方が直面しやすい課題と、老後に備えて行うべき終活の内容について詳しく解説します。
独身・身寄りなし高齢者が直面する老後の課題とは
「独身で身寄りがない」ことに不安を抱える人は、家族や親族と疎遠だったり、そもそも相続人がいなかったりするケースもあります。
具体的にどのような課題があるのか、詳しくみていきましょう。
判断能力の低下や病気、死亡に備える必要がある
高齢になると、認知症などにより判断能力が低下するリスクや、年齢を重ねることで病気にかかる確率も高まります。
また、身寄りがなく地域とのつながりも疎遠になってしまうと、他人と会話する機会が激減し、体調などの変化に気づいてもらいづらく、認知症などの健康問題も深刻化しやすくなってしまいます。
家族がいれば支援してもらえるような場面でも、いざというときに代わりに対応してくれる人がいないため、自らしっかりと備えておくことが求められるでしょう。
身元保証人がいない
身元保証人とは、本人(高齢者)に代わって、金銭的な連帯保証、緊急時の連絡先、医療方針への同意、入退院時のサポートなどの役割を担う立場の人のことを指します。
多くの病院や介護施設では、入院・入所時に身元保証人を求められます。
入院・治療に関しては、身元保証人なしで柔軟に対応してもらえるケースもあるでしょう。
しかし、身元保証人が不要の介護施設は、入所条件が厳しく定められていることも多く、加えて希望者も多いため、すぐに入所できるとは限りません。
独身で家族がいないと身元保証人を探すのが難しく、保証人がいないと施設や医療機関の受け入れを断られるケースもあるため、あらかじめ成年後見制度や身元保証サービスの利用を検討し、備えておくことが現実的な対策といえるでしょう。
財産管理や生活支援をしてくれる人がいない
日常の買い物や、通院、銀行や行政の手続きや届け出など、高齢になると支援が必要になる場面が増えますが、家族がおらずサポートしてくれる人もいない場合、第三者に頼る必要があります。
そのためには、事務委任契約や財産管理契約を活用し、生活支援や財産管理に関して、信頼できる第三者と契約を結んでおくことが重要です。
死後の手続き・葬儀の不安
死亡後には、役所への届け出、葬儀、火葬、納骨、遺品整理、相続手続き、契約していたサービスの解約など、さまざまな事務作業が発生します。
身寄りがなく、特に生前契約等もしていなかった人が亡くなった場合、本人の意思が反映されずに行政処理される可能性も高く、周囲の人に負担をかけてしまう可能性も。
生前契約や死後事務委任契約を利用し、信頼できる第三者に死後の手続きを託しておくことで、安心して老後を過ごすことができるでしょう。
【関連記事】
終活はおひとりさま(身寄りなし)でも必要?独身・一人暮らしがすることや費用を紹介
女性の一人暮らしに終活は必要?準備することや費用・メリットも解説
独身で身寄りのない人の老後の対策と制度
独身で身寄りがない人も安心して生活を送るためには、判断力があるうちに必要な対策を行っておくことが重要です。
以下に、代表的な制度や対策を紹介します。
任意後見制度と成年後見制度
「判断能力があるうちに、将来のために後見人を指定しておける」のが任意後見制度で、本人が判断力を失ったときに効力を発揮します。
後見人には、司法書士や福祉法人、信頼できる知人などを指定できます。
契約内容は、財産管理から日常生活の支援まで、幅広く設定可能ですが、認知症などで判断力が低下してからでは契約できないので注意が必要です。
また、任意後見制度の利用には、公証役場での契約と家庭裁判所への申立てが必要です。
一方で成年後見制度は、すでに判断能力が低下した人のために裁判所が後見人を選任する制度です。
家庭裁判所が後見人を選任するため、本人の意思が十分に反映されない可能性も。
とにかくできるだけ早めに、任意後見制度の利用を検討しておくことが望ましいでしょう。
財産管理・事務委任契約
任意後見契約が発効する前の段階から、財産管理や生活の支援を依頼するための契約が「財産管理契約」や「(生前・死後)事務委任契約」です。
財産管理契約
「財産管理契約」は、本人に判断能力はあるものの、身体上の不調などで財産管理や生活上の支払いが難しくなった場合を想定して、第三者に代理権を与える契約です。
任意後見契約と組み合わせて財産管理契約を締結することで、契約の締結後すぐにこの財産管理契約が発効。
その後、本人の判断能力が低下した際に、任意後見契約へと移行する形を取れます。
事務委任契約
事務委任契約には「生前事務委任契約」と「死後事務委任契約」の2つがあります。
「事務委任契約」は、高齢を理由に、財産についての管理や契約更新などの手続きが難しくなってきた場合に、家族や専門家である第三者などにその事務を委任する契約です。
公共料金や医療や介護の契約手続きや支払い、行政手続きの代行、郵便物の受け取りなど、日常的な事務のサポートを第三者に依頼できます。
事務委任契約は幅広い事務手続きを委任できるのに対し、財産管理契約は財産に関する事務に限定されます。
死後事務委任契約
「死後事務委任契約」とは、自分の死後に発生するさまざまな事務手続きを、生前のうちに専門家に依頼しておく契約のことです。
葬儀やお墓の準備、病院や介護施設への費用の支払い、公共料金やクレジットカードの解約、役所への届け出についても、信頼できる第三者に委任できます。
ただし、死亡届の提出など一部は、法律上、一定の届出資格者に限られるため、代理で行えない手続きがあることも知っておきましょう。
契約の依頼先と注意点
これらの契約は、司法書士や行政書士との契約が一般的で、裁判所が関わることなく、本人と代理人の間で契約を締結できるため、メリットもたくさんあります。
ただし、ご自身で受任者の業務内容をしっかりチェックする必要が出てくるため、トラブルが心配な場合などは、公正証書で作成するのが望ましいでしょう。
身元保証サービス
近年は、家族に代わって身元保証を行うサービスを提供する法人や団体も増えています。
買い物や病院受診などの日常生活のサポートや、介護施設や病院への入所時に必要な保証人業務を、契約により代行してもらう仕組みです。
なかには、24時間体制の緊急対応や、亡くなる前後のサポートを受けられるものも。
身元保証サービスが提供するサービスは幅広く、会社や団体によってサービス内容は異なります。
法的な保証能力や信頼性は事業者ごとに差が大きいため、選ぶ際のポイントは費用体系の明確さと、必要なサポート範囲がカバーされているかの2つが重要です。
独身・身寄りなしの人が老後の終活で準備しておきたいこと
終活とは、自分自身がよりよく生きるため、残された人に負担をかけないようにするための、事前準備のこと。
以下では、独身・身寄りのない方が行っておくべき終活内容を紹介します。
遺言書の作成
遺産の有効活用を希望するのであれば、遺言書の作成を考えるとよいでしょう。
家族や相続人がいない場合、何も対策をしていないと、財産は最終的に国に帰属することになります。
遺言書等がなかった場合、法律によって自分の意図しない財産継承が行われる可能性も。
遺言書には、公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、特にこだわりがなければ公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言の作成には費用がかかりますが、弁護士などの公証人が作成するため、遺言内容が確実に実行される安心感があります。
一方の自筆証書遺言は、不備があると無効になってしまうリスクがあるため、特別な事情がなければ公正証書遺言を選ぶのがいいでしょう。
エンディングノートの活用
エンディングノートには、財産情報、医療・介護の希望、葬儀の内容などを自由に記載できます。
法的効力はありませんが、家族や専門家が本人の意思を把握するための有効な手段です。
区市町村の窓口やホームページで無料配布されているものもあるので、まずは手に取って試しに書き進めてみることが終活の第一歩となるでしょう。
【関連記事】
エンディングノートとは?おすすめの内容や書き方・終活ですべきことを解説
相続対策と生前整理
エンディングノートには、財産目録を作成する項目があります。
預貯金や不動産、保険などのすべての資産を一覧できるように記載し、重要書類(保険証券や権利書など)の保管場所も併せて明記しておきましょう。
これにより、自分の財産の全体像を把握しやすくなり、不要な口座の解約や不用品の処分など、生前整理にも役立ちます。
また、相続人を明確にし、相続に関する意向を明確にすることも可能です。
ただし、法的拘束力はなく、あくまで参考情報になるため、遺産について確実に意向を反映させたい場合は、遺言書を作成しておくのがいいでしょう。
生前整理を通じて必要なものと不要なものを整理しておくことは、死後の各種手続きを円滑に進めるための重要な準備です。
さらに、生前に整理を済ませておくことで、遺された人の負担を軽減することにもつながります。
物の整理とあわせて、心の整理も行うことで、心身ともに安定した日々を過ごせるでしょう。
【関連記事】
生前整理とは?いつから始めるのか・生前整理をやるメリット&デメリットなど解説
身辺整理とは?意味や終活でできるやり方・整理すべきことを解説
デジタル遺品・データの管理
SNSアカウント、クラウド上の写真や文書、オンラインバンキング、その他のあらゆる契約情報などのデジタル遺品も増えています。
デジタル遺品は見つけにくく処理が難しいため、最低限、主要なアカウントとパスワード、そして解約や削除の希望があれば、その方法を記録しておくことで、遺された人の負担を軽減できるでしょう。
パスワード管理ツールなどを使えば、紛失リスクを減らしつつスムーズに整理でき、GoogleやAppleでは、死亡時のデータ処理を設定できるサービスやツールも提供されています。
こうしたサービスも活用しながら、事前に整理しておくことが大切です。
葬儀・埋葬に関する希望
近年は、葬儀形式や埋葬方法に関してもあらゆる選択肢があります。
身寄りがない方は永代供養、樹木葬、散骨などを選択される方も増えていますが、葬儀の形式や希望する埋葬方法、宗教・宗派の指定などを明確にしておくとよいでしょう。
また、葬儀社との生前契約を締結できる場合もあるので、その場合は希望どおりの葬儀が実現できます。
前述した「死後事務委任契約」を活用し、死後の手続きをすべて信頼できる第三者に依頼しておくのもおすすめです。
専門家へ相談
成年後見制度や、財産管理契約・事務委任契約、遺言書作成などには、法的な専門知識が必要です。
司法書士や弁護士、行政書士などの専門家に相談することで、自分に合った契約内容や対策を立てられます。
もっと気軽な相談をしたい、という場合には地域の包括支援センターや社会福祉協議会を利用するとよいでしょう。
地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口で、介護保険の利用相談から福祉サービスの紹介など無料で相談できます。
社会福祉協議会の日常生活自立支援事業では、判断能力に不安のある方向けに、福祉サービスの利用手続き支援、預貯金の出し入れ代行、公共料金の支払い支援などを行っています。
行政の相談窓口や支援制度を活用したり、民間の支援サービスを活用したりすることで不安を解消しやすくなるでしょう。
自分らしい老後を過ごすためには備えが大切。独身・身寄りなしなら早めにご準備を
独身で身寄りがない方にとって、老後と死後の備えは非常に重要です。
判断能力があるうちに各種制度を利用したり、契約や終活を早いうちから始めたりすることで自分の意思を明確にでき、老後の備えとなります。
相続や財産に関する内容を法的に有効にするためには、エンディングノートだけでなく、公正証書遺言などの正式な書面の作成を検討するとよいでしょう。
専門家の力を借りながら、安心して暮らせる老後を築くことが、自分らしい人生を全うするための第一歩です。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要