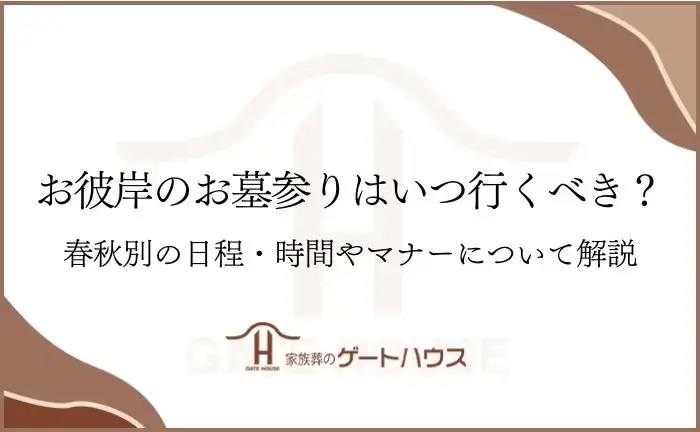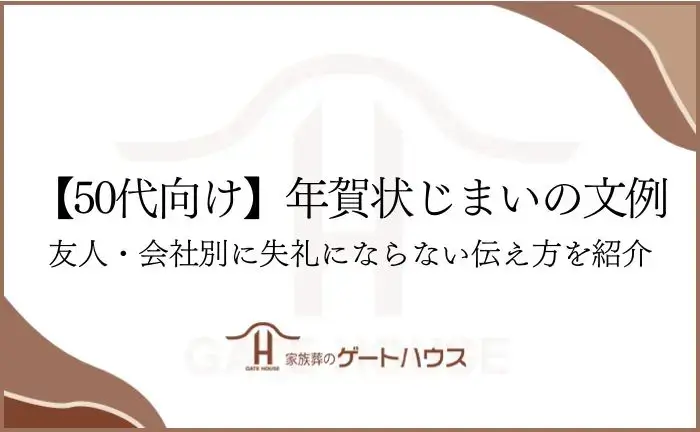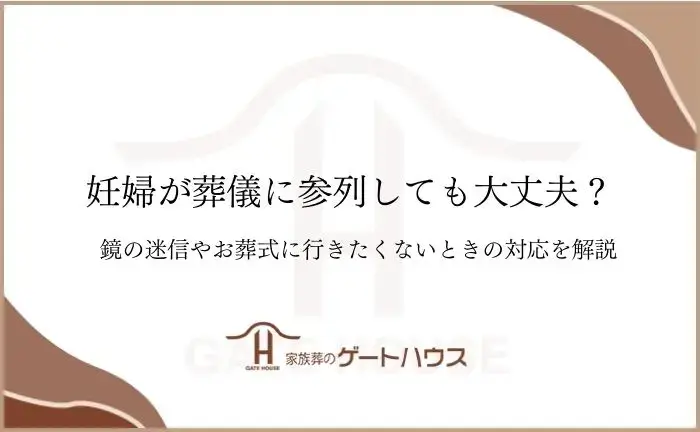親が亡くなる前にしておくこととは?やることチェックリストで手続きを解説
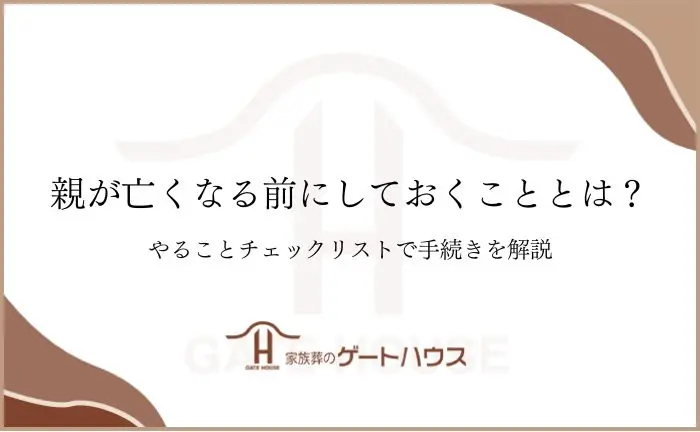
親が亡くなる前にしておくべきことは、相続や葬儀、金銭関係の準備など多岐にわたります。
やることチェックリストを使い、銀行口座や不動産の整理、葬儀の手配まで事前に手続きを確認しておき、いざという時に慌てずに対応しましょう。
今回は、事前に準備しておきたい確認や手続きなどをわかりやすく解説します。
親が亡くなる前にしておくこととは?やることチェックリストで確認
【金銭関係】
- 銀行預金口座や証券口座の情報を確認し、お金を引き出して集約する
- 定期預金やサブスクなどを解約する
- 家賃や光熱費・クレジットカードの引き落とし先を確認する
- スマホやPCなどの電子機器情報を整理する
【相続関係】
- 親名義の不動産などを生前贈与しておく
- 遺言書やエンディングノートを作成してもらう
- 財産目録を作成する
- 相続税などのかかる費用を算出しておく
【葬儀関係】
- 葬儀社の見積もりを取り決定しておく
- 葬儀の内容を決定しておく
- 訃報を連絡する相手を決めておく
- 葬儀の流れを頭に入れておく
親が亡くなる前に準備しておくべきことは、主に「金銭関係」「相続関係」「葬儀関係」の3つです。
金銭関係では、銀行口座や定期預金の確認と整理や電子機器やサブスクの情報も整理しておくと、後の手続きがスムーズになります。
相続関係では財産目録の作成や生前贈与の検討、遺言書の準備・確認をしておきましょう。
葬儀関係では事前に葬儀社を選び、内容や参列者を決めておくことで、親の最期をしっかり見送るための準備が整います。
親が亡くなる前にしておくこと|金銭関係
親が亡くなる前には、まず金銭関係の整理をしておきましょう。
銀行口座や定期預金・支払い先の確認・解約などを事前に把握しておけば、相続手続きがスムーズに進みます。
また家族間のトラブルを避けるためにも、情報の共有をしておくことも必要です。
銀行預金口座や証券口座の情報確認・集約
親の預金や証券口座が複数ある場合は、生前のうちに情報を確認して、できる限り集約しておきましょう。
親が亡くなった後は銀行口座が凍結されます。
解約には戸籍謄本や印鑑証明書が必要なので、手続きに時間がかかるのです。
そのため、日常的に使用していない口座は、事前に解約し残高をメインの口座にまとめると後の管理が容易になります。
家族と共有できる範囲で通帳や暗証番号も含めて確認し、スムーズな相続準備を進めてください。
サブスクや光熱費の引き落としなどの金銭関係情報の整理
光熱費や各種サービスの引き落とし先も、必ず確認しておきましょう。
サブスクリプションサービスや定期購入など、親が契約しているものを把握しておけば、亡くなったあとに不要な支払いを防げます。
さらに、親が持つ電子機器やオンラインアカウントの情報も整理し、必要なアカウントの削除や解約を事前におこなっておくことも大切です。
これにより後の手間を減らすとともにトラブル防止にもなり、家族の負担が軽くなります。
親が亡くなる前にしておくこと|相続関係
親が亡くなる前に相続に関する準備を整えておけば、相続後のトラブルを防ぎスムーズな手続きが可能になります。
不動産の名義変更や遺言書作成、財産の整理を進め、相続税対策もしっかりおこないましょう。
親名義の不動産などを生前贈与しておく
親名義の不動産は、生前に贈与をおこない手続きがスムーズに進めておきましょう。
生前贈与は贈与者の意志を直接反映できるため、相続する人間同士の意見がぶつかるリスクを軽減できるのです。
ただし、生前贈与には不動産取得税がかかるほか、固定資産税も受贈者の負担となるため、税額を考慮して進める必要があります。
贈与税と相続税の基礎控除額や税率の違いも確認し、効果的な方法を選びましょう。
贈与時のトラブルを防ぐため、書面を残すことも大切です。
遺言書やエンディングノートを作成してもらう
遺言書やエンディングノートは、親の意思を明確に残す重要な書類です。
遺言書には法的効力があり、遺産分割の方針を示すため、相続人間のトラブルを回避できます。
一方、エンディングノートに法的効力はありませんが、医療や葬儀の希望・身の回りの事柄が記載でき、遺族が困らないための指針となってくれるのです。
自筆証書遺言や公正証書遺言など遺言書には形式があるため、作成には税理士事務所や法律事務所の専門家に相談すると、書類の不備を防げます。
【関連記事】
エンディングノートとは?おすすめの内容や書き方・終活ですべきことを解説
財産目録を作成する
財産目録は、相続財産の全体像を把握するために役立ちます。
プラスの財産だけでなく、借入金などマイナスの財産も関わってくるため、一覧化しておくことが重要です。
金融機関の口座や証券・不動産などをすべてリストにしておけば、相続人がスムーズに分割協議を進められます。
また、財産内容や受取人が把握できていないと、相続税の申告漏れが発生するリスクが高くなるため注意しましょう。
財産目録を生前に作成し、税理士など税務の専門家にチェックしてもらうのがおすすめです。
相続税などのかかる費用を算出しておく
相続税は思わぬ負担になることが多いため、事前に計算して支払い準備を整えておくことが大切です。
とくに相続税は現金一括納付が原則のため、財産が不動産や株式のみだと支払いが難しくなるケースがあります。
相続税の納付期限に遅れると、延滞税がかかるため注意が必要です。
また、生命保険の非課税枠の活用や、財産の一部を生前贈与して相続税額を減らす方法も検討しましょう。
親が亡くなる前にしておくこと|葬儀関係
親が亡くなる前に葬儀に関する準備を整えておくと、当日慌てることなく故人を見送れます。
葬儀社の選定や式の内容、訃報の連絡先などを事前に確認しておくと安心です。
それぞれについて、どのように準備をすればいいのかを見ていきましょう。
葬儀社の見積もりを取り決定しておく
葬儀社の見積もりは、複数社から取り寄せ比較して決めましょう。
各社のプラン内容や費用には大きな違いがあり、親の意向に合う内容を確認しておくことが大切です。
また家族葬や一般葬など、参列者数や形式によっても費用は変わるため、親が望む葬儀の規模に合ったプランを選ぶといいでしょう。
さらに、いざという時に迅速に対応してもらえるよう、お客様に寄り添ってくれる24時間対応の葬儀社を選んでおくと当日も安心して迎えられます。
【関連記事】
葬儀の事前相談をするメリット7つ丨お葬式前に準備しておきたいこととは?
葬儀社の選び方のポイント丨失敗しないための決め方や気をつけることを解説
葬儀の内容を決定しておく
葬儀の内容についても、事前に親と話し合い具体的な方針を決めておきましょう。
たとえば、通夜や葬儀の形態・仏式や無宗教式など、宗派や形式を確認し、故人の希望に沿った演出やお別れの場をどのようにするかを考えることも大切です。
とくに親の好みや思い出の品、写真などを取り入れると家族にとっても心に残る式になるため、そうした意向も確認しておいてください。
事前に内容が固まっていれば、家族も心に余裕を持って対応できます。
訃報を連絡する相手を決めておく
訃報を連絡する相手をリストアップしておくと、スムーズに訃報の連絡がおこなえます。
親しい友人や親戚の連絡先・職場関係など、訃報を知らせる範囲を事前に話し合って決めておきましょう。
また、家族葬の場合は参列を控えてもらうための案内も必要になるため、連絡の仕方や文面を考えておくことも大切です。
訃報の連絡先リストを事前に用意しておくことで、当日慌てることなくスムーズに対応できます。
葬儀の流れを頭に入れておく
葬儀の一般的な流れを把握しておくことで、当日の混乱を防げます。
葬儀は通夜・告別式・火葬の順で進むことが一般的ですが、宗教や地域によっても異なる場合があるため事前に確認しておきましょう。
また、参列者への案内や喪主としての役割も事前に理解しておくと、慌てずに済みます。
葬儀の進行や手配については葬儀社と相談しながら決めておくと、当日スムーズに進行でき、故人を穏やかに送り出せます。
【関連記事】
親が亡くなる前にしてあげられること
親が亡くなる前に最期の時間をできるだけ快適に過ごせるよう、いくつかの心遣いが大切です。
主にどんなことをしてあげれば、親に穏やかなひとときを過ごさせてあげられるのか、代表的な例を紹介します。
枕やベッドを清潔に保つ
親が心地よく過ごせるよう、ベッドや枕は常に清潔に保つことが大切です。
高齢になると、肌が敏感になりがちなので、少しの汚れでも不快に感じやすくなります。
シーツや枕カバーを頻繁に交換し、寝具の清潔を維持してください。
さらに、こまめな換気や適度な温度・湿度の管理もおこない、快適な環境を整えておくと健康や気分的にも良い影響を与えます。
心地よい空間作りが、親にとって安らかな時間につながるのです。
思い出の曲をかける
親が好きだった曲や思い出深い音楽をかけることも、穏やかな時間を一緒に過ごすためのひとつになります。
音楽は心を落ち着かせ安心感を与えるため、静かに流れる音楽があると会話がなくても心が通う瞬間が生まれるでしょう。
また音楽によって過去の思い出が蘇り、親との対話のきっかけになることもあります。
親がどんな音楽を好んでいたかを思い出しながら、リラックスした空間を作りましょう。
話しかける
親が横になっている時も、日常的に優しく話しかけることが大切です。
簡単な近況報告や思い出話など、何気ない会話が親にとっても安心感につながるでしょう。
また、話すことで親の気持ちが少しでも軽くなるよう、聞き手に徹することも大切です。
容態によっては感情表現が難しくなる場合もありますが、反応が少なくても焦らずに穏やかに接しましょう。
大切なのは、親に自分がそばにいると感じてもらうことです。
会いたい人を呼ぶ
親が望む場合は、会いたい友人や家族・親族を呼び、再会の機会を設けましょう。
長年連絡を取っていなかった友人や恩人などに会うことで、親にとっても気持ちが落ち着き、喜びが生まれることがあります。
再会が叶うよう、あらかじめ会いたい人の連絡先を確認し、スムーズに調整できるよう準備しておくのも大切です。
会いたい人に会うことで、満足感を得られる貴重な時間を作ってあげられます。
ありがとうを伝える
親に「ありがとう」の気持ちを伝えることは、お互いにとってとても大切な時間になります。
普段なかなか伝えられない感謝の気持ちがあるのなら、今こそ素直に表しましょう。
感謝の言葉は、親にとっても心に残るものであり、安心感や満足感につながります。
また、感謝の言葉を通じて、親も心を開いて話しやすくなり自然に親子の絆も深まっていくでしょう。
最後だからこそ後悔しないよう、親と向き合って気持ちをしっかりと伝えてください。
【関連記事】
危篤状態とはどんな意味?回復する確率や連絡を受けたらすべきことを解説
危篤の連絡を受けたらどうする?会社にメールを送る時の例文や伝え方を紹介
老衰とは?死ぬ直前に表れる症状やサイン・死亡までの期間にできることを解説
親が亡くなった時の手続きは何がある?
親が亡くなった時には、多くの手続きが必要です。
公的手続きや私的な連絡事項、相続関連の処理など、どれも速やかにおこなう必要があります。
これらの内容を確認し、しっかり対応していきましょう。
公的な死亡後の手続き
親の死亡後、最初におこなうべき公的な手続きは、死亡診断書の受け取りと死亡届の提出です。
死亡届は死亡を確認する法的手続きであり、提出後には火葬許可証が交付されます。
あわせて年金や健康保険の受給停止手続きも迅速におこないましょう。
また、介護保険の資格喪失や世帯主の変更も必要です。
これらの手続きを役所で速やかにおこなうことで、後の手続きがスムーズに進みます。
私人間の死亡後の手続き
親の死亡後は親族や友人への訃報連絡、葬儀社の手配が必要です。
訃報の連絡は、近親者から始め、友人や職場の関係者へ順におこないましょう。
その後、葬儀社と打ち合わせをして葬儀の日程や内容・参列者数を決定します。
葬儀社は遺体の搬送や準備もサポートするため、できれば事前に相談し親族の意向に沿った内容を確認しておくと安心です。
相続関係の死亡後の手続き
相続に関連する手続きは、遺言書の確認から始まり、家庭裁判所での検認が必要になります。
また、遺産分割や不動産預金の名義変更なども速やかにおこないましょう。
相続税の申告は10ヵ月以内が期限であり、相続人や財産の確認が済んでいる必要があります。
こうした手続きには時間がかかる場合もあるため、事前に必要な書類を揃えて進めるとスムーズです。
【関連記事】
自宅で亡くなった場合どこに連絡するべき?警察・救急車の判断や流れを解説
施設・老人ホームで亡くなった場合の葬儀は?検死はある?流れや注意点を解説
親が亡くなった後にすべきではないこと
親が亡くなった後、避けるべき行動もいくつかあります。
自分も、周りも気持ちが落ち着いていない時期だからこそ、勝手な行動はトラブルの元です。
とくに以下の点には気を付けましょう。
親の預貯金の勝手な引き出し
親の死亡後、預貯金は相続人全員の共有財産となるため、無断で引き出してはいけません。
勝手な引き出しは相続トラブルの原因となり、後々不正使用と見なされる可能性もあります。
口座は、銀行が名義人の死亡を確認した時点で凍結され、正当な手続きを踏まないと資金を動かせなくなるため、必要な引き出しは本人の死亡前に同意のもとおこなっておきましょう。
とくに、葬儀費用に充てるための出金も相続人の了承を得た上でおこない、支払い内容は領収書を残して明示しておくことが重要です。
遺言書の断りのない開封
親が遺した遺言書を見つけた際は、勝手に開封せず必ず家庭裁判所で「検認」の手続きをしましょう。
無断開封は違法行為に該当し、法的に5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
また故意ではなくても他の相続人から不信感を抱かれ、遺産分割協議が円滑に進まない恐れもあるため注意が必要です。
相続人全員で遺言書の内容を共有し、公正な相続手続きがおこなえるように配慮しましょう。
飲み会や慶事への参加
親が亡くなった後の喪中期間中は、葬儀直後の慶事への参加は控えましょう。
親しい人が亡くなったばかりでの飲み会や結婚式の出席は不適切とされ、周囲にも気を遣わせてしまうことが多いです。
また、喪に服す期間は地域や宗教によって異なりますが、一般的には49日や1年間は、祝い事や社交的な行事への出席を避け、家族や親族の心のケアを優先するのが無難とされています。
【関連記事】
親が亡くなる前にしておくことはたくさんある。やることチェックリストで漏れが無いよう確認を
親が亡くなる前に準備しておくべきことは多く、金銭管理や相続、葬儀準備など幅広くあります。
銀行口座や不動産の整理・生前贈与・遺言書の作成などを事前に進めることで、家族が相続手続きに悩まずに済み、スムーズに進められるでしょう。
また、葬儀内容や連絡すべき人のリストを整えておくと、いざという時に慌てず対応できます。
こうした、やることのチェックリストを活用し、大切な準備に漏れがないように確認をおこないましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要