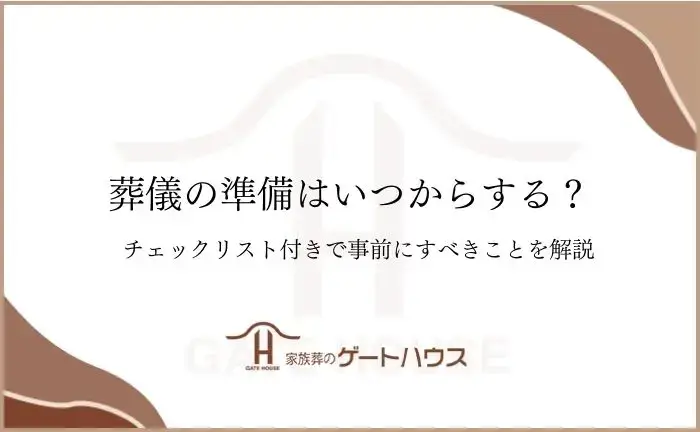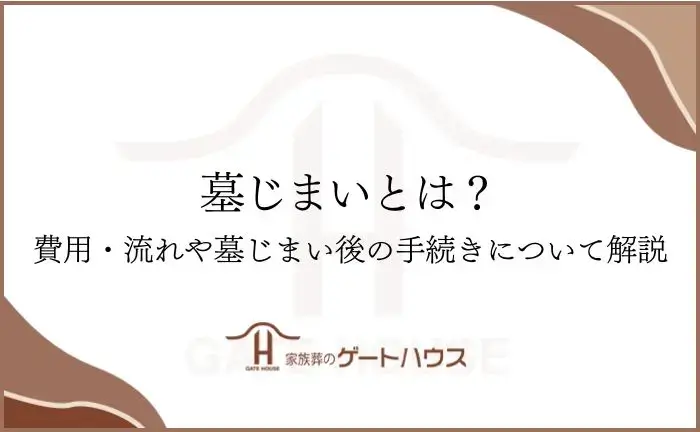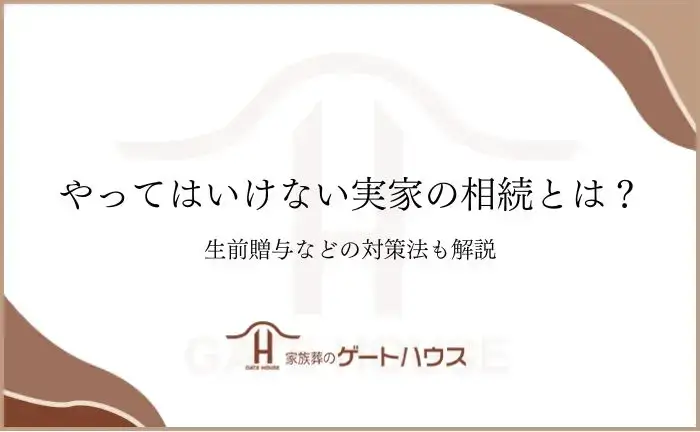施餓鬼(せがき)とは?行かないのはあり?意味・お布施の書き方マナー・宗派別の違いを解説
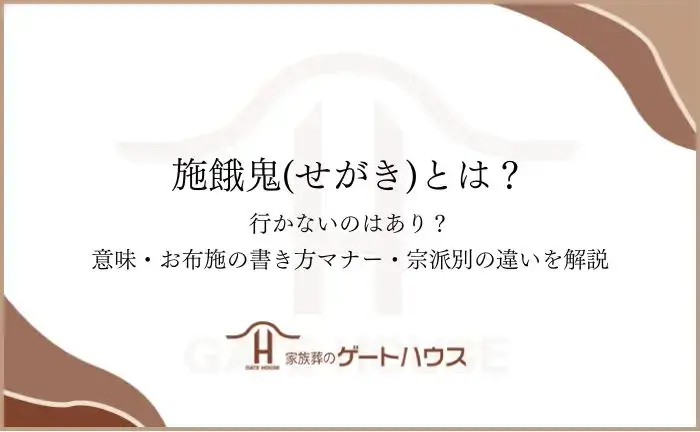
施餓鬼(せがき)とは、お盆の時期に行われる大切な仏教行事です。
餓鬼道に堕ちた霊を救うための儀式であり、先祖供養だけでなく、あらゆる苦しむ存在への慈悲を表します。
この記事では、施餓鬼の意味やお布施のマナー、宗派による違いなどを詳しく解説し、初めて参加する方でも安心して臨めるようご案内します。
施餓鬼(せがき)とは?いつする?
施餓鬼は、日本の仏教における重要な法要のひとつで、主にお盆の時期に行われます。
施餓鬼とは、餓鬼道に落ちて苦しんでいる霊や、無縁仏など供養されずにさまよっている霊に対して、飲食物を施し、その苦しみを和らげ成仏を願うための儀式です。
お盆と同じように、ご先祖様や無縁仏の供養を大切にする日本の伝統的な風習のひとつで、多くのお寺で行われており、家族や地域の絆を深める場にもなっています。
施餓鬼の「餓鬼」
「餓鬼」とは、仏教の六道のひとつ「餓鬼道(がきどう)」に生まれ変わり、飢えと渇きの苦しみの中にいる亡者たちを指します。
餓鬼道は、生きている間に強い欲を持ちわがままであった者、必要なことを怠り人を傷つけた者が死後に落ちるとされている、死者の世界です。
餓鬼道では、常に食べ物や水が足りず、どんなに飲食物を口にしようとしても炎に変わってしまうため、餓鬼のお腹が満たされることはありません。
施餓鬼は、こうした餓鬼道の苦しみから霊を救済するための法要なのです。
施餓鬼の由来
施餓鬼の法要は、仏教に伝わる古いお経「救抜焔口餓鬼陀羅尼経(くばつえんくがきだらにきょう)」に由来します。
お釈迦様の弟子の1人である阿難(あなん)は、修行中に出会った餓鬼の霊から「お前は餓鬼道に落ちるだろう」との予言を受けました。
困った阿難がお釈迦様に助けを求めたところ「陀羅尼(だらに)」という祈りの言葉と作法を用いて、無数の餓鬼や僧侶に食べ物を施し供養するよう教えられたのです。
阿難がその教えに従ったところ、餓鬼は救われ、阿難自身も寿命を延ばすことができたと伝えられています。
この説話が元となり、施餓鬼法要が仏教行事として広まったのでした。
施餓鬼をする時期
施餓鬼法要を行う時期に厳密な決まりはなく、地域や宗派によってさまざまですが、一般的にはお盆の期間と重なる7月または8月に行われることが多いです。
お盆の時期は「地獄の釜の蓋が開き、亡者が現世に戻ってくる」とされ、ご先祖様だけでなく餓鬼もこの世にやってくると考えられているため、施餓鬼法要が盛んに行われます。
また、特定の災害や大きな出来事があった際、犠牲者や無縁仏の供養のために、臨時で施餓鬼が行われることもあります。
【関連記事】
新盆(初盆)とは?やり方は?用意するものやいつ法要を行うか解説
盂蘭盆会(うらぼんえ)との違い
施餓鬼と盂蘭盆会は、どちらもお盆の時期に行われるため、混同されがちですが、それぞれ異なる意味を持ちます。
盂蘭盆会は、先祖の霊を供養するための行事であるのに対し、施餓鬼は、餓鬼道に堕ちた亡者や、無縁仏を供養するための行事です。
現代では、多くの寺院でお盆行事と施餓鬼法要を同じ時期や同日にまとめて行うこともあるため、境目があいまいになってきていますが、目的や対象が異なります。
【関連記事】
盂蘭盆会(うらぼんえ)とは?意味やお盆・施餓鬼会との違いを解説
宗派別に見る施餓鬼の違い
施餓鬼法要は、宗派によって行い方や考え方に違いがあります。
ここでは、主な仏教宗派ごとの施餓鬼の特徴を解説します。
自分の菩提寺の宗派では、どのように施餓鬼が行われているのか知っておきましょう。
曹洞宗・臨済宗
曹洞宗や臨済宗といった禅宗では、施餓鬼法要を「施食会(せじきえ)」と呼ぶのが一般的です。
これは「施す者と施される者に身分の差があってはならない」という、平等の精神に基づいています。
そのため曹洞宗では特に「餓鬼だけでなく、すべての精霊や無縁仏にも供養を施すべし」という考えが強いです。
臨済宗では、焼香をあげる代わりに洗った米や水を供物棚に供える、「水向け」を行うことも特徴の1つとされています。
【関連記事】
曹洞宗の初盆飾りの仕方は?精霊棚(祭壇)の飾り方・お供え物・提灯について解説
真言宗
真言宗では、施餓鬼法要が他宗派よりも頻繁に行われるのが特徴です。
真言宗の教えでは「餓鬼への施しは連日でも良い」とされており、特に夕方から護摩を焚いて祈祷を行う施餓鬼法要が多く見られます。
お盆や彼岸だけでなく、毎日施餓鬼法要を行う寺院もあり、地域の人々が集まる大切な行事となっています。
【関連記事】
真言宗の初盆とは?準備するお供え物や行うこと・服装マナーを解説
浄土宗
浄土宗では、施餓鬼法要を非常に重視し、多くの寺院で大規模に行われるのが特徴です。
「阿弥陀仏の慈悲によってすべての人が救われる」という教えを持ちつつも、現世での善行や供養を重視するため、大きな徳を積めるとされる施餓鬼も積極的に行われています。
毎年お盆の時期には、大規模な施餓鬼法要が各寺院で開催され、多くの檀家が参加し、先祖や無縁仏、餓鬼への供養を行っているでしょう。
日蓮宗
日蓮宗の施餓鬼法要は、「法華経・お題目の教えにあずかることなく餓鬼道をさまよう霊」に対して救済を願うものです。
法華経を読誦し、お題目(南無妙法蓮華経)を唱え、食べ物や飲み物を施して供養します。
日蓮宗には「川施餓鬼」と呼ばれる独自の風習があり、開祖・日蓮聖人が鵜飼の霊魂を三日三晩かけて成仏させたという伝説に基づき、川辺や水辺での施餓鬼供養が各地で行われています。
浄土真宗
浄土真宗は、他の多くの仏教宗派と異なり、施餓鬼法要を一切行いません。
「亡くなった人はすぐに阿弥陀仏の力で極楽浄土に行く」とされているため、餓鬼や無縁仏という存在自体を認めていないのです。
浄土真宗の寺院や信者の間では、施餓鬼に関する行事や供養は行われず、代わりに念仏や追悼法要を通じて故人を偲びます。
【関連記事】
浄土真宗の初盆の迎え方は?お布施相場やお供え物・仏壇の飾り方など解説
施餓鬼に行かないのはあり?
施餓鬼法要に参列するかどうかは、個人の自由であり、参加は強制ではありません。
しかし、先祖供養という観点からは可能な限り参列することが望ましいでしょう。
参列できない場合も、何らかの形で供養の気持ちを表すことで、先祖とのつながりを維持することができます。
お寺や家族と相談しながら、自分にとって最適な方法を見つけると良いでしょう。
施餓鬼で事前に用意するもの
施餓鬼法要に参加する際には、準備しておきたいものがいくつかあります。
特に初めての場合、何を用意すればよいのか迷うこともあるでしょう。
ここでは代表的な事前準備品について解説します。
地域によっても異なる場合があるため、迷ったときは菩提寺に相談すると安心です。
卒塔婆(そとば)
卒塔婆(そとば)は、施餓鬼法要で最も一般的に用いられる供養具の1つです。
細長い木の板に戒名(法名)や俗名を書き、供養の対象となる方の魂が成仏できるよう祈りを込めます。
卒塔婆は通常、菩提寺で注文します。
法要の1週間から10日前には注文し、当日または後日お墓に立てに行きましょう。
施餓鬼旗(せがきばた)
餓鬼を供養するため、五色の布で作られた施餓鬼旗を準備することもあります。
法要後はお墓に供えるか、仏壇に飾り、お盆が終わると送り火と一緒に焚いたり、お寺でお焚き上げしてもらったりすると良いでしょう。
五色の色には、それぞれ以下のような意味があります。
【色の意味】
| 緑色 |
【妙色身如来(みょうしきしんにょらい)】 美しい身体と健康を与える仏様 |
| 黄色 |
【過去宝勝如来(かこほうしょうにょらい)】 別名「多宝如来」と言い、餓鬼世界で苦しむ人々を救済する仏様 |
| 赤色 |
【甘露王如来(かんろおうにょらい)】 煩悩を消し、心身を穏やかにする仏様 |
| 白色 |
【廣博身如来(こうはくしんにょらい)】 餓鬼の狭い喉を広げ、食事の楽しさ・美味さを与える仏様 |
| 紫(青)色 |
【離怖畏如来(りふいにょらい)】 慈悲の心で恐怖や苦痛を取り除く仏様 |
お布施
お布施は、施餓鬼法要を執り行う僧侶やお寺に気持ちを表す大切なものです。
金額には決まりがありませんが、相場は3,000円~1万円程度で良いでしょう。
卒塔婆や施餓鬼旗をお願いする場合は別途の費用が加算されることもあります。
お布施については、のちほど詳しく解説しますので参考にしてください。
水の子
鬼の喉を潤すための供え物で、賽の目に切ったキュウリ・ナスと洗った生米を混ぜ、蓮の葉の上に盛ります。
葉が入手困難な場合は、皿に直接盛っても問題ありません。
餓鬼道の霊は、喉が針のように細く、普通の食べ物が摂取できないとされているため、細かく刻んだ野菜と水気のある米で飢えや渇きを癒しましょう。
施餓鬼米(遠州地方)
遠州地方(静岡県西部)特有の風習で、玄米や白米を小袋に詰めた、施餓鬼米を寺院に納めます。
これは、故人があの世で食べ物に困らないようにとの気持ちを込めて準備されたもので、他の地域ではあまり見られない風習です。
他にも地域によって独自のお供え物がある場合があるため、その土地の風習に合わせて準備すると良いでしょう。
施餓鬼の流れ
施餓鬼法要には、お寺で行う場合と自宅で行う場合があります。
どちらの場合も、基本的な流れは似ていますが、場所によって異なる点もあるので注意が必要です。
ここでは、それぞれの場合の流れについて説明するので、参考にしてください。
お寺で施餓鬼をする場合
お寺で施餓鬼法要に参加する場合は、以下のような流れです。
【流れ】
| 1.「施餓鬼法要」を申し込んだ後、依頼した日時にお寺へ向かう |
| 2.受付を済ませてお布施・お供え物・卒塔婆料を渡す |
| 3.会食が行われる |
| 4.僧侶による法話・読経・焼香が行われる |
| 5.卒塔婆・施餓鬼旗の受取後、お墓参りに行く |
| 6.親族に返礼品を渡して解散 |
自宅で施餓鬼をする場合
自宅で施餓鬼を行う場合は、僧侶を自宅に招いて法要を行います。
この場合の流れは以下の形です。
お布施を渡す頃合いに決まりはありませんが、渡し忘れがないよう、あらかじめタイミングを決めておいた方が良いでしょう。
【流れ】
| 1,自宅で「施餓鬼法要」ができるかお寺に確認し、依頼日時を伝える |
| 2.自宅に来た僧侶や親族にお茶出しをし、僧侶にお布施・卒塔婆料を渡す |
| 3.僧侶による法話・読経・焼香が行われる |
| 4.卒塔婆・施餓鬼旗の受取後、お墓参りに行く |
| 5.お墓参りの後、会食を振る舞う |
| 6.親族に返礼品を渡して解散 |
施餓鬼を行う時のマナー
施餓鬼法要は先祖や亡くなった方々を供養する大切な仏事です。
参列する際には、適切なマナーを心得ておくと安心でしょう。
ここでは、施餓鬼法要に参加する際に知っておきたい基本的なマナーについて解説します。
参列時の服装
施餓鬼法要に参列する際の服装は、基本的に喪服ほど厳格である必要はありません。
平服で良いとされていますが、清潔感のある落ち着いた服装が望ましいです。
男性の場合は、ダークスーツに白いワイシャツ、黒または濃紺のネクタイなどを着用し、カジュアルな服装は避け清潔感のあるフォーマルな装いを心がけましょう。
女性の場合は、黒や紺、グレーなどの落ち着いた色のワンピースやスーツが適しています。
露出の多い服装や派手な色、アクセサリーは控えめにするのがマナーです。
僧侶への挨拶
施餓鬼の際には、僧侶や寺院関係者への挨拶も重要なマナーです。
読経や法要を務めてくださる僧侶には、法要前や終了後に「本日はよろしくお願いいたします」「どうもありがとうございました」など、丁寧な言葉であいさつを伝えましょう。
受付や案内を担当している方にも「お世話になります」と一声かけることで、周囲との和やかな雰囲気を作ることができます。
あいさつのタイミングや内容は特別難しくありませんが、感謝と敬意の心を持って接することが大切です。
お布施・数珠を忘れない
施餓鬼法要に参列する際は、お布施と数珠を忘れないようにしましょう。
お布施は、法要を営んでくださる僧侶への感謝の気持ちを表すものです。
また、法要中は手に数珠を持ち、読経の際や焼香の際に使用します。
万一忘れてしまった場合は、寺院で貸していただけることもありますが、事前に自分専用の数珠を持参すると丁寧な印象になるので、準備しておくと良いでしょう。
【関連記事】
葬儀に使う数珠の持ち方は?必要ある?色の決まりはあるか・どこで買うかを紹介
お布施とは?金額の相場やお金の入れ方・渡し方のマナーを徹底解説
施餓鬼のお布施のマナー|書き方や相場
施餓鬼法要に参列する際、お布施は欠かせないものです。
お布施は僧侶への感謝の気持ちを表すとともに、ご先祖様や亡くなった方々への供養の一部としても大切な意味を持っています。
ここでは、施餓鬼法要でのお布施の相場や書き方、包み方などのマナーについて解説します。
お布施の相場
施餓鬼法要のお布施の金額は、明確な決まりはありませんが、一般的には3,000円~1万円程度が相場とされています。
さらに、卒塔婆を用意する場合には3,000円~1万円、自宅で法要する場合には5,000円〜1万円、盂蘭盆会と一緒にする場合にも5,000円〜1万円ほど追加で用意しておくと良いでしょう。
住んでいる地域や宗派によっても相場が異なる場合があるため、迷った場合は寺院に直接問い合わせるか、地域の古くからの習慣に詳しい方に相談すると安心です。
【関連記事】
お布施が少ないと言われたらどうしたらいい?金額相場・マナーについても解説
お布施の書き方
お布施の封筒には、正しい表書きや名前の書き方のマナーがあります。
表面には「御布施」「お布施」「御施餓鬼料」のいずれかを、中央に大きく毛筆または筆ペンで書きましょう。
寺院や宗派によって好まれる表書きが異なります。
心配な場合は、事前に寺院に確認すると良いでしょう。
下段には施主(自分や家族の代表者)の名前を、フルネームか「○○家」で記入します。
裏面には住所・電話番号・旧字体で金額(例:金参仟圓也)を書くのが一般的です。
お布施の包み方
正式には奉書紙(ほうしょがみ)で包みますが、白無地の封筒でも問題ありません。
包むお札は、できれば新札が望ましいです。
お札の肖像画が、表書き側に向くように揃えて入れましょう。
渡す際は袱紗(ふくさ)に包み、法要前後の挨拶時に僧侶へ手渡します。
大規模な法要の際には、受付で現金を直接渡す寺院もあるため、事前に確認しましょう。
施餓鬼とは餓鬼道に堕ちた者を供養する法要。お盆と同じく大切な風習
施餓鬼法要はご先祖様だけでなく、この世に苦しむすべての存在に感謝と施しの心を届ける機会です。
家族で心を合わせ地域社会とのつながりを持てる大切な風習として、お盆と同じように継承していきましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要