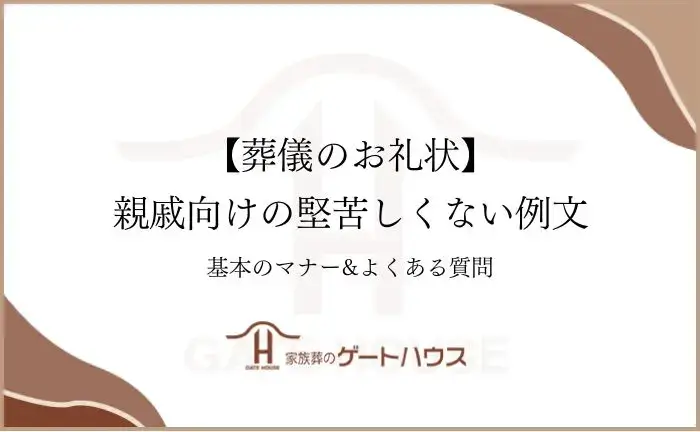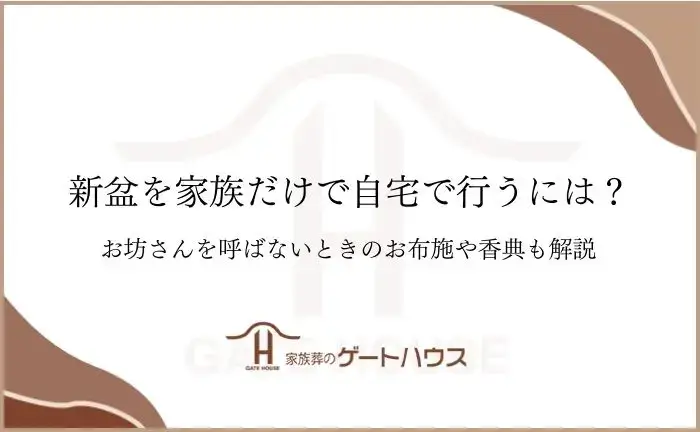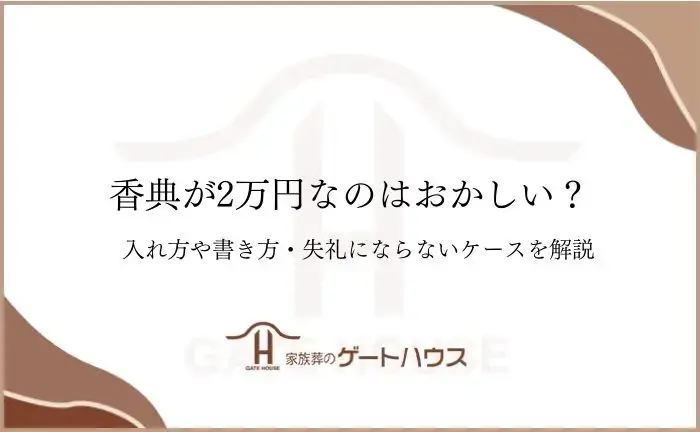お清めの塩の使い方とは?しないとどうなる?意味やない場合の対処法も解説
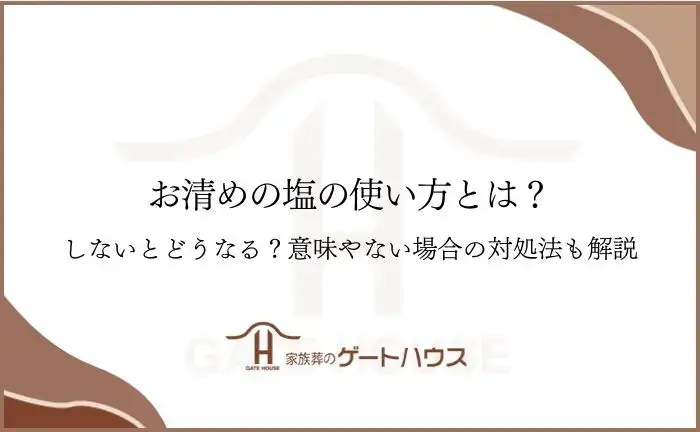
お清めの塩とは?しないとどうなる?
葬式や通夜の参列者に、返礼品と一緒にお清めの塩を渡されることがありますが、どのような目的があるのでしょうか。 はじめに、お清めの塩の意味や由来と、お清めをしないと問題があるのかどうかを解説します。お清めの塩の意味・由来
葬儀会場で渡されるお清めの塩は、自宅に入る前に「穢れ(けがれ)」を祓うために使うものです。 昔から日本では神道の考え方により、死は穢れとされてきました。 そして葬儀に参列した人は、他の場所に穢れを持ちこまないように、浄化の力を持つ塩で穢れを祓う習慣ができたのです。 葬儀会場で参列者に塩が渡されるようになったのも、その習慣によるものです。 大きな葬儀場では、出口にお清めの塩が用意され、踏んで外に出るところもあります。お清めの塩をしないとどうなる?
お清めの塩に関しては、宗教や地域の習慣、家族の考え方などによりさまざまな解釈がされていて、絶対的なものではありません。 そのため、お清めの塩を葬儀場で渡されても、実際に使うか使わないかは自分次第だと言えるでしょう。 お清めの塩が不要な葬儀については、別の章で詳しく説明します。お清めの塩の使い方|火葬場から葬儀場へ戻った時
お清めの塩を使うタイミングは、火葬場から葬儀場へ戻った時と、葬儀場から自宅に帰った時です。 それぞれの使い方やマナーについて、正しい知識を身につけておきましょう。 まず、火葬場から葬儀場へ戻った時に行う、お清めの塩の使い方を紹介します。用意された塩で手を清める
火葬場から葬儀場へ戻った時に、お清めセットが用意されていた場合は、それを使ってお清めをします。 まず、両手の手のひらにお清めの塩をかけて、手を清めます。 お清めの塩を使わない宗教や宗派の場合は、塩ではなくおしぼりなどを渡される場合もあるでしょう。桶に入った水を柄杓で掬って手を洗う
お清めの塩で手を清めた後は、桶に入っている水を柄杓で掬って、両手を洗い流してから葬儀場に戻ります。 ただし、宗教や地域、習慣などによってお清めの手順や方法が異なる場合があるため、葬儀会社やお寺の指示に従うようにしましょう。お清めの塩の使い方|葬儀場から自宅に帰った時
次は、葬儀場から自宅に帰った時の、お清めの塩の使い方を説明します。 帰りの車に乗る前や、家に入る前に玄関の前で使うのも一般的です。 住まいがマンションでドアの前を汚したくない場合は、共有部分に入る前に行うといいでしょう。手を洗う
正式なお清めの方法ではお清めの塩を使う前に、まず手を洗います。 ただ玄関に入る前に手を洗うのは難しいため、省略されることが多いかもしれません。 手を洗えない場合は、家の中にいる家族に頼んで水を持ってきてもらうといいでしょう。胸・背中・肩・足元の順に塩をかける
次に、体にお清めの塩をかけます。 塩は、邪気が血と共に体内を巡らさないために、血液が流れる順番にかけるのがいいとされています。 胸→背中→肩→足元の順にかけ、自分でかけるのが難しいところは、家族にかけてもらいましょう。 お清めが済んだ後は、かけた塩をきれいに払い落としてから家に入ります。 塩が残っていると、穢れを家に持ち込むことになるので、念入りに落としましょう。床や地面に落ちた塩を踏んでから玄関に入る
お清めの塩を払い落とした後は、地面に落ちた塩を踏んでから玄関に入ります。 落ちた塩を踏むことで、完全に穢れを断ち切れると言われているからです。 意識的に踏まなくても、お清めや払い落とす工程の間に踏んでいることも多いでしょう。 ここまでお清めが済んだら、玄関に入っても大丈夫です。お清めの塩が必要ない場合
以前は、葬儀場で参列者にお清めの塩を渡すところが多かったのですが、近年は必要ないケースを考慮して、渡さないことも増えてきました。 続いては、お清めの塩が必要ないとされる葬儀に、どんな種類があるのかを紹介します。神道以外の葬儀の場合
神道以外の葬儀では、基本的にお清めの塩は必要ありません。 神道では死を穢れとする考え方があり、葬儀の参列者が自宅に穢れを持ち帰らないように、お清めの塩を使います。 しかし仏教やキリスト教など他の宗教では、死を穢れとしていないので、原則としてお清めは不要です。 近ごろは、お清めの塩を廃止している葬儀場もあります。 ただし、日本では昔から葬儀の後にお清めの塩を使う習慣があるため、慣習的にお清めの塩が使われることも少なくありません。 【関連記事】 神式の葬儀“神葬祭”の流れとは?通夜や告別式のマナー・作法も解説浄土真宗での葬儀の場合
穢れの概念がない仏教の葬儀でも、慣習に合わせてお清めの塩を使う場合があるでしょう。 しかし浄土真宗の葬儀だと、お清めの塩は不要とされています。 浄土真宗は死や葬儀、火葬場などは穢れでないため、お清めをするべきでないという考えの宗派です。 また、お清めの塩は故人に対して失礼に当たるとして、塩を禁止しています。 そのため浄土真宗の葬儀は、返礼品にお清めの塩が入っていなかったり、使わない理由を説明する手紙が入っていたりするでしょう。 ただし、参列者の宗派や気持ちを尊重し、お清めの塩を渡す場合もあります。 【関連記事】 浄土真宗の葬儀の流れは?お布施の相場や本願寺派・大谷派別に葬式の順序を解説無宗教葬の場合
無宗教の葬儀の場合は、原則としてお清めの塩は不要です。 葬儀後にお清めの塩で穢れを祓う慣習は、宗教に基づいたものだからです。 ただし、どのような葬儀をするのかは、あくまで喪主や遺族の考え方によります。 そのため、無宗教の葬儀でもお清めの塩を使う場合もあるでしょう。 お清めの塩を使ったり、返礼品として渡したりしても、マナー違反ではありません。身内の葬儀の場合
一般的に、身内の葬儀の場合だと、お清めの塩は必要ないとされています。 遺族にとって身近な人の葬儀を、穢れと考えるのは気分的にもよくないためです。 しかし、葬儀についてのルールを決めるのは喪主や遺族。 そのため、身内の葬儀でもお清めするべきと考えたなら、お清めの塩を使うこともあります。 その際にお清めの塩を用意したり使ったりしても、マナー違反とはなりません。お清めの塩に関するよくある質問
お清めの塩に関して「ない時はどうしたらいいのか」「余った場合はどう処分するべきか」など、疑問に思うこともあるでしょう。 最後は、お清めの塩に関するよくある質問を紹介します。お清めの塩は何でもいいの?ない場合は?
葬儀でお清めの塩をもらわなかった場合は、自分で用意した食塩を使ってお清めをしても問題ありません。 どんな塩でもいいのですが、日本神話に基づくなら原材料が海水100パーセントの塩がおすすめです。 家に入る前に使う必要があるため、家族に玄関まで持ってきてもらうか、葬儀の帰りにコンビニなどで購入しましょう。 インターネットなどで、あらかじめお清めの塩を購入できますので、葬儀の後に必ずお清めをしたいと思う場合は、事前に準備しておくといいでしょう。お清めの塩を使うのを忘れてしまったらどうすればいい?
お清めの塩を使うのを忘れて家に入った場合は、もう一度玄関の外に出てお清めをすれば大丈夫です。 お清めの塩はあくまで慣習的なものであり、死を穢れとする神道以外の葬儀では必要ないものなので、あまり深刻に考えなくてもいいでしょう。 既に着替えたのならもう一度、喪服を着用してお清めをするのが正式なマナーです。お清めの塩は食べてもいい?
塩を使わなかったり残したりしても、残った塩は食べないようにしましょう。 お清めの塩には乾燥剤が入っていることもあるため、食用としては不向きです。 また、塩によってはパッケージに「非食用」と記載されている場合もあります。 お清めの塩を使う際には、残さないで全て使い切るようにしましょう。 もし残った場合は、次に説明する方法で処分して、誤って口にしないよう注意しましょう。お清めの塩が余ったらどうする?処分方法は?
お清めの塩が余った場合は、お住まいの自治体のルールに従って通常の可燃ごみとして処分しましょう。 罰が当たるようで心配かもしれませんが、役目を果たした物なので捨てても構いません。 ゴミとして捨てるのが気になる場合は、懐紙などでくるんで捨てたり、キッチンやトイレに流したりしてもいいでしょう。 乾燥剤が入っている場合もあるため、庭に撒くことやバスソルトなどで再利用するのはおすすめしません。お清めの塩には正しい使い方がある。手順やマナーを知って慌てないようにしよう
お清めの塩は、葬儀の後に穢れを祓うため、塩でお清めをする習慣からできたものです。 死を穢れとする神道の教えに基づいた習慣なので、必要ないと思えば使わなくても問題ありません。 塩を使うのは、火葬場から葬儀場に戻った時と、葬儀場から自宅に戻った時なので、お清めの正しい手順や使い方をチェックしておきましょう。 塩が不要な葬儀もありますが、使ってもマナー違反にはなりません。 お清めの塩の正しい使い方や扱い方を理解して、いざという時に慌てないようにしておきましょう。葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要