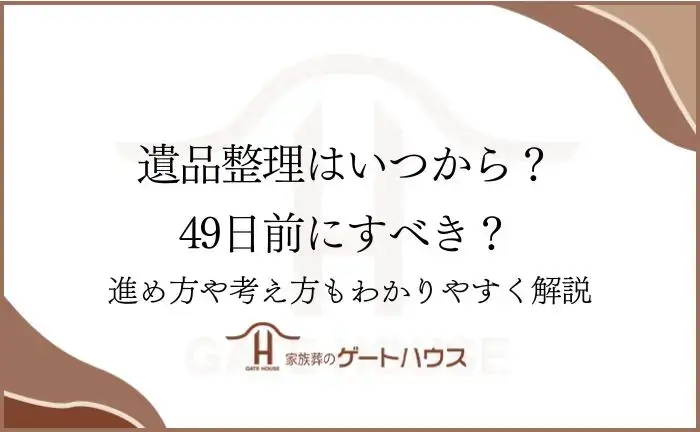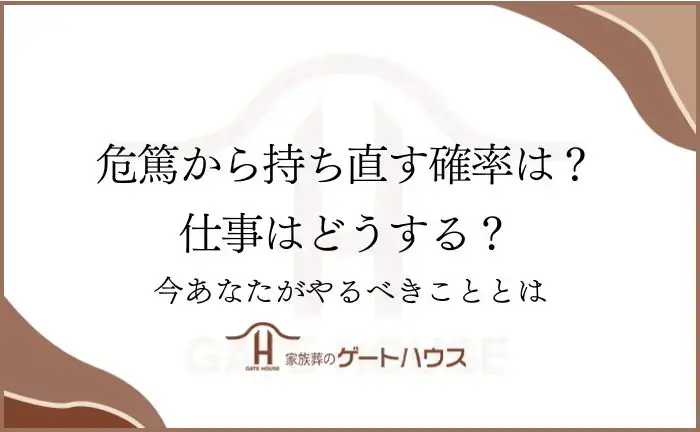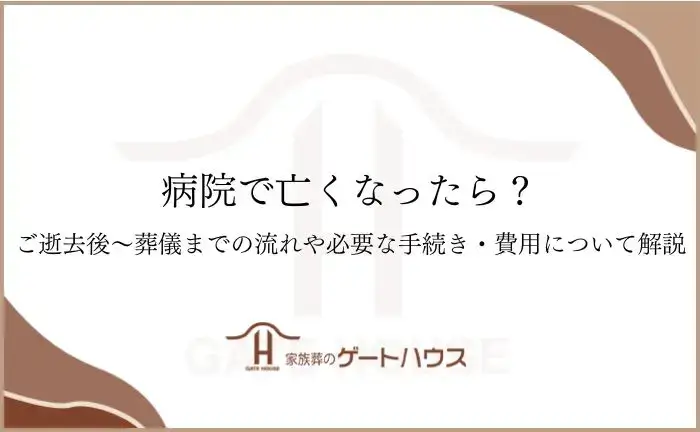寝ずの番の過ごし方とは?寝てしまった場合の対処法や注意点も解説
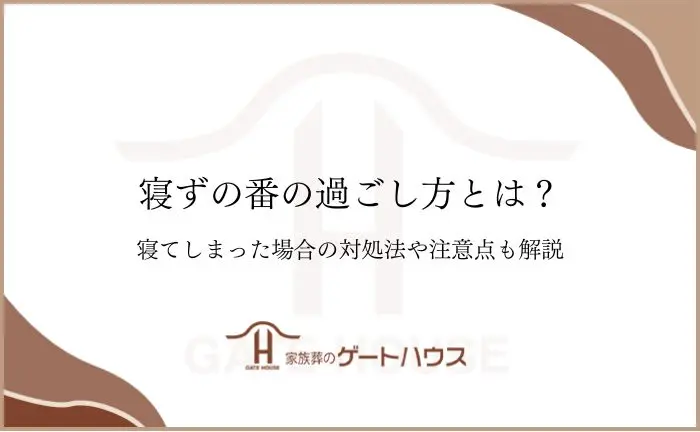
日本のお葬式において「寝ずの番」という役割があることをご存知ですか?
言葉を耳にしたことがあっても、誰が何をするのかまで詳しく知らない人も多いかもしれません。
そこで、この記事では「寝ずの番」とは何か、やり方や注意点など詳しく解説します。
寝ずの番とは何をする人?なぜ行うようになった?
「寝ずの番」とは遺族が夜通しでご遺体を見守り、線香やろうそくの火が消えないように灯し続けることです。
元々は本当に亡くなっているかを確認するために行われていました。
昔は、現代ほど医療が発達していません。
そのため、臨終を告げられても亡くなっていない可能性があったため、息を吹き返さないかを夜通し見守ることで確かめていたのです。
また、故人に悪霊を寄せ付けず、安心してあの世へと旅立てるようにする意味が込められています
ちなみに、この「夜通し」が「通夜」という言葉の由来になったとも言われています。
【関連記事】
寝ずの番の過ごし方とは?寝てしまった場合の対処法や注意点も解説
寝ずの番は誰がやるのが一般的?
基本的に寝ずの番は遺族が行います。
誰が務めるかに明確な決まりがないものの、故人の遺族や親族が行うのが一般的です。
他にも、故人と特別に親しくしていた友人や知人が行うケースもあります。
また、寝ずの番を行う人数に決まりはないため、家族全員で行ったり、子供や孫たちで集まったりするケースも少なくありません。
寝ずの番は交代制で行うことが最もおすすめ
前述の通り、寝ずの番を行う人数に決まりはなく、交代で行っても問題はありません。
葬儀の準備や身内を亡くしたことで疲れている可能性が高いため、体調を考えると順番にゆっくり休める交代制で行うのが良いでしょう。
どのタイミングで交代するか、またはどの時間を担当するかは、あらかじめ決めておくとスムーズです。
寝ずの番に参加を希望する人同士で、事前に話し合っておきましょう。
最近は寝ずの番をしないご家庭が増えている
自宅葬が主流だった時代は寝ずの番が当たり前でしたが、近年は葬儀場で行うことが多く、寝ずの番をしない家庭も増えています。
家族葬の場合は、その日の内に通夜を終わらせる「半通夜」で済ますことも多く、そもそも寝ずの番を行うタイミングがありません。
ただ、葬儀場によっては寝ずの番を行うための設備が完備されています。
地域によっては寝ずの番が伝統として残っていることもあり、この場合はお葬式の規模や場所に関係なく行われることが多いです。
寝ずの番のやり方・過ごし方
続いては寝ずの番の具体的なやり方や、当日の過ごし方について解説します。
内容を把握しておき、万が一寝ずの番を任されたときに慌てず対応できるようにしましょう。
故人と朝まで一緒に過ごす
寝ずの番では、故人との最期のときをゆっくりと過ごしましょう。
寝ずの番を単独で行う場合は故人との思い出に浸る、または感謝の気持ちを伝えるのがおすすめです。
親族や知人と数名で行う場合は、生前の故人について語り合い別れを偲ぶのが良いでしょう。
ただ、賑やかに過ごしたり騒いだりするのはマナー違反にあたるため、注意が必要です。
なるべくしめやかに過ごしてください。
線香とろうそくの火を絶やさないようにする
寝ずの番では祭壇の線香やろうそくに火を灯し、それらが消えないように見守ります。
複数の線香・ろうそくを使用すると煙が増え、故人があの世に行く途中に迷うとされているため、使用するのは原則としてそれぞれ一本のみです。
短くなってきたら新しい線香・ろうそくに火を移し替え、一晩明かりを灯し続けましょう。
もし火が消えてしまった場合は、慌てずに改めて火をつければ大丈夫です。
最近はろうそく型のライトを代用することも増えているため、くれぐれも負担のない範囲で行いましょう。
寝ずの番をしていて寝てしまったとしても大丈夫
寝ずの番の途中で寝てしまったとしても、問題はありません。
むしろ睡眠不足で体調を崩せば、故人も悲しんでしまうかもしれません。
火を灯し続けることも大切ですが、それよりもしっかりと休息を取り、体調を気遣うことが重要です。
時間を区切って交代したり、ライト型のろうそくを代用したりして、家族・親族がゆっくりと休める環境を作るように心がけてください。
寝ずの番を行うときの持ち物・あると便利な物
寝ずの番は夜通し行うため、以下のアイテムがあると便利です。
- 就寝用の衣服
- アイマスク
- 歯ブラシや洗顔などのアメニティー
寝ずの番に服装の決まりはありません。
長時間に渡ることや途中で就寝することを考えると、喪服の他にリラックスして着用できる衣服を持参すると良いでしょう。
また、夜通し火が灯っているため、明るさが気になる場合はアイマスクを持参するとゆっくりと休息をとれます。
寝ずの番を自宅で行う場合は必要ありませんが、斎場で行う場合は歯ブラシや洗顔、タオルなどのアメニティーを持参しておくと安心です。
寝ずの番を行うときの注意点やマナー
寝ずの番は故人と最期のときを過ごすことに意味がありますが、守るべきマナーもあります。
故人を穏やかな気持ちで見送れるように、次の注意点・マナーは必ず守りましょう。
服装はリラックスできるものでOK
前述の通り、寝ずの番を行うときの服装にルールはありません。
喪服でなくても問題なく、むしろゆったりと過ごせるようなリラックスウェアでOKです。
ただ、派手な色や柄の衣服は避けたほうが無難でしょう。
特に親族や知人など数名で寝ずの番を行う場合、中には不快に思う人がいるかもしれません。
黒やグレーなど落ち着いた色、または無地のものなど、できるだけシンプルな衣服を選ぶように心がけましょう。
【関連記事】
葬儀で女性が着るべき服装とは?喪服の種類やお葬式の身だしなみマナーを解説
電気はつけたままにしておく
「故人が安らかに眠るためにも、電気は消したほうが良いのでは?」と思う人もいるかもしれませんが、基本的に電気はつけたままで構いません。
寝ずの番では常に誰かが起きているため、安全面に考慮する意味でも、電気は消さずにつけておいたほうが良いでしょう。
部屋の明かりが気になって寝られない場合は、アイマスクを着用するのがおすすめです。
お線香は1本ずつ供える
寝ずの番では、原則として1本の線香に火を灯し続けます。
「火が消えないように」と複数の線香を供えることは避け、1本の線香が短くなったら別の線香に取り替えるようにしましょう。
また、このときにマッチやライターを使用するのはマナー違反です。
必ずろうそくを利用して線香に火をつけ、反対に火を消すときは息を吹きかけたり手で仰いだりせず、専門の道具を使用しましょう。
無理はせず体調が悪いときは休む
寝ずの番は通夜式の大切な行事の一つですが、それ以上に体調も大切です。
故人を亡くした悲しみが辛いときや、準備で疲れているときは、無理をせずしっかりと休みましょう。
心身ともに疲れ切っている状態に睡眠不足が加わると、翌日の葬儀で体調を崩す可能性が高いです。
どうしても寝ずの番を行いたい場合は誰かに協力してもらい、交代しながら行うと良いでしょう。
棺の中に顔を入れない
棺の中にはご遺体を綺麗に保つために、ドライアイスが入っています。
ドライアイスは氷ではなく二酸化炭素の固体であり、一定の温度になると二酸化炭素へ変わります。
二酸化炭素は低い場所に溜まる特性があり、棺の中は二酸化炭素が充満している可能性が高いため、棺の中に顔を入れることは絶対にやめてください。
中毒症状により体調不良を引き起こしたり、場合によっては死に至ったりする可能性があります。
故人の顔を見るときは必ず一定の距離を取り、定期的に部屋の換気を行いましょう。
寝ずの番が怖いときの対処法
寝ずの番が怖い場合は、複数人で行うのがおすすめです。
自分以外に誰かがいれば安心感が生まれやすく、故人との思い出を語り合ううちに恐怖が和らぐ可能性があります。
どうしても一人で行わなければならない場合は、リラックスできるような音楽をかけたり、お守りを用意したりするのも良いでしょう。
また、温かい飲み物で緊張を和らげたり、恐怖から意識を逸らすために本を読んだりするのもおすすめです。
心身ともに安らぐようなアイテムを用意し、恐怖心が軽減するように工夫しましょう。
寝ずの番は寝てしまっても大丈夫。最近は行わないことが一般的になりつつある
寝ずの番は夜通し行う儀式ですが、仮に寝てしまったとしても問題はありません。
目が覚めたタイミングで火を灯し直し、故人とゆっくり過ごしましょう。
また、近年は寝ずの番を行わないケースが主流になりつつあります。
精神的にも肉体的にも疲れている場合は無理に行わず、休息を取ることを大切にしてください。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要