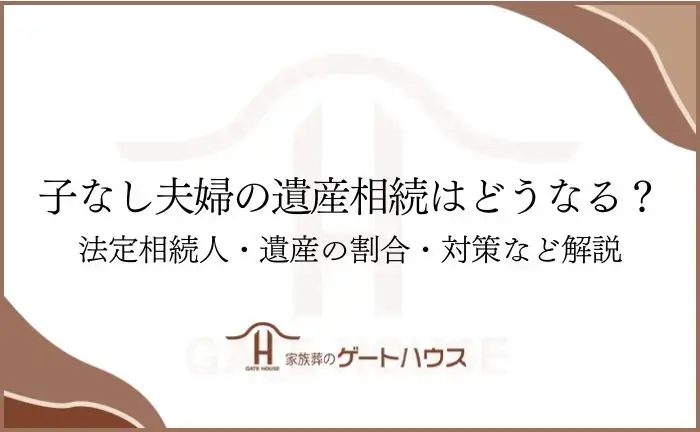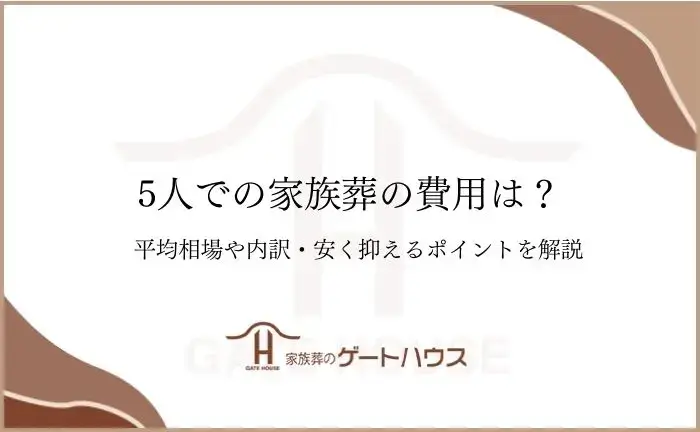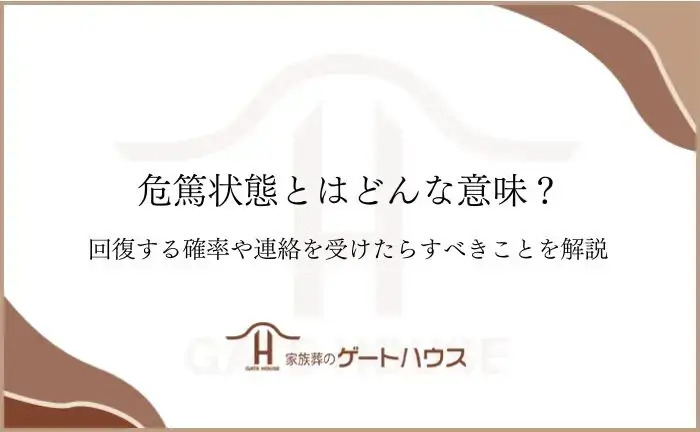実家じまいの費用は?片付け・処分・解体はいくら?補助金や手順も解説
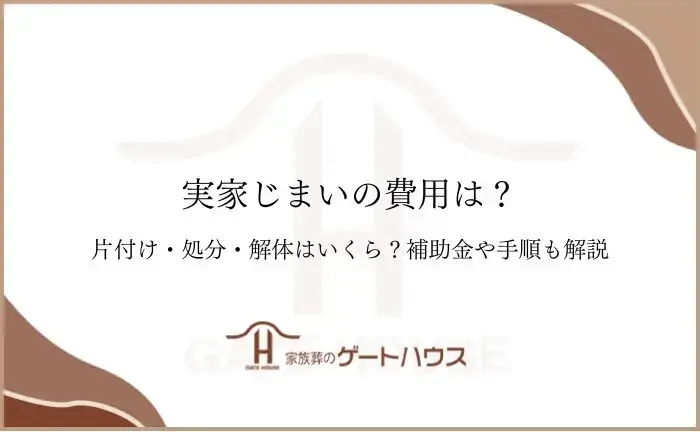
実家じまいを検討する際に「費用はどれくらいかかる?」「具体的な流れが知りたい」と思う人も多いでしょう。
片付けや解体などにかかるコストは、できるだけ抑えたいところです。
この記事では、実家じまいにかかる費用や利用できる補助金などについて解説します。
実家じまいの費用|片付け
実家じまいでは、さまざまな費用がかかります。
何にどれくらいの金額が必要なのか把握しておかないと、途中で予算オーバーになる可能性も。
まずは、実家じまいの片付けにかかる具体的な費用をチェックしてみましょう。
①不用品にかかる費用
【不用品回収費】
| 自分でする場合 | 数千~数万円 |
| 業者に依頼する場合 | 約10~50万円 |
実家じまいの不用品処分にかかる費用は、自分で行う場合は数千~数万円、業者に依頼する場合は10~50万円程度が目安です。
自分で大量の不用品を処分するには、戸別収集を申し込んだり、処分場に持ち込んだりする方法があります。
ゴミ袋や掃除用具など処分に必要な備品の購入や、大型の家具や家電を運ぶためのレンタカー代なども、処分代として費用が発生するでしょう。
不用品回収業者に依頼する場合は、物量や建物の立地条件などによって料金が変動します。
②売却にかかる費用
【売却費】
| 不動産仲介手数料 | 売却価格 × 3% + 6万円 |
| 所有権移転登記 (売買、贈与、交換など) |
固定資産税評価額 × 2.0%(土地) 固定資産税評価額 × 2.0%(建物) |
| 抵当権抹消登記費用 | ・物件1つ|1,000円 ※司法書士に依頼時:約1~2万円 |
実家の売却には不動産売却費用として、主に不動産仲介手数料、所有権移転登記、抵当権抹消登記費用がかかります。
不動産仲介手数料は、不動産の売買や賃貸において、価格交渉や手続きなどの仲介業務に対する報酬として支払うものです。
所有権移転登記は、家の売買や相続などで所有権が変わった際にする手続きで、権利関係を法的に示すために行います。
抵当権抹消登記費用は、売却する実家に住宅ローンが残っているときに発生する費用で、ローンを完済する際に必要です。
参考:国税庁HP「No.7191 登録免許税の税額表」
③売却するときにかかる税金
実家じまいで家を売却するときには、税金もかかります。
主に譲渡所得税、印紙税が必要になるため、予算に含めておくことが大切です。
譲渡所得税と印紙税は、不動産の売却金額によって変動します。
それぞれの税金について、チェックしておきましょう。
譲渡所得税
計算式は「収入金額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除額 = 課税譲渡所得金額」で、売却価格そのものではなく、実際に得た利益(譲渡所得)が課税対象になります。
譲渡費用には仲介手数料やリフォーム費用なども含まれます。
また、要件を満たせば「3,000万円特別控除」などの制度が使えるため、利益が出ていても課税されないケースもあります。
特に実家が築年数の古い住宅や土地であれば、控除の適用により譲渡所得税がかからないことも少なくありません。
参考:国税庁HP「譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」
印紙税
印紙税は、不動産売買契約書に貼り付けて納める税金です。
税額は実家の売却金額によって変動します。
たとえば1,000万円で売却した場合は5,000円、500万円で売却した場合は1,000円の印紙税が必要です。
ただし、この税額には租税特別措置法が適用されており、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成された不動産売買契約書に限られます。
詳しくは、国税庁のホームページを確認してください。
参考:国税庁HP「国税庁HP 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
④解体時にかかる費用
【解体費】
| 鉄筋コンクリート(RC造) 1坪:約5~8万円 |
・30坪|150~240万円 ・40坪|200~320万円 |
| 鉄骨造(S造) 1坪:約5~7万円 |
・30坪|150~210万円 ・40坪|200~280万円 |
| 木造 1坪:約4~5万円 |
・30坪|120~150万円 ・40坪|160~200万円 |
実家じまいで解体する場合は、解体工事費用が必要です。
費用は家の大きさや立地条件、建物の構造などによって変動します。
更地にしたほうが売却しやすいこともありますが、解体費用がかかるほか、固定資産税が高くなる点にも注意してください。
⑤清掃にかかる費用
【清掃費】
| ハウスクリーニング代 | 約6~20万円 |
| 消臭・除菌代 | 約6,000~16万円 |
| 害獣・害虫駆除代 | ・害獣5~25万円(1回) ・害虫1~6万円(1回) |
実家じまいで建物を残して売却したり、賃貸に出したりする場合は、清掃にかかる費用も必要です。
不用品回収業者に依頼する場合は掃除が含まれていないこともあり、その場合は別にハウスクリーニングを依頼しなければなりません。
状況に応じて、消臭・除菌、害獣・害虫駆除も行いましょう。
資産価値を下げないためにも、空き家は適切に管理することが大切です。
⑥相続にかかる費用
【相続費】
| 相続税 | (遺産総額-基礎控除) × 10~55% |
| 相続登記 | 固定資産税評価額 × 0.4%(土地) 固定資産税評価額 × 0.4%(建物) |
親が亡くなって実家を相続する際には、相続税や相続登記にかかる費用が発生します。
相続税は、実家などの不動産に限らず、現金・有価証券・貴金属などのプラスの財産に加え、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産もすべて含めた「遺産総額」から計算されます。
この遺産総額からは、基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)が差し引かれ、この控除額を超えた場合にのみ相続税が課税されます。
また、相続登記とは、土地・建物の不動産登記簿の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きです。
2024年4月からは相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内に申請しなければならなくなりました。
相続登記は、相続人自身が行うこともできますが、一般的には司法書士に依頼して手続きを進めるケースが多いです。
参考:国税庁HP「相続税の税率」
⑦引越しにかかる費用|費用
親が介護付き住宅などに引っ越したり、家族が実家で暮らしたりしている場合は、住み替えに伴い引越し費用が発生します。
引越しにかかる費用は物量や距離だけでなく、繁忙期や閑散期などの時期によっても大きく変動するため注意してください。
実家じまいの費用|解体に関わるもの
【解体費用】
| 鉄筋コンクリート(RC造) 1坪:約5~8万円 |
・30坪|150~240万円 ・40坪|200~320万円 |
| 鉄骨造(S造) 1坪:約5~7万円 |
・30坪|150~210万円 ・40坪|200~280万円 |
| 木造 1坪:約4~5万円 |
・30坪|120~150万円 ・40坪|160~200万円 |
実家じまいの解体費用は、建物の構造によって変動します。
建物の構造以外にも、付帯物や立地などの条件によって追加費用がかかることもあるでしょう。
地中埋設物・アスベストの量で変わる
実家じまいで家を解体する際の費用は、地中埋設物やアスベストの量によっても変わります。
地中埋設物とは、地面に埋まっているコンクリートや浄化槽などのことです。
新しく建物を建てるときの障害物になるため、撤去する必要があり、追加で費用がかかります。
アスベストは建材の一種ですが、健康被害を引き起こす恐れがあり、2006年から使用禁止になりました。
屋根材や外壁材、内装材、断熱材などに使用されている場合は、工事前に撤去することが義務付けられています。
付帯物があると費用がかかる
実家じまいの解体作業では、付帯物があると追加費用が発生します。
付帯物の撤去は手作業で行われるケースが多いため、費用が高額になりやすい傾向があります。
費用は付帯物の種類や量によって費用が変わりますが、敷地内にカーポートやブロック塀、植物や門扉、倉庫などの付帯物がある場合は注意しましょう。
重機が使いにくい立地だと費用が高くなる
重機が使いにくい立地の場合も、費用が高くなる可能性があります。
たとえば前面道路の幅が狭く重機が入れなかったり、重機を駐車できる場所がなかったりすると、手作業が増えるため費用がかさむでしょう。
また、隣接地との距離が近いと騒音や粉塵などにも配慮が必要になるため、工期が延びやすく、人件費や重機の稼働費がかさんでしまいます。
実家じまいの費用|空き家の状態で維持する場合
【維持費】
| ・固定資産税 ・都市計画税 ・火災保険費 |
年間|数万~数十万円 |
| 光熱代 | 年間|数千~数万円 |
| 修繕代 | 数万~数百万 ※工事の内容で変動します |
「費用がかかるなら、実家をそのまま維持しよう」と考える方もいるかもしれません。
しかし空き家の維持にも、固定資産税や保険料、光熱費、修繕費などのコストがかかります。
住んでいない家は劣化が早く、定期的なメンテナンスが必要です。
さらに、放置が続くと「特定空き家」に指定される可能性があり、修繕命令や税優遇の解除、過料(最大50万円)などのリスクもあります。
空き家の維持は意外に負担が大きいため、早めに実家じまいを検討することが大切です。
実家じまいの費用を抑える方法
実家じまいには、多額の費用がかかるケースもあります。
「想像以上にお金が必要になって困る」「少しでも安くする方法は?」と悩む人もいるかもしれません。
ここでは、実家じまいの費用を抑える方法を紹介します。
早めに決断する
実家じまいの費用を抑えるには、早めに決断することが大切です。
長期的に空き家の維持や管理をしていると、経済的な負担が大きくなります。
また、悩んでいるうちに築年数が古くなると、資産価値も低下するでしょう。
自分が生まれ育った実家を処分するのは、大きな決断です。
しかしコストを抑えるのであれば、できるだけ早めに決めましょう。
片付けられる物は自分でする
実家の片付けを自分ですることで、不用品回収や遺品整理業者に依頼する費用を抑えられます。
自分で片付けると時間はかかりますが、1つずつ確認しながら手元に残すか、処分するか判断しながら作業を進められるでしょう。
費用面だけでなく、思い出を振り返りながら、気持ちの整理ができる点もメリットです。
自分で片付けをしつつ、運ぶのが難しい大型の家具家電は専門業者に任せるなど、メリハリをつけながら実家じまいを行いましょう。
繫忙期を避ける
実家じまいをする時期は、繁忙期を避けましょう。
一般的に、引っ越し業者は3月~4月、解体業者は2月~3月、片付け業者は年末年始と3月~4月が繁忙期といわれ、料金が高額になる傾向があります。
実家じまいをはじめる時期に、明確な決まりはありません。
費用を抑えたい場合は、できるだけ繁忙期を避けてスケジュールを組むのがおすすめです。
2社以上から相見積もりをする
実家じまいで業者を利用する場合は、2社以上から見積もりをとるようにしましょう。
不用品回収業者や解体業者、引越し業者などに依頼する際は、相見積もりをすることで価格やサービス内容の比較検討ができます。
また買取業者も複数社で見積もりをとると、より高値で買い取ってくれる業者を選べるので、買取額を実家じまいの費用に充てることも可能です。
依頼するときは、最初に相見積もりを依頼していると伝えると、話がスムーズでしょう。
補助金を利用する
実家が空き家になっている場合は、補助金を利用できるかもしれません。
近年空き家問題が深刻化しており、自治体によっては解体費や修繕費などを補助する制度を整備しています。
補助金の内容や対象となる条件、上限金額などは自治体ごとに異なるため、補助金の利用を検討している人は、空き家がある自治体の窓口に相談してみましょう。
実家じまいの費用に関する注意点
実家じまいでは、費用に関して気をつけたいポイントがあります。
知っているのと知らないのでは、最終的な支払額に大きな差が出る可能性も。
「知らずに損した」「もっと早く知りたかった」ということがないように、事前に確認しておきましょう。
契約書がないと譲渡所得税が高くなる
| 長期譲渡所得(5年以上) | 税率:20% |
| 短期譲渡所得(5年以下) | 税率:39% |
※取得費:購入時にかかった費用
※譲渡所得額:購入時より高く売れた時の利益
参考:国税庁HP「土地や建物を売ったとき」
実家じまいの際に契約書がないと、譲渡所得税が高くなる点に注意してください。
譲渡所得税は、譲渡所得額(購入時より高く売却したときに出る利益)にかかる税金です。
不動産を購入したときの契約書や領収書などの証明書類がなければ、購入時にかかった取得費が5%しか認められません。
つまり、売却価格の95%に課税されてしまうのです。
証明書類があれば、不動産の所有期間が5年以上で20%、5年以下で39%の課税になります。
税額の差が大きくなるため、契約書などの証明書類は大切に保管しておきましょう。
相続税が高くなる恐れがある
実家じまいで相続する遺産の中に不動産がある場合は、タイミングを誤ると相続税が高くなる可能性があるので注意しましょう。
相続する不動産の価値は「評価額」といい、国税庁が定める基準「相続税路線価」によって算出されます。
評価額は、売却値の約8割程度に設定されることが多いです。
相続税路線価で計算する前に不動産を売却し現金化して相続すると、売却時の価格が相続税の対象となります。
そうすると、相続財産の総額が高くなり、基礎控除額を超えて相続税が高額になる可能性があるのです。
実家じまいの費用が高くなるかもしれないので、不動産売却のタイミングは慎重に判断してください。
参考:国税庁HP「財産評価基準書」
空き家だと特例で3,000万円の控除がある
【特例を受ける条件】
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されている
- 区分所有建物登記がされていない建物(例:マンション)
- 相続日から3年後の12月31日までに売却している
- 売却価格が1億円以下である
実家が空き家の場合は、特例で3,000万円の控除が適用される可能性があります。
特例の対象となる空き家は、相続する直前まで被相続人(亡くなった人)が住んでいた物件、老人ホームなどの施設に入居してから賃貸に利用していない物件などです。
これらの物件で、かつ上記の条件を満たしていれば、譲渡所得から最大3,000万円が控除されるかもしれません。
実家じまいにかかる費用が大きく変わるので、対象に該当するか確認してみましょう。
参考:国税庁HP「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
実家じまいの補助金には何がある?
新耐震基準を満たしていない老朽化が進んだ建物は、地震による倒壊の恐れがあるため、解体費用に対して補助金が出ることがあります。
自治体によって名称や補助額などは違いますが、実家じまいで利用できる補助金制度を確認してみましょう。
建て替え建設費補助金
実家を解体して、新しく建て替える場合は「建て替え建設費補助金」が利用できる可能性があります。
この補助金は、古い家屋を解体して、一定基準を満たす住宅を新たに建築する際に適用されるものです。
良質な住宅や賃貸部分を含むなどの条件がありますが、クリアしていれば解体費用と建築費用の一部が支給されます。
条件や申請手続きなどの詳細は、自治体に問い合わせてみましょう。
空き家解体撤去助成金
老朽による危険性がない一般的な空き家には「空き家解体撤去助成金」が適用されることがあります。
近年、日本の空き家問題は深刻化しており、空き家数は1993年から2023年までの間に約2倍に増加しています。
空き家を放置すると、草木が生い茂って近所迷惑になったり、不法侵入や放火、不法投棄など犯罪の温床になったりする危険性も。
そこで改正された「空家等対策の推進に関する特別措置法」に伴い、空き家の活用が進まない原因になっている解体費用に対して、助成金がおりるようになりました。
老朽危険家屋解体撤去補助金
老朽化によって倒壊のリスクが高まっている空き家を解体する場合は「老朽危険家屋解体撤去補助金」が使えるでしょう。
地域社会の安全性を向上させるために、老朽化した空き家の早期解体を推奨するための助成金で、自治体による現地調査で解体が必要と判断された場合に適用されます。
自治体によって基準や上限額は異なりますが、解体にかかる費用は100万円を目安に1/5から1/2程度が補助されるケースが多いようです。
ただし、申請者の所得制限が設けられている可能性もあるので、詳しくは自治体に確認してみてください。
都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金
実家じまいで使える「都市景観形成地域老朽空き家解体事業補助金」は、街の景観を守るために交付される補助金です。
住宅街や観光地に放置された空き家があると、景観を損ねるだけでなく、安全面が問題になる可能性もあります。
解体後に景観形成基準を満たす土地利用計画を提示することで、解体費用の1/5から1/2程度が補助される自治体が多いようです。
実家じまいの手順・流れ
実家じまいにかかる費用の目安が分かったら、手順や流れについても確認しておきましょう。
実際は多少前後するかもしれませんが、以下の内容を参考にすることでスムーズに進められるはずですよ。
家族でしっかり話し合う
実家じまいをするときに、まずは家族でしっかり話し合うことが大切です。
親が存命であれば、親が納得した上で進めてください。
実家じまいは心理的負担も大きいため、家族の中に反対している人がいるにも関わらず強引に推し進めるのはやめましょう。
わだかまりが残ると、後々の相続でトラブルに発展する可能性もあります。
家族全員が納得できるまで話し合いを重ね、準備を進めるのが理想です。
親の引っ越し先を決める
実家に親が住んでいる場合は、引っ越し先を決めます。
子どもと同居するのか、高齢者向け住宅や老人ホームなどの施設へ入居するかなど、親の気持ちを尊重しながら家族で話し合いましょう。
おそらく親は、この引っ越し先で人生の最期を迎えることになるため、最後まで安心して暮らせる環境を整えることが大切です。
不用品の回収・片づけをする
実家じまいでは最終的に家の中を空にするので、不用品の回収や片づけを行います。
親が存命の場合は、引っ越し先に持っていく荷物を整理して、不要なものは処分しましょう。
親の生前整理として片づけを手伝うと、スムーズに進むかもしれません。
すでに亡くなっていて遺品整理をする場合は、貴重品や形見として残したいもの、処分するもの、買取に出すものなどを仕分けしながら行います。
遺品整理には時間・労力・気力が必要なので、業者に依頼するのも選択肢の1つです。
実家をどうするか決める
実家じまいでは、最終的に実家をどうするか決める必要があります。
具体的な処分方法としては、解体、売却、賃貸に出すことが考えられるでしょう。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、家族で話し合って納得できる方法を選んでください。
悩んだときは、不動産会社などの専門家に相談するのもおすすめです。
解体する
実家じまいで解体すると、空き家のメンテナンスが不要になります。
維持にかかる費用を節約できるだけでなく、空き家の管理に通う手間も省けるでしょう。
また、土地だけの方が売却しやすいというメリットもあります。
ただし解体には費用がかかり、100万円単位の出費になるケースも珍しくありません。
建物が建っている土地の固定資産税は最大1/6になる軽減措置が適用されますが、更地にすると適用外となり、税金の負担が大きくなる点にも注意が必要です。
売却する
実家を建物付きのまま売却すると、ある程度まとまった金額が手に入ります。
親が存命であれば介護費用などに充てられるほか、現金化することで相続の際、スムーズに遺産分割を進められるでしょう。
現状で売却できれば、リフォームや修繕にかかる費用も抑えられます。
しかし、売却価格は低くなる可能性があり、立地や状態によっては買い手がつかないこともあるでしょう。
賃貸にする
実家じまいで空き家を賃貸にすると、定期的な家賃収入が得られます。
売却ではなく賃貸に出すことで、将来的に住むという選択肢も考えられるでしょう。
ただし、入居者がいなければ収入は得られません。
借り手の満足度を高めるには、事前のリフォームやクリーニングなどが必要になるため、準備や維持管理の手間がかかるでしょう。
【関連記事】
親が亡くなる前にしておくこととは?やることチェックリストで手続きを解説
50代から終活を始めるべき理由とは?老後に向けたやるべきことリストも公開
実家じまいにかかる費用は片付けや解体。早めに決断することが大切
実家じまいには、片付けや解体などに費用がかかります。
空き家を維持管理するにもお金がかかるので、コストを抑えたいのであれば、早めに決断することが大切です。
家族でよく話し合い、後悔のない実家じまいをしましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要