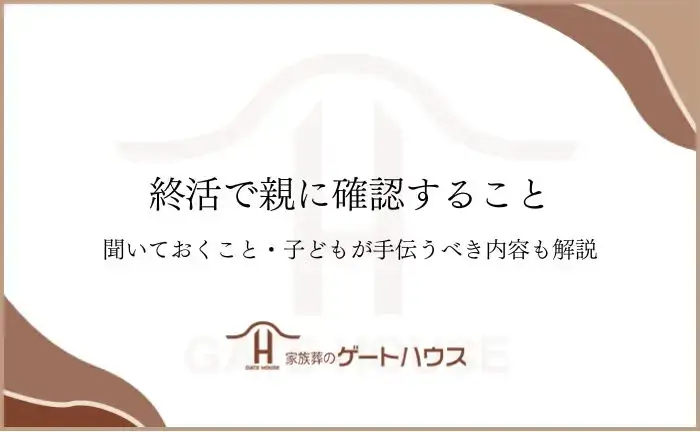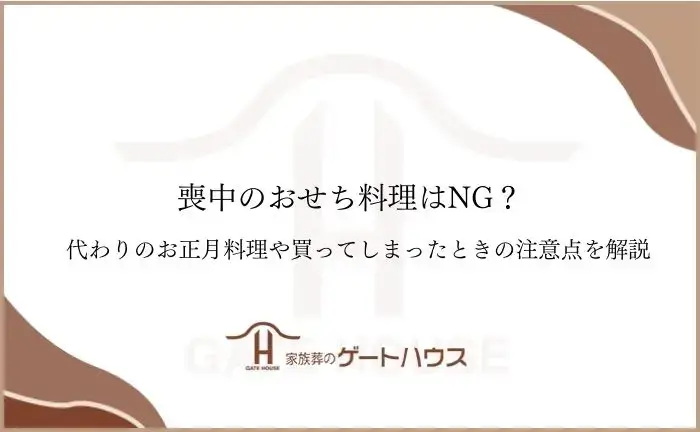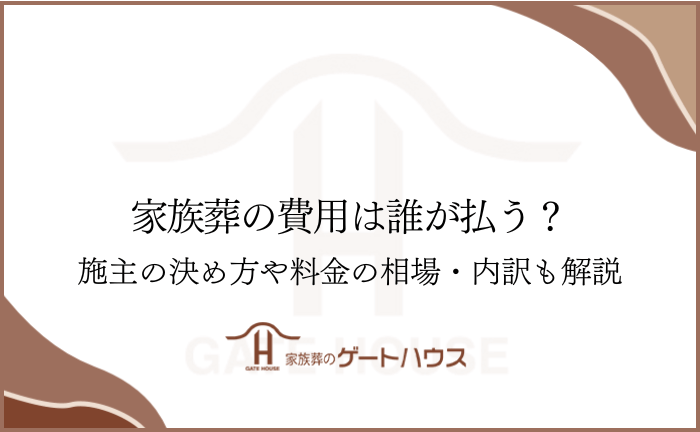やってはいけない実家の相続とは?生前贈与などの対策法も解説
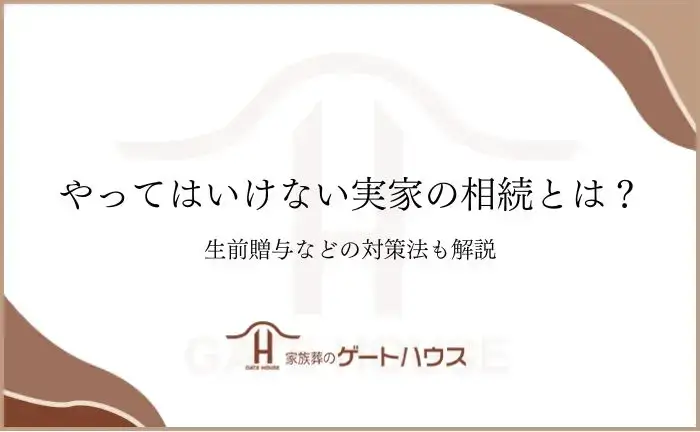
親が亡くなった場合、親が住んでいた実家を相続するケースがあります。
しかし、空き家となった実家を相続する際には慎重に対処しなければなりません。
特に地方にある資産価値の低い実家の場合は要注意です。
この記事では、自分が実家を相続する可能性があるときにやってはいけないことをくわしく解説します。
やってはいけない実家の相続に要注意
「とりあえず」で安易に実家の相続をすると、後で頭を抱えることになるかもしれません。
たとえば、住む予定がないのに実家を相続した場合は、維持費やリスクだけが増えてしまい、後悔につながることも少なくないのです。
空き家であっても固定資産税や火災保険料などの費用がかかります。
さらに、メンテナンスのために電気や水道を契約したままにしておくと、年間で5〜6万円ほどの基本料金が発生します。
綺麗に保とうとすると定期的な室内の清掃や庭の手入れも必要になりますし、実家が遠方であれば交通費の負担も無視できません。
かと言って手入れをせず長期間放置すれば、建物の劣化が進み、雨漏りや壁のひび割れといった修繕が必要になる可能性も。
また、誰も住んでいないと分かれば、不法投棄や放火などの犯罪リスクが高まり、近隣住民とのトラブルに発展するケースもあるでしょう。
実家を相続する際はこのような費用とリスクを十分に理解し、慎重に判断することが大切なのです。
やってはいけない実家の相続7選
金融資産の相続とは異なり、不動産相続の場合、さまざまな問題があります。
ここでは、実家を相続する場合に、やってはいけないことを7つ紹介します。
活用方法を決めないで実家を相続する
活用方法を決めずに実家を相続するのは避けるべきです。
たとえば、親が亡くなった後、子どもがすでに別の場所で暮らしている場合、その実家は空き家になる可能性が高くなります。
住む予定がないまま相続してしまうと、実家は使われないまま放置され、固定資産税や維持管理費といったコストだけがかかり続けることになります。
事前に「住むのか」「売却するのか」「貸すのか」「取り壊すのか」など、活用方法を検討しておきましょう。
複数人の共有名義で相続する
実家を兄弟姉妹など、複数人の共有名義で相続すると後でトラブルに発展するかもしれません。
不動産のような財産を共有すると、管理や処分の際には民法に基づいた制約が生じます。
たとえば売却は「変更行為」に該当し、共有者全員の同意が必要です。
兄弟4人のうち3人が売却に賛成しても、1人が反対すれば実行できません。
賃貸や駐車場として活用したい場合でも、過半数の賛成が必要になります。
さらに意見が真っ二つに分かれてしまえば、何も決まらないまま時間だけが過ぎていきます。
加えて、共有者の誰かが亡くなれば、その配偶者や子どもが持ち分を相続することになり、関係がさらに複雑化するでしょう。
こうした事態を避けるためにも、共有名義での相続は慎重に考えるべきです。
相続した実家の名義変更を行わない
相続した実家の名義を変更せずに放置すると、後々の相続関係が複雑になり、トラブルの原因になります。
相続が発生したら、必ず法務局で名義変更の手続きを行いましょう。
2024年4月1日からは相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内に手続きを行わなければなりません。
正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、2024年4月1日以前の相続についても、3年間の猶予期間があり、2027年3月31日までに手続きをすれば過料の対象にはなりません。
早めに登記を済ませておきましょう。
過去に実家の名義変更が行われていない
相続前の実家の名義がどうなっているかも、確実にチェックしておきたいポイントです。
2024年4月1日から相続登記が義務化されましたが、それ以前は手続きが任意だったため、名義変更されないまま何代も放置されている不動産も少なくありません。
親が住んでいたからといって、その実家が親の名義とは限らず、登記簿を調べてみると、すでに亡くなっている祖父母や、複数の名義人が残っているケースもあるようです。
たとえ相続人が自分一人であっても、登記簿上に他の共有者がいると、その全員の持ち分を整理する必要があり、戸籍をたどって相続人を調べるなどの手間がかかります。
あまりにも手間がかかるため相続人が途中で手続きを放棄し、空き家として放置されることも多いです。
近年は、所在不明の共有者がいる場合の対応手続きが整備され、以前よりは進めやすくなりましたが、それでも裁判所での申立てや調査が必要になります。
代々住み継いできた実家ほど名義が古い可能性があるため、相続が発生する前に一度登記簿を確認しておくことをおすすめします。
相続したまま実家を放置し続ける
相続した実家を放置したままにしておくのは非常に危険です。
空き家であっても、毎年固定資産税は発生しますし、建物や庭のメンテナンスも必要になります。
定期的に訪れて換気や掃除を行い、庭の雑草や樹木の管理も欠かせません。
管理が不十分なまま放置していると、自治体から「特定空家」に認定される可能性があるのです。
そうなると行政による立ち入り調査や指導を受け、改善が見られなければ「勧告」が出されます。
勧告を受けると、土地に対する固定資産税の優遇措置(住宅用地特例)が外れ、税額が最大6倍に跳ね上がることも。
さらに、空き家の管理不足が原因で近隣に被害が及ぶことも考えられます。
たとえば、放置された庭木が強風で倒れ、隣家に損害を与えた場合は、損害賠償を請求される可能性もあるでしょう。
たとえ住む予定がなくても、きちんと管理し続ける責任が伴うのが「実家を相続する」ということなのです。
相続した実家を解体する
相続した実家を解体する際は慎重に判断する必要があります。
建物を取り壊して更地にすると、「住宅用地の特例」が適用されなくなり、土地にかかる固定資産税が最大で6倍になることがあります。
「古い家の維持費がもったいない」「更地の方が売れやすい」と考えるかもしれませんが、使用目的や売却先が決まっていない状態での安易な解体はおすすめできません。
地域によっては、建物付きのほうが需要がある場合もあります。
解体を検討する際は、固定資産税の増額リスクや不動産市場の動向をよく確認し、計画的に進めることが大切です。
相続した後すぐに売却する
相続した実家をすぐに売却するのは、税制面で損をする可能性があるため注意が必要です。相続税には「小規模宅地等の特例」という制度があり、被相続人が住んでいた自宅の土地について、相続税評価額を最大80%減額できるというものです。
ただし、この特例を使うには、一定の条件を満たす相続人(たとえば同居していた子どもなど)が自宅を相続し、住み続ける必要があるため、売却を急ぐことで適用が受けられなくなるケースもあります。
一方で、下記のように相続後に売却することで利用できる特例もあります。
- 1.空き家譲渡の特例
2.取得費加算の特例
1つは「空き家譲渡の特例」で、被相続人が一人暮らしをしていた自宅を、相続開始から3年を経過する年の年末までに売却すると、譲渡所得から最大3,000万円が控除されるというものです。
ただし、1981年5月31日以前に建てられた建物であること、耐震改修済みまたは取り壊して売却することなど、いくつかの条件があります。
この特例は2027年末までが期限とされています。
そして2つ目は「取得費加算の特例」。
これは、相続税を支払った人が、相続した不動産を相続開始から3年10カ月以内に売却した場合、その相続税の一部を譲渡所得の「取得費」として加算でき、結果的に課税対象額が減って所得税を軽減できる制度です。
これらの特例を最大限に活用するには、売却のタイミングをしっかり見極めることが重要といえます。
相続税の申告期限である10カ月を含め、全体の流れと自分のケースに合った特例の適用可否を見ながら、慎重に判断しましょう。
かなり専門的な内容になってくるため、税理士などの専門家に相談をするのがおすすめです。
もし空き家の実家を相続してしまったら
空き家となった実家を相続してしまった場合、思った以上に手間や費用、リスクが発生することがあります。
税金や管理コストがかかるだけでなく、放置すれば近隣トラブルや行政からの指導につながることも。
ここでは、空き家の実家を相続した際の対処法についてわかりやすく解説します。
売却する
空き家となった実家は、適切なタイミングで売却することで、維持費や管理の手間から解放され、相続人同士の公平な分割も可能になります。
ただし、売却の時期によっては、税金の負担に大きな差が出るため注意が必要です。
たとえば、「空き家譲渡の特例」や「取得費加算の特例」は、相続開始からおおむね3年〜3年10カ月以内の売却で適用でき、税負担を軽減できます。
※いずれも適用には細かな要件があるため、専門知識を持った人へご相談ください
逆に、早すぎたり遅すぎたりすると、これらの特例が使えない場合があります。
また、一般的な売却では建物の解体が必要となることが多く、構造や立地にもよりますが、50坪程度の家で100万〜400万円の費用がかかることも。
譲渡所得税も発生するため、費用や税金を事前に確認した上で、計画的に進めましょう。
自分または家族が住む
相続した実家に、自分や家族が住むという選択肢もあります。
立地が良く、建物の状態が問題なければ、住み替えを前向きに検討してみても良いでしょう。
特に現在賃貸住宅に住んでいる場合は、家賃の支払いが不要になり、長期的には経済的なメリットも期待できます。
自分が住まない場合でも、条件が合えば子どもや親族に住んでもらうという活用方法も考えられます。
賃貸住宅にする
実家を賃貸住宅として活用し、家賃収入を得るという方法もあります。
立地や周辺環境が良ければ、長期的な収益につながる可能性があるでしょう。
ただし、必ずしも借り手が見つかるとは限りませんし、築年数が古い場合はリフォームが必要になることも。
さらに、賃借人との契約交渉や建物の維持管理など、継続的な手間も発生するでしょう。
一度賃貸に出すと、借地借家法によって借主の権利が保護されるため、オーナー側から一方的に退去を求めたり、家賃を簡単に変更したりすることはできません。
賃貸経営には法律の知識や管理ノウハウが欠かせないため、自分で対応できるのか、もしくは信頼できる管理会社に委託するのかを含めて、慎重に判断したいところです。
更地にして活用する
相続した実家を更地にして活用するのも1つの手です。
たとえば、月極駐車場やトランクルームなどにすれば、空き家のまま放置するよりは有効活用でき、比較的リスクも抑えられます。
特に駐車場であれば、舗装や区画の整備などの初期費用もそれほど高額にはならないことが多いです。
ただし、こうした用途に需要があることが前提となるため、立地や周辺環境の確認は不可欠です。
また、建物の解体費用が必要になるうえ、住宅が建っていた土地は「住宅用地特例」の対象外となるため、更地にすると固定資産税が最大6倍に上がる点にも注意が必要でしょう。
更地にして土地を賃貸する
更地にした土地を他人に貸すという選択肢もあります。
たとえば、資材置き場や企業の駐車場用地などとして利用されるケースがあり、自分で運営する必要がないため手間が少なく済みます。
初期費用は建物の解体費用のみで、その後のコストはほとんどかかりません。
ただし、自分で活用する場合に比べて収益は少なめです。
その分、管理リスクは低く、安定した地代収入が見込めるかもしれません。
寄付する
相続した実家の活用や売却が難しい場合、寄付や相続放棄を検討する方法もあります。
相続放棄は、相続を知った日から3カ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。ただし、相続放棄はすべての相続財産を対象とするため、「実家だけ放棄して他の財産は受け取る」といった選択はできません。
また、相続財産を使ったり処分したりすると、放棄が認められなくなる可能性があるので注意が必要です。
寄付の選択肢としては、自治体やNPO、近隣住民、企業などが考えられます。
ただし、売却が難しい不動産であれば、寄付の受け入れ先が見つからないことも。
それでも、たとえば隣地の住民が自宅を増築したい場合や、近隣の企業が資材置き場として利用したい場合など、個別のニーズによって引き取り手が現れるケースもあるようです。
注意点として、無償で譲渡した場合でも「みなし譲渡所得税」が発生することがあります。国や自治体、公益法人などへの寄付は非課税ですが、企業や個人への無償譲渡は課税対象になる可能性があるため、事前に税理士など専門家へ確認しておくと安心です。
【関連記事】
実家じまいの費用は?片付け・処分・解体はいくら?補助金や手順も解説
実家じまいとは?かかる費用・手順・片付けのタイミングを解説
実家を相続する前にできる対策
実家を相続してから後悔しないためには、事前の準備が欠かせません。
相続後に発生する税金や維持費、活用の手間やトラブルを回避するためには、あらかじめ実家の状況や相続の方向性について家族で話し合っておくことが重要です。
ここでは、実家を相続する前にできる具体的な対策や考えておくべきポイントを紹介します。
【関連記事】
親が亡くなった時の手続き一覧表|家族や身内の死亡後にすることを順番に解説
親が元気なうちに実家のことを話し合う
親が元気なうちに、実家を将来どうするかを家族で話し合っておきましょう。
まずは、親自身の意向を確認することから始めてください。
長年住み慣れた家に対して強い愛着を持っていることもあり、手放すことに抵抗を感じる場合もあります。
そのうえで、子ども側の意見や今後の生活設計も含めて、家族全体で方向性をすり合わせておくことが大切です。
また、実家の名義が誰になっているかも必ず確認しておきましょう。
登記上の名義がすでに亡くなった祖父母のままになっているケースもあり、その場合は早めの名義変更が必要です。
あわせて、実家以外の資産状況も整理しておくと判断がしやすくなります。
他にめぼしい資産がなく、実家にも大きな価値が見込めないようであれば、相続放棄の選択肢も出てくるでしょう。
事前にこうした情報を共有し、家族全員が納得できる形で実家の扱いを決めておくことが、将来のトラブル回避につながります。
遺言書を作成する
実家の処分方法が決まったら、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
相続財産に現金のように分けやすいものと、不動産のように分けにくいものが混在している場合、誰が何を相続するかで相続人同士が揉める可能性があります。
あらかじめ遺言書で分割内容を明記しておけば、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。
特に不動産については、できるだけ1人の相続人に相続させる形にすると、その後の管理や売却がスムーズです。
複数人による共有名義にしてしまうと、意見の不一致や手続きの煩雑さから、将来的に揉め事に発展するケースも多いため注意が必要です。
【関連記事】
エンディングノートとは?おすすめの内容や書き方・終活ですべきことを解説
生前贈与をする
相続対策としてよく活用されるのが生前贈与です。
相続税がかかると見込まれる場合、早めに資産を贈与することで、相続時の税負担を軽減できる可能性があります。
毎年110万円までの贈与であれば「基礎控除」の範囲内となり、贈与税はかかりません。
この非課税枠を利用して、時間をかけて少しずつ資産を移すことが、節税の基本的な手法です。
特に、預貯金が多い場合や、地価の高い地域に自宅がある場合は、生前贈与を検討することがおすすめです。
ただし、税制改正により、2024年以降は「亡くなる前の7年間」に行われた贈与は、相続財産として加算される仕組みに変わっています。(※従来は3年)
そのため、節税効果を最大限に活かすには、なるべく早めに贈与を開始することが重要です。
制度の詳細や最適な方法については、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
【関連記事】
生前整理とは?いつから始めるのか・生前整理をやるメリット&デメリットなど解説
実家の相続は慎重に。相続前に家族での話し合いと準備が重要
実家を相続する際には、あらかじめ将来の活用方法について考えておくことが大切です。
深く考えずに相続してしまうと、管理の手間や固定資産税の負担がのしかかり、思わぬ苦労を招くことがあります。
できるだけ早い段階で、家族と話し合いの場を持ち、親の意向も含めて実家をどうするか共通の理解を持っておくことをおすすめします。
いざ相続が発生した後も、実家を放置せず、できるだけ早く方向性を定めることが望ましいでしょう。
特に売却を検討する場合は、タイミングによって税金の負担が変わることもあるため注意が必要です。
相続や不動産の売却には専門的な知識が求められる場面も多いため、税理士や不動産の専門家に相談することも視野に入れておくと安心です。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要