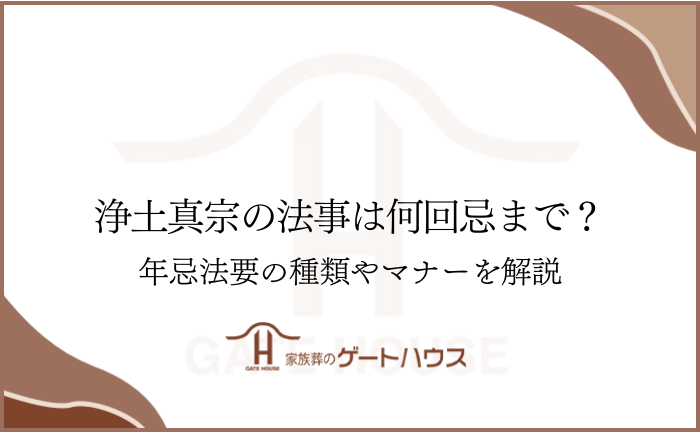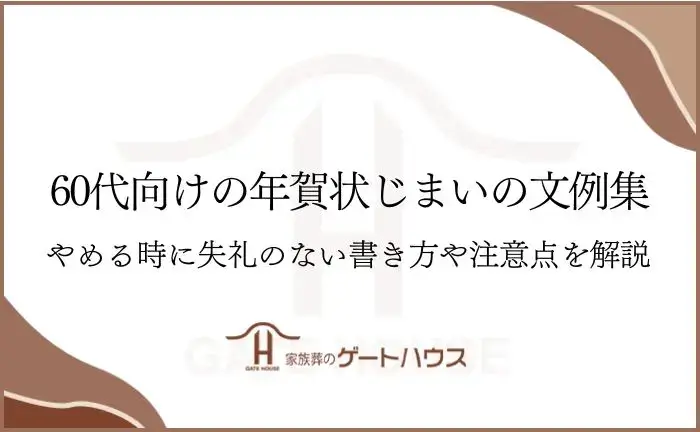女性の一人暮らしに終活は必要?準備することや費用・メリットも解説
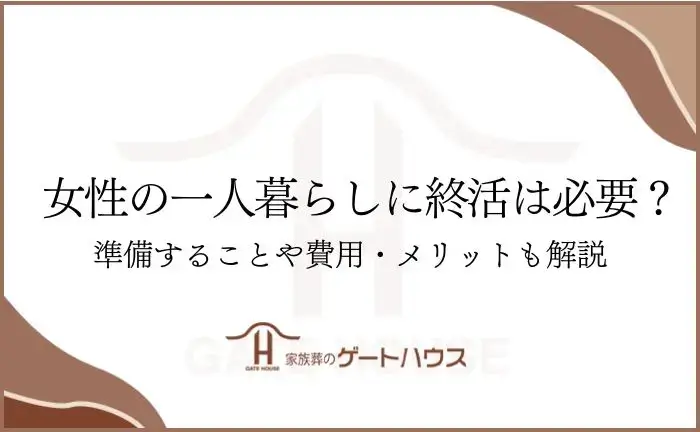
現代では、女性で一人暮らしを選ぶ方や、生涯独身で過ごす高齢者も増えています。
しかし、一人暮らしをしている女性にとって、老後や死後のことは大きな不安の種です。
認知症や介護の問題、身元保証人がいない不安、そして孤独死のリスクなど、さまざまな課題があります。
本記事では、女性の一人暮らしにおける終活の必要性、老後のリスクと対策、準備すべき内容や費用について解説していきます。
女性の一人暮らしに終活は必要?
終活は誰にとっても重要ですが、パートナーや子どもがいない一人暮らしの女性の場合は特に「自分の安心」と「周囲への配慮」の両面で重要です。
親族がいる場合も「迷惑になることは避けたい」「負担をかけたくない」と考える人は多く、老後の生活や各種手続きなど自分で準備を進める必要があります。
孤独死や死後の不安を軽減
一人暮らしの人が終活を考える際に避けられないのが、孤独死の問題です。
高齢になるにつれ、病気や事故が原因で誰にも気づかれずに亡くなるリスクが高まります。
見守りサービスや定期的な連絡先を決めておくことで、孤独死のリスクを大きく減らすことができます。
また、死後の希望を誰にも伝えないまま亡くなった場合は、葬儀や相続が希望通りに行われない可能性も。
身近な親族に希望を伝える、エンディングノートなどに希望を書き記しておく、事務委任契約で任せておく、などできる範囲での準備をしておくと、死後の不安の軽減にもつながります。
残された家族・親族の負担軽減
自分が亡くなった後の手続きは自分で行うことができないため、誰かにやってもらうしかありません。
人が亡くなった後は、葬儀、相続手続き、財産整理、遺品整理など多くのことに対応する必要があり、故人の希望や財産の全貌がわからないまま進めるとなると、遺族には多くの負担がかかるでしょう。
その点、遺言書やエンディングノートを作成し、財産を整理しておけば、葬儀や相続の流れを明確にし、家族や親族の負担を大幅に軽減できます。
終活は「自分のため」でもあり「残された人のため」でもあります。
一人暮らし女性の終活|老後のリスクと対策
一人暮らし女性が老後に直面しやすいリスクには、介護や医療、財産管理の問題などが挙げられます。
具体的な対策を講じておくことが、自分の生活を守ることにつながります。
防災・防犯の見直し
高齢になると体力や判断力が低下し、災害時のケガのリスクも高くなるでしょう。
家具の固定や避難経路の確認、防災グッズの用意、緊急時の連絡先等の情報をまとめておくと、災害時のケガだけでなく、万が一の病気の際の対策にもなります。
頼れる人が身近にいない場合は、見守りサービス等も検討しましょう。
また、住んでいる地域の治安や防災対策の状況も確認し、必要に応じて安全で便利な場所への引っ越しの検討も必要です。
引っ越しまでは必要ない場合でも、防犯カメラ・センサーライト、万が一の侵入を防ぐ窓やカギの採用など防犯設備を見直し、強化することも考えましょう。
介護・医療の備え
誰しもが将来的に介護が必要になる可能性を考えなければなりませんが、一人暮らしの女性は特に「自分が動けなくなった時に誰が助けてくれるのか」を考える必要があります。
介護保険サービスの利用や、訪問医療、施設入居を選択するなど、早めに情報収集しておくと安心です。
また、かかりつけ医の情報・持病や薬の情報を整理し、緊急時に医療機関へ提供できるようにしておくと、万が一の際の対応がスムーズになり、命を守ることにもつながります。
さらに、生命保険や医療保険の内容を見直し、将来的な介護費用や医療費に備えることも大切です。
認知症に備える
認知症になると、判断能力が低下し、財産管理や生活全般が難しくなります。
早めに財産管理等委任契約や死後事務委任契約を結び、信頼できる人に財産や事務手続きを任せる準備をしましょう。
また、成年後見制度の1種である任意後見制度は、自分が判断能力が不十分になった際に、あらかじめ選んだ人に代わりにしてもらいたいことを公正証書によって決めておく制度です。
任意後見を依頼できる家族がいない場合は、友人等に依頼することも可能です。
一方で法定後見制度は、既に認知症の症状が進行している場合でも利用できますが、家庭裁判所によって選ばれた後見人が、本人の生活や療養などに関することに対応します。
孤独死の防止策
定期的に家族や友人と連絡を取り合い、安否確認を行うことで孤独死のリスクを減らせます。
実際に会えなくても、電話やメール、SNSなどを利用してコミュニケーションを維持しましょう。
また、地域のコミュニティや趣味のサークル・イベント等に積極的に参加することで、社会的な孤立を防ぐことにもつながります。
それらが難しい場合は、定期的な訪問サービスや、緊急通報システム、見守りサービス、安否確認のサービスの活用を検討しましょう。
保証人がいない場合の対策
高齢になって、施設に入所する際や病院に入院する際、多くの場合「身元保証人」や「身元引受人」が必要になります。
保証人がいると、本人に代わって金銭的な連帯保証や、医療方針への同意など入退院時のサポートをしてくれます。
身寄りがない場合は、保証人代行サービスや身元保証サービス、成年後見制度を活用することで、スムーズに契約を進められるでしょう。
一人暮らし女性の終活|準備しておきたいこと
老後のことはまだ考えられないという30代・40代の方も、早いうちから準備できることはあります。
終活は「自分らしい生活を最後まで続けるための準備」です。
早めに取り組んでおくと、老後に対する安心感が高まりますので、何から始めたら良いのか分からない方は参考にしてください。
身の回りの整理
普段から不要な物を整理しておくことは、突然の入院や死亡時の負担を大きく減らせます。
不要な物を処分することで、災害時のリスクを減らしたり、日常生活のケガのリスクを抑えたりすることにもつながります。
衣類や家財道具、書類などを定期的に見直し、自分にとって本当に必要な物だけを残す習慣をつけると残された人が遺品整理をする時も困りません。
定期的な整理を習慣化させることで、万が一の際の負担が少なくなります。
財産を整理・管理
預貯金、不動産、保険、株式などの財産は、家族であっても同居していなければ、なおさら把握しにくいものです。
すべての資産が一覧できるように財産目録を作ってまとめておくと自分自身も全体像を把握できますし、残された人の負担を軽減することにもつながります。
エンディングノートには財産目録を作成する項目がありますので、まずは気軽に始めてみるのがおすすめです。
事務委任契約・財産管理等委任契約の活用
認知症などで判断能力が低下したときに備えて、事務委任契約や財産管理等委任契約を活用しましょう。
「事務委任契約」は家族や専門家である第三者などに、公共料金や医療関連などの契約や支払い、行政手続きの代行などの事務を依頼できます。
「死後事務委任契約」は、死後の事務手続きに限定して依頼が可能です。
「財産管理等委任契約」は、自身に判断能力があるうちに第三者へ財産管理を委任できます。
判断能力が不十分になってからでは活用できない制度もありますので、早いうちから準備しておくようにしましょう。
エンディングノートで自分の想いを整理
家族へのメッセージや葬儀の方法、遺品の管理など遺言書では書けない思いを残すには、エンディングノートを活用しましょう。
区市町村で無料配布されているものもありますが、自分で自由に作成することも可能です。
遺言書のように法的効力はありませんが、自分の価値観を見直すきっかけや自分の心を整理することにもつながります。
【関連記事】
エンディングノートとは?おすすめの内容や書き方・終活ですべきことを解説
専門家に相談
司法書士、行政書士、弁護士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することで、契約や手続きを正確に進められます。
特に遺言書の作成や財産管理契約など法律にかかわる部分は、専門家に相談するのが良いでしょう。
費用はかかりますが、将来的なトラブルは防げます。
一人暮らし女性の終活|費用と具体的な内容
終活には一定の費用がかかりますが、早めに準備することで無駄な出費を防ぐことが可能です。
【関連記事】
終活やることリスト11選|何から始めるか・いつからがいいか解説
遺言書の作成
遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
公正証書遺言は2人以上の証人の立ち会いのもと、原則的に公証役場で公証人が作成するため、法的効力が高く安心です。
個人で直接公証役場に依頼することも可能ですが、専門知識が無い場合は、弁護士や行政書士など専門家に依頼した方がスムーズでしょう。
専門家に依頼した場合、財産の価額や内容、弁護士事務所によっても変わりますが費用がかかります。
一方、自筆証書遺言は費用がかからないため、自分で気軽に作成できて、何度も書き直せますが、不備があると無効になる可能性もあるため注意が必要です。
財産が多い場合や、自分の死後の希望を必ずかなえてほしい場合は、公正証書遺言がおすすめです。
死後の準備
葬儀に関連する費用は、葬儀代金だけでなく、僧侶に支払うお金や埋葬費用もかかります。
墓石を新たに購入する場合は、それらに加えた費用がかかりますが、永代供養墓や樹木葬などを選ぶことで、全体の費用や管理負担を減らすこともできます。
事前に調べて相見積もりを取ったり、比較したりすることで自分の希望に沿うものを見つけられるでしょう。
【葬儀に関するお悩みはこちらから】
葬儀社の選び方のポイント丨失敗しないための決め方や気をつけることを解説
葬儀の事前相談をするメリット7つ丨お葬式前に準備しておきたいこととは?
生前整理
費用は部屋の広さや量によって異なりますが、遺品整理業者や不用品回収業者などの専門業者に依頼すると数万円〜数十万円程度の費用がかかります。
自分で計画的に進めておけば、コストを削減できますし、残された家族の負担も減らせるでしょう。
また物品整理だけでなく、デジタル機器やデータ、アカウント情報の整理や、財産の整理、人間関係の整理も生前整理に含まれます。
ネット銀行口座の預金や電子マネー、証券口座、暗号資産などのデジタル資産に関しては、遺族が発見できずにトラブルになる可能性もあるので、注意が必要です。
人間関係の整理では、慶弔記録を整理したり、親族や友人知人の連絡先を確認・整理したりして、葬儀に呼んでほしい人をリストアップしておくのも良いでしょう。
【関連記事】
生前整理とは?いつから始めるのか・生前整理をやるメリット&デメリットなど解説
終活サービスや支援制度の活用
自治体の支援制度や民間の終活サービスを利用することで、財産管理や死後事務、医療・介護のサポートを受けられます。
民間の終活サービスでは、相談内容や事業者のプランによって費用が大きく異なり、生前整理や遺言書作成、相続手続き、葬儀、墓じまいなど、依頼する項目に応じて数十万円から数百万円以上かかることも珍しくありません。
特に、身元引受や成年後見、死後事務委任契約といった包括的なサービスでは、契約時に数十万円から百万円以上の預託金や初期費用が必要になるケースがあります。
早めに準備することで自分に合ったサービスを見つけることができますし、一人暮らしの不安を大幅に軽減できるでしょう。
【関連記事】
独身・身寄りなしの老後の課題とは?高齢者が行うべき終活内容を解説
一人暮らし女性の終活は早めの準備が安心
一人暮らしの女性にとって、終活は「まだ早い」と思われがちですが、実際には早めに始めることで多くのリスクを回避できます。
遺言書や事務委任契約、エンディングノートの活用は、安心して暮らすための強い味方です。
終活は高齢になってから始めるのではなく、できるだけ早めに取り組むことで、生活の質を高め、家族や相続人の負担も軽減できます。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要