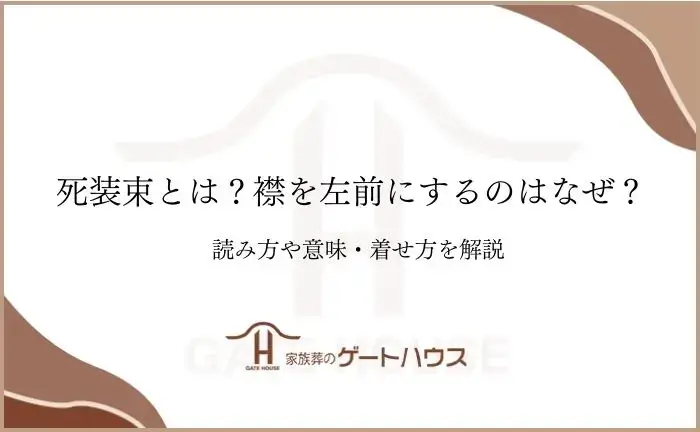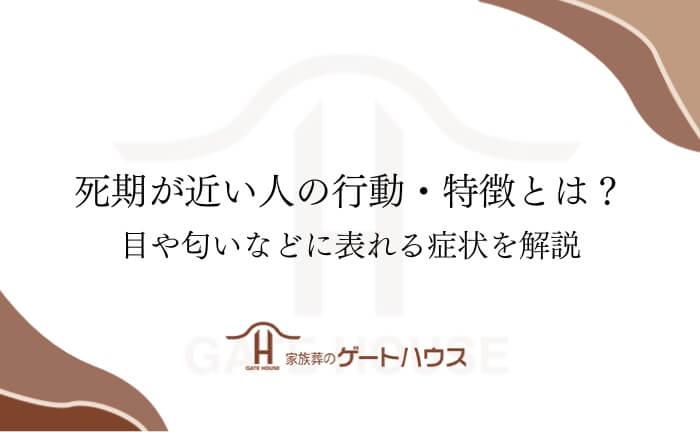孫からの香典は出すべき?いらない場合もある?相場や渡すときのマナーを解説
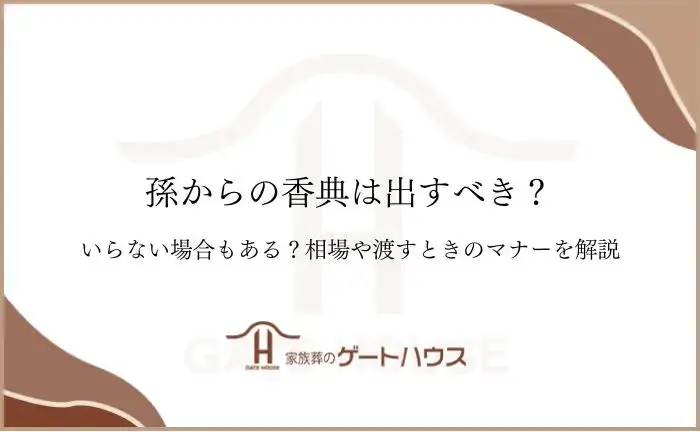
祖父母のお葬式で孫が香典を出すべきかどうかは、一概には言えません。
孫の社会的立場や祖父母との関係性によって異なります。
この記事では、孫から香典を出すべきかどうか、いらない場合はどのようなケースであるかについて詳しく解説します。
孫からの香典は出すべき?いらない場合もある?
祖父母の葬儀で孫が香典を出すべきかどうかは、孫の立場や状況によって異なります。
出す・出さないを判断するうえでのポイントは3つです。
②祖父母と孫が同居しているかどうか
③香典を辞退しているかどうか
次項で個別の事例について具体的に解説します。
孫からの香典がいらない場合
孫からの香典がいらないのは、孫が収入のない未成年の場合や亡くなった祖父母と同居していた場合などです。
それぞれのケースについてくわしく紹介します。
孫が未成年・学生である
最も明確なのは、孫が未成年や大学生の場合です。
祖父母と別居している場合であっても、収入がなければ香典を出す必要はありません。
親の扶養家族となっているはずなので、香典は孫の親が出します。
孫と祖父母が同居している
孫が収入のある社会人の場合であっても、孫と祖父母が同居していれば香典を出さなくても大丈夫です。
同居している場合、孫は遺族の立場になります。
香典は、弔問客が遺族に対して渡すものなので不要です。
香典を辞退している
最近主流となっている家族葬だけでなく一般葬でも、香典辞退というケースが増えつつあります。
孫が成人していて祖父母と別居しているような場合であっても、喪主が香典を辞退していれば出さないのがマナーです。
どうしても弔意を示したいのであれば、代わりに葬儀で飾るお花を出すことなどを検討しましょう。
「孫一同」などとして、お花を出すケースはよくあります。
ただし、このような場合は、事前に遺族に対して確認を取るようにしましょう。
孫が香典を出す場合
孫が香典を出すのは、基本的に祖父母と別居していて成人している場合です。
それ以外の香典を出すケースも含めて紹介します。
祖父母と別居していて成人している
孫が成人していて祖父母と別居している場合は、香典を出すのが一般的です。
しかし、孫が親と同居しているのであれば親だけが出して孫は出さないケースもあります。
香典は、基本的に世帯単位で出すのが一般的な慣習です。
未成年でも孫一同で出す
孫が何人かいてほぼ全員未成年の場合であっても、みんなで少額ずつ負担して「孫一同」として香典を出すケースもあります。
成人して収入がある・結婚している場合は、個人名で出すべきでしょう。
結婚している孫が香典を出す場合、香典袋の表書きは夫婦のうち血縁関係のある方の個人名を書くのが基本です。
しかし結婚して名字が変わっている場合は、孫夫婦の連名にします。
孫の香典の相場はいくら?
孫が出す香典金額の相場は、主に年齢によって異なります。
| 孫の年齢層 | 金額相場 |
| 20代 | 1〜3万円 |
| 30代 | 1〜3万円 |
| 40代以上 | 3〜5万円 |
ただし、祖父母との関係性や孫の社会的地位、葬儀の規模などによってさまざまです。
香典には、遺族の葬儀費用の負担を軽減する意味もあります。
祖父母だけで生活していて年金暮らしだった場合などは、少し多めに包むことも検討しましょう。
また、他の孫が出す金額も参考にする必要があります。
【関連記事】
香典の相場はいくら?葬儀・法要での金額目安を関係性・年齢別に解説
香典の書き方
香典の書き方にも一定のルールがあります。
特に、宗教・宗派によって表書きの書き方が異なる点には、十分注意しなければなりません。
薄墨で書く
香典の文字は、薄墨で書くのがマナーです。
薄墨を使用する理由にはいくつか説があります。
ひとつは、悲しみのあまり涙で墨が薄くなってしまったとの意味を暗示している説。
もうひとつは、突然の知らせを聞いて急いで準備したので、墨を十分時間をかけてすれずに薄いままで書いてしまったとの説です。
いずれにしても、遺族への思いやりから生まれた慣習といわれています。
筆記具は、できれば筆や筆ペンを使用するのが望ましく、文房具売り場では薄墨タイプの筆ペンも市販されています。
こうした背景を知っておくと、より丁寧な気持ちで香典を用意できるかもしれませんね。
【関連記事】
香典袋は薄墨でないとだめ?書き方やいつまで濃墨を使わないべきかを解説
表書き|宗教・宗派によって異なる
香典袋(不祝儀袋)の表書きは、宗教・宗派によって書き方が異なります。
浄土真宗以外の仏教宗派では、表書きの上段には「御霊前」と書くのが一般的です。
浄土真宗では、亡くなると霊としてさまよわず、すぐに仏になるという教えなので「御仏前」と書くのがマナーです。
神式の葬儀では「御玉串料」「御神前」など。
キリスト教は「御花料」であれば、カトリックでもプロテスタントでも使えます。
表書きの下段には、自分の名前を書きましょう。
親族の葬儀なので、同じ名字が複数いる可能性があります。
他の人と混同される恐れがないよう、フルネームで記載しましょう。
中袋|金額と住所・氏名を記載
香典の中袋の表側には、金額を記載します。
金額は旧字体の漢数字「大字(だいじ)」を使用します。
たとえば「伍仟圓」「壱萬圓」「参萬圓」「拾萬圓」など。
丁寧に書く場合は「金壱萬圓也」などと数字の頭に「金」、最後に「也」を加えます。
中袋の裏面には、自分の氏名・郵便番号・住所を記載します。
いずれも縦書きで記入してください。
孫が香典を渡すときのマナー
祖父母と親しい間柄の孫なら、それほど細かいマナーを気にする必要はないと考えるかもしれません。
しかし、お世話になった祖父母を心をこめて見送るためにも、基本的なマナーは把握しておきましょう。
新札の使用は避ける
香典に新札を使用するのはNGです。
新札は、まるで亡くなるのを予想して、香典を前もって準備していたかのようにとらえられる恐れがあるので、避けなければなりません。
とはいえ、逆にシワだらけでボロボロのお札も相手に対して失礼です。
旧札であっても、比較的きれいなお札を選びましょう。
どうしても新札しか用意できない場合は、お札に折り目を付けるのがマナーです。
折り目の付け方にはっきりとした決まりはありませんが、真ん中で半分に折って縦の折り目を付けると良いでしょう。
折り目を付けた後はきれいに伸ばしてください。
受け取った人には、渡す方の気配りとマナーが伝わるはずです。
金額は数字に注意
香典に包むお金を用意する際は、数字に注意が必要です。
不吉なこと・縁起の悪いことを連想させるような数字を使うのは、マナー違反とされています。
4や9の数字は「死」「苦」を連想させるので、4万円や9万円という香典は避けましょう。
また、偶数は割り切れる数字なので「別れる」「縁が切れる」につながるため、避けた方が無難です。
どうしても偶数にしなければならない場合は、お札の枚数を変える方法があります。
たとえば2万円を包みたい場合、1万円札1枚と5千円札2枚にします。
2は割り切れる数字ですが、お札の枚数は3枚なので奇数です。
なかにはこれでもマナー違反ととらえる人もいるかもしれませんが、一定の配慮をしていることは相手に伝わるでしょう。
【関連記事】
香典で包んではいけない金額とは?料金相場や包み方・書き方のマナーも解説
袱紗を準備する
香典は、袱紗(ふくさ)に包んで持参するのが基本的なマナーです。
受付で渡すときは、袱紗から取り出し、お盆か台の上に載せるか、お盆がなければ袱紗の上に置いて渡します。
香典の表書きが相手から読めるよう向きを確認するのも忘れずに。
袱紗がないときは、白または黒のハンカチか、小さめの風呂敷でも代用可能です。
香典の金額は他の親族に配慮する
他にも孫がいる場合、香典の金額には一定の配慮をしましょう。
他の孫とあまりにもかけ離れた金額を出したり、自分だけ香典を出したり、逆に自分だけ出さなかったりするのは避けた方が無難です。
香典を包むときは、他の孫や自分の親とも相談して金額を決めると良いでしょう。
孫が香典を渡すかどうかは状況次第。重要なのは故人への哀悼の気持ち
祖父母の葬儀に際して、孫が香典を渡すかどうかは、その人の年齢や立場、家族の意向など状況によって異なります。
この記事では基本的な判断基準を紹介しましたが、何より大切なのは祖父母を思う気持ちです。
香典を渡すかどうかにかかわらず、心を込めて故人を見送り、感謝と哀悼の意を表すことが大切です。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要