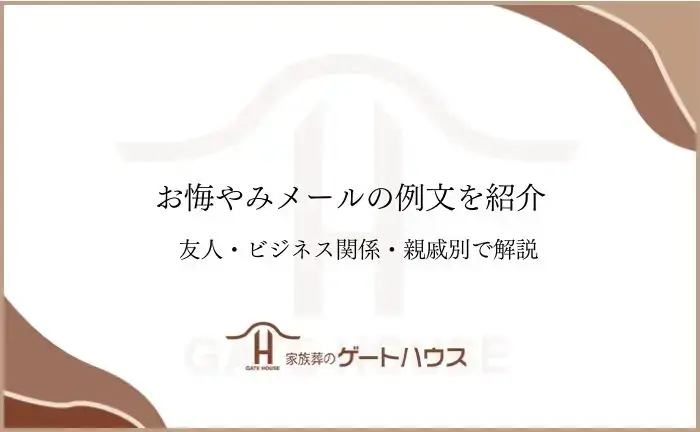初盆法要をお寺で行うには?お布施や持ち物など合同法要について解説
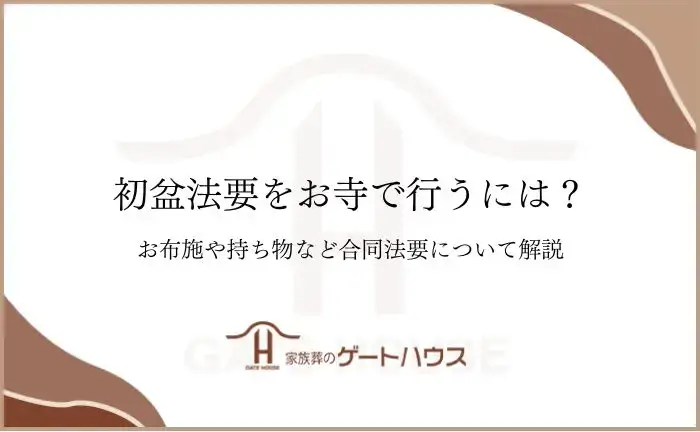
大切な故人を見送ってから初めて迎えるお盆の法要は、しっかりと供養するためにもお寺で行いたいと考える人は多いでしょう。
この記事では初盆法要をお寺で行うことはできるのかについてや、初盆法要をお寺で行う際のお布施や持ち物、マナーについて詳しく解説します。
初盆法要をお寺で行うことはできる?
初盆(新盆)の法要は自宅で行うのが一般的ですが、先祖代々お世話になっている菩提寺がある場合は、お寺で初盆法要を行うことができます。
ただし、お寺で行う場合は、同じ年に初盆を迎える檀家が合同で故人を供養する「合同法要」に参加するのが一般的です。
というのも、僧侶はお盆になると檀家をまわって読経する「棚経」で忙しく、初盆法要のために自宅に赴いてもらうことが難しくなります。
初盆法要を自宅で行うのが難しいのであれば、合同法要が向いているでしょう。
合同法要の種類
合同法要は「家系ごとに行うケース」と「寺院や地域で行うケース」の2種類があります。
前者の家系ごとの合同法要は、初盆に限らず、三回忌や七回忌など法要が重なる場合にも、合同で法要を行うことが多いです。
遺族の負担を軽減できるほか、親族が集まりやすく、故人の思い出を語り合う場にもなるというメリットがあります。
一方、後者の寺院や地域による合同法要は、お盆やお彼岸といった先祖供養の時期に合わせて開催されることが多く、同じ年に初盆を迎える檀家や地域住民が一堂に会して行われます。
同じ地域に住む参列者と一緒に故人を偲ぶことで、地域社会との繋がりが深まる点がメリットとして挙げられます。
初盆法要をお寺で行う理由
初盆法要をお寺で行う理由として多く挙げられるのが、準備や後片付けの負担軽減です。
核家族化が進む現代においては、葬儀や法要を自宅で行うケースは減りつつあります。
そのため、初盆法要のためにスペースを確保したり、準備や後片付けを行ったりするのは遺族にとって大きな負担となるため、初盆法要もお寺で行うケースが多いです。
また、自宅に仏壇がない、お寺に納骨されているなどの理由から、初盆法要をお寺で行うケースもあります。
初盆法要をお寺で行う時のお布施
初盆法要をお寺で行う場合は、お布施を用意するのがマナーです。
この項目ではお布施の相場や表書き・中袋の書き方、用意する封筒や水引などについて解説します。
【関連記事】
お布施とは?金額の相場やお金の入れ方・渡し方のマナーを徹底解説
お布施の相場
合同法要に参加する場合のお布施は、5千円〜3万円が相場です。
ただ、宗派ごとに法要の内容や初盆法要に対する考えが違うため、お布施の相場も異なります。
たとえば、真言宗の場合は追善供養を重視するため、初盆法要の相場は3〜5万円ほどと他の宗教・宗派より高くなる傾向があります。
また、法要に関わる僧侶の人数や地域性によってもお布施の金額が変わるため注意が必要です。
不安な場合は菩提寺か、家族・親族に確認すると良いでしょう。
【関連記事】
お布施が少ないと言われたらどうしたらいい?金額相場・マナーについても解説
御膳料(おぜんりょう)
初盆法要では、お布施のほかに御膳料も必要です。
御膳料とはお食事代として僧侶に渡すお礼のことで、相場は5千円〜1万円ほど。
法要では僧侶をもてなすために会食の場が設けられるのが一般的ですが、僧侶が会食への参加を辞退した場合は、御膳料を渡します。
僧侶が会食に参加した場合は御膳料を用意する必要はないため、会食への参加の有無は事前に確認しておきましょう。
御車料(おくるまりょう)
御膳料の他に、御車料を用意するケースもあります。
御車料とは交通費として僧侶に渡すお礼のことで、相場は3千〜5千円ほど。
移動距離が長くなるほど、金額は多くなるのが一般的です。
僧侶が車やタクシーを使って移動した場合に渡し、移動が伴わない場合やタクシーを手配し料金を支払った場合、誰かが僧侶を送り迎えした場合などは、御車料を用意する必要はありません。
表書き・中袋の書き方
表書きは、水引で分けた上段の真ん中に記します。
お布施の場合は「お布施」または「御布施」、食事代の場合は「御膳料」または「お斎料」「御食事代」、交通費の場合は「御車料」と書きましょう。
また、下段には施主の名前をフルネームで記載してください。
中袋には表面中央に金額、裏面左下には住所・氏名を記すのがマナーです。
住所は必ず郵便番号から記載し、集合住宅の場合はマンション名や部屋番号なども忘れずに記載してください。
金額の書き方
中袋の表面に金額を記載する時は、必ず旧書体を使用しましょう。
「一」は「壱」、「五」は「伍」などの数字はもちろん、「千」は「仟」、「万」は「萬」、「円」は「圓」と記すなど、単位にも気をつけてください。
また、金額の前には「金」、最後に「也」と記載するのもマナーです。
例えばお布施として3万円を包むなら、表面には「金参萬圓也」と記載してください。
使う封筒・水引
お布施を入れる不祝儀袋は、白を基調としたシンプルなものを用意しましょう。
白無地であれば、宗教や宗派を気にせずに使用できます。
また、金額が数千円〜1万円であれば封筒タイプ、3万円以上を用意するのであれば中袋がついているタイプのものを用意してください。
水引は白と黒、または銀と白のものが一般的ですが、関西の一部の地域では黄色と白の水引を使うこともあります。
初盆法要をお寺で行う時の準備
続いては初盆法要をお寺で行う時の準備について、具体的に解説します。
まずは何から行うべきなのか、それぞれ何をすべきなのかを確認し、初盆法要に備えましょう。
お寺に法要の依頼をする
初盆法要をお寺で行うことを決めたら、まずはお寺に法要の依頼をしましょう。
菩提寺に連絡を入れ、合同法要のスケジュールを確認・決定してください。
前述の通り、お盆はお寺にとって非常に忙しい期間であるため、遅くとも1ヶ月前には連絡をしておくと安心です。
また、その際に僧侶に会食への参加の有無を確認しておくと良いでしょう。
合同法要の日程が決まったら、法要に招待する人へも忘れずに日程を連絡し、同時に会食に参加するか否かを確認してください。
法要の内容を決める
続いては、僧侶と相談して法要の内容を決めましょう。
具体的には誰の法要を合同で行うのかを伝え、読経や法話の内容などについて相談します。
また、お布施の金額に不安があれば、このタイミングで相談するのもおすすめです。
合同法要の場合はお供物に決まりがあることもあるため、お供物は故人が好きだったものを用意して良いかも確認しておくと良いでしょう。
持ち物を確認する
初盆法要をお寺で行う場合は、お供物やお布施以外にも用意すべきものがあります。
当日になって慌てることがないように、持ち物に関しても事前にお寺に確認しておくと良いでしょう。
また、初盆法要をお寺で行う際の一般的な持ち物に関しては、次の項目で詳しく解説します。
初盆法要をお寺で行う時の持ち物
| 【初盆法要をお寺で行う時の持ち物】 |
| ①位牌・遺影 ②お布施 ③数珠 ④御仏前、御供物料 ⑤その他(ハンカチ・時計・傘・手袋・バッグ・小物入れ) ※菩提寺によって持参物は異なるため、詳細は法要を依頼する菩提寺にお聞きください |
地域の特性や菩提寺によって持ち物は異なりますが、お寺で新盆法要を行う場合は位牌や遺影、白提灯などの仏具を持参することが多いです。
お経を唱える際は数珠を使用するため、必ず自分の数珠も用意しましょう。
家族・親族から数珠を借りることはマナー違反になります。
また、当日は黒のシンプルなバッグ、または小物入れを用意し、その中にお布施やハンカチを入れて持参してください。
その他、気候に合わせて傘や手袋なども用意しておくと良いでしょう。
初盆法要をお寺で行う時にお供え物はいる?
初盆の法要をお寺で行う場合、具体的には合同法要に参加する場合は、基本的にはお供物は必要ありません。
すでにお寺で用意したものがお供えされているケースが多いです。
ただ、地域やお寺によっては自由にお供物を用意して良いこともあります。
この場合は故人が好んでいた食べ物や飲み物、または旬の果物や花などを持参するのがおすすめです。
花を用意する場合は可能な限り白を基調とした花を、お菓子を用意する場合は日持ちするものを選びましょう。
初盆法要をお寺で行う時の流れ
| 【初盆法要をお寺で行う時の流れ】 |
| ①僧侶による読経 ②参列者による焼香 ③住職による法話 ④会食を設ける |
初盆法要の当日は、まずは僧侶がお経を上げます。
合同法要の場合は故人が複数いるため、戒名も複数読み上げられるのが一般的です。
続いて参列者による焼香が行われますが、焼香のやり方は宗教によって異なるため、必ず事前にやり方を確認しておきましょう。
その後、参列者とともに住職による法話を聞き、法要が終わった後は参列者へのお礼を述べ、最後は会食です。
会食を行う場合は参列者の席順、料理の内容にも気をつけながら、事前に手配を進めましょう。
初盆法要をお寺で行う時の服装マナー
初盆法要をお寺で行う時は、服装にも配慮が必要です。
基本的にはブラックフォーマル、または準喪服を着用しましょう。
この項目では男性・女性・子どもに分けて、それぞれの服装マナーを詳しく解説します。
男性
男性は黒を基調とした、無地のスーツを着用するのが基本です。
ダークグレーや紺色など、落ち着いた色であれば黒でなくても問題はありません。
いずれの場合も、シャツは無地の白いワイシャツを着用してください。
また、ネクタイや靴下などの小物類も、黒やダークグレー・紺色などの落ち着いた色で、無地のものを選ぶのがマナーです。
明るい色や柄のあるものは避けましょう。
女性
女性は黒を基調とした、無地のワンピースやアンサンブルを着用するのが基本です。
男性と同じようにダークグレーや紺色でも問題ありませんが、必ず膝や肘、デコルテが隠れるデザインを選びましょう。
素足はマナー違反になるため、黒または肌色のストッキングを着用してください。
靴は飾りのない、シンプルな黒のパンプスが好ましいです。
また、パンツスーツを着用する場合は、白のワイシャツをと合わせることを心がけてください。
子ども
学生の場合は、学校指定の制服を着用しましょう。
制服がない場合は白いシャツにブレザー、またはジャケットを用意し、男子はパンツ、女子は膝丈のスカートを着用することが望ましいです。
足元は革靴、なければスニーカーでも構いません。
いずれの場合も黒・紺色・ダークグレーなど、落ち着いた色味でシンプルなデザインのものを選んでください。
また、小さな子どもの場合は絵柄入りの服を避け、シンプルな服を身につけましょう。
【関連記事】
初盆(新盆)の服装マナーとは?男性・女性別の着こなし方や注意点を解説
各宗派の初盆法要の特徴
初盆法要のやり方は、宗派ごとに特徴があります。
この項目では浄土真宗、浄土宗、真言宗、曹洞宗の4つの宗派について、初盆法要の特徴を解説します。
浄土真宗
浄土真宗では、基本的に初盆法要は行いません。
故人の魂は死後すぐに極楽浄土へ召されると考えられているため、お盆にご先祖様が帰ってくるという概念がないのです。
そのため、追善供養も行わないのが一般的です。
浄土真宗のお盆は初盆法要の代わりに、阿弥陀様やご先祖様に感謝の気持ちを示したり、祈りを捧げたりする「歓喜会(かんぎえ)」を行います。
【関連記事】
浄土真宗の初盆の迎え方は?お布施相場やお供え物・仏壇の飾り方など解説
浄土宗
浄土宗では故人が亡くなり、四十九日法要が終わってから初めて迎えるお盆に、初盆の法要を行います。
内容は一般的な初盆とほとんど同じです。
具体的には精霊棚を用意し、お供物や提灯を置いたり、故人を迎え入れるための目印として白提灯を飾ったりします。
お供物は季節のお花や故人が好きだった食べ物を用意しますが、浄土宗ではお酒やタバコなどの嗜好品をお供えすることはマナー違反に当たるため、注意してください。
真言宗
真言宗の初盆法要も、浄土宗と同じく一般的な初盆法要を行います。
ただ、真言宗は「追善供養」という考えを大切にするのが特徴的です。
「追善供養」とは故人に対してのみお参りをするのではなく、仏様にもお参りをすることで、故人・先祖の成仏を願います。
したがって初盆法要も故人のお墓だけでなく、菩提寺に足を運んでお参りをします。
【関連記事】
真言宗の初盆とは?準備するお供え物や行うこと・服装マナーを解説
曹洞宗
曹洞宗も一般的なお盆と大きく変わりはありませんが、お盆飾りに独特な決まりがあるのが特徴的です。
一般的に盆棚には「まこも」と呼ばれる稲の一種を編んだ敷物を敷きますが、曹洞宗の場合は白い布を敷きます。
また、盆棚には「浄飯」と呼ばれる炊き立てのご飯、「浄水」と呼ばれるお水、「水の子」と呼ばれる小さく四角に切ったキュウリやナス、お米などをお供えします。
【関連記事】
曹洞宗の初盆飾りの仕方は?精霊棚(祭壇)の飾り方・お供え物・提灯について解説
初盆はお寺で行うことができる。その場合は合同法要に参加する
初盆の法要はお寺で行うことができ、その場合は合同法要に参加するのが一般的です。
お布施の金額やお供物の有無は地域やお寺によって異なるため、必ず事前に確認しましょう。
その他、初盆法要に参加する時の服装や、お布施の包み方等のマナーも事前に押さえておくと安心です。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要