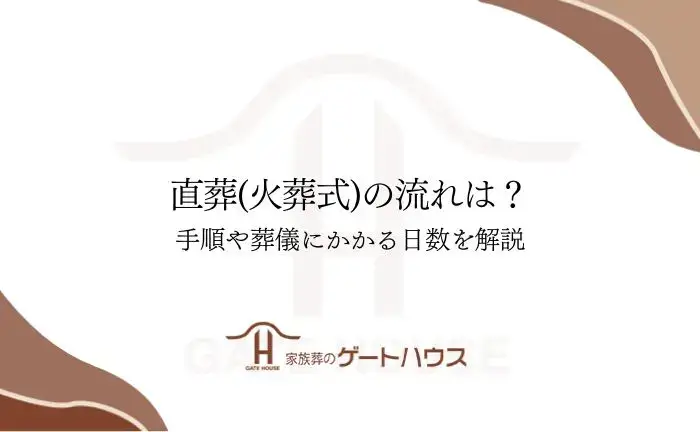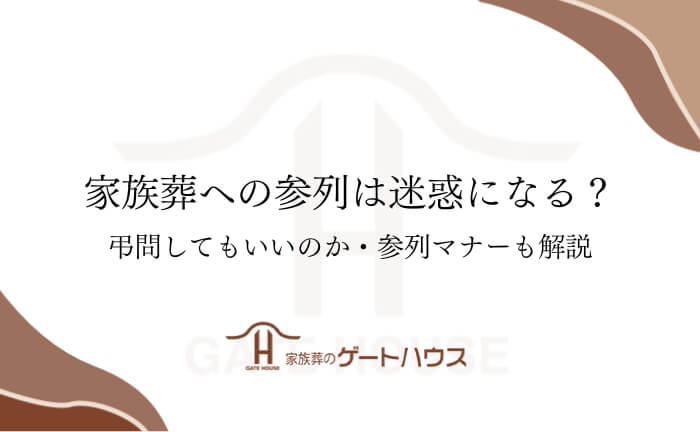訃報LINEへの返信例文を相手別に紹介!お悔やみを伝える10のマナー
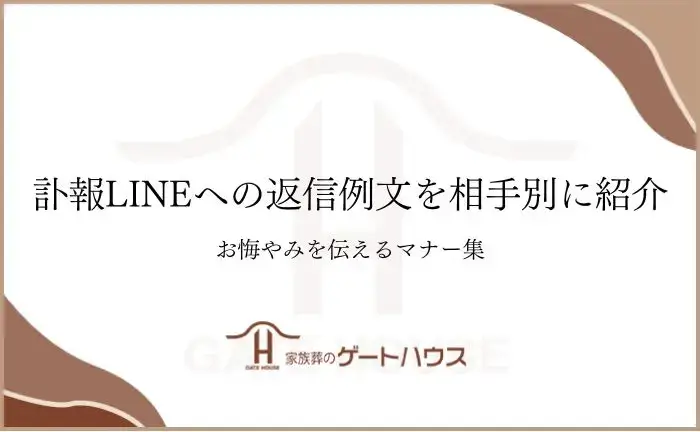
訃報の連絡をLINE(ライン)で受け取った際、どのように返信すれば良いのか分からず、不安に思う人もいるでしょう。
「LINEで返信するのはマナー違反?」「お悔やみは何と伝えるべき?」などと、迷うかもしれません。
この記事では訃報のLINEについて、マナーや例文などを紹介します。
訃報にLINEで返信するときの10個のマナー
訃報の連絡をLINEで受け取ったときに、LINEで返信するのはマナー違反ではありません。
ただし、返信する際には注意点もあるので、事前にチェックしておきましょう。
まずは、訃報にLINEで返信するときのマナーを解説します。
できる限り早く返信する
訃報をLINEで受け取ったら、できる限り早く返信しましょう。
相手は家族が亡くなって大変なときに連絡してくれているので、なるべく早く返信するのがマナーです。
訃報を受け取ったその日のうちに返すのがベストですが、難しい場合は「返信が遅くなり申し訳ありません」などのお詫びを伝えましょう。
忌み言葉を避ける
訃報をLINEで返信する際には「苦しい」「消える」などの忌み言葉を使わないようにしましょう。
また「くれぐれも」「重ね重ね」といった重ね言葉、「死ぬ」「生きる」など生死を連想する言葉も避けてください。
故人が亡くなったことは「ご逝去」などの言葉で表現しましょう。
| 重ね言葉 |
くれぐれも、重ね重ね 色々、段々、引き続き … など |
| 忌み言葉 |
苦しい、終わる 辛い、消える … など |
| 生死を連想する言葉 |
死ぬ、急死 生きていたころ … など |
句読点を使わない
訃報LINEの返信には、句読点を使わないのがマナーです。
文章を区切る句読点を使わないことによって、葬儀が滞りなく進むようにという思いや、故人への敬意を表します。
途切れない気持ちを表すこともできますが、LINEやメールなどの文面では句読点がないと読みにくく感じられるかもしれません。
その場合は句読点の場所にスペースを入れたり、改行などを使ったりして分かりやすくしましょう。
スタンプや絵文字は使わない
訃報LINEに返信する際には、スタンプや絵文字の使用は避けましょう。
スタンプや絵文字は日常会話の中で気軽に使われるもので、たとえ親しい関係性であっても弔事の連絡に使用するのはマナー違反です。
相手からのLINEにスタンプや絵文字が使われていたとしても、受け取った側が返信に使うのは控えてください。
故人には敬称を使う
訃報LINEでは、故人に敬称を使って返信しましょう。
父親は「ご尊父様」、母親は「ご母堂様」など、故人との続き柄によって敬称が異なります。
しかし、少し堅い表現になってしまうので、相手との関係性によっては馴染みのある「お父様」「お母様」や、普段の敬称の方が良いかもしれません。
宗教・宗派ごとの禁句を避ける
訃報LINEの返信では、宗教や宗派によって使ってはいけない言葉にも気を付けましょう。
たとえばキリスト教や神道の場合、お悔やみの言葉として「往生」「冥福」などの仏教用語を使うのは不適切です。
キリスト教は「安らかな眠りをお祈りいたします」、神道は「御霊のご平安をお祈りします」、仏教は「ご冥福をお祈りします」と伝えます。
宗教・宗派が分からないときは、どの宗派でも使える「お悔やみ申し上げます」などの表現を使いましょう。
なるべく短く・簡潔にする
メッセージはなるべく短く簡潔に返信するのも、訃報LINEのマナーです。
LINEでは気軽にやり取りができますが、長文になると受取人も丁寧に返さないといけないプレッシャーを感じてしまうかもしれません。
前置きや時候の挨拶なども不要です。
相手の負担にならないよう、短い文章でまとめましょう。
亡くなった原因を詮索しない
訃報のLINEを受け取った際の返信で、亡くなった原因を尋ねるのはマナー違反です。
どうして亡くなったのか気になる人もいるかもしれませんが、死因に関することはとてもデリケートな話なので、あれこれ詮索するのは失礼にあたります。
相手から亡くなった理由を明かされても、こちらから詳しい内容を尋ねるのは控え、お悔やみを伝えるだけにしてください。
「返信不要」の旨を伝える
訃報LINEを返すときに、返信不要である旨を伝えてください。
遺族は身内を亡くした悲しみの中で、葬儀の準備をしたり、関係者に連絡をしたりしています。
慌ただしい中で返信するのは負担に感じられる可能性があるので、メッセージの最後は「返信は不要です」と締めくくりましょう。
勝手に他人に訃報を知らせない
遺族の許可を得ず、勝手に他の人へ訃報を知らせるのは控えましょう。
訃報を誰に伝えるかは、遺族が決めることです。
「◯◯さんにも伝えておいてほしい」「グループで共有してもらいたい」など頼まれた場合以外は、自分の判断で拡散してはいけません。
相手別|訃報への返信LINEの例文
訃報をLINEで受け取ると「どのように返せば良い?」「みんなはどんなお悔やみの文章を送っているんだろう」と悩んでしまうかもしれません。
どう返信すれば良いのか迷ったときは、例文を参考に考えてみましょう。
ここでは、訃報LINEの返信例文を、相手別に紹介します。
友達
訃報LINEを友達から受け取った場合は、相手との関係性にもよりますが、かしこまった表現で返信しなくてもかまいません。
フランクな言葉遣いでも問題ありませんが、くだけすぎた文章は控えてください。
悩んだときは敬語を入れることで、きちんとした表現になるでしょう。
突然の訃報に接し 心よりお悔やみ申し上げます
何か手伝えることがあれば いつでも声をかけてください
大変だと思いますが どうぞご自愛ください
例文②:もう少し砕けたパターン
突然の訃報に驚いています
〇〇が無理をしていないか心配です
つらいと思いますが どうか体を大切にしてください
本当に大変だったね
つらいときに連絡してくれてありがとう
落ち着いたらお話聞くから いつでも連絡してね
【関連記事】
身内が亡くなった人にLINEでかける言葉丨友達や職場の人に使える例文集
上司・取引先
上司や取引先への訃報LINEの返信は、フォーマルな表現を心がけましょう。
故人の敬称にも気を配り、相手の立場を尊重しながら礼儀正しい文章で返信してください。
葬儀に参列できない場合は、おわびの言葉も添えましょう。
ご尊父様ご逝去の報に接し 心よりお悔やみ申し上げます
略儀ながら まずはLINEにて失礼いたします
大変な時期かと存じますが どうかお体を大切になさってください
ご身内にご不幸があったと伺い 大変驚いております
本来であれば直接ご弔問に伺うべきところ LINEでのご連絡となり申し訳ありません
心より哀悼の意を表します
【関連記事】
「お悔やみ申し上げます」はビジネスシーンでどう伝える?上司・取引先にメールで送る際の例文も紹介
同僚・部下
同僚や部下の場合、忌引きとはいえ、会社を休んでいることを申し訳なく思っている可能性があります。
そのため訃報LINEの返信では、仕事のことは心配しないで良いという旨を伝えましょう。
お母様のご逝去を知り 驚いています
心身ともに大変な時期だと思います
無理しないよう 仕事のことは気にせず休んでください
心よりお悔やみ申し上げます
突然の訃報に接し 心よりお悔やみ申し上げます
仕事のことは心配しなくて大丈夫なので 今は家族との時間を大切にしてください
何かあればフォローするので 遠慮なく言ってくださいね
【関連記事】
お悔やみの言葉の例文集|友人・親戚へのメールやLINEのマナーとは?
グループLINEで訃報連絡があったときの返信例文
複数の友人で会話できるLINEのグループ機能を使って、訃報の連絡が来るケースもあるかもしれません。
個別に連絡が来たときと同様に、返信に配慮が必要です。
それでは最後に、グループLINEで訃報連絡があったときの返信について解説します。
グループLINEで遺族から連絡を受けたとき
グループLINEで遺族から連絡を受けたときは、関係性に応じて例文を参考にしながらお悔やみの言葉を伝えます。
他のメンバーにも通知が行ってしまうので、返信は個別に送るのが良いかもしれません。
グループに参加している人数が多いと、受け取る返信も多くなるため「返信は不要です」などのメッセージを添えましょう。
グループLINEで訃報連絡が回ってきたとき
遺族がいないグループLINEで訃報連絡が回ってきたときは、まず連絡をくれた人にお礼を伝えます。
そしてグループ内で葬儀などへの参列を話し合ったり、偲ぶ会を計画したり、今後の対応について考えましょう。
お葬式のことで遺族へ個別に連絡する場合は「大変なときに申し訳ないのだけれど」など、相手を思いやる一言を添えてください。
訃報LINEへの返信はマナーを押さえて。配慮ある対応を心がけましょう
訃報LINEにはできるだけ早く返信する、なるべく簡潔にまとめるなど、マナーを押さえて対応しましょう。
また、相手によって返信の内容や言葉遣いにも配慮することが大切です。
「何を伝えたら良いのだろう?」「この文面はマナー違反にならない?」と迷ったときは、例文を参考に考えてみてください。
親しい友人にはかしこまった表現にこだわる必要はありませんが、「親しき仲にも礼儀あり」であることを忘れず、相手に寄り添った対応を心がけましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要