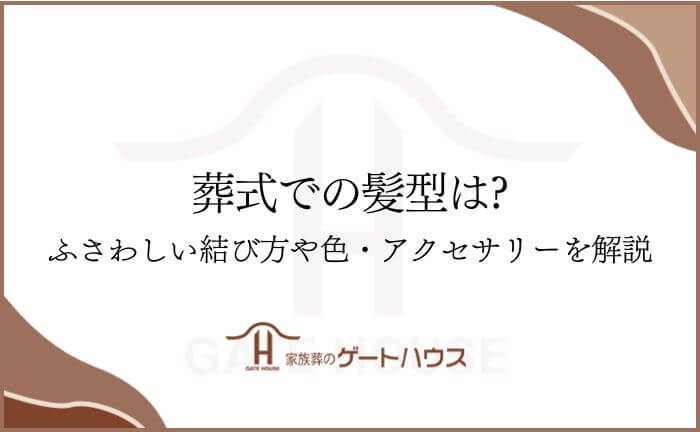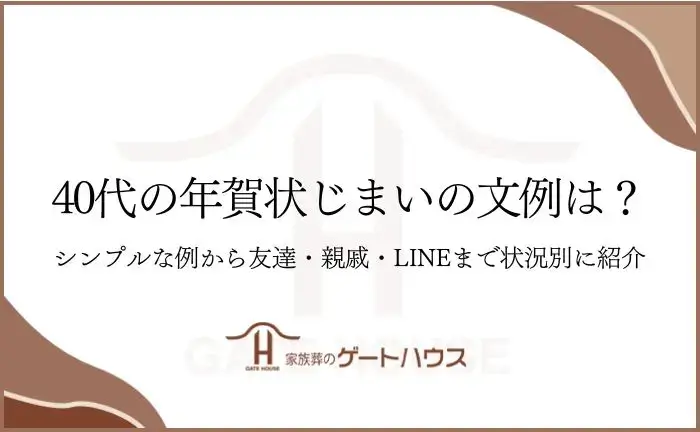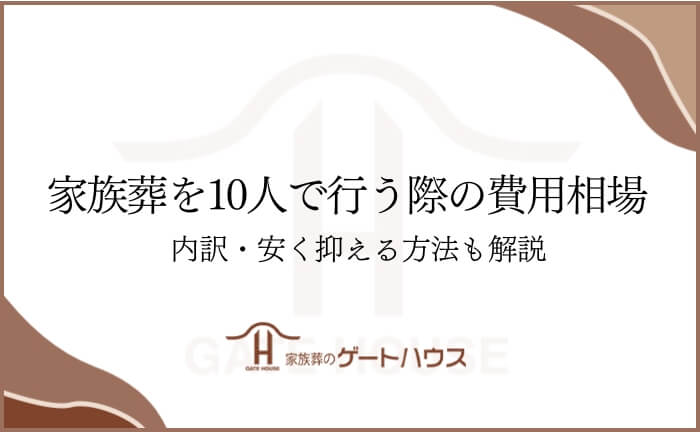曹洞宗の初盆飾りの仕方は?精霊棚(祭壇)の飾り方・お供え物・提灯について解説
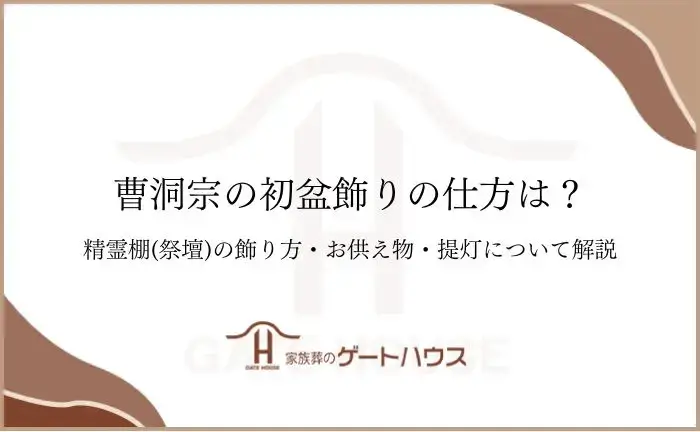
曹洞宗の初盆飾りは、ほかの仏教宗派とは異なる点があります。
きちんと供養するには、精霊棚の飾り方やお供え物、提灯などの用意を前もって行うことが大切です。
この記事では、曹洞宗の初盆を迎えるにあたって準備したいことや段取り、初盆飾りの飾り方などについて詳しく解説します。
曹洞宗における初盆とは
曹洞宗は、坐禅の教えを重んじる仏教宗派です。
施主としてはじめて初盆を迎えるにあたり「通常のお盆と何が違う?」「時期はいつだろう?」など、不安に思う人もいるかもしれません。
まずは、曹洞宗における初盆について解説します。
初盆について
初盆とは、故人が亡くなって四十九日を過ぎた忌明け後に、はじめて迎えるお盆のことです。
初盆は「はつぼん」「ういぼん」と読み、他にも新盆(読み:しんぼん、あらぼん、にいぼん)とも呼ばれています。
お盆は、ご先祖様の霊がこの世に帰ってくると信じられている期間です。
初盆は故人が亡くなってはじめて家に帰ってくる特別な日なので、親戚や親しい友人などを招くのが一般的です。
僧侶による読経や焼香、会食などを行い、通常のお盆よりも手厚く供養します。
【関連記事】
新盆(初盆)とは?やり方は?用意するものやいつ法要を行うか解説
曹洞宗における初盆の時期
曹洞宗における初盆の時期は、新暦盆(8月13日~16日)か、旧暦盆(7月13日~16日)のいずれかです。
どちらの時期に行うかは、地域や寺院によって異なります。
最近では会社や学校の夏休みに合わせて、遠方の人も集まりやすいよう8月に行うケースが多い傾向にあります。
それぞれの風習や考え方によって変わるので、初盆の時期を親族やお寺に確認しておきましょう。
曹洞宗の初盆飾りで必要な物
曹洞宗の初盆飾りは、ほかの仏教宗派と同じ飾り方が多いですが、水の子をお供えするなど独自の作法もあります。
滞りなく初盆を迎えられるように、曹洞宗の初盆飾りで必要な物を確認しておきましょう。
精霊棚(祭壇)
精霊棚とは、お盆の期間中に飾り物やお供え物を置き、ご先祖様の霊を迎える祭壇のことです。
仏壇の前に設置するもので、盆棚ともいいます。
曹洞宗では精霊棚の四方に竹を立てて、周囲をほおずきなどで飾るのが正式な飾り方です。
精霊棚には真菰(まこも)のゴザを敷き、その上に飾り物やお供え物などを置いていきます。
精霊棚や真菰のゴザは、仏具店などで購入可能です。
盆提灯
曹洞宗の初盆飾りとして、盆提灯も用意しましょう。
通常のお盆提灯には華やかな絵柄のものを用意することが多いですが、初盆では白提灯を飾るのが一般的です。
亡くなって近いうちは「清浄無垢」を意味する白い花がたむけられるのと同様に、盆提灯も華美なものを控えるという意味があります。
また、白提灯は、はじめてお盆を迎える故人の霊が、迷わず戻ってこられるよう願いを込めて飾られます。
【関連記事】
新盆(初盆)の提灯は誰が買う?飾り方・選び方やいつから飾るのかを解説
水の子
曹洞宗の初盆では、水の子をお供えします。
水の子はキュウリやナスをさいの目切りにしたものと、洗ったお米を混ぜたものです。
地域によっては、ニンジンを入れることもあります。
曹洞宗を象徴するようなお供え物で、全ての霊をもてなすという考えに基づき、餓鬼道に落ちた無縁仏に対してお供えするものです。
平皿に蓮の葉か里芋の葉を敷いた上に水の子をのせて、精霊棚に飾りましょう。
団子
曹洞宗の初盆飾りには団子も必要で、迎え団子と呼ばれます。
地域によって7個、13個、49個など、数に違いがあります。
なかには故人の年の数だけ団子をお供えする地域もあるようです。
団子の種類は特に決まりがないので、白玉団子やきなこ団子などをお供えしましょう。
曹洞宗の初盆飾り|精霊棚・提灯の飾り方
曹洞宗の初盆飾りは、ほかの仏教宗派と同様の部分もあれば、独自の飾り方をするものもあります。
ここでは曹洞宗のお盆飾りについて、精霊棚の作り方や提灯の飾り方、霊供膳の並べ方を確認してみましょう。
精霊棚(祭壇)の作り方
曹洞宗の精霊棚の飾り方は、以下の通りです。
| 精霊棚の飾り方 |
|
①精霊棚の上に白い布を敷く ②精霊棚の一番奥に釈迦如来をご本尊として安置する (地域によっては十三仏の掛軸も用いる場合もある) ③位牌を御本尊の前に置いて棚の中心になるようにする ④山盛りのご飯を茶碗に盛り、位牌の前に供える ⑤ご飯の周りに故人が好きだった食べ物を供える ⑥精霊馬を置く ⑦盆提灯を精霊棚の両脇に置く ⑧おがらで作った梯子を棚に立てかける場合がある (地域の風習により) ⑨棚の四隅に竹を立て、上に縄を張ってほおずきを吊るす (地域の風習により)
|
精霊棚は、仏壇の前に作るのが一般的です。
おがらで作った7段、もしくは13段の梯子をかけるのは、精霊棚にご先祖様が上がる道具になるとともに、あの世とこの世を結ぶ架け橋になると考えられています。
詳細な飾り方は表を参考にしつつ、菩提寺に相談しながら作りましょう。
盆提灯の置き方
曹洞宗の初盆飾りで、盆提灯は玄関先や軒先などに吊るします。
近年では住宅事情などが変化しており、玄関の内側や仏壇の近く、精霊棚の横など室内に飾るケースも多いようです。
盆提灯は基本的に2対で1組ですが、スペースの関係で1つだけ置く家庭も増えています。
霊供膳(りょうぐぜん)の並べ方
曹洞宗における霊供膳の並べ方は、以下の通りです。
| 霊供膳の並べ方 | |
| 左上 | 平椀 (野菜の煮物用の平たく底の浅い皿) |
| 左下 | 親椀 (山盛りのご飯を盛る皿) |
| 中央 | 壺椀 (酢の物や胡麻和えなどを入れる皿) |
| 右上 | 高坏 (ぬか漬けや梅干しなどを入れる皿) |
| 右下 | 汁椀 (味噌汁・お吸い物を入れる皿) |
霊供膳とは、お盆の期間に帰ってきたご先祖様や故人に頂いてもらう食事のことです。
仏教の不殺生戒の教えに従い、肉や魚を使わない精進料理を用意しましょう。
お盆の期間中は家族も同じものを食べる風習がありましたが、最近では違うメニューにする家庭も増えています。
器の並べ方は宗派によって異なるため、表を参考にしながら置いてください。
曹洞宗の初盆飾り|お供え物
曹洞宗の初盆飾りでは、お供え物も用意します。
仏事のお供え物は「五供(ごく)」が基本です。
ふさわしいお供え物がある一方で、お供えには向かないものもあるので、事前に確認しておきましょう。
代表的なお供え物
曹洞宗の初盆飾りとして代表的なお供え物には、香・花・灯明・浄水・飲食があり、これらを「五供」といいます。
「香」は線香、「花」は生花、「灯明」はロウソクなどの明かりのことで、この3つは「仏の三大供養」と呼ばれ、仏教において最も大切なお供え物です。
「浄水」はお水やお茶、「飲食」はお菓子や果物を意味します。
初盆のお供え物には、故人の好物や日持ちする食べ物、個包装のお菓子やジュースなど、五供に基づいた消費できる品物が代表的です。
【関連記事】
お盆のお供え料理の定番メニューは?置き方・期間・基本マナーも解説
お盆のそうめんの飾り方&意味を解説!いつお供えする?正しい配置は?
お供えに向いていない物
お供えに向いていない物には、肉や魚などの殺生を連想させるもの、日持ちしない生ものなどがあげられます。
また、「五辛(ごしん)」と呼ばれる香りや辛味が強いニラ・ニンニク・ラッキョウ・ネギ・はじかみ(生姜や山椒など)は供えません。
これらは仏教修行を妨げになるとされることから、お供え物にも不向きです。
香りが強い花や、トゲがある植物も控えましょう。
高価な品物をお供えするのも、遺族側に負担をかける可能性があるため避けるべきといわれています。
【関連記事】
初盆(新盆)にやってはいけないことは?言葉遣いや浄土真宗などでタブーな行為を紹介
曹洞宗の初盆で準備すること
故人が亡くなってはじめて迎えるお盆では、通常のお盆より手厚く供養する初盆法要を行います。
僧侶による読経の手配をしたり、特別な準備が必要だったりするため、余裕をもって前月から用意しておくようにしましょう。
ここでは、曹洞宗の初盆飾りで準備することを紹介します。
菩提寺に初盆法要を依頼する
曹洞宗の初盆では、まず菩提寺に初盆法要を依頼します。
お盆は僧侶が忙しくなる時期なので、法要の日程と場所が決まったら、できるだけ早めに連絡しましょう。
初盆法要は自宅に僧侶を招いて読経してもらう場合が多いですが、菩提寺の考え方によっては、その年に初盆を迎える檀家で合同法要が行われることもあります。
どのような形で行うのか分からない場合は、事前にお寺へ確認しておきましょう。
【関連記事】
初盆法要をお寺で行うには?お布施や持ち物など合同法要について解説
仏壇とお墓を掃除する
曹洞宗の初盆を迎えるにあたり、仏壇とお墓を掃除を行います。
仏壇の掃除をするときに雨が降っていると、カビや痛みの原因になるので、できるだけ晴れた日を選んでください。
また、掃除の際に仏具を動かすと、元の位置が分からなくなる可能性もあるため、写真やメモなどで記録を残しておくと安心でしょう。
一方、お墓の掃除で墓石を洗うときは、石の変色を避けるために洗剤などは使わず、柔らかい布やスポンジなどで水洗いします。
お墓の周りに生えている雑草を抜き、可能であれば除草剤などで雑草を対策するのもおすすめです。
【関連記事】
お墓掃除でやってはいけないことは?正しい掃除の仕方・流れについて解説
会食の手配をする
曹洞宗の初盆供養では、集まる人数に応じて会食の手配をします。
会食の場所は、自宅や法要会館、レストランなどが一般的です。
場所によっては、お盆の時期だと予約が埋まりやすいこともあります。
おおよその人数を予測して、遅くとも法要の1ヶ月前までに手配しておきましょう。
初盆の案内連絡をする
法要に参列してもらいたい人へ初盆の案内を連絡しましょう。
参列者には「誰を呼ばなければならない」といった決まりはないので、故人の希望に従ったり、家族と話し合ったりしながら決めてください。
8月のお盆の時期は連休になることが多いため、旅行などの計画を立てる人もいます。
親族であれば法要を予想してくれるかもしれませんが、相手への配慮としてできるだけ早めに連絡することが大切です。
曹洞宗の初盆における供養の流れ
曹洞宗の初盆では、迎え火やお墓参りなどを行い、故人の霊をお迎えして供養します。
ただし、地域や僧侶の考え方によって流れが異なることもあるので、親族や菩提寺に確認しておきましょう。
ここでは、一般的な曹洞宗の初盆における供養の流れについて解説します。
①迎え火を焚く
曹洞宗の初盆では、まず迎え火を焚きます。
迎え火とは、故人の霊が迷わず自宅に帰ってこられるように、目印として焚かれる火のことです。
13日の夕方頃から、麻の皮を剥いて乾燥させたおがらを燃やしてください。
一般的には玄関先や庭先で行いますが、お墓で焚く地域もあります。
【関連記事】
お盆の迎え火・送り火のやり方は?いつやる?マンションでできる代用方法も解説
②お墓参りする
曹洞宗の初盆では、集まった家族や親族でお墓参りをしてください。
お墓には線香や花、故人の好物などを持参して、お供えしましょう。
ただし、飲み物や食べ物はカラスなどが散らかしたり、腐敗して周りを汚してしまったりする可能性があるため、必ず持ち帰ってください。
火事の危険性があるので、ロウソクの火も忘れずに消しましょう。
お墓参りは地域によっては、後述する棚経前に行く場合と、棚経後に行く場合があります。
【関連記事】
新盆はお墓参りだけでも良い?お坊さんを呼ばない場合や持ち物・服装を解説
③棚経を行う
曹洞宗では、初盆で棚経を行います。
棚経とは、僧侶が檀家の自宅を訪問してお経をあげる風習のことで、初盆では精霊棚の前で読経をしてもらいます。
お布施が必要なので、あらかじめ用意しておきましょう。
④送り火を焚く
曹洞宗の初盆では、お盆最終日の夕方や日没後に送り火を焚きます。
送り火は、故人の霊を送り出すために焚くもので、あの世へ迷わず帰れるように願いを込めて行う儀式です。
迎え火と同じように、玄関先や庭先などでおがらを燃やして行いましょう。
地域によって送り火の日が異なることもあるので、分からないときは親族や菩提寺に尋ねてみてください。
【Q&A】曹洞宗の初盆でよくある質問
曹洞宗の初盆を迎えるにあたり「線香は何本あげる?」「お布施はいくら包めば失礼にならない?」などの疑問が浮かんでくるかもしれません。
最後に、曹洞宗の初盆でよくある質問にお答えします。
曹洞宗であげる線香の本数は?
曹洞宗では、線香を1本あげるのが基本です。
線香につけた火を手であおぐか、軽く振って消して、折らずにそのまま香炉へ立てましょう。
線香をあげる本数や置き方は宗派によって異なり、真言宗や天台宗は3本香炉に立て、浄土真宗では1本の線香を2つに折って香炉に寝かせます。
お布施の金額相場と表書きは?
曹洞宗の初盆で用意するお布施の金額相場は、3万~5万円程度です。
表書きは上部中央に「御布施」もしくは「御経料」と記し、その下に施主の名前を書きます。
表書きには薄墨ではなく、濃墨を使用してください。
裏には郵便番号、住所、電話番号、金額を記入しましょう。
お布施以外にも、僧侶に来てもらった際の交通費として「御車代」を5千~1万円、僧侶が法事後の会食に参加しない場合は「御膳料」を5千~1万円ほど、それぞれ包んでください。
初盆法要の服装はどうする?
施主や遺族として曹洞宗の初盆法要を迎える際の服装は、基本的に喪服です。
男性はブラックスーツに黒のネクタイ、女性は黒無地のアンサンブルやワンピースなどのブラックフォーマルを着用しましょう。
子どもは学校の制服があれば着用し、ない場合は白いシャツに黒やネイビー、グレーなどの落ち着いたカラーのボトムスを合わせましょう。
お盆の時期は気温が高くなるため、特に子どもや年配者は体調や暑さに配慮して服装を選んでください。
【関連記事】
初盆(新盆)の服装マナーとは?男性・女性別の着こなし方や注意点を解説
精霊棚が置けないときはどうする?
スペースの関係で、曹洞宗の初盆飾りである精霊棚が置けないこともあるかもしれません。
その場合は、小さな机などで代用したり、仏壇をそのまま利用して飾りつけたりしても問題ありません。
供養において最も大切なのは、ご先祖様に対する気持ちです。
無理のない範囲で準備を行い、心を込めて故人を偲びましょう。
曹洞宗の初盆飾りは、早めの準備で心を込めたご供養を
曹洞宗の初盆飾りには、他の仏教宗派とは異なる作法やお供え物があります。
故人が亡くなって初めて迎えるお盆は、通常のお盆以上に丁寧に供養したいものです。
正しい作法に沿って心を込めた供養ができるよう、早めに準備を始めて、必要なものや段取りを整えておきましょう。
また、地域によって風習が異なる場合もありますので、不安なときは親族や菩提寺に相談しながら進めると安心です。
【その他宗派の初盆についてはこちら】
真言宗の初盆とは?準備するお供え物や行うこと・服装マナーを解説
浄土真宗の初盆の迎え方は?お布施相場やお供え物・仏壇の飾り方など解説
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要