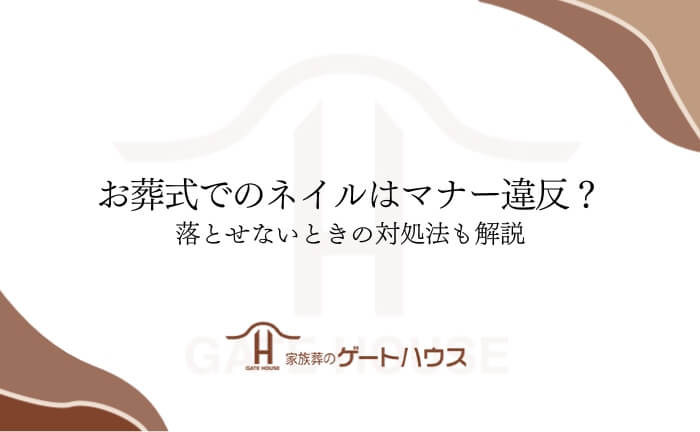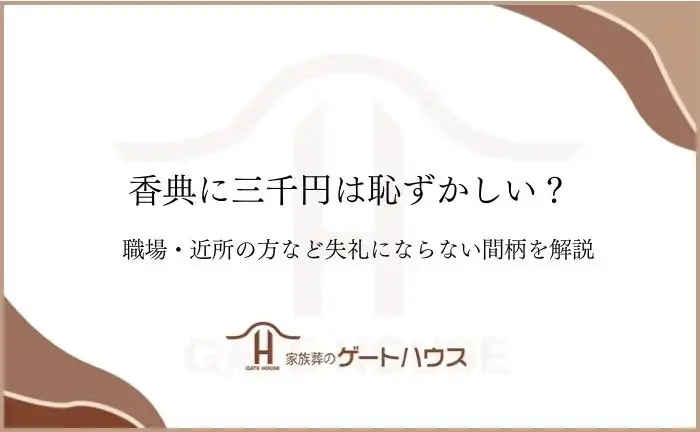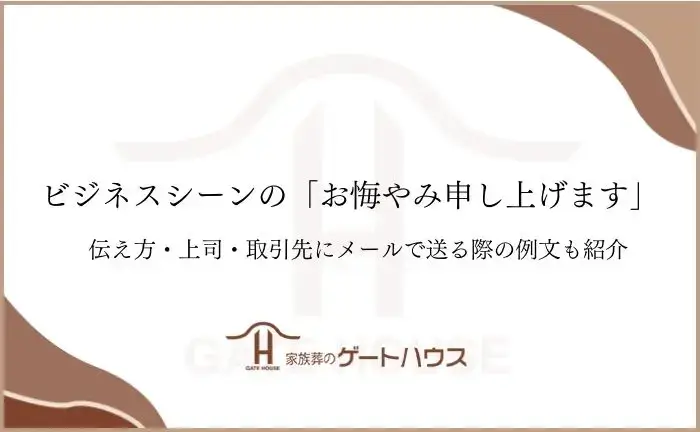葬儀のお花代の相場は?封筒の書き方やお金の入れ方・渡すときのマナーを解説
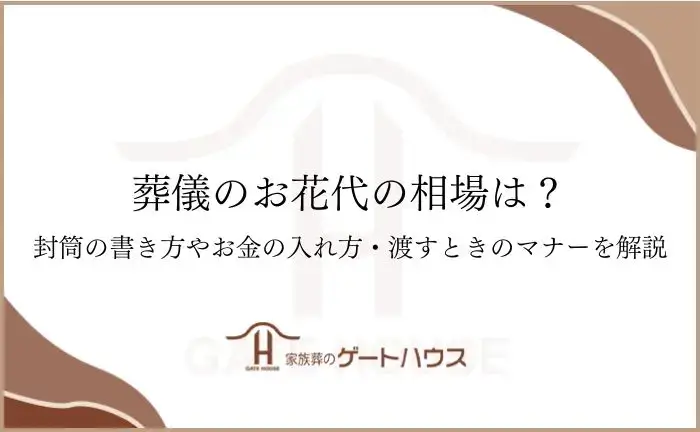
葬儀の際に用意されるお金の1つ「お花代」。
名前は知っているけれど、こちらの役割や意味、関連するマナーなどが分からないという人も多いのではないでしょうか?
この記事では、お花代の概要や相場、書き方・渡し方のマナーについてを解説します。
葬儀のお花代とは?
「お花代」とはお通夜や葬儀の式場、祭壇などにお供えされる花「供花」の代金のことです。
供物として生花や花輪を手配してもらっているとき、葬儀会社にお花を直接注文したときなどに用意するお金で、「供花料(きょうかりょう)」とも呼ばれます。
また「香典の代わり」としてお渡しするケースもあります。
こちらのケースになるのは、葬儀に参列できなかった人が後日「お花代」としてお金を渡した場合や、葬儀の宗派が分からないために香典の表書きを「お花代」にした場合など。
渡し方やシーンによって意味が異なるため少し複雑ですが、基本的には供花の代金と考えると適切に対応できるでしょう。
香典とお花代の違い
香典とお花代の主な違いは意図する用途です。
香典は故人様の霊前に供えする金銭で、遺族への金銭的な支援や葬儀費用のサポートが主な用途となっています。
一方のお花代は供花の代金であるため、用途も供花代金の支払い、供花の購入に限定されます。
弔意を表すという点は同じですが、意図する用途は異なると覚えておきましょう。
また、香典はお通夜・葬儀で渡すものであるのに対し、香典の代わりとしてのお花代は葬儀を終えた後に渡すこともできるなど、渡せるタイミングが異なるのも両者の違いです。
御花料とお花代の違い
お花代と似た言葉に「御花料(おはなりょう)」というものがあります。
この御花料とはキリスト教の葬儀の際に用意されるお金で、仏教の葬儀での香典に相当します。
お花代と字面が似ているため混同してしまいがちですが、意味や用途が異なるためしっかりと区別しておくようにしましょう。
また「御花料」と書かれた封筒を仏教のお葬式で使用すると、マナー違反となるため表書きを書く際や、封筒の購入時には間違えないよう注意してください。
葬儀のお花代の相場はいくら?
次は、葬儀で渡すお花代の相場についてを解説します。
供花の代金として支払う場合、香典の代わりとして支払う場合の両方を解説しているので、金額で迷っている方はぜひ参考にしてみてください。
供花の代金として支払う場合
供花の代金として支払う場合、お花代の相場は1万5千円前後です。
これは、一般的な葬儀で使用される花輪1つが1万5千円ほどだからです。
そのため、お花代を渡す予定であれば、この金額を目安に用意すると良いでしょう。
また、小規模な葬儀で使われる花輪は1万円前後、花籠であれば5千円〜1万5千円とお花のタイプによって若干金額が異なります。
正確な金額を知りたい、金額で迷っている場合は、一度葬儀社や喪主などにお花のタイプや種類を確認することをおすすめします。
香典の代わりとして支払う場合
【香典の相場】
| 両親・兄弟 | 約5万~10万円 |
| その他親族 | 約1万~5万円 |
| 友人・知人 | 約5千~1万円 |
| 職場・取引先 | 約5千~1万円 |
参考:碑文谷創「葬儀概論 四訂」,葬祭ディレクター技能審査協会,2020年4月,171ページ
香典の代わりとして支払う場合のお花代の相場は、香典の相場と同じです。
そのため、いくら包むべきかを迷っている場合は、香典の相場を参考にしましょう。
ここからは故人との関係別の、お花代の相場を解説します。
【関連記事】
家族葬の香典はいつ渡す?参列しない場合の渡し方や金額相場・マナーを解説
香典に三千円は恥ずかしい?職場・近所の方など失礼にならない間柄を解説
香典が2万円なのはおかしい?入れ方や書き方・失礼にならないケースを解説
家族葬に参列しない時の香典の金額相場は?代わりに弔意を示す方法も解説
身内・親族
故人が両親や兄弟のような、関係が深い親族であれば5万〜10万円、その他の親族の場合は1万〜5万円程度が相場となります。
ただし、故人との関係や年齢、地域によって適切な金額が変わるので、相談できる親族がいる場合には一度相談することをおすすめします。
また、兄弟姉妹がいる場合は、事前に相談し同じ額を包むようにするとネガティブな印象を抱かれにくいでしょう。
知人・友人
故人が友人・知人、または職場や取引先関連の人である場合は5千〜1万円が相場です。
地域や風習によっても若干の差はありますが、自身が20代であれば5千円を目安に、30代以上であれば1万円を目安とすると良いでしょう。
また、故人と関係が深い場合や自身の立場によっては、年齢に関わらず1万円以上の金額を包むこともあります。
葬儀のお花代を入れる封筒の書き方や選び方
お花代を入れる封筒、封筒に記載する文字にはいくつかの決まり事があります。
この決まり事を意識せずに準備を進めてしまうとマナー違反となり、相手に不快な思いをさせてしまう可能性もあるので、必ず把握しておきましょう。
次は、お花代を入れる封筒の選び方、正しい書き方を紹介します。
不祝儀袋を使うのが一般的
お花代を入れる封筒・包みは「不祝儀袋(ぶしゅうぎぶくろ)」を使うのが一般的です。
不祝儀袋とは葬儀や法事といった、お悔やみ事・弔事で使用する封筒のこと。
香典用の封筒というイメージが強いですが、お花代もお悔やみ事に関する金銭なので、この不祝儀袋を使います。
水引に関しては1万円〜3万円ほどを包むのであれば、黒白かつ結び目が上に付いた「結び切り」のものを。
1万円以下であれば、封筒に水引が印刷されたものを使うと良いでしょう。
また、不祝儀袋の用意が難しい場合は、無地の白い封筒を使用しても問題ありません。
毛筆・筆ペンを使用し薄墨で記載
不祝儀袋に書く文字は、毛筆・筆ペンを使用するのが基本です。
ボールペンや鉛筆を使っても文字は書けますが、これらを使うとマナー違反となるので必ず毛筆や筆ペンを利用するようにしましょう。
また、お花代や香典で使用する封筒の文字の色は、薄いほうが好まれます。
文字の色が濃いとネガティブな印象を抱かれる可能性があるので、毛筆の場合は墨を水で薄めて作る「薄墨」、筆ペンなら薄墨タイプの商品を使用することをおすすめします。
表書きは「御花代」が無難
お花代に使う不祝儀袋の表書きは「御花代」とするのが無難です。
「お花代」と記載してもとくに問題はありませんが、全てを漢字で書くこちらの表現のほうがより丁寧な印象を与えられます。
また、書く場所に関しては封筒の上部中央、水引の結び目の真上が基本。
文字は縦書きかつ、ひと目で何の封筒なのかが分かるサイズで記載します。
名前は下部中央に記載
名前は封筒の表側の下部中央、水引の結び目の真下に記載します。
記載するのは名字だけでもマナー違反ではありませんが、個人を判別しやすくするためにもフルネームで記載しましょう。
2名での連名の場合は年長者の名前を右側に書きます。
3名以上の連名の場合は「〇〇(団体名など)一同」と書き、封筒の中に全員の名前が書かれた紙を入れます。
また、文字のサイズに関しては「御花代」よりも少し小さな文字で書くとバランスが良くなるので、記入する際はぜひ意識してみてください。
お花代のお金を封筒に包むときの入れ方
封筒の書き方にもいくつかのルールがあるお花代ですが、お金の入れ方や入れるお金にもルールがあります。
こちらも守らないとマナー違反となるため、事前にしっかりと把握しておきましょう。
次は、お花代のお金を封筒に包むときのルールや入れ方についてを解説します。
新札・汚れがひどいお札は避ける
お花代として包むお金は、新札・汚れがひどいお札でないものを使用するのが基本です。
これは不祝儀に使用するお札は、比較的きれいな「旧札」を使うのがマナーであるため。
仮に新札を入れてしまうと「不幸を見越して用意した・不幸を期待した」と思われてしまう可能性があります。
また、あまりにも汚れがひどいお札の場合は、単純に相手を不快にさせてしまうため避けたほうが良いでしょう。
基本的にはきれいな旧札、新札しか用意できない場合は軽く折り目を付けてから入れるようにしてください。
人物が書かれた表側を封筒の下側へ入れる
お花代として包むお金は、人物が書かれているほうが封筒の下側、金額の数字が封筒の上部にくるように入れるのがマナーです。
向きに関しては、お札の表側が封筒の裏側の面にくるようにします。
お金を入れたときにお札と封筒の裏表が逆かつ、人物の絵が下側になっていれば大丈夫です。
お花代はもちろん香典を包む際にも同じ入れ方をするので、葬儀に参列する予定の人はぜひ覚えておきましょう。
お葬式におけるお花代の渡し方のマナー
お葬式における、お花代の渡し方にもいくつかのマナーがあります。
基本的なものは以下の4つ。
- 遺族が香典や供物を辞退している場合は渡さない
- 葬儀会社に供花を依頼した場合は、葬儀会社に払う
- 喪主が供花を立て替えている場合は、喪主に行き渡るように渡す
- お花代と香典は別々に包む
ほかにも、渡す相手やシーンごとにマナーがあるので、失礼なく渡すためにもぜひ覚えておきましょう。
最後に、お葬式におけるお花代の渡し方のマナーを渡す相手やシーン別に紹介します。
直接手渡す場合
お花代を渡す方法としては手渡しが一般的です。
家族や親族として参加するのか、一般参列者として参加するのかによってマナーが異なります。
ここからは、家族・親族に手渡す場合、一般参列者として手渡す場合のマナーを解説します。
家族・親族の場合
家族・親族の場合は、故人や喪主、遺族との関係によって渡し方が異なります。
葬儀の打ち合わせに参加する、よく顔を合わせるほどの親しい関係であれば、葬儀以外のタイミングで封筒に包まず、直接渡しても良いでしょう。
あまり関係性が深くないのであれば不祝儀袋を使い、顔を合わせたときや葬儀の前後などに渡すのがマナーです。
一般参列者の場合
一般参列者として参加する場合は、葬儀会場の受付で手渡すのが基本です。
会場によってはお花代の受付が別のところに設けられている場合もあるため、どこで渡せば良いか迷った場合には、葬儀場のスタッフや受付に尋ねるようにしましょう。
お金に関しては、不祝儀袋に入れてから渡すのがマナーです。
また、遺族に直接渡したい場合は、葬儀の最中は避けるようにし、式の前や終了後などに渡すようにしましょう。
郵送する場合
お花代を郵送する場合は一度お金を不祝儀袋に入れ、その不祝儀袋をゆうゆう窓口や郵便局で購入した「現金書留封筒」に入れてから送ります。
このとき、不祝儀袋を使わず、現金書留封筒のみで送ってしまうとマナー違反となるので注意しましょう。
また、郵送する際は、メッセージを添えるのがマナーです。
内容に関してはお悔やみの言葉や故人との思い出、遺族を気遣う言葉を、あまり長くならないよう端的な表現で記載すると良いでしょう。
お花代が届く時期は、葬儀・告別式が終わってから1週間〜1ヶ月の間に設定するのが基本です。
葬儀のお花代にもマナーがある。失礼に当たらないよう事前に確認を
葬儀のお花代には封筒の書き方やお金の入れ方、渡し方などに関するマナーがあります。
香典と共通する部分も多いですが、渡し方や金額のように異なる部分がいくつかあるので、失礼に当たらないようにするためにも事前に確認しておきましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要