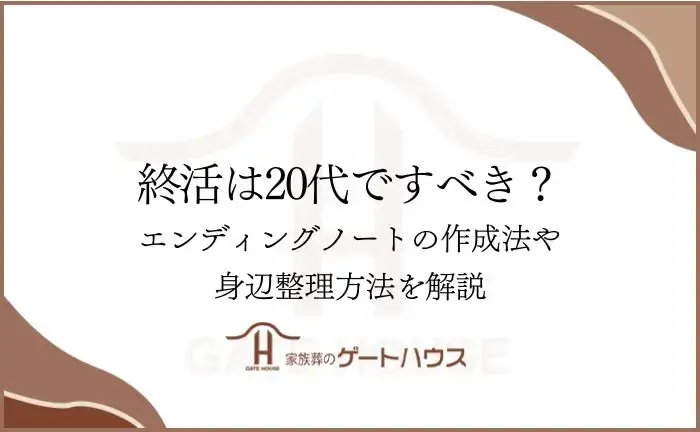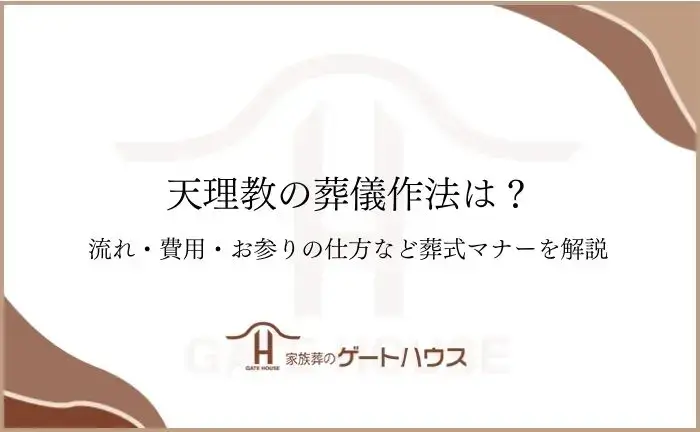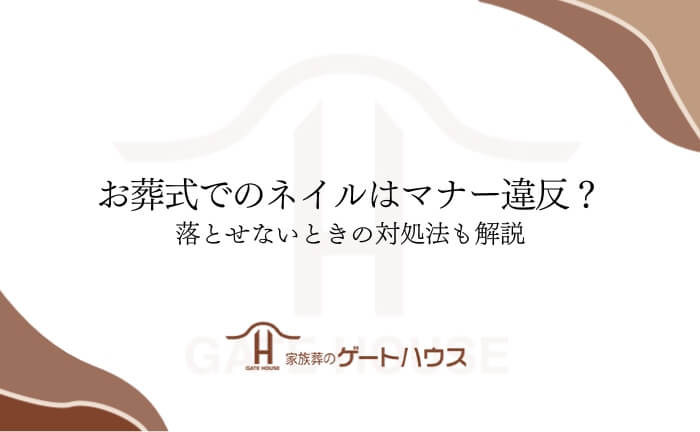葬祭扶助とは?生活保護の受給が条件?申請方法や制度の流れを解説

経済的に困窮している方に葬儀費用を支給する制度「葬祭扶助」。
制度の存在は知っているけれど、その概要や流れ、受給条件などがよく分からないという方も多いのではないでしょうか?
この記事では、葬祭扶助の概要や申請方法、制度利用の流れを解説します。
葬祭扶助とはどんな制度?
葬祭扶助とは、扶養義務者(配偶者、父母、祖父母、子、孫など)が葬儀費用を捻出するのが難しい場合に、必要最低限の葬儀費用を自治体が支給する制度です。
生活保護法第18条に基づいた制度で、これを利用すれば生活保護を受給している方、経済的に困窮している方でも問題なく葬儀を執り行えます。
申請に関しては、申請者の住民票がある自治体の福祉事務所に行うのが一般的です。
また、この制度を利用した葬儀のことを「福祉葬(生活保護葬)」と呼びます。
葬祭扶助の基準額|支払われる金額はいくら?
葬祭扶助の基準額は「大人209,000円以内・子ども(12歳未満)167,200円以内」です。
実際の金額は自治体によって異なりますが、おおよそ基準程度の金額が支払われると考えておくとスムーズに物事を進められるでしょう。
ただし、この金額には告別式やお通夜の費用、お布施などの費用は含まれていません。
そのため葬儀形式は必然的に、短時間のお別れと火葬、収骨を行う「直葬(火葬式)」となります。
また、故人に預貯金があるケースでは、不足分のみの支給が基本です。
仮に葬儀費用をまかなえる額の預貯金があった場合には、葬祭扶助は受けられません。
【関連記事】
葬祭扶助の条件とは?生活保護の受給は必須?
【条件】
- 遺族の方が生活保護受給者などで困窮している
- 扶養義務者がおらず遺族以外の方が葬儀を執り行う
※どちらかを満たしていれば申請可能
葬祭扶助を利用するための条件は上記の通りです。
ここからは、それぞれの条件の詳細を解説します。
葬祭扶助の利用を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
遺族の方が生活保護受給者などで困窮している
葬祭扶助の条件の1つ目が「遺族の方が生活保護受給者などで困窮している」ことです。
「生活保護受給者など」となっているのは、「生活保護は受けていないけれど生活に困窮している方」も対象になっているため。
つまり、生活保護を受給している方はもちろん、受給されていない方でも申請が通りさえすれば制度を利用できるのです。
制度自体は生活保護の一部ではありますが、受給は必須ではないと覚えておきましょう。
扶養義務者がおらず遺族以外の方が葬儀を執り行う
「扶養義務者がおらず、遺族以外の方が葬儀を執り行う」場合も、葬祭扶助の対象となります。
遺族以外の方とは、近隣住民や民生委員、病院関係者、家主、知人などの第三者のこと。
この第三者が、存在しない扶養義務者に代わって葬儀を執行する場合には、葬祭扶助制度を利用できます。
条件さえ満たせば、申請者や故人の経済状況に関係なく利用できるのも特徴です。
ただし、1つ目の条件と同様に、故人様に多少の預貯金や資産がある場合は、不足分のみの支給となります。
葬祭扶助の申請方法|制度の流れ
条件の次は、葬祭扶助の申請方法と制度の流れを解説します。
どうやって手続きを進めるのかが分からない、申請に不安を感じている方は、ぜひ参考にされてみてください。
申請条件を満たすか確認する
葬祭扶助を利用すると決めたら、まずは自身が申請条件を満たしているかを確認しましょう。
条件は「生活保護受給者・生活困窮者」または「扶養義務者ではない第三者」のいずれかです。
これらの条件に該当する場合は、申請を受け付けてもらえます。
余裕があるなら、預貯金や資産の状況を整理しておくと、今後の手続きをスムーズに進められるでしょう。
葬儀社を選ぶ
条件の確認の次は、次は葬儀社を選ぶステップです。
もう少し後でも問題はありません「葬祭扶助申請を代行してもらえる」「葬儀準備の負担を減らせる」など多くのメリットがあるので、早めに実施しましょう。
選ぶ際のポイントは、葬祭扶助を利用した福祉葬に対応した葬儀社を選ぶことです。
対応していない業者を選ぶと、後々トラブルに発展する可能性があるため、福祉葬に対応している葬儀社を選んでください。
また、相談する際には、福祉葬を執り行いたい旨を必ず伝えましょう。
【関連記事】
葬儀社の選び方のポイント丨失敗しないための決め方や気をつけることを解説
亡くなられる
故人様が亡くなられたらご遺体の搬送を依頼するために、前のステップで選んだ葬儀社に連絡をします。
その後、その葬儀社によって自宅または安置所にご遺体が運ばれます。
葬儀社選びが済んでいない場合は、自治体から紹介された葬儀社に搬送を依頼することがほとんどです。
自治体の福祉事務所へ連絡する
ご遺体の搬送が済んだタイミング、または葬儀社に連絡した直後に、自治体への連絡を行います。
具体的な連絡場所は「葬儀を執り行う遺族(喪主)の住民票がある自治体の福祉事務所(福祉課)」。
連絡する内容は、葬祭扶助を利用したいことと自身の経済状況、現状などについてです。
また、今後の手続きや進め方などの相談にものってくれるので、不安がある場合はこのタイミングで解決しておきましょう。
葬祭扶助を申請する
【提出書類例】
- 遺族の方の収入証明書
- 故人の死亡診断書
- 遺族の戸籍謄本
※自治体により異なる場合があるため確認してください
自治体の福祉事務所への連絡が済んだら、次は葬祭扶助を申請するステップです。
福祉事務所の窓口に、上記の必要書類を用意した上で向かい、申請手続きを行います。
葬儀社に申請の代行を依頼している場合は、担当者が代わりに申請を進めてくれます。
その後、ケースワーカーや民生委員による審査と調査が実施され、問題がないようであれば葬祭扶助制度を利用することが認められ、手続きは完了です。
申請のタイミングは葬儀前と決まっているので、必ず葬儀の執行前に行いましょう。
葬儀の執行
葬祭扶助制度を利用した福祉葬が認められたのちに、葬儀が執り行われます。
福祉葬では家族や少数の友人のみが参列し、火葬のみを執行する「直葬(火葬式)」が実施されます。
そして、火葬が終了したら遺骨を拾い、それを骨壺に収める「収骨」を行い、葬儀は終了となります。
自治体により葬祭費用の支払いが行われる
福祉葬が終わると、自治体による葬祭費用の支払いが行われます。
この支払いは、基本的に葬儀会社に直接行われるため、喪主の手元にお金が渡ることはありません。
納骨に関しては葬祭扶助の対象外となるため、永代供養や納骨堂、散骨のような有料の方法、もしくは自宅で保管する方法のいずれかを選ぶことになります。
葬祭扶助制度に関するよくある質問
葬祭扶助の申請方法や流れ、条件については分かったけれど、疑問点がいくつか残っているという方も多いのではないでしょうか?
頻繁に利用する制度ではないので、一度の説明で全てを把握することは難しいですよね。
最後に、葬祭扶助制度に関するよくある質問とその回答を紹介します。
葬祭扶助はいつまで申請できる?
葬祭扶助は、葬儀を執り行う前までに申請するのが原則です。
そもそも葬祭扶助は、葬儀前の申請を前提としたシステムになっています。
葬儀が終わったあとの申請は、費用を払う能力があったと判断されてしまうため、基本的に受理してもらえません。
そのため、この制度を利用したいなら、葬儀を執り行う前までに申請を済ませましょう。
また、いざというときに正しく動けるか不安な場合には、事前にケースワーカーや自治体に相談し、不安を解決しておくと良いでしょう。
葬祭扶助は生活保護受給者じゃないと申請できないの?
葬祭扶助は、生活保護受給者でなくとも申請できます。
生活保護制度は、8つの扶助から成り立っており、その内の1つだけを受給する「単給」も認められています。
「経済的に困窮している」という条件さえ満たしていれば、生活保護の扶助の1つである「葬祭扶助」のみを申請することも可能なのです。
申請が通るかどうかは状況にもよりますが、生活が苦しくて葬儀費用をまかなえないときには、一度自治体に相談してみることをおすすめします。
葬祭扶助を受けても香典はもらっていい?
葬祭扶助を利用している場合であっても、香典は受け取って大丈夫です。
香典は役所への報告義務があるものではなく、さらに所得税や贈与税の対象となるものでもありません。
そのため、葬祭扶助を受けていても、受け取ることができます。
しかし、香典返しの費用は自己負担となるため、受け取るかどうかは慎重に考えましょう。
葬祭扶助とは葬儀による経済的な負担を軽くする制度。自分が申請できるか確認を
葬祭扶助とは、葬儀の執行に関する経済的な負担を軽くするための制度です。
ご自身の負担を軽減するのはもちろん、故人様の尊厳を守ることにも役立つので、大まかにでも制度の概要や流れを把握しておくようにしましょう。
利用を考えている方は、自分が申請できるか確認するところから始めることをおすすめです。
申請できそうな場合は、ご自身の負担を減らし、不安を解決するためにも、早めに葬儀会社や自治体に相談するようにしてください。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要