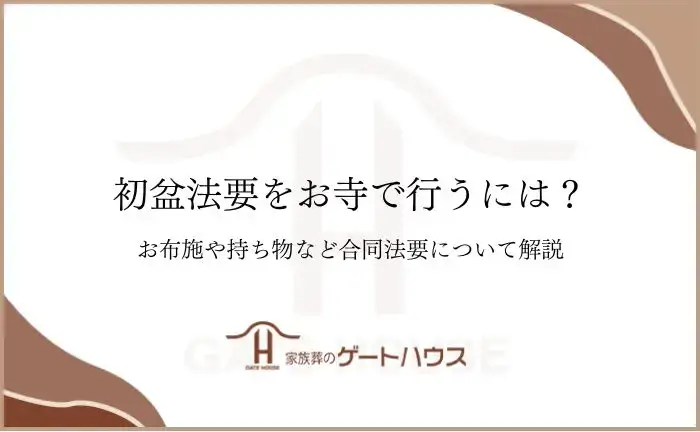お布施とは?金額の相場やお金の入れ方・渡し方のマナーを徹底解説

葬儀や法要などの際に、僧侶に渡すお布施。
しかし、包むときに「相場はどれくらいなんだろう?」「そもそもお布施とは何のためにあるの?」など、さまざまな疑問が浮かんでくるかもしれません。
この記事ではお布施について、金額の相場や渡し方などのマナーについて解説します。
お布施とは?意味や由来を解説
お布施とは、葬儀や法要、法事などの際に、戒名の授与や読経などを執り行ってくれた僧侶に渡す金銭のことです。
お布施には「施しを与える」という意味があり、仏教では修行の一環とされています。
お布施とは僧侶への報酬ではなく、仏様を供養するために自分の意志で行うものなのです。
包む金額に決まりはなく、悩んだときは直接お寺に尋ねても失礼にはあたりません。
「お気持ちで」という回答だったり、聞きにくかったりする場合は、葬儀をあげたことがある親族や、葬式を依頼する葬儀社などに相談してみましょう。
お布施の由来・歴史
「お布施」の由来は「六波羅蜜(ろくはらみつ)」という、僧侶の修行です。
六波羅蜜には6つの修行にあたる徳目があり、この徳目のうちの1つに「布施(ふせ)」があります。
布施には分け与えるという意味があり、さらに「法施(ほうせ)」「財施(ざいせ)」「無畏施(むいせ)」の3つに分けられます。
法施は仏法を説き人々の心を救うこと、財施は金品などを施すこと、無畏施は困った人に手を差し伸べて不安や恐れを取り除く行いのことです。
読経してもらった謝礼としてのお布施は財施にあたり、やがて総じてお布施とよばれるようになりました。
お布施の金額の相場とは?いくら包めばいい?
お布施の金額に決まりはないものの、おおよその相場を目安にすることはできます。
一般的に、葬儀や告別式は、法要より相場が高い傾向があるでしょう。
地域や宗派などによっても変わりますが、迷ったときは相場金額を参考にしてみてください。
【お布施金額の相場早見表】
| 弔事 | お布施金額の相場 |
| 葬儀・告別式 | 10万円~50万円 |
| 四十九日法要 | 3万円〜5万円 |
| 納骨法要 | 3万〜5万円 |
| 新盆・初盆法要 | 3万〜5万円 |
| 一周忌法要 | 3万〜5万円 |
| 三回忌以降 | 1万〜5万円 |
葬儀・告別式
葬儀・告別式の金額相場は10万〜50万円といわれています。
葬儀は僧侶による読経や焼香、戒名授与などを行うことで、故人の死を弔い、冥福を祈る儀式です。
告別式では焼香や献花、弔辞などを行い、故人に感謝を伝え最期のお別れを告げます。
葬儀と告別式は同時に執り行われることが多いため、お布施として包む金額も高くなる傾向があるでしょう。
戒名のランクや地域、宗派などによっても異なるので、不安な場合はお寺に尋ねてみてください。
四十九日法要
四十九日法要のお布施相場は、3万円〜5万円です。
葬儀・告別式の際に包んだお布施の10%〜20%を目安にするという考え方もあります。
故人が亡くなって49日目に執り行われる法要で、極楽浄土に行けるかどうかが決まる大切な日です。
四十九日法要は親族や友人を招き、僧侶による読経や供養が行われます。
浄土真宗においては、亡くなった人はすぐに成仏すると考えられているため、四十九日は故人を偲ぶ日としたり、四十九日法要自体を執り行わなかったりするケースもあるでしょう。
納骨法要
納骨法要で包むお布施の金額相場は、3万円〜5万円です。
納骨法要は納骨式ともよばれ、故人の遺骨をお墓や納骨堂に納める儀式のことで、僧侶による読経が行われます。
納骨をする時期に明確な決まりはありませんが、四十九日を迎えたタイミングで行われるケースが多いようです。
代々続く旧家のお墓に納骨したり、新しくお墓を購入して開眼供養をしたりする場合は10万円ほど包むこともあるでしょう。
新盆・初盆法要
新盆・初盆法要でのお布施にかかる費用は、3万円〜5万円が目安です。
故人が亡くなって初めて迎えるお盆を新盆や初盆とよび、僧侶による読経や供養が行われたあと、親族や親しい友人などで会食します。
通常のお盆より、お布施に包む金額は高くなるでしょう。
お盆の時期は8月13日〜16日ですが、7月の地域もあります。
また四十九日の前にお盆が来る場合は、次の年に新盆・初盆法要を行うケースもあるため、確認しておきましょう。
一周忌法要
一周忌法要のお布施金額は、3万円〜5万円が相場とされています。
故人が亡くなって最初の命日に行われる一周忌法要は、喪明けを迎える大切な儀式です。
親族や親しい友人などを招き、僧侶による読経や供養が行われたあとに会食をします。
法要の規模は、故人や家族の意向で決めてかまいません。
命日の日に法要を執り行うことができない場合は、後ろ倒しではなく、命日の前に行うようにしましょう。
三回忌以降
三周忌以降の法要は、お布施の相場が1万〜5万円ほどになります。
三周忌以降も僧侶を招き、読経や供養を行いましょう。
一般的に葬儀や告別式から近い法要はお布施が高く、時間の経過とともに相場が下がっていく傾向があります。
年忌法要は七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十五回忌、三十三回忌と続き、三十三回忌を年忌明けとして最後の法要にするケースが多いです。
お布施の包み方
僧侶にお布施を渡す際に「どうやって包んだら良いんだろう?」「正しい礼儀作法が知りたい」と思う人も多いのではないでしょうか?
最も大切なのは気持ちですが、感謝を伝えるためにも、細かなマナーまで心得ておきたいものです。
ここでは、お布施の包み方について解説します。
お布施に使う袋
お布施には、いずれかの袋を使いましょう。
- 半紙・奉書紙
- 白い封筒
- 水引の色と結び方が適したのし袋
お布施は半紙で現金を包んだ中包みを作り、中包みを奉書紙で包むのが正式な方法です。
奉書紙は古来より伝統的に用いられてきた和紙なので、僧侶に対して感謝の気持ちを最大限に伝えられるでしょう。
奉書紙の代わりとして、白い封筒やのし袋も使えます。
封筒は、郵便番号を記載する欄など、余計な印字がない白無地のものを選びましょう。
お布施に水引は不要ですが、水引の色が白黒や双銀などで、淡路結びや結び切りの不祝儀袋であれば使用可能です。
二重封筒はNG
お布施に使う袋として、二重封筒はマナー違反になります。
二重のものは不幸が重なることを連想させるので、使わないようにしましょう。
薄手の白い封筒もありますが、中身のお札が透けて見えてしまうかもしれません。
半紙でお金を包んでから封筒に入れたり、厚手の封筒を選んだりすると安心です。
新札を包む
お布施には新札を包むようにしましょう。
新札を使うのは、感謝の気持ちを表す心遣いやマナーです。
お布施は僧侶に謝礼として渡すことが決まっているため、新札を用意しておくべきとされています。
どうしても準備できない場合は、できるだけきれいなお札を使うようにしてください。
一方、香典に新札を包むと不幸を予期していたと受け取られる可能性があるので、古いお札を使うのがマナーです。
【関連記事】
香典は新札でもいい?ピン札しかない時の対処法やお札に関するマナーを解説
お札は「表側・上向き」で入れる
お布施を包むときは、お札が表側・上向きになるように揃えて入れてください。
お札の向きは、お布施袋の表側に肖像画が見えるように入れましょう。
このとき肖像画の位置は、お布施袋の口側にくるようにしてください。
お札の角が揃っていると、より丁寧な印象を与えるでしょう。
ちなみに、香典の場合は故人の死を悼むように、肖像画が裏側・下向きになるように包むのがマナーです。
【関連記事】
香典袋への5000円の入れ方は?中袋なし・あり別の不祝儀袋の書き方も解説
袱紗に包む
お布施袋をそのまま手渡すのはマナー違反です。
僧侶に渡すまでは、袱紗に包んで持ち歩きましょう。
弔事に用いる袱紗は、紺や灰色、紫などのダークカラーで、無地のものを選びます。
袱紗に包むときは、まず袱紗がひし形になるように角を上にして広げ、中央よりやや右寄りにお布施袋を置いてください。
そして中央に向かって右側を折り、次に下側を持ち上げるように折って、続いて上側を下に向かって折ります。
最後に左側の角を右にもっていき、あまった部分は裏に折り返しましょう。
お布施の書き方
お布施は僧侶に感謝を伝えるものなので、薄墨ではなく黒墨で書きましょう。
ここではお布施の書き方について、表書きと裏書それぞれのマナーについて紹介します。
表書きの書き方
お布施の表書きは、奉書紙もしくは白い封筒の正面中央上部に「お布施」もしくは「御布施」と書きます。
あらかじめ印刷されている封筒を使う場合は記入しません。
その下には、喪主の名前を書きます。
フルネームでも、名字のみでもかまいませんが、はじめて葬儀をお願いする場合はフルネームの方が良いでしょう。
「〇〇(名字)家」と記入することもできますが、その場合には裏書に喪主の名前をフルネームで記してください。
ただし、地域によって書き方が異なるため、迷った場合はしきたりに従うようにしましょう。
裏書の書き方
中袋を使わない場合は、お布施の裏書に金額や喪主の名前などを記しましょう。
一般的には裏面の右上に金額、左下に郵便番号、住所、名前、電話番号を書きます。
番地や番号などの数字を記入する際は、漢数字を使ってください。
金額には旧字体を使い「金〇〇圓也」のように記入します。
旧字体の漢数字は「壱(一)」「弐(二)」「参(三)」「伍(五)」「萬(万)」などで、たとえば3万円を包むときは「金参萬圓也」と書いてください。
お布施の渡し方と渡すタイミング
「お布施はいつ渡せばいいの?」「どうやって渡すのがマナー?」など、お布施の渡し方について悩む人もいるのではないでしょうか。
失礼な印象を与えないためにも、渡し方のマナーについても心得ておきたいですね。
お盆に乗せる
僧侶にお布施を渡すときは、お盆に乗せてください。
慶弔両用で使われる切手盆という黒塗りのお盆に乗せて、お布施の表書きが僧侶の正面を向くように渡しましょう。
僧侶がお布施を受け取ったら、お盆をさげてください。
お布施はお盆に乗せて渡す直前まで、袱紗に包んでおきましょう。
お盆がない場合は、お布施を袱紗の上に乗せる形で差し出します。
慣れない作法に慌ててしまうかもしれませんが、ひとつひとつの動きをゆっくり丁寧に行うように意識してみてくださいね。
挨拶の言葉を添える
お布施をお盆に乗せて渡す際に、挨拶の言葉を添えましょう。
挨拶の文言などに決まりはありません。
「この度の葬儀ではお世話になります。よろしくお願いいたします」「無事に葬儀を執り行うことができました。ありがとうございました」など、簡単な内容で良いので、お世話になることへの感謝の気持ちを込めて挨拶してください。
通夜の閉式後の挨拶のタイミングで渡す
お布施を渡すタイミングにはっきりとした決まりはありませんが、葬儀のときは通夜の閉式後の挨拶で渡すとスマートです。
葬儀の前はなにかと慌ただしく、挨拶の時間がとれないこともあります。
法事が終わり、落ち着いたタイミングを見計らって渡しましょう。
僧侶が複数人いる場合は、最も地位の高い方に渡してください。
お布施以外に僧侶に渡すお金
お布施以外に僧侶に渡すお金として、お車代と御膳料があります。
表書きにはそれぞれ「御車料」「御膳料」と記し、その下に喪主の名前を書きましょう。
ここでは、それぞれを渡す目的や金額相場について解説します。
お車代
お車代とは、僧侶の交通費として渡すものです。
僧侶が自家用車やタクシー、電車、バスなどで会場に来てくれたときに渡します。
一般的な相場は5千円~1万円ほどです。
遠方から新幹線などで来てもらったり、宿泊を伴ったりするときは、実費を考慮したうえで包んでください。
遺族が車で送迎したり、手配したタクシーに乗ってもらったり、会場がお寺で交通費が発生しない場合などは、用意しなくてかまいません。
しかし、地域や親族の方針によっては交通費の有無に関わらず、必ず渡すのが良しとされていることもあるため、事前に確認しておきましょう。
お車代はお布施と同じタイミングで、お布施が入った封筒の下に重ねて渡してください。
御膳料
御膳料とは、僧侶の会食費用にあたります。
葬儀や法要が終わったら、僧侶や参列者を招いて会食するのが一般的です。
僧侶が会食を辞退する際に、おもてなしの代わりとして、料理に見合った額を渡してください。
会場が自宅や斎場の場合は5千円〜1万円程度、料亭やホテルなどの場合は1万円〜2万円程度が相場です。
僧侶が複数人の場合は、人数分の金額を1つの封筒に包んで渡しましょう。
渡すときはお車代と同じく、お布施の下に重ねてお盆に乗せてください。
このとき、お車代と御前料の順番に決まりはありません。
お布施に関するよくある質問
お布施については細かな礼儀作法があるため、特にはじめて渡すときは失礼にあたらないか不安になることが多いでしょう。
最後に、お布施に関するよくある質問について解説します。
お布施を渡す時の挨拶の例文を教えてほしい
僧侶にお布施を渡すとき、どのように挨拶を添えるのか、不安な方も多いでしょう。
葬儀前に渡す場合は「本日はどうぞよろしくお願いいたします」「遠方からお越しいただきありがとうございます」などの挨拶が一般的です。
葬儀後に渡すときは「本日は大変お世話になりました」「お心のこもったおつとめをありがとうございました」など、お礼の言葉を簡潔に伝えましょう。
お布施を入れる封筒はコンビニでも買える?
お布施を入れる白い封筒は、コンビニでも購入可能です。
ほかにもスーパーやホームセンター、文具店、100円ショップなどでも販売されています。
お布施だけでなく、お車代や御前料を包むこともあるので、複数枚買っておくと良いでしょう。
どうしても準備する余裕がない場合は、葬儀社が用意してくれるケースもあるので、困ったときは相談してみてください。
お布施ってどのタイミングで渡せばいいの?
お布施を渡すタイミングに明確な決まりはありませんが、葬儀や法要が終わったタイミングがおすすめです。
たとえば通夜の開式前に渡してしまうと、僧侶は控室などに大金を置いたまま読経しなければなりません。
そのため葬儀や法要が終わってお寺に戻られる前に、お礼の言葉とともにお布施を渡すのが望ましいでしょう。
すでにお寺との関係ができていたり、何らかの事情で当日にお布施を渡せなかったりする場合は、後日お寺に出向いて渡してもかまいません。
「あらためてお寺にお持ちします」など伝えておくと、僧侶にも安心してもらえるはずですよ。
お布施で渡してはいけない金額はいくらですか?
お布施において、渡してはいけない金額はないとされています。
ご祝儀では2万円などの割り切れる数字、お香典では「四(死)」や「九(苦)」などの数字を避けるのがマナーです。
しかしお布施では、偶数や不吉とされる数字を包んでも問題ないといわれています。
ただし、1万500円などの中途半端に小銭が含まれる金額は避け、最低でも千円単位で包むようにしてください。
【関連記事】
香典で包んではいけない金額とは?料金相場や包み方・書き方のマナーも解説
お布施とは僧侶に渡す金銭のこと。弔事ごとに金額の相場が違うのでご注意を
お布施とは、葬儀や法要の際に僧侶に渡す金銭を指します。
包む金額に明確な決まりはありませんが、弔事ごとに金額の相場が違うので、迷ったときには親族や葬儀を依頼する葬儀社などに相談してみましょう。
葬儀は宗教的な儀式であるため、お布施に関しても包み方や渡し方などのマナーがあります。
普段の生活ではあまり知る機会がないかもしれませんが、しきたりや作法を心得たうえで、感謝の気持ちを伝えたいですね。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要