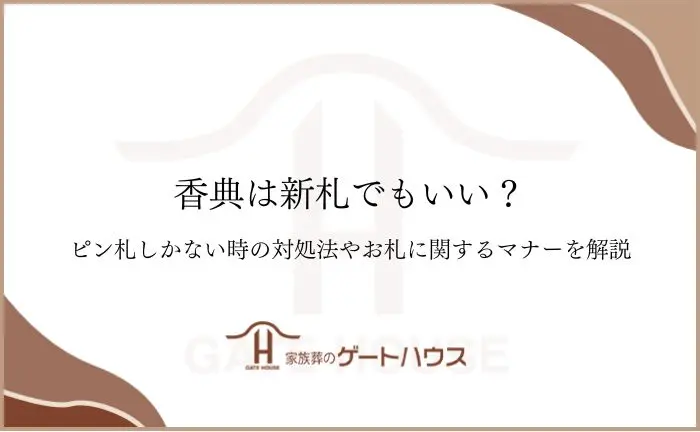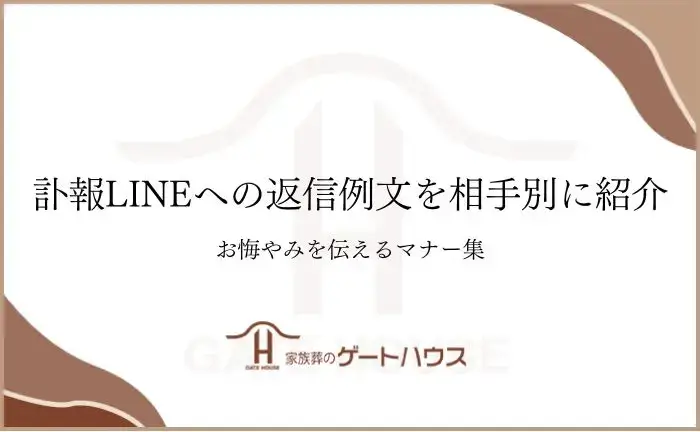精進落としとは?意味・マナー・当日の流れと挨拶例文を解説
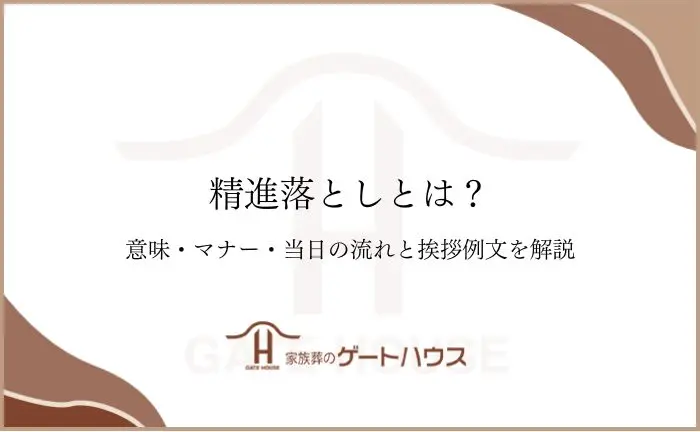
精進落としは、かつては忌明けに行われる食事でしたが、現在では初七日法要や火葬後に行われるようになりました。
葬儀だけでなく、精進落としにも独特のマナーや挨拶の仕方があるので、事前に理解しておく必要があります。
本記事では、精進落としの意味やマナー、当日の流れなどを紹介します。
精進落としの挨拶でそのまま使える例文もあるので、ぜひ参考にしてください。
精進落としとは
精進落としは本来仏教の教えに基づく慣習で、忌明けに行われる食事でした。
しかし現代では、葬儀当日の火葬後に参列者にふるまう食事へと変化しています。
精進落としの位置づけの変遷や、通夜振る舞いとの違い、仏教以外の宗教での習慣を紹介します。
精進落としの本来の意味と現代の位置づけ
精進落としとは、葬儀に参列してくれた人や僧侶をねぎらうために、葬儀の後に行われる会食です。
かつて多くの仏教宗派では、亡くなってからの四十九日間は、肉・魚を使わず植物由来の食材のみを使った精進料理を食べる習慣がありました。
四十九日の忌が明け、精進料理を終了して最初に食べる普通の食事が、本来の精進落としです。
その後、精進落としは、故人が亡くなってから七日目に行われる最初の法要(初七日法要)が無事に終わったことを報告し、関係者の労をねぎらう席へと変化します。
さらに現代では初七日法要も簡略化されはじめ、繰り上げ法要として、葬儀当日の火葬後に行うケースが多くなりました。
これにともない精進落としも、葬儀当日の最後の行事でもって参列者に感謝の意を伝える食事として定着しました。
浄土真宗では、精進落としのことを「お斎(おとき)」と言います。
地方によっては、「精進上げ」「忌中祓い」「仕上げ」などの別名があります。
通夜振る舞いとの違い
通夜振る舞いは、通夜のあとに参列者にふるまう料理です。
参列した人に感謝の意を表すという点では精進落としと同じですが、多くの人が参列する可能性があり人数が確定できないので、サンドイッチやお寿司などの大皿料理を出すのが一般的でしょう。
一方、精進落としは人数が確定しているので、一人ひとりに御膳が用意される会席料理の形式をとることがほとんどです。
精進落としは神道やキリスト教でも行う?
神道の場合
神道の葬儀にも、仏式の精進落としに相当する「直会(なおらい)」があります。
神道式の葬儀の正式名称は「神葬祭(しんそうさい)」。
神葬祭は仏式の葬儀との共通点も多く、葬儀の最後に参列者や神職の労をねぎらうために行う飲食を「直会」と呼びます。
仏式の精進落としとの違いは、葬家が火を使った料理を作ることはよくないとされている点です。
肉や魚を食べることは問題ありませんが、火の通った料理を出す際には、仕出しなどを利用するのが一般的です。
【関連記事】
神式の葬儀“神葬祭”の流れとは?通夜や告別式のマナー・作法も解説
キリスト教の場合
キリスト教の葬儀には本来、精進落としに相当する宗教的な行事はありません。
ただし、日本で行われるキリスト教式の葬儀では、日本の一般的な慣習に従い、会葬者へのお礼として同じようなもてなしを行うケースがあります。
もてなす場を設けるかどうかは葬家の意向次第です。
その場合でも、お茶菓子や軽食を出すことが多く、お酒をふるまうことはあまりないようです。
精進落としの事前準備
精進落としをスムーズに進めるためには、事前に以下のような点を検討する必要があります。
詳しくみていきましょう。
精進落としはいつ行う?
現代では精進落としは、葬儀当日の最後に実施するケースがほとんどです。
基本的には、亡くなってから七日目に行われる初七日法要が終わったあとに、精進落としを実施します。
しかし、葬儀の七日後に再び関係者を招くのは、招く方にとっても招かれる方にとっても大きな負担です。
そのため、初七日法要は繰り上げ法要として葬儀当日に行うケースが多くなっています。
葬儀当日に精進落としをする場合は、火葬・骨上げなどの一連の宗教行事がすべて終了した後に実施するのが一般的です。
しかし、地域や葬家のしきたりによっては、火葬中の空き時間を利用する場合もあります。
精進落としはどこで行う?
精進落としを行う場所は自宅、飲食店(料亭)、葬儀式場、お寺などさまざまです。
予算や葬儀をどこで行うかによって、適切な場所を選択すると良いでしょう。
飲食店を選ぶ場合、懐石料理を出す店であれば精進料理に対応しているケースが多いので、よく利用されています。
ほとんどの場合は和食で、中華料理や洋式のレストランは仏式の精進落としにはあまりふさわしくありません。
自宅で精進落としを行う場合は、仕出し料理(仕出し弁当)を利用するケースが多いようです。
精進落としには誰を呼ぶ?
精進落としでは、通常、大皿料理ではなく一人ひとりにお膳を出すので、事前に人数を確定しなければなりません。
精進落としに呼ぶのは、基本的に火葬に参列した人です。
どこまでの範囲の人を火葬に呼ぶべきかに関して特に決まりはありませんが、家族葬が多くなっている最近の葬儀では、ごく身近な親族と僧侶が立ち会うケースが多いようです。
葬儀の規模や遺族の意向によっては、故人の会社関係者や特に親しかった友人などを火葬や精進落としに招くケースもあります。
火葬場では、火葬炉に故人を収める前に僧侶が読経する「納めの式」が行われます。
一般的には、精進落としにも僧侶を招くのが通例です。
【関連記事】
家族葬の定義とは?メリット・デメリットや費用・流れをわかりやすく解説
献杯の発声は誰に頼む?
精進落としでは、最初に献杯を行います。
献杯とは、故人をしのんで杯を捧げる慣習で、葬儀や法要など、弔事の後の会食を始める際に実施します。
献杯の発声は喪主が務める場合もありますが、喪主は開式の挨拶を行い、献杯は親族代表に依頼することが多いようです。
誰に依頼するかに明確な決まりはありませんが、親族の中で最も年長となる人や、故人の最年長の兄弟などに依頼するケースがよく見られます。
他の人に依頼する場合は、喪主は事前に打診しておかなければなりません。
精進落としの流れ(葬儀当日に行う場合)
精進落としの進行に関して特に難しい点はありませんが、席次と献杯のやり方には注意が必要です。
一般的なマナーを紹介するので、それぞれ確認しておきましょう。
精進落としの席次
精進落としでは、葬儀を司ってくれた司式者(仏教では僧侶、神道では神主、キリスト教では司祭・牧師など)が上座、喪主・遺族は末席に座るのが通例です。
なぜなら精進落としは「参列者に感謝の意を表して、喪主や遺族が客人をもてなす場」だからです。
大規模な葬儀の場合、僧侶の次に葬儀委員長や世話役、会社関係者や友人・知人、親族という順に座ります。
葬儀では、一番前に喪主・遺族が座りますが、精進落としでは葬儀とは逆の席順になるので注意しましょう。
開始の挨拶
全員が席に着いたら、最初に喪主が挨拶をします。
葬儀・告別式が無事終了したことと、葬儀への参列のお礼を簡潔に述べてください。
献杯
続いて、会食を始めるきっかけとして献杯を行います。
精進落としに僧侶を招いている場合は、献杯の前に僧侶に法話をお願いするケースもあります。
献杯の発声は、親族代表が行うのが一般的です。
後で述べるように、献杯は乾杯とは異なり独特のマナーがあるので注意しなければなりません。
会食
献杯が終わると、会食を始めます。
故人の思い出を語りながら、食事をしましょう。
ただし、大声を出したり、騒いだりするのはマナー違反です。
会食中、喪主は参加者の席を回ってお礼の言葉を述べたりお酌をしたりします。
終了の挨拶
会場の予約時間や料理の進み具合を考慮して喪主が終了の挨拶を行い、会をお開きにします。挨拶では、再度葬儀参列へのお礼を述べましょう。
精進落としでの挨拶例文
精進落としでは、「開始時」「献杯時」「終了時」に挨拶を行います。
それぞれの挨拶で盛り込むべきポイントと例文を紹介します。
開始時の挨拶例文
精進落としを始める際には、喪主は葬儀がすべて無事に終了したことの報告と参列へのお礼を述べます。
本日はご多忙のところ、亡き父のためにお集まりいただきありがとうございます。
おかげさまで無事に葬儀・告別式を執り行うことができました。
ささやかではありますがお席を用意しましたので、お時間の許す限りごゆっくりとおくつろぎください。
本日は誠にありがとうございました。
献杯時の例文
喪主ではなく親族代表者が献杯の発声を行う際は、まず故人との関係、続いて参列者への感謝、最後に献杯の発声を行います。
〇〇(故人の名前)の弟、△△です。本日はお忙しい中、兄の葬儀にお集まりいただきありがとうございます。
生前お世話になった方々に見送られて、兄もさぞかし喜んでいることと思います。
お食事を召し上がりながら、兄の思い出話などをお聞かせいただければ幸いです。
それでは献杯のご唱和をお願いいたします。
皆様、グラスをお持ちください。
献杯。
ありがとうございます。
終了時の挨拶例文
終了時間になったこと、再度参列へのお礼、故人が亡くなったあともお付き合いをお願いしたいことなどを盛り込みます。
皆様、お時間となりました。
私の知らなかった父の意外な一面をお聞かせいただいて、私にとってもたいへん有意義な時間でした。
もっとお話をお伺いしたいところですが、皆様もお疲れだと思いますので、このあたりでお開きにしたいと思います。
父が亡くなったあとも、どうぞ変わらぬお付き合いをお願いいたします。
本日はありがとうございました。
精進落としで出す料理と費用相場
主に飲食店で行う場合を中心に、精進落としの料理内容や費用相場を紹介します。
精進落としで出す料理の特徴
通夜振る舞いでは、参列者に自由に会食してもらうために大皿料理が中心です。
一方で精進落としの場合は、出席者の数が決まっているのでコース料理やお膳単位の料理を出すのが一般的。
料理の内容については特に厳しい決まりはなく、肉や魚を出しても大丈夫です。
お酒を出すのも問題ありません。
ただし、おめでたい席で出される、鯛や伊勢エビなどは避けるべきとされています。
飲食店で行う場合は会席料理、自宅やお寺で行う場合は仕出し弁当が選ばれるケースが多いようです。
日本料理店では「精進落し用コース」を用意している場合もあります。
精進落としの費用相場
精進落としで会席料理や仕出し弁当を出す場合、費用相場は概ね3,000円〜1万円程度です。
基本的には一人当たり5,000円程度を目安にして、お店やメニューを検討すると良いでしょう。
香典を辞退する場合は、多少費用を少し抑えめにしてもかまいません。
精進落としで注意すべきマナー
精進落としには、注意すべき独特のマナーがいくつかあります。
精進落としをスムーズに進めるために、以下のような注意点を参考にしてください。
献杯は乾杯とは違う
通常、お祝い事の会食のはじまりには「乾杯」を行いますが、弔事では「献杯」を行います。
献杯には、乾杯とは全く違うルールがあるので注意が必要です。
献杯の発声を担当する人は、挨拶を行ったあと静かに杯を軽く上げて「献杯」と発声します。
他の人は唱和しません。
他人とグラスを打ち付けたり、大きな声で「献杯」といったりするのはNGです。
また、乾杯のようにグラスを掲げて一口飲んだ後、拍手をすることもありません。
献杯のマナーは、年長者であっても知らないケースがよくあります。
親族代表などに献杯を依頼する際は、これらのマナーも確認することをおすすめします。
親族代表が年長者で喪主から言いにくい場合は、葬儀社の担当者に説明してもらうと良いでしょう。
挨拶では忌み言葉に注意
弔事の挨拶には、縁起が悪いなどの理由で使ってはいけない「忌み言葉(いみことば)」があります。
不吉なこと・不幸を連想させる言葉、不幸が重なることを連想させる「重ね言葉」は避けなければなりません。
忌み言葉には以下のようなものがあります。
- 不幸を連想させる言葉
四・九・消える・落ちる・枯れる など - 重ね言葉
ますます・重ね重ね・次々・相次ぎ など
僧侶が同席しない場合の対応
僧侶が精進落としに出席してくれるかどうかは、事前に確認が必要です。
辞退された場合は、お布施とは別に「御膳料」を渡します。
御膳料の相場は、5,000円〜1万円程度です。
僧侶に対しては、葬儀場まで足を運んでくれた交通費として「御車代」も包みます。
御車代の金額は、特に遠方から来てくれた場合を除いて、御膳料と同額でかまいません。
僧侶が精進落としに参加する場合、御膳料は必要ありません。
また、御膳料の代わりに持ち帰り用の弁当を渡す場合もあります。
精進落としをしない場合はどうする?
最近は葬儀の簡素化・小規模化が進み、精進落としをしないケースも増えています。
特に、通夜を省略する一日葬や、火葬のみを行う直葬などでは、精進落としをしない割合が多いようです。
精進落としの代わりに、持ち帰り用の弁当などを渡すケースもあります。
精進落としをしない場合は、事前に参列者にその旨を通知しましょう。
【関連記事】
精進落としは葬儀当日の最後の行事。参列者に感謝を伝えるのが重要
精進落としは、現在では葬儀当日の最後の行事として故人を悼み、参列者に感謝を示す場に変化しています。
精進落としの出席者は、遺族や故人と特に親しかった人など限られた人たちで、お酒を出すケースもあるでしょう。
羽目を外さないように気をつけて、故人の思い出などを語り合い親睦を深めてください。
喪主や遺族にとっては、次の日から新しい生活を始めるための一区切りとなる行事です。
精進落としの流れやマナー、献杯の正しいやり方などを守って葬儀の最後を締めくくりましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要