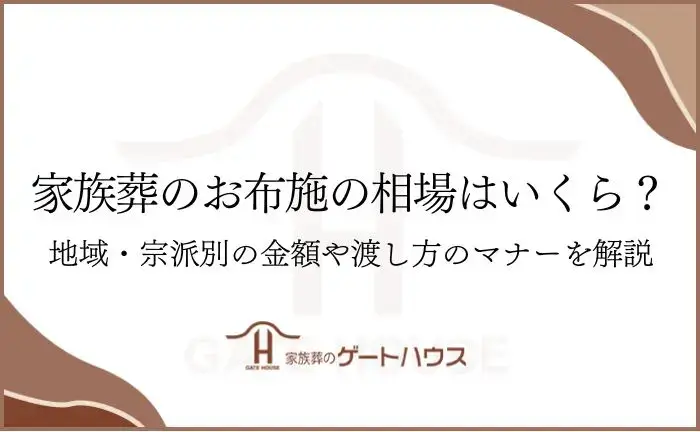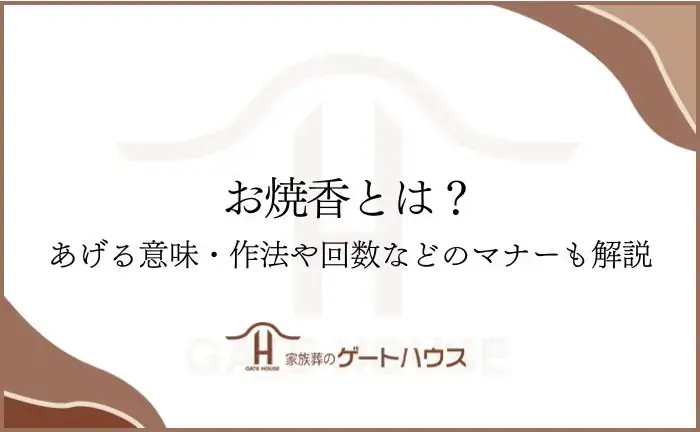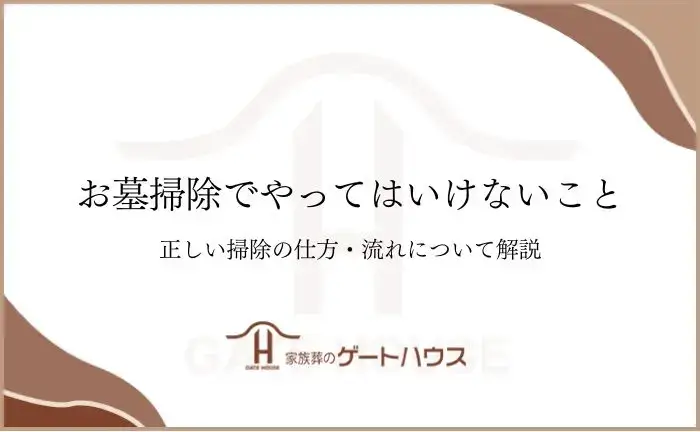友達の親が亡くなった時にかける言葉とは?LINEやメールで使える文例を解説
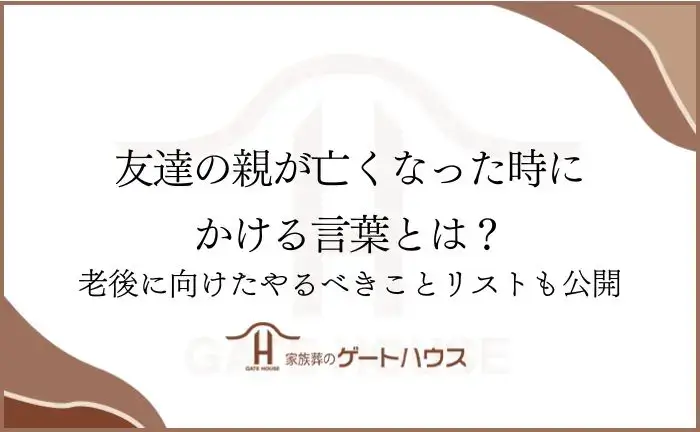
突然、友達から「親が亡くなった」という訃報を受け取ると、どんな言葉をかければよいのか、どのように連絡すればよいのか悩む方は多いでしょう。
マナー違反は避けたいけれど、マナーに沿ったお悔やみの言葉では堅苦しく、友達との関係性に合っていないと感じる場合もあるかもしれません。
本記事では、友達の親が亡くなった時にかける適切な言葉から注意点、LINEやメールで送る際の文例、香典や弔問のマナーまで詳しく解説します。
友達の親が亡くなった時、最初にすべき対応と心遣い
まず大切なのは、相手の気持ちや状況に寄り添う姿勢です。
訃報を受け取った際は、すぐに連絡を取ることが望ましいですが、まずは相手の状況を最優先に考えましょう。
突然の訪問や長電話は、むしろ負担になる可能性もあります。
また、近年は近親者のみで執り行う家族葬も増えており、故人と親しい間柄の人以外は、弔問や葬儀への参列を遠慮される傾向もあります。
葬儀への参列を検討する間柄であれば、訃報を受け取り、葬儀の詳細が通知されてからお悔やみの言葉を伝えても遅くはありません。
葬儀に参列していいか分からないのであれば、まずはお悔やみの言葉を伝えてから、葬儀への参列可否を尋ねると良いでしょう。
【関連記事】
家族が亡くなった人にかける言葉は?メール・LINE・口頭別に例文を紹介
友達の親が亡くなった時にかける言葉と注意点
友達との関係性やシチュエーションによって、どのようなお悔やみの言葉が適切かは変わりますし、その友人が親の死をどのように感じているかにも配慮する必要があります。
親しい友人であるならば、友人の気持ちに寄りそう言葉を選ぶことが重要です。
また、どのシチュエーションにおいても、死因について尋ねるのはマナー違反になりますので、友人自らが話さない限りは詮索しないようにしましょう。
友達への具体的な声かけの文例
お悔やみの言葉はどんなに親しい友人であっても、場面によっては定型的な言葉が適切な場合もあります。
また、どのように訃報を受け取ったかによっても、伝える言葉や対応の仕方が変わるでしょう。
それでは、シチュエーション別に文例を紹介します。
電話の場合
電話で連絡を取る場合は、必要最低限の言葉にとどめるのが基本です。
相手は色々な方に電話しなければならない可能性もあるため、長々と話すのではなく、状況を思いやった言葉を選びましょう。
「大変な時にわざわざ連絡ありがとう。葬儀が終わるまで大変だと思うので、無理しすぎないようにして、何かできることがあれば遠慮なくいってね。心よりお悔やみ申し上げます。」
「お父様の訃報を聞きました。この度はご愁傷様です。忙しい時に電話してごめんね。体調は大丈夫?何かできることがあれば遠慮なくいってね。」
メール・LINEの場合
LINEやメールは送る前に文章を整理できるため、落ち着いて気持ちを伝えたい時に便利です。
また、相手は訃報を一斉に送っている可能性もあるため「返信不要です」と添えると、相手の負担を減らせます。
短くても心のこもった文面を心がけましょう。
「お父様(またはお母様)のご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。突然のことで驚いています。お葬式には参列させて頂く予定です。どうか無理をなさらず、お体に気をつけてください。」
「お父様(またはお母様)のことを聞きました。この度はご愁傷様です。突然で大変だったね。何か私で役に立てることがあればいってください。」
【関連記事】
身内が亡くなった人にLINEでかける言葉丨友達や職場の人に使える例文集
お悔やみメールの例文を紹介|友人・ビジネス関係・親戚別で解説
面会・弔問時の言葉
弔問や通夜で実際に対面で話す際は、他にも弔問客がいるため「このたびはご愁傷様でございます」といった基本的なお悔やみの言葉を使います。
シチュエーションにもよりますが、長話はしないようにして、簡潔に伝えましょう。
お悔やみの基本フレーズ・注意したい言葉遣い
お悔やみの言葉は「ご愁傷様でございます」「心よりお悔やみ申し上げます」「ご冥福をお祈り申し上げます」などが基本のフレーズです。
親しい間柄の友人に対しては、自分の言葉で励ましたくなりますが、その際は忌み言葉や重ね言葉に注意しましょう。
忌み言葉は「死ぬ」「消える」「切れる」「落ちる」など、死や不幸を直接連想させるような言葉です。
「死ぬ」「死去」は「亡くなる」「他界」「永眠」などと言い換えます。
その他の言い換えが難しい言葉は使わないようにしましょう。
重ね言葉は「ますます」「度々」「くれぐれも」「重ね重ね」など同じ言葉を繰り返す言葉を指します。
不幸が重なることを連想させるので、縁起が悪いとされています。
「ますます」は「一層」と言い換え、「度々」は「何度も」「よく」などと言い換えが出来ますので、注意するようにしましょう。
【関連記事】
「ご愁傷さまです」は使ってはいけない?メールで使うと失礼?使い方と例文を紹介
お悔やみ申し上げます・ご冥福をお祈りしますはどっちを使う?メールでの例文も紹介
友達の親が亡くなった時の連絡はLINEやメールで問題ない?
現代では、LINEやメールでの連絡は一般的ですので、マナー的に問題ありません。
ただし、送る相手やその表現の仕方によっては不快に感じてしまう場合もあります。
下記の点に注意しながら文章を作成しましょう。
即時性と配慮のバランス
LINEやメールは気軽に連絡を取れる手段でもありますし、受け取った側のタイミングで読むことが可能なので、急ぎではないお悔やみの連絡の場合は、LINEやメールの方が良いでしょう。
ただし、送る際は一度文章を読み直し、誤字脱字がないか、失礼な表現が含まれていないか確認することが重要です。
また、家族ぐるみで親しくしていた友人の親が亡くなった際など、自分と相手の関係性によっては電話が望ましい場合もあります。
返信を求めない姿勢を大切に
親を亡くした友人は、通夜・告別式の準備や葬儀社との打ち合わせ、事務手続きのほか、故人が自宅に安置されているのであれば、弔問客の対応で多忙です。
そのため、訃報を受け取った人全員から連絡が来ると負担になってしまうこともあります。
葬儀日程や参列可否に関する質問などは、友人間の代表者が電話で確認するのも一つの手段です。
また、急ぎではない連絡の場合は、メッセージの最後に「返信不要です」と添えることで、相手に心理的な負担をかけずに済みます。
電話や直接会う場合との使い分け
親しい関係性なら、直接電話や面会してお悔やみを伝える方法もありますが、相手の精神状態によっては控えた方が良いこともあります。
相手からの訃報連絡が電話の場合は、関係性が近いことが伺えますので、電話でのやりとりや訪問を検討しても良いでしょう。
ただし、葬儀が家族葬の場合は遺族と近しい親族のみで執り行うため、突然の訪問や電話は避け、先にメールやLINEで意思を確認するのがマナーです。
友人からの連絡手段がメールかLINEならば、そのまま返信するようにしましょう。
友達の親が亡くなった時の香典は?金額とマナー
友人の親が亡くなった時は、香典を出すのが一般的ですが、地域の風習や友人との関係性、葬儀形式によっても変わってきます。
また、香典を出す場合にも金額相場やマナーがありますので、細かいポイントを確認しましょう。
香典を出すべきか判断するポイント
香典を出すか迷う場合は、友達との距離感や普段の交流頻度を判断材料に、相手との関係性を考慮します。
また、地方の場合は、同級生というくくりで親の訃報がまわり、現在交流が無くても通夜の開式前に弔問に行き、香典を出す風習がある場合も少なくありません。
ただし、近年では家族葬も増えてきたこともあり、現在も交流があるかどうかを重視している人が多い印象です。
また、家族葬では香典を辞退される場合もあるので、訃報時の連絡内容を確認しましょう。
葬儀に参列したかったけれども出来なかった、という場合には後日手渡しするか現金書留で送るという方法もあります。
香典の相場と香典袋の選び方
香典の相場は、一般葬では5,000円~10,000円程度が目安です。
特に友人のご両親と直接の関わりがない場合は5,000円程度、特に親しい友人やお世話になっている関係性ならば、10,000円程度が適切でしょう。
香典袋(不祝儀袋)は、水引が白黒や双銀(印刷でも可)で結び切りのものを使用します。
関西地方では黄白・黄銀の結び切りを使用する場合もあります。
また、蓮の模様が入っている香典袋は仏式でしか使えませんので注意してください。
表書きは仏式の葬儀であれば「御霊前」(浄土真宗は「御仏前」)か「御香典」、神式であれば「御霊前」か「御玉串料(御榊料)」、キリスト教式であれば「御花料」と書くのが一般的です。
また、香典には新札を使わないというマナーがあるため、事前に用意しておくと安心です。
【関連記事】
香典の相場はいくら?葬儀・法要での金額目安を関係性・年齢別に解説
葬儀や通夜への参列・弔問のマナー
葬儀への参列は、直接訃報を受けたかどうか、一般葬かどうかで基本的には判断します。
地域の風習にもよりますが、一般葬であれば人づてや連絡網などで訃報を受け取った場合でも参列・弔問は自由です。
一般葬なら、故人である友人の親と面識がなくても、喪主や喪主の兄弟である友人と親しければ参列しても構いません。
ただし、家族葬の場合、基本的に身内や特別親しい人以外は参列しないので、声をかけられなければ参列できません。
また、家族葬に参列して欲しいと伝えられた場合は、時間・場所・喪主など詳細について確認しておきましょう。
参列する場合のマナー
通夜や告別式に参列する場合、黒いスーツなどフォーマルな喪服を着用します。
女性はアクセサリーを控え、黒い靴とバッグが基本です。
また、受付で香典を渡す際は「このたびはご愁傷様でございます」と一言添えるのがマナーです。
弔問する場合の注意点
弔問する場合も、突然の訪問は負担になるかもしれないので、事前に相手の都合を確認しましょう。
訪問時には、香典やお線香、お菓子、花などを持参する場合がありますが、相手の意向を確認したうえで準備します。
参列できない場合の対応
仕事や距離の関係で参列できない場合は、電話やメール、弔電でお悔やみを伝え、香典は郵送、もしくは参列する友人に依頼するという方法もあります。
関係性によっては、枕花や供花を贈ることも珍しくありません。
後日訪問できる距離や関係性であれば、その際に香典を渡しましょう。
友達の親が亡くなった時にかける言葉や香典マナーは「気持ち」が最優先
友達の親が亡くなった時にかける言葉は「お悔やみ申し上げます」や「ご愁傷様です」といったような一般的なお悔やみの言葉で構いません。
関係性によっては、相手の心労や体調を気遣う言葉を添えても良いでしょう。
香典は必ず渡さなければいけないという訳ではありませんので、友人との関係性や葬儀形式に配慮して決めましょう。
どちらも、相手の気持ちや事情をくみ取って対応する気持ちが大切です。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要