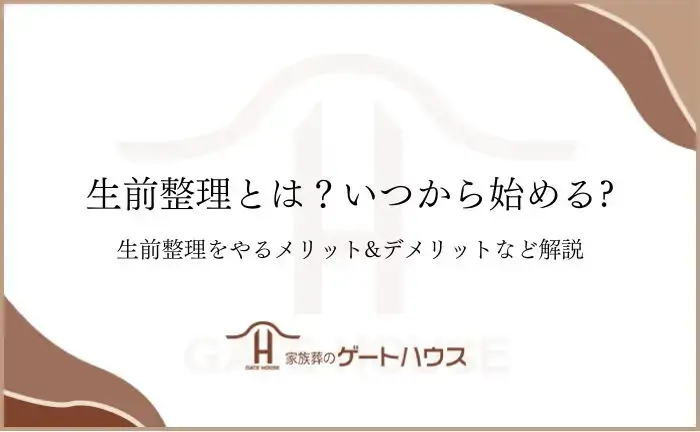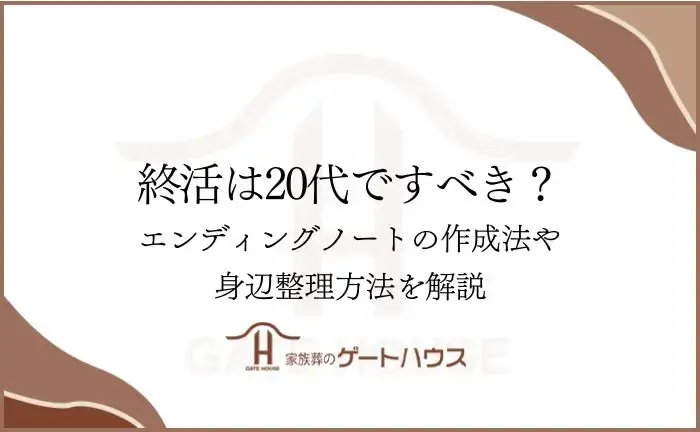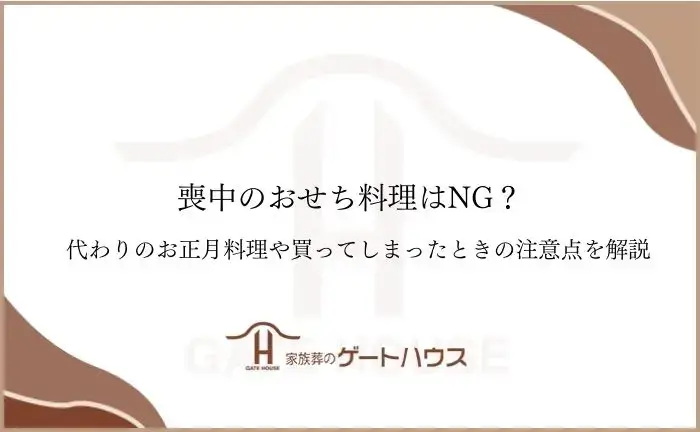盂蘭盆会(うらぼんえ)とは?意味やお盆・施餓鬼会との違いを解説
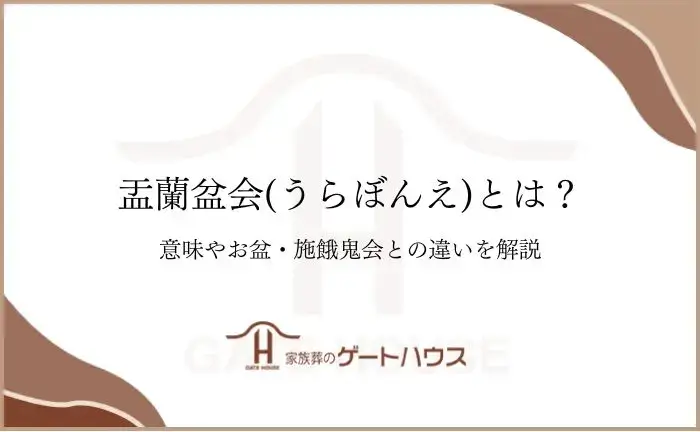
夏に迎えるお盆には、盂蘭盆会(うらぼんえ)という正式名称があります。
この記事では、盂蘭盆会とは何か、その意味や由来、施餓鬼会との違いを解説します。
ご先祖様を供養する大切な期間だからこそ、そのルーツを知り、心を込めてお迎えしましょう。
盂蘭盆会の意味とは
盂蘭盆会は、祖先の霊を迎え入れ供養するための大切な期間で、日本の仏教行事の中でも広く親しまれている行事です。
多くの家庭ではお盆と呼ばれ、家族みんなでご先祖様をもてなして、感謝の気持ちを伝える風習が根づいています。
まずは盂蘭盆会の意味や由来、期間について詳しく見ていきましょう。
【関連記事】
新盆(初盆)とは?やり方は?用意するものやいつ法要を行うか解説
盂蘭盆会の意味・読み方
盂蘭盆会は「うらぼんえ」と読みます。
この言葉は、古代インドの言葉であるサンスクリット語の「ウラバンナ(ullambana)」を漢字にしたものだといわれ、その意味は「逆さ吊りのような苦しみ」です。
供養を受けられず苦しんでいる霊を救うという仏教の教えに由来し、日本に伝わってからは「ご先祖様を供養し、その魂を慰める行事」という意味合いが強くなりました。
家族や親戚が集まり、お墓参りや仏壇への手合わせ、供え物などをして、亡くなった人たちのために祈るという現在のお盆行事につながっています。
盂蘭盆会の由来
盂蘭盆会の由来は、古代インドの仏教で伝承される、目連尊者(もくれんそんじゃ)の物語に遡ります。
目連尊者は、亡くなった母親が餓鬼道に落ちて苦しんでいる姿を神通力で見たため、お釈迦様に相談しました。
お釈迦様は「旧暦7月15日に多くの僧侶たちに食事を施すと、その功徳によって先祖の霊を救える」と助言し、目連尊者がその通りにすると母親は救われたといわれています。
中国を経由して日本へ仏教が伝わる中で、この目連尊者の伝説が、日本の先祖崇拝や祖霊信仰の風習と結びつきました。
そして、今のような盂蘭盆会が日本に定着したのです。
盂蘭盆会はいつからいつまで?
盂蘭盆会の期間は、旧暦7月15日を中心に、7月13日から16日までの4日間が基本とされています。
しかし、明治時代の改暦以降は新暦に合わせて行われることが多くなり、全国的には8月13日から16日、いわゆる「月遅れ盆」が一般的です。
一部の地域や宗派では、旧暦の7月13日~16日に行う場合もあります。
たとえば、沖縄や奄美地方などでは、毎年旧暦に基づいてお盆を迎えるため、日程が年によって変動します。
そのため、お住まいの地域の風習に合わせて、正しい日程を確認することが大切です。
盂蘭盆会とお盆・施餓鬼会との違いとは?
盂蘭盆会・お盆・施餓鬼会(せがきえ)は、いずれも先祖供養に関連する仏教行事ですが、それぞれに意味や目的、起源が異なります。
これらの違いを理解することで、先祖供養の行事がどのように日本文化に根付いているのかを深く知れるので、その違いについて見ていきましょう。
盂蘭盆会とお盆の違い
盂蘭盆会という言葉は、お盆の正式な仏教用語です。
そのため、この2つに大きな違いはありません。
本来、仏教儀式として使われていた盂蘭盆会が、時代とともにお盆という一般的な表現に変化していきました。
盂蘭盆会は仏教の経典に由来する供養式典を指し、お盆はその日本風の略称であり、祖先を供養するための家庭的・地域的な行事全般を指します。
そのため、お寺で行われる法要などの改まった場面では「盂蘭盆会大法要」といったように、正式名称が使われることが多いです。
盂蘭盆会と施餓鬼会の違い
盂蘭盆会と施餓鬼会は、どちらも仏教の行事ですが、供養の対象や意味に違いがあります。
盂蘭盆会は、主にご先祖様や故人の霊を供養するための行事です。
家族や親族で集まって仏壇やお墓にお供えをしたり、僧侶を招いて読経してもらったりします。
一方、施餓鬼会は「餓鬼道(がきどう)」に落ちて苦しんでいるすべての霊、特に無縁仏(供養される人がいない霊)や飢えや渇きに苦しむ霊を供養するための法要です。
施餓鬼会は「施食会(せじきえ)」とも呼ばれ、お寺や地域の共同体で行われることが多く、すべての霊に対して供養を行います。
施餓鬼会の時期は寺院によって異なりますが、お盆の時期に行われることが多いです。
そのため混同されやすいのですが、違いを覚えておくと良いでしょう。
【関連記事】
施餓鬼(せがき)とは?行かないのはあり?意味・お布施の書き方マナー・宗派別の違いを解説
盂蘭盆会とは何をする?
盂蘭盆会は、ご先祖様が年に一度、私たちの元へ帰ってこられる大切な期間です。
そのため、感謝の気持ちを込めて、ご先祖様をしっかりとおもてなしするための準備や行事を行います。
具体的にどのようなことをするのか、代表的な4つの習わしを見ていきましょう。
迎え火・送り火を焚く
盂蘭盆会の始まりと終わりに欠かせないのが、迎え火と送り火です。
迎え火は、ご先祖様の霊が迷わず家に帰ってこられるように、家の門や玄関先で火を焚きます。
おがらや松の木を使って火をつけますが、火を焚くのが難しい場合は盆提灯でも良いでしょう。
火を灯すことで「ここがあなたの家ですよ」と合図を送り、ご先祖様を温かく迎え入れる意味があります。
盂蘭盆会の終わりには、ご先祖様の霊があの世へ無事に帰れるように見送るための送り火を焚きます。
迎え火と同じように、門や玄関先で火を焚き「また来年もお越しください」という気持ちを込めてお見送りしましょう。
【関連記事】
新盆(初盆)の提灯は誰が買う?飾り方・選び方やいつから飾るのかを解説
お盆の迎え火・送り火のやり方は?いつやる?マンションでできる代用方法も解説
精霊棚を飾る
ご先祖様の霊が家に帰ってきた時に休んでもらう場所として、精霊棚(しょうりょうだな)を用意します。
精霊棚は、仏壇の前や部屋の一角に、野菜や果物、故人の好きだったものなどをお供えして飾る棚のことです。
キュウリやナスに割り箸を刺して馬や牛の形を作り「馬に乗って早く帰ってきて、牛に乗ってゆっくり帰ってください」という願いを込める風習もよく見られます。
精霊棚には、季節の花やお線香、ろうそくなども飾り、ご先祖様が快適に過ごせるよう心を込めて準備すると良いでしょう。
【関連記事】
お盆のナスとキュウリ「精霊馬」の向きは?意味・地域・宗派の違いや作り方も解説
精進料理を供える
盂蘭盆会の期間中は、肉や魚を使わない精進料理をお供えするのが一般的です。
精進料理は、野菜や豆腐、海藻などを使ったシンプルな料理で、動物の命をいただかず、心身を清めるという意味があります。
お盆の時期は、仏様やご先祖様に対して感謝と敬意を表すため、精進料理を仏壇や精霊棚にお供えし、家族も一緒にいただきましょう。
煮物やおひたし、胡麻豆腐、そうめん、季節の野菜の天ぷらなどがよく供えられます。
【関連記事】
お盆のお供え料理の定番メニューは?置き方・期間・基本マナーも解説
お盆のそうめんの飾り方&意味を解説!いつお供えする?正しい配置は?
お墓・仏壇を掃除する
盂蘭盆会の大切な準備として、お墓参りや仏壇の掃除も欠かせません。
ご先祖様の魂が安心して帰ってこられるように、お盆の前や期間中に家族でお墓を訪れ、草むしりや墓石の掃除などをします。
また、家の中では仏壇を掃除し、新しいお花やお供え物を用意し、ご先祖様を気持ちよくお迎えするための準備を整えましょう。
【関連記事】
新盆はお墓参りだけでも良い?お坊さんを呼ばない場合や持ち物・服装を解説
盂蘭盆会期間中の伝統行事
盂蘭盆会の期間中、日本各地ではご先祖様を供養する儀式だけでなく、地域に根差したさまざまな伝統行事が行われます。
一見すると、お盆とは関係ないように思える夏の風物詩が、実は盂蘭盆会と深い繋がりを持っていることも少なくありません。
ここでは、私たちの夏を彩る代表的な伝統行事と、その背景にある盂蘭盆会との関わりについてご紹介します。
お中元
お中元は、盂蘭盆会の時期に親戚やお世話になった人へ贈り物をする風習で、もともと中国から伝わった行事です。
中国では旧暦7月15日を「中元」とし、神仏や祖先を祭る日でした。
それが日本で行われていた盂蘭盆会と融合し、現在では「日頃の感謝を伝える夏のご挨拶」として定着しています。
お中元の品物は、そうめんやお菓子、ジュース、ハムなど、夏に喜ばれる食べ物や飲み物が多く選ばれます。
お中元を通じて、家族や親戚、友人との絆を深めましょう。
七夕
七夕は、7月7日に行われる星祭りで、織姫と彦星が年に一度だけ天の川で会えるという中国の伝説がもとになっています。
もともとは農作物の豊作や家族の健康を祈る行事でしたが、やがて個人の願いごとをする日として親しまれるようになりました。
盂蘭盆会の時期と重なることから、七夕飾りをお盆の精霊棚に一緒に飾る地域もあり、祖先を迎える準備を始めるという意味合いもあります。
五山送り火
五山送り火は、京都で毎年8月16日に行われる有名な伝統行事です。
お盆の終わりに、ご先祖様の霊をあの世へ送り返すため、山に「大」や「妙・法」などの大きな火文字を灯します。
これは、火を目印にして霊が迷わず帰れるようにという願いが込められています。
京都以外にも全国各地で送り火の行事が行われており、長崎の「精霊流し」なども有名です。
盆踊り
盆踊りは、盂蘭盆会にあわせて日本各地で開催される踊りのイベントです。
夜になると町や村、商店街や学校の校庭などに集まり、やぐらを囲んでみんなで踊る姿は日本における夏の風物詩として広く知られています。
起源は、先祖の霊をなぐさめたり、地域の人々の交流を深めたりするために踊られた「念仏踊り」と言われています。
全国には個性豊かな盆踊りがあり、徳島の阿波おどりや岐阜の郡上おどりなどが有名です。
ご先祖様の霊を慰め、共に楽しむための盂蘭盆会の時期に欠かせない行事となっています。
打ち上げ花火
夏の夜空を美しく染め上げる打ち上げ花火ですが、実はこの花火もお盆の行事と無関係ではありません。
もともと花火には、亡くなった人々の魂を慰める、鎮魂や供養の意味が込められていました。
花火の大きな音や閃光には、悪霊や災いを追い払う力があると信じられており、お盆の送り火の一種として、ご先祖様の霊を供養する役割も担っています。
私たちが何気なく楽しんでいる夏の夜空の祭典には、盂蘭盆会に通じる、亡き人々への深い祈りと鎮魂の思いが込められているのです。
盂蘭盆会は宗派ごとに違いはある?
盂蘭盆会は、日本の仏教において広く行われる重要な行事ですが、宗派によってその考え方や儀式の方法に違いがあります。
それぞれの宗派が持つ教えや歴史的背景によって、盂蘭盆会の捉え方や行い方が異なるためです。
ここでは、4つの宗派について、その特徴や違いについて紹介します。
浄土真宗の場合
浄土真宗では、盂蘭盆会と言わず代わりに「歓喜会(かんぎえ)」と呼び、「お盆法要」と呼ばれることも多くあります。
他の宗派と大きく違う点は、ご先祖様の霊がこの世に帰ってくる考え方ではないことです。
浄土真宗では、亡くなった人はすぐ阿弥陀如来の浄土に生まれ変わるとされており「霊が帰ってくるから迎え火や送り火を焚く」という風習はありません。
そのため、浄土真宗のお盆では、仏壇やお墓をきれいにし、家族や親族が集まって阿弥陀仏の教えに感謝し、亡くなった人々を偲ぶ法要を行います。
【関連記事】
浄土真宗の初盆の迎え方は?お布施相場やお供え物・仏壇の飾り方など解説
浄土宗の場合
浄土宗では、盂蘭盆会は「盂蘭盆会法要」として、ご先祖様の霊を迎えて供養するという考え方が大切にされています。
迎え火・送り火や精霊棚を飾るなど、一般的なお盆の風習がそのまま行われることが多いです。
浄土宗独自の特徴としては、ほおずき、枝豆、ガマの穂などを逆さに吊るして生けることが挙げられます。
真言宗の場合
真言宗も、浄土宗と同様に一般的な盂蘭盆会法要を行いますが、他の宗派に比べて提灯の意味が強調されているのが特徴です。
提灯は「霊魂が迷わずこの世に戻ってこられるように」という願いを込めて飾られ、亡くなった人が迷いの世界で道に迷わないように灯りで導く役割も持っています。
迎え火や送り火とともに、家や仏壇の前に提灯を灯してご先祖様を丁寧にお迎えします。
また、追善供養を重要視しているため、故人のお墓だけでなくご本尊へのお参りも欠かせません。
【関連記事】
真言宗の初盆とは?準備するお供え物や行うこと・服装マナーを解説
曹洞宗の場合
曹洞宗でも盂蘭盆会は重要な行事で、迎え火・送り火や精霊棚、精進料理など一般的なお盆の風習をほぼ踏襲しています。
曹洞宗では「施食会(せじきえ)」と呼ばれる法要が特に重視されており、これはご先祖様だけでなく、すべての精霊や無縁仏にも食べ物を施して供養する行事です。
その際、水の子(賽の目に切ったキュウリやナスと洗った米を盛りつけたもの)と閼伽水(あかみず)を仏さまにお供えします。
【関連記事】
曹洞宗の初盆飾りの仕方は?精霊棚(祭壇)の飾り方・お供え物・提灯について解説
盂蘭盆会とはお盆の正式名称!由来を知り供養の意味に触れよう
盂蘭盆会(うらぼんえ)は、お盆の正式な呼び名であり、古くから祖先の霊を供養し、感謝や祈りの心を伝えてきた大切な日本の行事です。
その由来は、仏教の教えに基づき、ご先祖様への感謝が時代とともに形を変え、各家庭や地域で受け継がれてきました。
迎え火や送り火、供え物や伝統行事など、どれもご先祖様への敬意や命のつながりを意識するきっかけとなります。
盂蘭盆会を通じて、いま一度、家族や大切な人たちへの感謝の気持ちを深めてみてはいかがでしょうか。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要