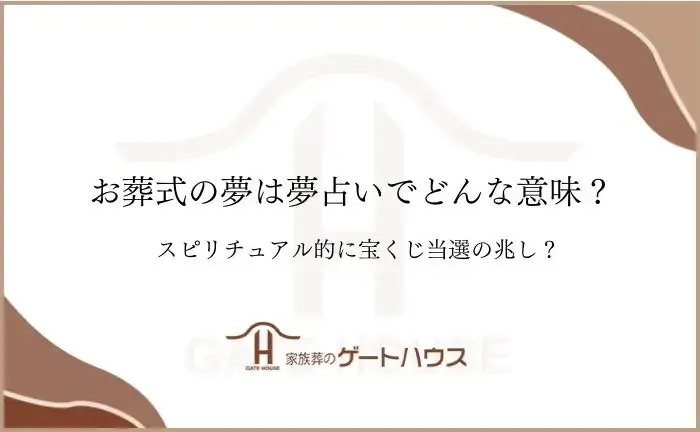喪主挨拶でカンペを使うのはあり?通夜や告別式で使える例文を紹介
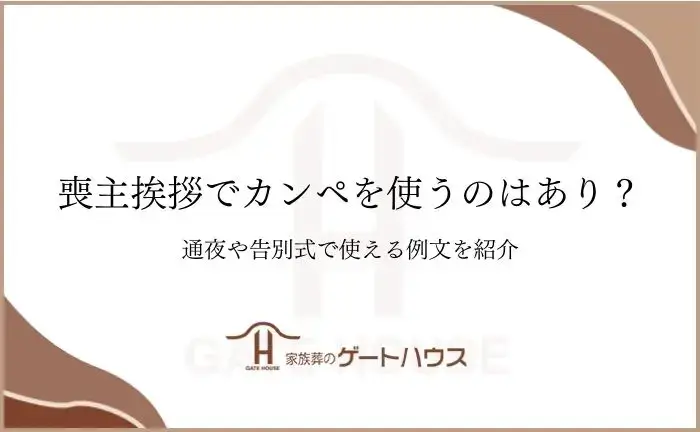
葬儀では、何度か喪主が挨拶をしなければならない場面があります。
しかし、葬儀で挨拶する経験はそう多くはないので不安に思っている方もいるでしょう。
できれば失敗しないようにカンペを準備しておくと安心です。
この記事では、葬儀で喪主がカンペを使うのはマナー違反にあたらないか、カンペの作り方、実際の例文を紹介します。
喪主の挨拶でカンペを使用しても問題ない
喪主挨拶で、カンペを使用しても問題ありません。
“カンペ”はカンニングペーパーの略です。
本来は試験などで不正をするために利用する紙を意味するのであまり印象はよくありませんが、冠婚葬祭などの挨拶でメモを見ながら話すことはマナー違反にはなりません。
カンペを使用するメリット①:落ち着いて葬儀に臨める
人前で話すことに慣れていない場合、緊張してうまく言葉が出てこなくなる可能性も考えられます。
葬儀の最中も挨拶がうまくできるか気になって、故人を悼む気持ちがおろそかになっては本末転倒です。
喪主は葬儀全体を取り仕切る重要な役目を担っています。
挨拶以外に葬儀内容の決定や会葬者の窓口など、さまざまなことに対応しなければなりません。
挨拶の文言を考えたとしても、事前にしっかりと暗記するのは難しいでしょう。
カンペを用意していれば、落ち着いて葬儀に臨めます。
カンペを使用するメリット②:言いたいことを正確に伝えられる
喪主は、葬儀の挨拶で参列してくれた人々に感謝の気持ちを伝えなければなりません。
大切な人を亡くして動揺している中、冷静な状態で参列者に感謝の気持ちや故人を偲ぶ思いを伝えるのは簡単ではないでしょう。
挨拶では故人の享年や亡くなった日にちを盛り込むケースもあります。
情報を正確に伝え、自分の思いを忘れずに話すためにもカンペを準備すると安心です。
喪主挨拶のカンペはスマホでなく紙に書く
カンペは、スマホに入力するのではなく紙に書くのが無難です。
スマホが普及し、さまざまな場面で利用するケースが増えてきました。
とはいえ、葬儀では年配者が参列することも多く、中にはスマホに対して抵抗感を持つ人がいるかもしれません。
できれば、言いたいことは紙に書いて準備するのが賢明でしょう。
使用する紙は、厳粛なセレモニーの場にふさわしく、色のついたものは避け、白い便箋などがおすすめです。
ちゃんとした体裁の紙であれば、カンペとしてこっそり見るのではなく堂々と出して読むこともできます。
カンペの内容は全文でも要点だけでもOK
カンペの原稿は、「全文書く」でも「要点だけまとめる」でもかまいません。
ご自身が作りやすい・話しやすいほうを選んでください。
故人の享年や亡くなった日付、葬儀の日程などは、紙に書いておけば間違える確率が圧倒的に下がります。
要点だけ書く場合は、特に事前の練習をおすすめします。
メモの内容だけで、本当によどみなくスムーズに話せるかを確かめておきましょう。
喪主挨拶文の作り方
喪主の挨拶文を作る際には、以下の点に留意してください。
要点を簡潔に、長さは1〜2分
挨拶の長さは1〜2分程度、長くても3分以内に収めるように心がけましょう。
逆にあまりにも短すぎるのもおすすめできません。
伝えるべきことを事前に整理して、要点を簡潔に話すことが重要です。
子どもに先立たれたり突然亡くなったりしたようなケースでは、悲しみのあまり故人の思い出を長々と語りだすような例もあります。
気持ちはわかりますが、自分の思いを正確に伝えるためにも事前に要点を整理しておくとよいでしょう。
忌み言葉を使用しない
葬儀では、「縁起が悪い」「遺族の悲しみを助長する」などの理由で、使うのがふさわしくない“忌み言葉(NGワード)”があります。
忌み言葉は以下の3種類に分かれます。
①重ね言葉
重ね言葉は、不幸を繰り返すという意味につながるので避けたほうが良いでしょう。
例:ますます、くれぐれも、とうとう など
②続き言葉
続き言葉も、重ね言葉と同様に不幸が続くことを連想させます。
例:再び、引き続き、繰り返し など
③死につながる言葉
「死ぬ」や「急死」などの直接死を意味する言葉もNGです。
さらに「生きていた」などの表現も避けましょう。
「生きていた頃」は「お元気だった頃」などに言い換えてください。
④不吉な言葉
死や不幸を連想させる言葉も忌み言葉です。
例)数字の4(死)、9(苦)、消える など
宗教ごとのマナーに注意
忌み言葉の一種とも言えますが、ある宗教・宗派で普通に使われる言葉が別の宗教では使えないケースがあります。
「成仏」や「往生」などは仏教用語なので神道やキリスト教では使いません。
仏教では「浮かばれない」「迷う」などは、極楽浄土にたどり着けないことを想起させるので別の表現に言い換える必要があります。
自分の思いを率直に伝える
厳粛な儀式とはいえ、着飾った言葉を使用する必要はありません。故人を悼む気持ちと参列してくれたことへの感謝を伝える点が重要です。
形式的な挨拶は、聞く人の心に響きません。
自分の言葉で率直に思いを伝えましょう。
他の遺族・葬儀社のスタッフに相談する
喪主は遺族を代表している立場ですが、すべてを一人でこなす必要はありません。挨拶文の作成に関しても、一人で悩まずに家族や親戚にも相談して作ると良いでしょう。
故人を知る人と話し合いながら進めたほうが、パーソナリティやエピソードが思いつきやすいかもしれません。
挨拶を考えるために遺族同士で故人の思い出を話し合うのも立派な供養のひとつです。
葬儀社のスタッフも、挨拶の仕方や葬儀で使ってはいけないNGワードなどのアドバイスをしてくれるでしょう。
喪主挨拶文の基本的な構成
通夜式や葬式の挨拶文は、基本的に以下の5つの要素で構成されます。
参列へのお礼
まずは葬儀に参列してくれたお礼を述べます。
参列者への感謝は、挨拶の中で最も重要な要素です。
状況に応じて、雨の日であれば「足元の悪い中」、寒い日であれば「お寒い中」などのフレーズを加えると良いでしょう。
故人の会社関係者など、面識のない人が多いようであれば、故人と喪主の関係など簡単な自己紹介を加えます。
亡くなったことの報告
次に、亡くなった日時、死因、亡くなった場所、享年などを伝えます。
死因や病名などは、事情によってははっきりと説明しなくても問題ありません。
享年は数え年で表すのが一般的です。
前項で述べたように「死亡した」などの直接的な表現は避け、「他界しました」「旅立ちました」などと言い換えましょう。
故人に関する思い出・エピソード
故人が生前、お世話になったお礼も挨拶に含めましょう。
それにからめて、生前のエピソードを加えます。
エピソードは、なるべく参列者の心に響くものを選択してください。
例えば、故人が定年退職後、将棋を趣味にしていたとします。
参列者にその関係者が多ければ、「定年後は趣味の将棋に没頭し、毎週の対戦を楽しみにしていました」など。
逆に参列者があまり知らないような故人の意外な一面を披露する方法もあります。
故人の会社関係者が多い場合「厳しい父でしたが、毎年夏には必ず旅行に連れて行ってくれました」などとして、家族だけが知るエピソードを簡単に語ると良いでしょう。
今後の予定
挨拶の後半では、葬儀関連で今後行われるスケジュールを伝えるのも重要です。
通夜式の挨拶では、別室で通夜振る舞いを用意していることや通常次の日に行われる葬儀・告別式の予定(日時、場所)を伝えます。
告別式では、四十九日法要などの法要への参加を要請するケースもあります。
結びのことば
最後は再度、参列してくれたお礼を述べるとともに、遺族を代表してこれからの思いを述べます。
今後も変わらず親交を深めてくれるようにお願いしたり、気落ちせずに頑張る決意を述べたりするのも選択肢のひとつです。
辛いと思いますが、心配している参列者に安心してもらえるような言葉も盛り込むことをおすすめします。
すぐに使える喪主挨拶の例文|タイミング別
そのまま使える喪主の挨拶例文を葬儀の場面ごとに紹介します。
【関連記事】
家族葬で使える喪主挨拶の簡単な文例は?お通夜・告別式で話すコツも紹介
お通夜
お通夜の挨拶では、参列への感謝、生前のお付き合いへのお礼に加えて、通夜振る舞いや告別式の案内をします。
告別式の案内をする場合の挨拶例文
通夜振る舞いの案内をする場合の挨拶例文
通夜振る舞い
開式時の挨拶例文
閉式時の挨拶例文
葬儀・告別式
精進落とし
従来、精進落としは初七日法要に行われていました。
しかし近年では初七日法要を葬儀当日に繰り上げて行う「初七日繰り上げ法要」が主流となっています。
ここでは、葬儀当日に初七日法要が行われることを前提とした文例を紹介します。
開式時の挨拶例文
献杯時の挨拶例文
精進落としを始める際には、献杯を行います。
献杯の挨拶は、喪主ではなく親族代表(年長者)が担当するケースもあります。
葬儀では「乾杯」ではなく「献杯」だという点に注意しなければなりません。
乾杯は結婚式などのおめでたい席で使う言葉です。
葬儀や法事などの弔事では献杯といい、大きな声で唱和したり、杯を高く掲げて他の人の杯と打ち合わせたりしません。
その後に拍手をするのも厳禁です。
閉式時の挨拶例文
葬儀の喪主挨拶で失敗しない4つのポイント
話す内容だけではなく、話し方も重要です。
挨拶する際に失敗しないためのポイントを解説します。
ゆっくり・はっきり話す
最も気をつけるべきポイントは、「ゆっくり」「はっきり」話すことです。
葬儀では高齢者も多いでしょう。
早口で話したり、悲しみのあまり小さな声で話したりすると聞き取りにくくなります。
特に人前で話す場面では、緊張してどうしても早口になりがちです。
意識的にゆっくり、はっきり話すように心がけてください。
通常のスピーチでは、1分間に300文字程度が理想のスピードだといわれています。
最初からメモ・カンペを出しておく
メモ・カンペを用意するのであればスピーチの最初から手元に持っておきましょう。
念のためポケットに入れておいて、詰まった時に取り出すやり方はおすすめできません。
話す内容を忘れると、一気に精神的に動揺してしまうからです。
動揺している状態でポケットからカンペを取り出そうとすると、あわててうまく取り出せなくなるような事態が予想されます。
また、途中から取り出すと、聞いている人に「この人、話す内容を忘れてしまったんだな」というあまりよくない印象を与えかねません。
それならば、最初から手元に持って堂々とカンペを見ながら話したほうが良いでしょう。
目線・姿勢に注意する
メモを見ながら話すとどうしても原稿に目を落として俯きがちになります。
また、親しい人をなくした悲しみから姿勢も猫背になります。
参列者を心配させる原因にもなるので、目線や姿勢には注意が必要です。
背筋を伸ばしてゆっくり、はっきり話しましょう。
時には目線をあげて前を向いてください。
前を向いている間はメモを見られませんが、その分ゆっくり話せるようになるでしょう。
練習をする
カンペを作るのであれば、できれば練習すると良いでしょう。
練習によって、自分の欠点がわかります。
可能であれば、録画・録音してください。
話すスピードが速すぎないか、正しい姿勢で話せているかなどをチェックできます。
練習すると事前の不安を和らげる効果も期待できるでしょう。
葬儀で喪主が挨拶できない・苦手な場合の対処法
葬儀では喪主が挨拶を行うのが通常ですが、何らかの事情により挨拶が難しいケースも考えられるでしょう。
そのような場合の対処法を紹介します。
【関連記事】
喪主をやりたくないなら?長男でも拒否できるか・したくないときの対処法も解説
喪主は誰がやると良い?続柄の優先順位や決め方・葬儀でやることを解説
代理で挨拶してもらう
喪主が高齢だったり、突然の悲しみで精神状態が不安定になっていたりして挨拶できないようであれば、故人や喪主に近い関係の人が代理で挨拶することも可能です。
若くして夫を亡くした妻が喪主を務める場合、挨拶できないようであれば故人の父が代理で挨拶をするケースもあります。
その場合、挨拶の冒頭に「故〇〇の父です。親族代表として皆様にご挨拶申し上げます」などの文言を入れると良いでしょう。
葬儀社のスタッフに代読してもらう
「参列してくれた人にぜひお礼を言いたい、自分の思いを伝えたい」けれども、人前で話すのが苦手、感情が高ぶってうまく話す自信がないというケースも考えられます。
このような場合は、挨拶文だけ作って葬儀の司会を務める葬儀社のスタッフに代読してもらうことも可能です。
家族葬では喪主挨拶を省略してもOK
最近は従来の形式にとらわれない小規模形式の家族葬が主流です。
「参列者が10〜20人程度でほとんどが3親等以内のごく親しい親族のみ」というような家族葬では、喪主のあいさつを省略するケースが増えています。
喪主の挨拶はカンペを見ながらでもOK。気持ちを伝えることが重要
葬儀のさまざまな場面で喪主が挨拶をする際にカンペを見るのはマナー違反ではありません。
挨拶で重要なのは、参列者への感謝の気持ちと故人に対する思いを確実に伝えることです。
カンペを準備することで、慣れない挨拶でも落ち着いて話せる効果も期待できるでしょう。
本記事を参考に、ぜひカンペの利用を検討してください。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要