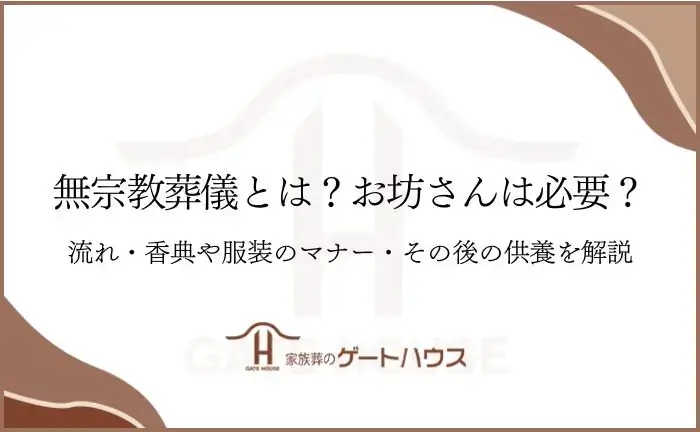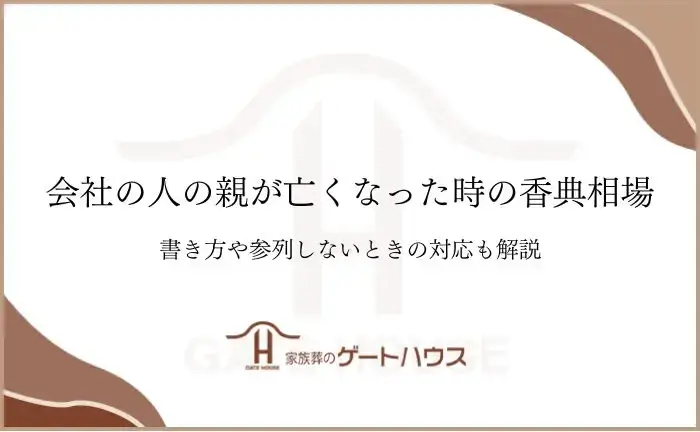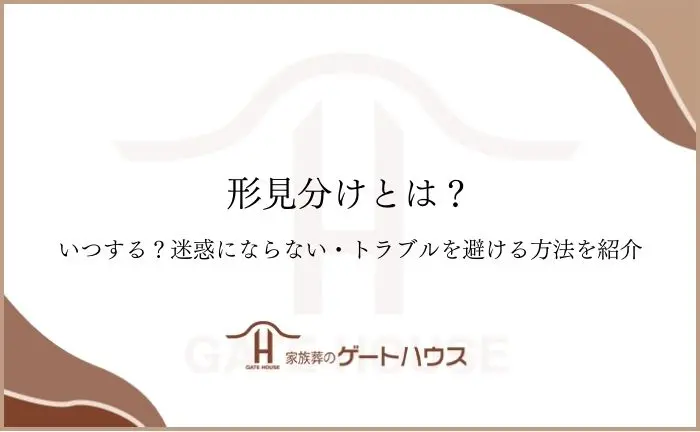お盆は海に入ってはいけない?ダメな理由や海水浴以外のしてはいけないことも解説
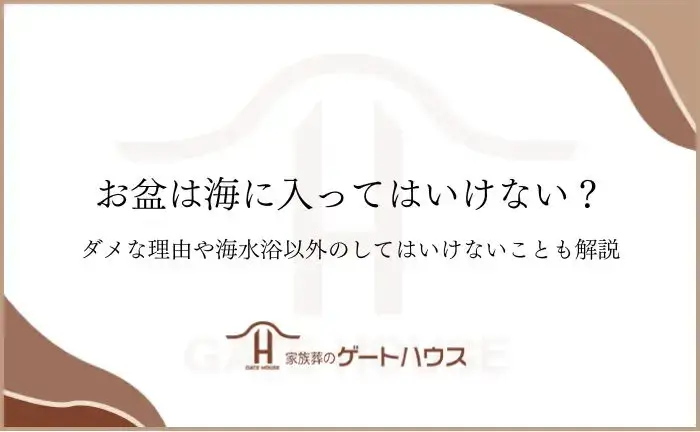
「お盆は海に入ってはいけない」という話を聞いたことがあるかもしれません。
「お盆の海に入ると足をひっぱられる」といった迷信が古くから語られており、そうした言い伝えを気にしてお盆の時期に海を避ける人も多いのではないでしょうか。
この記事では「お盆に海に入ってはいけない」といわれる理由や期間、海水浴以外で避けるべきことを詳しく解説します。
お盆に海に入ってはいけない期間
結論として「お盆の海に入ってはいけない」という明確な決まりはなく、安全に配慮すれば海に入っても問題ないといわれています。
しかしながら「お盆に海水浴をしてはいけない」という風習があるご家庭も少なくないでしょう。
海に入るのがタブー視されているお盆の期間は、下記の表を参考にしてください。
| 新盆 | 7月13日~7月16日 |
| 旧盆 | 8月13日~8月16日 |
お盆に海に入ってはいけない理由|風習編
「お盆に海に入ってはいけない」という話が広まった理由は、いくつかあります。
なかには確かな根拠のないものもありますが、地域によっては風習として根付いているところもあるので、知っておくべきでしょう。
ここでは、古くから言い伝えられている風習にまつわる理由を解説します。
閻魔斎日によるもの
古くから、旧暦の7月16日は閻魔様の休日を表す「閻魔斎日(えんまさつじつ)」といわれています。
この時期は、地獄の釜の蓋が開いて、あの世から霊魂が集まると言い伝えられているのです。
旧暦の7月16日は、現在の暦でいうと8月のお盆の時期に重なります。
「お盆に海に入ってはいけない」といわれるようになったのも「霊が海水浴をしている人の足を引っ張ってあの世に連れて行こうとする」という迷信が広まったからでしょう。
不確かな理由ではありますが、この迷信を恐れて海に入らないようにしている人も少なくありません。
ご先祖様への配慮
お盆とは、ご先祖様の霊を自宅にお迎えして供養する日本の風習のことです。
本来であれば、お盆は盆飾りを準備したり、家族でお墓参りや会食をしたりと、ご先祖様の供養のために過ごすのが一般的。
そんな大切な期間に、家を空けて海水浴場に出かけるという行動に対して「ご先祖様への配慮が足りない」と感じる人も少なくないでしょう。
「お盆に海に入ってはいけない」という話は、古くからのしきたりを重んじる人の多さから広まったのかもしれません。
【関連記事】
新盆(初盆)とは?やり方は?用意するものやいつ法要を行うか解説
お盆に海に入ってはいけない理由|環境編
「お盆に海に入ってはいけない」といわれる理由は、風習や迷信だけでなく、環境によるリスクも関係しています。
お盆の海の危険性について、意外と知られていない事実もあるので、よく理解しておきましょう。
ここでは「お盆に海に入ってはいけない」といわれる、環境にまつわる理由を紹介します。
離岸流が発生しやすいから
お盆の海では、離岸流(りがんりゅう)と呼ばれる、通常とは異なる波の流れが発生しやすいです。
離岸流とは、沖から海岸に打ち寄せられた波が、強い勢いで沖に戻ろうとする流れのこと。
一度離岸流に巻き込まれると、体格のいい大人や泳ぎが得意な人でも逃れられません。
あっという間に沖まで流されて、水難事故に遭う可能性が高くなるので、お盆の海には注意が必要です。
また、離岸流には「波の形が周辺と違う」という特徴もありますが、素人が見分けるのは難しいでしょう。
土用波が発生しやすいから
お盆の海は「土用波(どようなみ)」という波も発生しやすくなります。
土用波とは、立秋前の18日間にあたる「夏の土用」の時期に、海岸に打ち寄せる大波のことです。
土用波の正体は、日本から南に遠く離れた海上で発生した波が、台風の影響を受けて、うねりが発達したもの。
小さな波を飲み込み、かなり大きく発達した状態で日本の海岸に到達するので、風のない穏やかな気候でもいきなり大波が打ち寄せてくるのです。
場所によっては海水浴場が遊泳禁止になるほど、土用波は恐れられています。
クラゲが発生しやすいから
お盆前後の海は、クラゲが大量発生する時期でもあります。
クラゲに刺されると、強い痛みや腫れ、赤みなどが生じ、人によってはアナフィラキシーショックを引き起こす危険性もあるのです。
特に、抵抗力の弱い子どもは、大人よりも症状が強く出る可能性があるため、注意しましょう。
高波が発生しやすいから
台風シーズンでもあるお盆の海は、高波の危険性が増します。
台風の位置から海水浴場までの距離が離れている場合でも、波の大きさや潮の流れが通常とは異なる場合があるため、注意が必要です。
また、高波は、引く時の威力も強いといわれています。
海に入らず砂浜で水遊びしていたとしても、高波の影響で海にさらわれてしまう可能性があるため、台風時期の海には近づかないようにしましょう。
お盆に海に入る以外で避けるべきこと
「お盆に海に入ってはいけない」という言い伝えが有名ですが、そのほかにもお盆にしないほうがいいといわれていることがあります。
これも明確な決まりはありませんが、身内に気にする人もいるかもしれないので、頭には入れておきましょう。
最後に、海水浴以外でお盆に避けるべき注意点を解説します。
引っ越し
お盆は、ご先祖様が家に帰ってくる期間です。
この時期に引っ越しをすると、ご先祖様の霊が家に戻れず彷徨ってしまう可能性があることから、お盆の引っ越しは避けるべきといわれています。
また、土用期間中の18日間は、土いじりや土を動かすことがタブー視されています。
夏の土用の期間はお盆に近いことから、お盆時期の引っ越しが避けられる理由にもなっているのです。
むやみな殺生
お盆は、仏教において「不殺生戒(ふせつしょうかい)」の期間とされています。
「生きているものをむやみに殺生してはいけない」と考えられているため、いつも以上に生き物を大事にすることを心がけましょう。
また、地域によっては「お盆頃に飛び始めるトンボにご先祖様が乗って帰ってくる」と言い伝えられているところもあります。
虫捕りはもちろん、魚釣りなども殺生行為とみなされるため、お盆時期は避けてください。
お祝い事
「お盆休みは親族や友人が集まりやすい」という考えから、結婚式の計画を検討する人もいるかもしれません。
しかし、ご先祖様を供養する期間にあたるお盆は、お祝い事は避けるべきと考えられています。
特に年配の方にはこの考えが強く、お盆の結婚式に抵抗を覚える可能性があるため、もし式を挙げたい場合は事前に相談しましょう。
また、結婚式に限らず、入籍などもお盆に行うのは推奨されていません。
裁縫
お盆期間は、裁縫などの針を使うことも避けるべき行動の一つです。
仏教では血を「けがれ」として考えられており、針を指に刺して出血してしまう恐れがある裁縫は、お盆にしないほうがいいといわれています。
針を使うことだけでなく、トゲのある植物を扱うのもおすすめしません。
お仏壇に供える仏花にも「殺生・怪我を連想させる」という意味から、トゲのある花は避けられています。
川遊び
「お盆に海に入ってはいけない」という言い伝えの印象の強さから、海を避けて「川遊びならいいのでは」と考える人もいるかもしれません。
しかし、お盆時期の川は水温が下がることから、水草が増えやすくなります。
川の中で水草が足に絡まると、足さばきが悪くなり、溺れてしまう可能性も考えられるでしょう。
また、川の大きさによっては、海よりも流れが速く、水難事故のリスクも高まるので避けたほうが無難です。
【関連記事】
初盆(新盆)にやってはいけないことは?言葉遣いや浄土真宗などでタブーな行為を紹介
お盆は海に入ってはいけないわけではないが水辺に行く予定があるなら注意しよう
「お盆に海に入ってはいけない」という言い伝えには、明確な根拠や法律による禁止はありません。
しかし、昔から語り継がれてきた風習の一つとして、多くの人の間に根付いており、信じている人も少なくありません。
また、お盆の時期の海は、普段と異なる波の流れやクラゲの発生など、自然環境によるリスクも伴います。
お盆に水辺へ行く予定がある場合は、細心の注意を払い、安全第一で楽しむようにしましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要