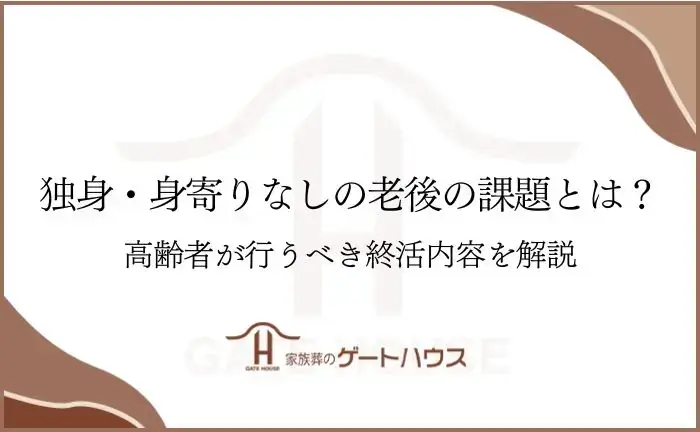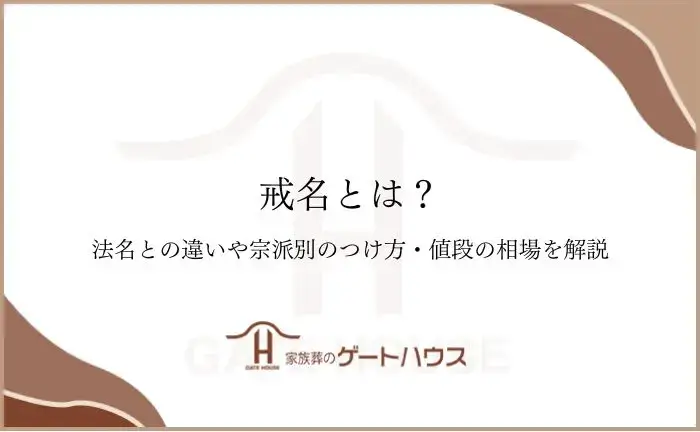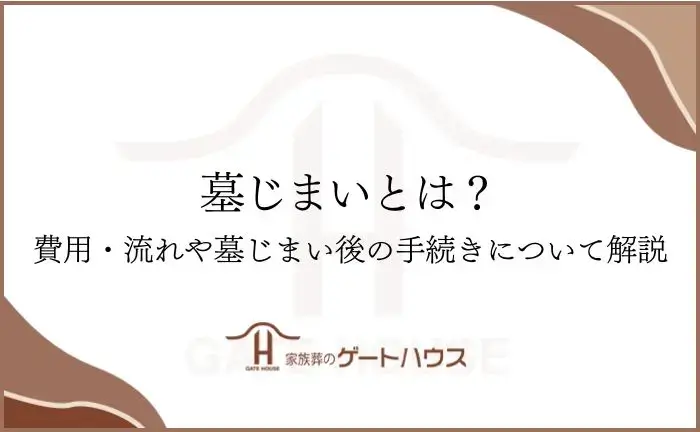真言宗の初盆とは?準備するお供え物や行うこと・服装マナーを解説
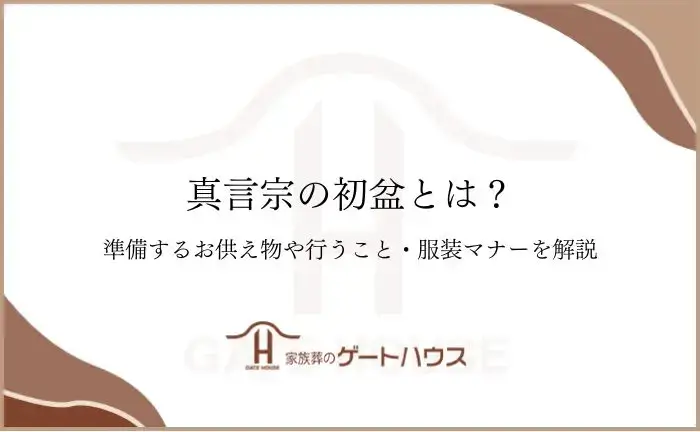
真言宗の初盆は、他の宗派とは異なる初盆飾りなどの特徴があります。
正しい供養ができるように、初盆に備えて準備するお供え物や供養の流れを理解しましょう。
この記事では、真言宗の初盆の特徴や準備するお供え物、お盆に行うことなどを解説します。
真言宗の初盆とは?
真言宗は平安時代に弘法大師(空海)が開いた密教で、基本的な教えは「即身成仏」です。
「即身成仏」とは、人も仏のように行動し清い心でいると、本来持っている仏性に目覚めて仏の境地に至るという教えです。
そのため真言宗では修行や信心を、とても重要視しています。
また、真言宗の本尊は大日如来なので、仏壇には大日如来が祀られていることが多いでしょう。
はじめに、真言宗における初盆の考え方や、他の宗派との違いについて解説します。
基本的なことは初盆と変わらない
真言宗の初盆の基本的なことは、他の宗派と変わりありません。
初盆とは、故人が亡くなった後の四十九日以降に初めて迎えるお盆で、家族は戻ってきた霊のため、いろいろな行事で供養します。
お盆の初日に「迎え火」、最終日に「送り火」を行うのが一般的ですが、地域によって日付や内容が異なる場合もあるでしょう。
また、お盆の期間中に僧侶を呼んで経をあげてもらったり、初盆法要(新盆法要)やお墓参りをしたりします。
さらに家庭では仏壇の前に精霊棚を作り、普段とは違う特別なお盆飾りをします。
【関連記事】
新盆(初盆)とは?やり方は?用意するものやいつ法要を行うか解説
曹洞宗の初盆飾りの仕方は?精霊棚(祭壇)の飾り方・お供え物・提灯について解説
初盆飾りに特徴がある
真言宗の初盆が他の宗派と違う特徴は、初盆飾り(新盆飾り)です。
初盆飾りには他の宗派と同じように果物や飲み物、花、提灯などを飾るのですが、真言宗では精進料理もお供えします。
精進料理とは、肉や魚といった動物性の食材を一切使わず、植物性の食材のみを使用した料理のことです。
また、真言宗では、先祖や故人以外の霊にも供養の心を向ける教えがあります。
そのため「閼伽水(あかみず)」「水の子」といった、先祖以外の霊へのお供え物を準備する点も、他宗派との大きな違いです。
施餓鬼法要がある
真言宗のお盆は先祖の供養だけでなく、施餓鬼法要も大切なこととされています。
施餓鬼法要とは、生前の悪行などにより餓鬼道で苦しんでいる餓鬼や、成仏できない無縁仏に食事を施す法要のことです。
真言宗では、お盆の正式名称である盂蘭盆会(うらぼんえ)に施餓鬼法要を行う寺が多く、施しをして功徳を積むと、生きている人のためにも先祖の供養にも繋がるとしています。
施餓鬼供養は、お盆以外にも行って良いといわれ、お寺によってはお盆からお彼岸まで大施餓鬼供養をするところもあります。
【関連記事】
施餓鬼(せがき)とは?行かないのはあり?意味・お布施の書き方マナー・宗派別の違いを解説
追善供養も行う
真言宗の初盆は、お墓参りをするだけでなく、菩提寺に行って本尊をお参りすることもあります。
これは真言宗で大切にされている、追善供養の教えによるものです。
追善供養とは、この世に残された人が、故人の冥福を祈ったり、菩提のため善行を積んだりすることによって、徳が備わり仏の心が育つという考え方です。
真言宗の初盆の目的は、故人の霊を迎えて供養することだけではなく、霊を迎える家族の仏性を高めるという意味も持っています。
真言宗の初盆は何をする?
真言宗の初盆に行うことは、他の宗派とほとんど同じです。
ただし、真言宗特有の呼び方や、真言宗の教えを反映した行事があるので注意しましょう。
初盆飾りの飾りつけ
真言宗の初盆で最初にすることは、初盆飾りの飾りつけです。
初盆飾りは仏壇の前に精霊棚を設置し、精進料理や精霊馬、ほおずきなどを飾りつけ、家に帰ってきた霊を特別なお供え物でもてなします。
真言宗ではお盆に施餓鬼法要を行うため、閼伽水や水の子も飾り付けます。
お盆の期間は、故人の霊がずっと滞在していると考え、お供え物は毎日取り替えるようにしましょう。
迎え火
真言宗のお盆の初日に行うのが「迎え火」です。
迎え火を焚くと煙と共に、故人の霊が帰ってくると言われています。
「焙烙(ホウロク)」と呼ばれる素焼きの皿に、麻の皮をむいて乾燥させた「オガラ」を乗せて火を付けますが、地域によってオガラではなく木を使うところもあります。
迎え火に手を合わせて拝み、燃え尽きるまで見守った後、水をかけて消火しましょう。
迎え火ができない場合は、盆灯籠や代用のロウソクを使うこともあります。
【関連記事】
お盆の迎え火・送り火のやり方は?いつやる?マンションでできる代用方法も解説
仏壇への読経(棚経)
お盆の14日か15日は僧侶を家に呼んで、お経 お教をあげてもらうことが多いでしょう。
この読経は、精霊棚の前で行うため「棚経」と呼ばれています。
棚経は、家ではなくお寺に人を集めて行われることもあります。
ただし、お盆の時期になると僧侶が多忙になるため、13日など早めの時期に棚経を行うこともあるでしょう。
また、精霊棚を飾り付けないで、飾り付けをした仏壇の前で、棚経をあげてもらう場合もあるようです。
お墓参り・法要
真言宗のお盆は、13日の日中にお墓参りをします。
これは故人の霊を迎えるためのお墓参りで「精霊迎え」と呼ばれています。
そのため、お墓は12日までに掃除しておくべきとされていますが、13日の午前中やお墓参りの時に行っても構いません。
また、お墓で迎え火を焚くところもあります。
初盆の場合は、自宅やお寺などで初盆法要を行い、その後でお墓参りをすることもあるでしょう。
お墓参りや法要の順番は、地域によって異なります。
【関連記事】
新盆はお墓参りだけでも良い?お坊さんを呼ばない場合や持ち物・服装を解説
送り火
帰ってきた先祖や故人の霊が、あの世へと戻っていく16日の夜には、自宅の前で送り火を焚いて見送ります。
送り火の手順は、迎え火と同じです。
地域によっては、送り火を焚いた後に精霊流しをするところもあるでしょう。
また、お盆の最終日にお墓に行って、お墓で送り火をする場合もあります。
ただし、夜間は墓参りが禁止されている施設もあるため、事前に確認が必要です。
真言宗の初盆で着る服装
真言宗の初盆法要を行うときは、自宅で行う場合でもお寺や斎場で行う場合でも、法要にふさわしい服装マナーを守ることが大切です。
続いては、真言宗の初盆法要の際に着る服装を、男性・女性・子どもそれぞれの場合に分けて紹介します。
男性
真言宗の初盆法要を行う主催者側の男性は、喪服を着用するのが一般的です。
初盆法要の場において、招く側の立場の人が参列者よりもカジュアルな服装になるのは避けます。
もし喪服を着ない場合は、仏事を意識した落ち着いた服装を選び、アクセサリーや華美な装飾品は外しましょう。
女性
真言宗の初盆法要において、女性も喪服を着用することとされています。
ただし、正式な喪服でなくても、黒のワンピースやアンサンブルなどの略式喪服でも問題ないでしょう。
男性と同じで、女性の場合も参列者よりカジュアルにならない服装を心がけることが大切です。
また、派手なアクセサリーや装飾品は避け、白またはグレーのパールなど控えめなものにとどめましょう。
子ども
新盆法要に子どもが参列する場合は、学校の制服があれば制服を着用させます。
制服がない場合は、落ち着いた色調の服装にすれば大丈夫です。
基本的にトップスは白のシャツやブラウス、ボトムスは黒のパンツかスカートで、スカートはあまり丈が短くないものがいいでしょう。
大人ほどマナーを気にする必要はありませんが、法要の場で不自然にならないような服装を選びましょう。
【関連記事】
初盆(新盆)の服装マナーとは?男性・女性別の着こなし方や注意点を解説
真言宗の初盆の飾り・お供え物
真言宗の初盆は、他の宗派よりも初盆飾りが多いため、お盆の直前に慌てなくて済むように、早めに準備を始めるといいでしょう。
忙しくなる前に、法要の手配を済ませ、必要となるものも揃えておきましょう。
次は真言宗の初盆を迎えるにあたって、準備するものを紹介します。
盆提灯
新盆の家庭では、故人の霊が帰って来るときの目印になるように、玄関先に「白紋天(しろもんてん)」と呼ばれる白い盆提灯を下げるのが一般的です。
近年は集合住宅に住む方や、ご近所に初盆であることを知らせるのに抵抗を感じる方も多く、屋内に白提灯を飾る家庭も増えています。。
盆提灯には伝統的な吊り下げ型のほか、スタンド型、コードレス型、LED照明付きのものなど、現代の住宅事情に配慮した多様なタイプが販売されています。
【関連記事】
新盆(初盆)の提灯は誰が買う?飾り方・選び方やいつから飾るのかを解説
精霊棚(盆棚)
新盆の時期には、仏壇の前に精霊棚(盆棚)と呼ばれる祭壇をセットして、位牌や初盆飾り、お供え物などを置きます。
玄関先に盆提灯を吊るさない場合は、精霊棚の横に置いて飾ることもあります。
精霊棚を新たに購入しなくても、四十九日法要の時に使った祭壇をとっておいて再利用したり、自宅にある台を使用することも可能です。
精霊棚に載せるお盆用品は、地域や家庭ごとの習慣によって異なるため、菩提寺や仏具店などで聞いてみましょう。
精霊馬
精霊馬とはナスやキュウリに爪楊枝、または箸を刺して馬や牛に見立てたもので、精霊棚に飾り付けるお供え物の1つです。
精霊馬は、ご先祖様や故人が乗る乗り物の意味があり、お盆の前半は内向きに置き、後半には外向きになるように置きます。
馬と牛がいる理由は、家に帰る時は「馬」に乗って早く来て、あの世に戻る時は「牛」に乗ってゆっくり帰れるようにという、願いが込められているからです。
【関連記事】
お盆のナスとキュウリ「精霊馬」の向きは?意味・地域・宗派の違いや作り方も解説
ほおずき
鮮やかなオレンジ色のほおずきは形が提灯に似ているので、真言宗の初盆だけでなく他の宗派のお盆飾りでも、盆提灯に見立ててお供えします。
お盆にあの世から戻ったご先祖様や故人の霊は、ほおずきの明るい色に招かれて、精霊棚へとやって来るのです。
かつては、お盆のお供え物にあまり多くの農作物が揃えられなかったので、華やかな雰囲気を演出するため、ほおずきを置くようになったともいわれています。
お団子
初盆にお供えする食べ物はいろいろですが、定番なのはお団子です。
お盆のお団子の種類は、故人の霊を迎える「お迎え団子」、お盆の中日に飾る「お供え団子」、お盆が終わってあの世に霊を送るための「送り団子」があります。
お迎え団子は旅の疲れを癒やしてもらうという意味で、味がついた団子をお供えすることもありますが、送り団子は必ず白いお団子にします。
お団子の数や積み方は地域によって異なるため、居住区の慣習に従いましょう。
精進料理
真言宗のお盆には、精霊棚に精進料理をお供えするという決まりがあります。
精進料理は、殺生につながる肉や魚介類、卵など動物性の食材を使わない料理で、野菜や芋類、海藻などを使った煮物や和え物、揚げ物などです。
また、五葷(ごくん)と呼ばれるニラやらっきょう、アサツキなど、香りの強い野菜を使いません。
お盆の期間は、毎食精進料理をお供えすることとされていますが、難しい場合はお盆の中日(14〜15日)だけにする場合もあります。
【関連記事】
お盆のお供え料理の定番メニューは?置き方・期間・基本マナーも解説
お供え物
真言宗の初盆は、精進料理以外にも独特なお供え物を準備します。
たとえば「閼伽水(あかみず)」は、器や蓮の葉に水を入れてミソハギ、または季節の花を添えたものです。
お盆の間、ミソハギの花にこの水を含ませてお供え物にかけると、餓鬼の救済や供養になるとされています。
また、さいの目に切った野菜と洗った米を混ぜて蓮の葉や器に盛り付けた「水の子」は、ご先祖様だけでなく無縁仏など、すべての霊に対する供養になります。
お布施
初盆の法要の手配をしたら、法要の後で僧侶に渡すお布施を準備します。
僧侶を家や斎場に呼ぶ場合は、お布施に加えて「お車代(交通費)」を包むのが一般的です。
また、法要後の会食に僧侶が参加されない場合は「御膳料」を別途包む場合もあります。
お布施は、不祝儀袋に「お布施」と表書きしたものに入れて渡します。
お車代や御膳料もそれぞれ別の封筒に分けて渡すのが基本ですが、お布施の袋に一緒に入れる場合は、内訳を明記した「明細書」を添えると丁寧です。
お供えへの返礼品
真言宗の初盆法要に親戚や知人を招いた場合は、香典やお供え物へのお返しを準備します。
返礼品の相場は2千〜5千円程度で、焼き菓子などの日持ちする食品や、石鹸などの消耗品を渡すのが一般的です。
予想よりも多くの参列者が来るケースに備えて、数は多めに準備します。。
もし予想より高額の新盆見舞を頂いた場合は、後日改めて別の返礼品を送るようにしましょう。
真言宗の初盆でのマナー
真言宗の方の初盆法要に招かれて自宅やお寺などに行くときや、初盆見舞いを送るときには、気をつけるべきマナーがあります。
次は真言宗の初盆のマナーを確認しましょう。
お供えを避けるべき品物に注意する
真言宗の初盆法要に参列するときや、初盆見舞いとしてお供え物を送るときは、タブーとされる品物を選ばないように注意しましょう。
お供え物にふさわしくないとされているのは、鰹節や昆布などのお祝いごとを連想させる品や、肉・魚など殺生を感じさせるもの、傷みやすい生ものの食品です。
また、強い香りを放つ花や故人とゆかりのある品も、初盆のお供えには避けるべきと言われています。
法要に参列する際には香典を準備する
真言宗の初盆法要に参列する際は、香典を準備するのが一般的です。
ただし、地域やご家庭によって異なるため、事前に年長の親族などに確認しておくと安心です。
香典の金額は、故人との関係性によりますが、3,000〜10,000円が相場とされています。
親しい身内の場合は、相場以上の金額を包むこともあります。
また、法要後の会食に参加する場合は、別途3,000〜10,000円程度を加えるか、あらかじめその分を香典に包むと良いでしょう。
お供え物を送る場合は、香典の金額をやや抑えることもあります。
【関連記事】
初盆(新盆)の香典相場は?不祝儀袋の選び方・書き方や表書きのマナーなど解説
真言宗の初盆に関するよくある質問
真言宗の初盆を迎えるにあたり、多くの人が疑問に思うことのQ&Aをまとめました。
最後は、真言宗の初盆に関する、よくある質問を紹介します。
真言宗の新盆の盆棚の飾り方は?
真言宗の初盆では、仏壇の前に「精霊棚(しょうりょうだな)」を設け、丁寧に飾り付けを行います。
まず棚の上に真菰(まこも)を敷き、仏壇から位牌を出して安置します。
新盆で供養する故人の位牌は、やや手前の中央に置くのが一般的です。
位牌の前には、香炉・燭台・花立からなる「三具足(みつぐそく)」を並べ、
その周囲に、精霊馬(きゅうりやナスの飾り)や果物、精進料理、飲み物などのお供え物を用意します。
精進料理は、箸を仏壇側に向けて配置するのが丁寧な供え方です。
果物は皮をむいて一口大に切り分けて供えると、より心のこもった印象になります。
お団子を供える際は、敷紙の尖ったほうを手前に向けるようにしましょう。
真言宗の初盆はいつから始まる?時期は?
真言宗の初盆の時期は、8月13〜16日または7月13〜16日に行います。
日本の多くの地域では、8月にお盆を迎える新暦盆が一般的ですが、東京や神奈川、北海道の一部の地域などでは、7月をお盆とする旧暦盆のところもあります。
これは宗教よりも地域性を反映しているので、自分の住む地域や家の習慣ではどちらをお盆にするのかを調べてから、初盆の準備をした方がいいでしょう。
真言宗の初盆で渡すお布施の相場はいくら?
真言宗の初盆で僧侶に渡すお布施の相場は、一般的に3〜5万円程度といわれています。
あくまで「気持ち」として包むものであり、金額に厳密な決まりはありません。
通常のお盆のお布施は3〜4万円程度といわれているので、新盆の場合はお布施が少し多めになると覚えておきましょう。
真言宗の初盆は他と大きくは変わらない。飾りや追善供養等の細かな違いにご注意を
真言宗の初盆は、他の宗派と大きくは変わりませんが、初盆飾りや施餓鬼法要、追善供養など、真言宗の教えにのっとった細かな違いがあります。
お盆が始まって忙しくなる前に準備するものを揃え、毎日備える精進料理の計画を立てたり、初盆法要の手配をしたりしておくといいでしょう。
また、迎え火や墓参りで始まり、送り火まで、初盆にすることを理解し、帰ってこられる故人の霊を正しく供養できるようにしておきましょう。
【他宗派・宗教における初盆】
神道に初盆は無い?祭壇の飾り方・香典やお礼の表書き・仏式のお盆との違いを解説
浄土真宗の初盆の迎え方は?お布施相場やお供え物・仏壇の飾り方など解説
曹洞宗の初盆飾りの仕方は?精霊棚(祭壇)の飾り方・お供え物・提灯について解説
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要