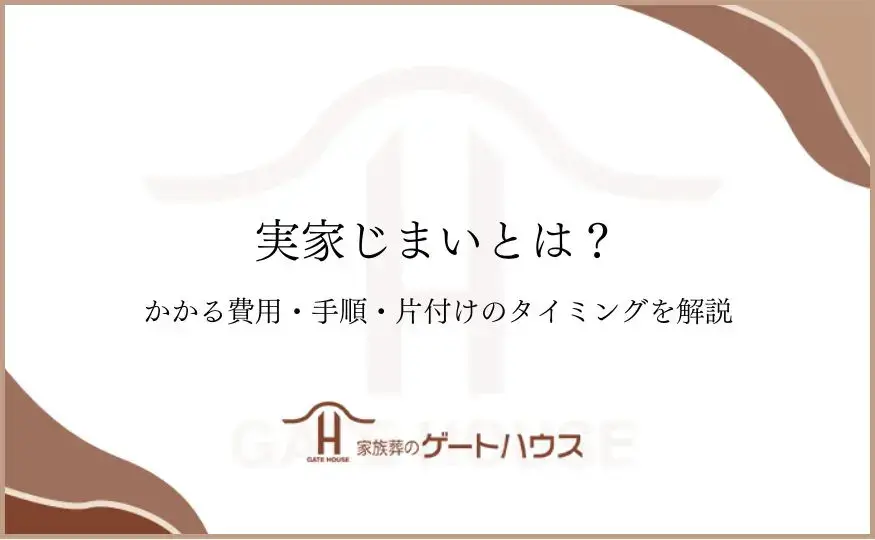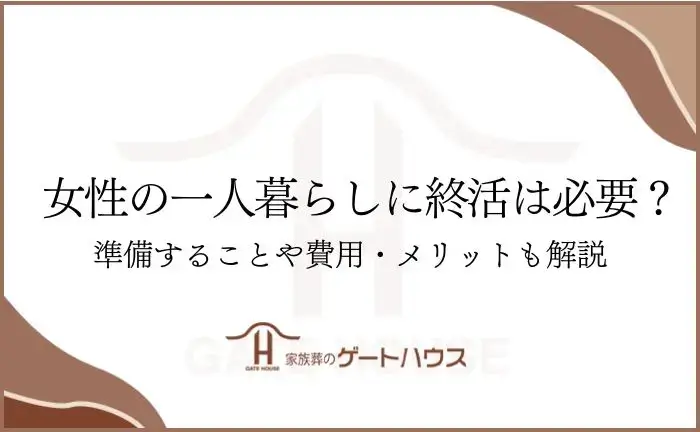お盆のそうめんの飾り方&意味を解説!いつお供えする?正しい配置は?
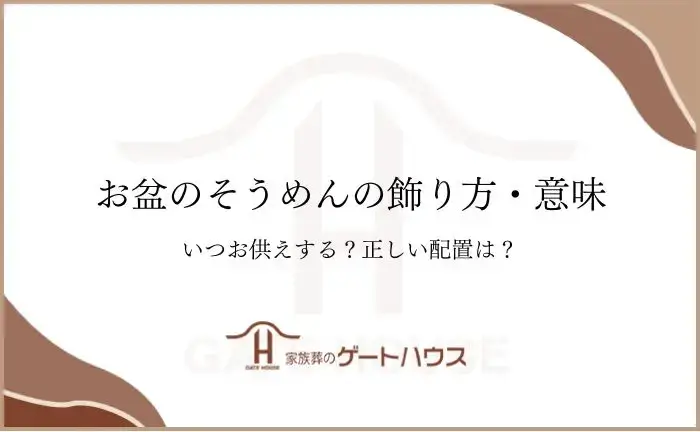
お盆にはそうめんを飾る習慣がありますが、正しい飾り方や意味をご存知ですか。
生のまま飾るのか茹でるのか、いつ供えるのが正しいのか、その由来は何かなど、この記事では、お盆の飾りそうめんについての基本をわかりやすく解説します。
ご先祖様への感謝の気持ちを込めた、正しい供え方を学びましょう。
お盆のそうめんの飾り方・期間
お盆にお供えするそうめんは、実は期間によって飾り方が変わります。
この飾り方や期間にはそれぞれ意味があるため、ご先祖様に失礼のないよう、正しく供えることが大切です。
地域やご家庭、宗派の慣習によって違いはありますが、ここでは一般的な飾り方の流れと期間について詳しく解説します。
お盆の間は盆飾りとして茹でずに飾る
地域による違いはありますが、ほとんどの家庭やお寺では、8月13日〜16日(地域によっては7月13日〜16日)のお盆の期間を通じて、そうめんは乾麺のままお供えします。
これは、そうめんが単なる食べ物ではなく、ご先祖様をお迎えし、お送りするための道具としての役割を持っているためです。
ご先祖様に失礼がないように、そして衛生的にも安心して過ごせるように、乾麺のままお供えします。
また、初盆(新盆)には早めに準備をする地域もあるため、その土地の風習に合わせましょう。
真菰(まこも)の上・白皿に乗せる
そうめんを飾る際には、置き場所や器にも意味があります。
最も丁寧な飾り方は、盆棚(ぼんだな)や精霊棚(しょうりょうだな)と呼ばれる、お盆のお供え物を飾るための祭壇の上に置く方法です。
仏壇の前に設置した盆棚に盆花を供え、真菰(まこも)というイネ科の植物で編んだゴザの上にそうめんの束を置きます。
盆棚や真菰がない場合は、白いお皿に乗せたそうめんをお供えするだけでも、心のこもったお供えになります。
束の本数は奇数に
そうめんの束は「3束」「5束」など、奇数にして供えるのが基本です。
日本では古くから奇数は縁起が良いとされ、「割れない・分けられない=縁が切れない」という考えとつながっています。
偶数は割り切れてしまう、つまり縁が切れてしまう数字とされ、慶事や仏事では避けられる傾向が強いです。
お盆飾りの果物や野菜、お菓子なども、奇数を意識すると良いでしょう。
ただし「9」は「苦」を連想させるため、避けたほうが無難です。
8月15日はお供え料理として茹でて飾る
8月15日には、乾麺ではなく茹でたそうめんをお供え料理として盆棚に供えましょう。
これには、「お帰りになるご先祖様に霊供膳としての食事を用意する」という意味合いが含まれています。
茹でたそうめんは、食べやすいように一口分ずつ巻いて盛り付け、薬味やつゆを添えておもてなし感を出すとご先祖様も喜ばれるのではないでしょうか。
茹でたそうめんをお供えすることは、ご先祖様への感謝の気持ちと供養、家族の健康や繁栄、絆を願う意味も込められています。
【関連記事】
お盆のお供え料理の定番メニューは?置き方・期間・基本マナーも解説
お盆にそうめんを飾る意味・由来
お盆にそうめんを飾るのは、日本各地で古くから伝わっており、そうめん自体にさまざまな意味や願いが込められています。
ここからは、なぜお盆にそうめんを飾るのか、その意味や由来について詳しく解説します。
細く長い形状に願いを込めて
そうめんの長さは「長寿」の象徴とされ、家族の健康と長生きを願う気持ちが表現されています。
また、細くても切れにくい強さは、家族の絆や先祖とのつながりを表していると言われており、昔からそうめんには「家族や子孫が長く、細く(絶えることなく)幸せに続きますように」という願いが込められてきました。
そうめんをお供えすることで、ご先祖様への感謝を伝えるとともに、残された家族の幸せと繁栄を祈っています。
ご先祖様の手綱に
お盆には、ご先祖様はあの世からきゅうりで作った馬(精霊馬)に乗ってできるだけ早く家に帰り、あの世へ帰るときは、なすで作った牛(精霊牛)に乗って名残を惜しみながらゆっくりと帰っていく、という言い伝えがあります。
古くからそうめんは、その乗り物を操る手綱の役割を果たすと考えられていました。
ご先祖様が迷わず安全に戻れるよう、そうめんを手綱に見立ててお供えしたのでしょう。
ご先祖様の荷造りの紐に
そうめんは、荷物をまとめるための紐に見立てたものともいわれています。
お盆の期間が終わり、ご先祖様があの世に帰るときに、この世での思い出や家族からのお供え物を持ち帰るための荷造り紐として、そうめんが使われるのです。
安全にたくさんお土産を持って帰ってもらいたいという、ご先祖様を気遣う家族の優しさが表れています。
麦の収穫祭をかねて
お盆の時期とそうめんの関係には、農耕文化に基づいた実用的な側面もあります。
そうめんの原料である小麦は、初夏に収穫される作物です。
ちょうどお盆の時期は、新しく収穫された小麦のそうめんが食べられる季節。
このため、麦の収穫祭の意味合いも込めて、そうめんをご先祖様に供えるようになったという説もあります。
七夕行事の名残
お盆のそうめんは、七夕行事の名残だという説もあります。
古来中国から伝わった七夕は、天の川や織姫・彦星物語になぞらえ、機織りが上達するようにとの願いもこめられてきました。
祭りの際には、白い糸に見立てたそうめんを食べる風習があり、それがお盆時期にも定着。
お供え物としてのそうめん文化が生まれたともいわれています。
お盆のそうめんの飾り方Q&A
お盆のそうめんの飾り方や意味について解説してきましたが、いざ準備するとなると「これはどうすればいいの?」と細かい疑問が出てくることもあると思います。
ここからは、お盆のそうめんにまつわるよくある質問にお答えしていきますので参考にしてください。
そうめんを供えたあとは食べてもいい?
お盆に供えたそうめんは、お参りが終わったあとに家族みんなでいただいて構いません。
昔から、お供え物を食べることで、ご先祖様のご加護を受けられるといわれてきました。
お盆の供物は「おさがり」とも呼ばれ、これをいただくことで、ご先祖様と心が繋がると考えられています。
お供えしたまま長く放置するのは衛生上良くないので、なるべく早めに下げていただきましょう。
そうめんの代わりにうどんや冷や麦でもいい?
そうめんの代わりに、うどんや冷や麦を使っても問題ありません。
地域や家庭の事情に合わせて柔軟に対応しましょう。
実際に、うどんが特産の地域ではうどんを食べる風習がある、ということもあります。
長い麺類が、長寿や家族のご縁の象徴である点に意味があるので、うどんや冷や麦を飾っても失礼には当たりません。
家族だけのお盆でも飾るべき?
お盆は家族だけで行う場合でも、可能な範囲で、そうめんを含めた供え物を飾ることをおすすめします。
規模は小さくても、ご先祖様を敬う気持ちを表すことが大切です。
ただ、忙しい現代生活の中では、全ての伝統的な作法を完璧に行うことは難しいかもしれません。
そうめんではなく、故人の好きだったものをお供えするなど、形式にとらわれず、できる範囲で心を込めてお迎えの準備をしても良いでしょう。
時間帯はいつ供えるのがよい?
乾麺のそうめんは、ご先祖様をお迎えする13日の午前中にはお供えしておきます。
8月15日の茹でたそうめんの場合は、朝にお供えしていた乾麺をいったん下げ、お昼にご家族が食事をとるのと同じタイミングで、茹でたそうめんをお供えし直してあげると良いでしょう。
ただし忙しい現代では、家族の集まりやすい時間帯に合わせて供えるなど、柔軟に対応する家庭も増えています。
【他のお盆に関するよくある質問はこちらから】
初盆(新盆)にやってはいけないことは?
初盆をしないとどうなる?
初盆(新盆)の服装マナーとは?
お盆のそうめんは、飾り方ひとつにも心を添えて
お盆のそうめんは、単なる供え物ではなく、ご先祖様への思いやりと敬意を形にした大切な習慣です。
飾り方や作法にこだわることは、私たちの心をご先祖様に届ける方法でもあります。
現代では簡素化する傾向もありますが、大切なのは形よりも心です。
伝統を守りながらも、自分の家庭に合った形でご先祖様との絆を確かめる機会としてお盆のそうめんを飾りましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要