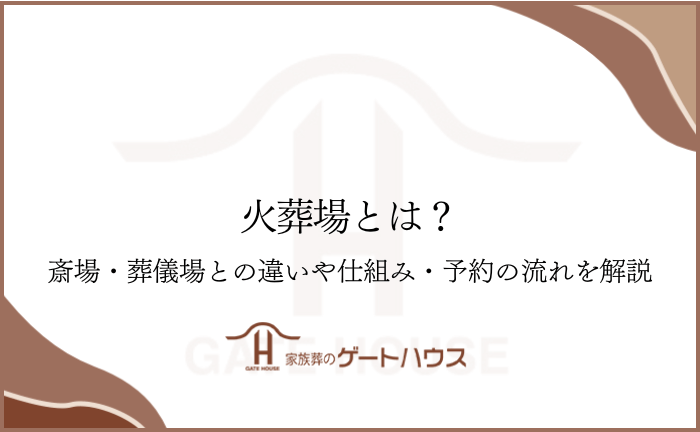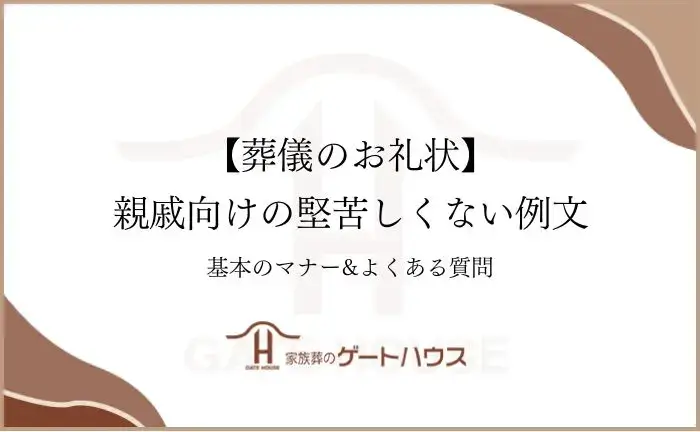告別式とは何をする?葬儀やお通夜との違い・マナー・流れを解説
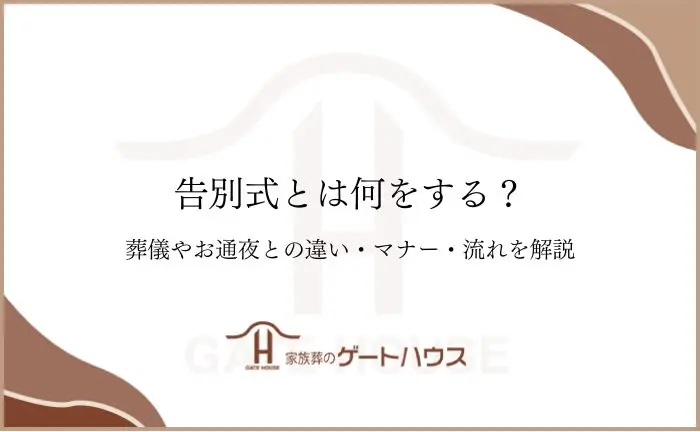
人が亡くなったときによく聞く告別式、葬儀、お通夜などの言葉。
これらはすべて弔事における儀式を表す言葉ですが、その違いをはっきりと理解している人はそれほど多くないでしょう。
この記事では、告別式が葬儀やお通夜とどう違うのかを解説します。
告別式のマナーや流れもあわせて紹介するので、お葬式に参列するとき・お葬式を執り行うときの参考にしてください。
告別式とは?葬儀やお通夜との違いは何?
現代では、葬儀と告別式の区別はなくなりつつあります。
一方、お通夜は、通常の日程では葬儀・告別式の前日に行われる儀式です。
これらの違いを正確に理解するには、日本において亡くなった人を見送る習慣がどのように変化していったかを理解することが欠かせません。
歴史的な経緯を踏まえて「通夜」「葬儀」「告別式」の違いを詳しく解説します。
通夜は本来近親者による儀式
通夜は正式名称を「通夜式」といいます。
かつては故人が亡くなった当日、家族が遺体の近くで夜通し過ごす儀式で、近親者のみで心置きなく故人を偲んでいました。
医学が発達していない時代では死亡の判定もあいまいで、亡くなったと思っていた人が生き返るというようなケースもあったため、故人の復活を願う儀式でもあったとの説もあるようです。
やがて、遺族の負担が大きいことや地域の相互扶助で行っていた葬儀関連の儀式を葬儀社に依頼するようになったことで、通夜の形態は変化します。
現代では、通夜は葬儀・告別式前日の夕方に開始し、比較的故人と親しかった人が供養を行う儀式になりました。
【関連記事】
葬儀は宗教的儀式
葬儀は、近親者が集まり故人を供養する宗教的儀式です。
「葬儀式」を略して葬儀または葬式と呼びます。
仏式の葬儀の場合は、亡くなった人が成仏できるように僧侶が読経を行います。
通夜の翌日の日中に行われるケースが多く、時間は30〜40分程度。
その後、引き続き告別式が行われます。
告別式は社会的儀式
告別式は、多くの人が参列し故人に別れを告げる社会的儀式です。
もともとは宗教的儀式である葬儀が終わったあとに、葬儀式場から墓地や火葬場まで遺体を運ぶ「野辺送り」の風習が告別式の由来とされています。
現代では葬儀と告別式は一体化
本来、葬儀と告別式は別のものでしたが、現代では一体化して実施されています。
厳密には、僧侶の読経と親族の焼香までが本来の葬儀。
それに続いて行われる一般参列者の焼香が告別式です。
しかし、実際には葬儀と告別式の境目はなく、特に区別することなく一連の儀式として執り行われています。
さらに告別式と通夜の違いもなくなりつつあります。
多くの場合、通夜は夕方から開始されるのが一般的です。
会社員などは、日中に行われる告別式よりも通夜の方が参列しやすい傾向にあります。
身内向けの行事であった通夜が次第に一般参列者向けへと変わり、結果として通夜と告別式で行われる内容はほとんど同じになっています。
【関連記事】
通夜と葬式の違いは?葬儀・告別式との違いや流れ・マナーも紹介
葬儀・告別式の流れ
葬儀社に依頼して仏式の葬儀・告別式を行う場合の一般的な流れを解説します。
細かい流れは、同じ仏教でも宗派によって異なります。
また地域や葬家の慣習、葬儀社のやり方などもあるため、順番などは必ずしも以下のとおりになるとは限りません。
基本的には、葬儀社のスタッフのアドバイスに従えば大丈夫です。
事前準備
告別式に臨む前に、喪主・遺族は以下のようなことを決めましょう。
受付担当者
葬儀の受付は、遺族の代表として弔問客を迎える重要な役割です。
一般的に、親族の中で比較的若く、作業の迅速な20代〜30代の孫や甥・姪に依頼することが多いです。
適任者がいない場合は、近隣の方や会社関係者にお願いすることもあります。
もし依頼できる人がいなければ、葬儀社のスタッフに代行を相談するのも一つの方法です。
式中に読み上げる弔電
弔電がたくさんある場合は、どれを式中に読み上げるかを決める必要があります。
その際、送信者の肩書や社会的地位を考慮しつつ、故人や遺族との関係性も踏まえて選びましょう。
また、内容が類似した弔電が複数ある場合は、代表的なものを選び、重複を避けることが望ましいです。
席次
式場での座る位置を決める際、基本的に遺族は祭壇に近い席に座り、一般参列者に向かい合うように配置されます。
親族の席順は、故人との血縁の近さや年齢を考慮して決めるのが通例です。
一般参列者の座席は特に決める必要はありませが、焼香は席順に沿って進められることが多いです。
また、関西を中心に「止め焼香」という習慣があります。
止め焼香とは、焼香の最後に故人と一番血縁関係が深い年長者が焼香するという習慣です。
故人が70~80代でなくなった場合は、故人の兄弟姉妹の中の年長者が止め焼香を行います。
止め焼香を行う人を事前に決めておくことも大切なので、親族間で相談しましょう。
喪主挨拶の内容
喪主挨拶の内容も事前に考えておきましょう。
挨拶に盛り込むべきポイントは、参列へのお礼と葬儀・告別式が無事終了したことの報告の2つです。
また、長くなりすぎないように簡潔に話すよう心がけてください。
もし、喪主が未成年などの理由で、挨拶が難しい場合は親族代表が代わりに挨拶を行います。
受付
受付をセッティングするのは、葬儀開始時間の30分ほど前です。
このときまでに、受付に必要な芳名録や筆記具を準備し、受付担当者は受付で待機します。
香典をもらうかどうかも受付担当者と打ち合わせておきましょう。
会葬に来た方には、会葬御礼を渡します。
会葬御礼は全員に渡すものなので、数に少し余裕を持って準備してください。
開式
遺族も参列者も、開式前に式場に入り、着席します。
時間になると宗教者(僧侶)が入場して、司会者が開式の挨拶を行います。
僧侶が入場する際は、黙礼と合掌でお迎えしましょう。
葬儀・告別式の司会・進行は、葬儀社のスタッフが担当するのが一般的です。
読経
続いて、仏式の葬儀では僧侶による読経が行われます。
読経の時間は通常30分程度。
浄土真宗以外の多くの宗派では、読経の後、引導が執り行われます。
引導とは、僧侶が法語を唱えて故人をあの世へと導く儀式です。
【関連記事】
浄土真宗の葬儀の流れは?お布施の相場や本願寺派・大谷派別に葬式の順序を解説
焼香
読経が一区切りついたところで司会者の合図で焼香が始まります。
焼香の順は、基本的に喪主、遺族、親族、一般参列者の順です。
厳密には遺族の焼香までが葬儀で、一般参列者の焼香からが告別式ですが、現代では特に区切りを設けず、親族の焼香が終わると引き続き一般参列者の焼香が始まります。
僧侶退場
すべての人の焼香が終了すると、僧侶が退場します。
参列している全員で合掌して退場を見送りましょう。
弔電の披露
続いて司会者が弔電を読み上げます。
弔電がたくさんある場合はいくつかを選んで読み上げ、残りは送信者の肩書(所属)と名前だけを紹介するのが一般的です。
喪主挨拶
告別式の最後では、喪主が参列者に対して参列への感謝の言葉を述べます。
喪主は事前に話す内容を考えておきましょう。
閉式
司会者が告別式の終了を伝えて、葬儀・告別式は終わります。
このあと、お別れの儀が行われます。
お別れの儀とは、故人と対面し最後の別れをする時間です。
葬儀で飾っていた花を敷き詰め(別れ花)、故人の愛用品や好物も一緒に棺の中に入れます。
ただし、多くの火葬場では不燃物を棺の中に入れることはできないため、事前に確認が必要です。
また、かつては棺のふたを閉じる際にクギを打つ「釘打ちの儀」が行われていましたが、近年では省略されるケースも増えています。
釘打ちが終わると出棺となり、火葬場へ向かいます。
出棺の際には、火葬に立ち会わない一般の参列者は合掌して見送ります。
【関連記事】
告別式での基本的な参列マナー
告別式には、葬儀特有のマナーがあります。
過度に意識する必要はありませんが、遺族に失礼にならないように基本的なマナーを理解した上で告別式に臨みましょう。
参列前の事前確認
最近は参列者を限定した家族葬が増えています。
とはいえ、家族葬だからといって参列すべき人が明確に決まっているわけではありません。
訃報の連絡を受けた時に、遺族側がはっきりと参列辞退をしているかどうかわからない場合は、あらためて遺族側に参列してもかまわないかどうかの確認をしましょう。
また、香典・供花・弔電を辞退する葬儀も増加傾向にあります。
この点も事前にチェックしなければなりません。
【関連記事】
訃報LINEへの返信例文を相手別に紹介!お悔やみを伝える10のマナー
受付でのマナー
葬儀式場に到着するとまずは受付です。
受付では、簡潔にお悔やみの言葉を述べて芳名録に記帳します。
お悔やみの言葉は「このたびはご愁傷様です」「心よりお悔やみ申し上げます」などの一般的なフレーズでかまいません。
「ご冥福をお祈りします」は避けた方が無難です。
「冥福」には「冥土(めいど)で幸福になる」という意味があります。
キリスト教や神道、仏教でも浄土真宗の教えにはそぐわない考え方です。
【関連記事】
お悔やみの言葉の例文集|友人・親戚へのメールやLINEのマナーとは?
「謹んでお悔やみ申し上げます」の意味は?メールやLINEで伝える時の例文も紹介
「ご愁傷さまです」は使ってはいけない?メールで使うと失礼?使い方と例文を紹介
お悔やみ申し上げます・ご冥福をお祈りしますはどっちを使う?メールでの例文も紹介
香典のマナー
香典は、受付で記帳が終わったあとに渡します。
香典の渡し方にもマナーがあります。
まず、香典は袱紗(ふくさ)に包んだ状態で持参するのが正しいマナーです。
渡すときは袱紗の上に不祝儀袋を乗せ、のし書きの文字が相手に読めるように向きを変えます。
不祝儀袋を両手で持ち「お納めください」などの言葉を添えて渡しましょう。
【関連記事】
香典袋は薄墨でないとだめ?書き方やいつまで濃墨を使わないべきかを解説
香典を書くのにボールペンしかないときは?外袋・中袋の書き方も紹介
着席時・告別式中のマナー
式場で座る席はあらかじめ決められている場合があります。
座っていい場所がわからない場合は、葬儀社スタッフなどに確認してください。
告別式が行われている最中に着信音や通知音が鳴らないよう、携帯電話は電源を切るか、マナーモードにします。
暑いときでも喪服の上着は脱がない、寒いときでもコートやマフラーは身に付けないのが基本です。
あまりにも暑い場合や寒い場合は、葬儀場スタッフにお願いしてエアコンの温度を調節してもらいましょう。
服装のマナー
告別式での服装は喪服が基本です。
喪服にもいろいろありますが、一般的に「略礼服」と呼ばれているものを着用すれば問題ありません。
男性の場合、黒の上下のスーツに白いワイシャツ、黒のネクタイ、黒の靴を身に付けます。
女性の場合は、黒のスーツやワンピース。
靴は黒で、ストッキングは薄めの黒または肌色が望ましいでしょう。
【関連記事】
葬儀で女性が着るべき服装とは?喪服の種類やお葬式の身だしなみマナーを解説
持ち物のマナー
告別式に参列する際は、数珠とハンカチを用意します。
ハンカチの色は白または黒が基本です。
香典を渡す場合は、袱紗も忘れずに準備しましょう。
バッグなどの小物類も黒色で、派手な装飾のないものを選んでください。
女性の場合、結婚指輪以外のアクセサリーは身につけないのがマナーです。
ただし、涙の象徴とされている真珠のネックレスだけは例外的に着用しても問題ないとされています。
【関連記事】
葬儀の持ち物チェックリスト!お葬式に必要なものやマナーを解説
葬儀用バッグのマナーとは?お葬式用カバンの選び方を男性・女性別に解説
葬儀用のハンカチは何色が適切?お葬式で使える柄や男女別のマナーを解説
焼香のマナー
焼香は、基本的に故人と親しい人から順番に行います。
まずは喪主・親族が行い、その後、会社関係者や特に関係の深い方が名前を呼ばれて焼香します。
一般参列者は名前を呼ばれることはなく、座っている順に速やかに焼香するのがマナーです。
また、焼香は仏教の儀礼であり、宗教によって異なる弔い方があります。
神道では玉串奉奠(たまぐしほうてん)、キリスト教では献花が行われるため、それぞれの宗教に合わせた作法でお別れをしましょう。
告別式での一般的な注意点
基本的なマナーに加えて、以下のような点にも注意が必要です。
忌み言葉を使わない
葬儀・告別式では、縁起が悪いとされる「忌み言葉」を使うのはマナー違反です。
受付で記帳するときや遺族に挨拶するときには、忌み言葉を使わないように気をつけなければなりません。
忌み言葉には直接的に「死」を表す言葉、不幸が繰り返されることを連想させる「重ね言葉」、不幸が続くことを連想させる「続き言葉」などがあります。
主な忌み言葉とその言い換え例を以下に示します。
| 忌み言葉 | 言い換え例 |
| ①直接「死」を表す言葉 | |
| 死ぬ | 亡くなる・逝去する |
| 急死 | 突然のこと |
| 生きていころ | ご生前 |
| ②重ね言葉 | |
| ますます | よりいっそう・一段と・もっと |
| 重ね重ね | 加えて |
| 次々 | 立て続けに |
| ときどき | 時折 |
| ③続き言葉 | |
| 再び | 今一度・さらに |
| 引き続き | 今後とも・これからも |
| 何度も | 頻繁に |
平服は普段着ではない
訃報連絡で、服装に関して「平服でお越しください」との注意書きが書かれているケースがあります。
この場合の「平服」とは普段着ではありません。
一般的には、黒またはダークカラーのスーツのことです。
急な訃報連絡を受けたり、会社帰りにお通夜に参列したりする場合は、平服でかまわないとされています。
わからないことは葬儀社のスタッフに尋ねる
葬儀は、普段の生活の中でそれほど多く経験するものではありません。
その一方で、葬儀・告別式には独特のマナーがあります。
わからないことがあれば、遠慮なく葬儀社のスタッフに尋ねてください。
喪主や遺族に確認したいことでも、直接聞きづらければ葬儀社のスタッフを介して確認するとよいでしょう。
告別式と通夜のどちらに参列すべき?
基本的にはどちらに参列してもかまわないので都合がつく方に出れば良いでしょう。
もちろん両方に参列してもかまいません。
かつては通夜は近親者を中心に行い、告別式は一般参列者が参加という流れでした。
しかし現代では、通夜が夜6時〜7時頃の開催、告別式は午前中の開催が一般的です。
そのため、会社勤めをしている場合、日中に行われる告別式には参列しにくいので通夜に参列するケースが増えています。
葬家と会葬者の宗教・宗派が違う場合、焼香はどうする?
焼香の仕方や数珠の持ち方は仏教の宗派によって微妙に異なります。
抹香(まっこう)をつまむ回数や額の付近までおしいただくのかどうか。
手を数珠にかける作法も、宗派によって違います。
しかし、葬家の宗派が何であっても自分の信仰する宗派のやり方でかまいません。
自分が信仰する宗派の焼香の仕方がわからない、あるいは宗派そのものがわからない場合、できれば事前に調べておくのが賢明です。
調べられなかった場合は、前の人が行う焼香の仕方を真似すると良いでしょう。
葬儀前に葬儀社スタッフに焼香の仕方を確認するのも一つの方法です。
葬儀によっては開式前に葬儀社スタッフが、焼香の方法を解説する場合もあります。
しかし、最近では焼香の正しいやり方を知らない人も多く、それほど気にする必要はなくなりました。
最も大事なのは心を込めて故人の冥福を祈ることです。
大切なのは故人を悼む気持ち。告別式の意味を理解して故人を見送ろう
葬儀は宗教的儀式、告別式は社会的儀式、お通夜は葬儀・告別式の前日に行われる儀式です。
現在では葬儀と告別式は一体となって実施されています。
失礼にならないようにマナーを理解して告別式に臨む必要がありますが、最も大切なのは故人を悼む気持ちです。
後悔することのないように、告別式の意味や基本的なマナーを理解して故人を見送ると、より一層心に残るお葬式になるでしょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要