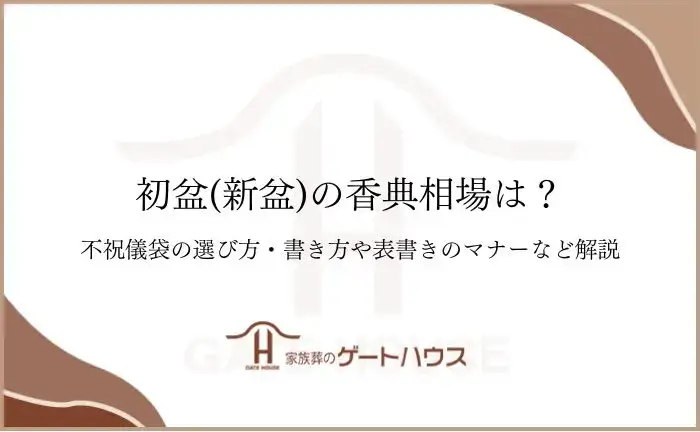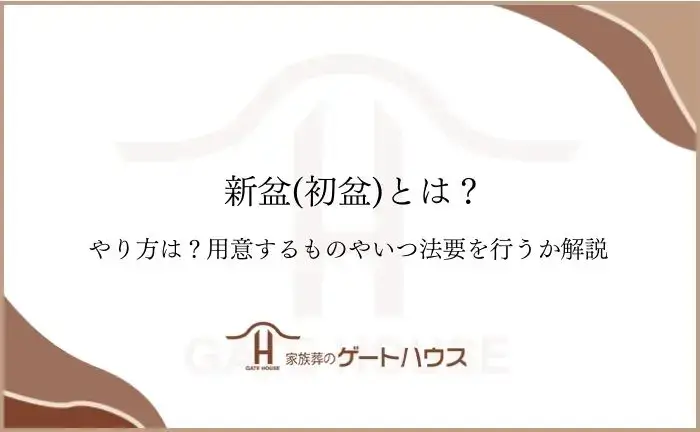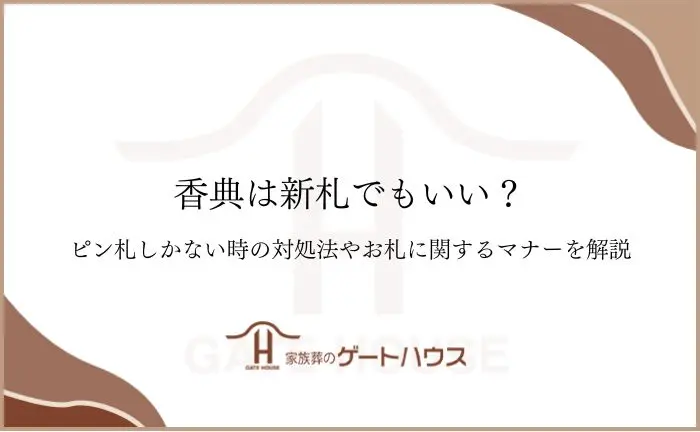お通夜とは何をするもの?意味や流れ・日程を解説
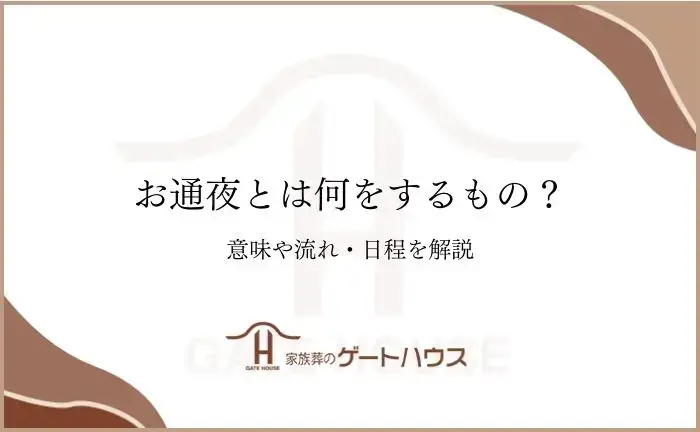
「お通夜」という儀式の名前は知っていても、いざ執り行ったり参加したりすれば一連の流れに戸惑う方も多いかもしれません。
今回の記事では、お通夜の意味や流れ・日程について詳しく解説します。
また、基本的なマナーや注意点・準備のポイントも押さえていきますので、ぜひ参考にしてみてください。
お通夜とは何をするもの?どんな意味がある?
お通夜は、故人との最後の夜を過ごし別れを惜しむ大切な時間です。
ここでは初めての方でも安心して参列できるよう、お通夜の意味や流れについて解説します。
お通夜の意味
お通夜は、故人と親しい人々が集まり最後の夜を共に過ごす大切な儀式です。
かつては夜通しで故人を見守り、祈りを捧げる「通夜」という言葉通りの形式が一般的でした。
しかし、現代では約1〜2時間程度で終わる「半通夜」が主流となっており、家族葬を選ぶ場合は行われないケースもあります。
この場は、故人との別れを惜しみながら共に過ごした日々を振り返る時間であり、遺族や参列者にとっても心の整理をする重要な機会です。
故人への感謝や思い出を語ることで、悲しみを共有し合い、支え合うことも通夜を開く意味となっています。
【関連記事】
家族葬にも通夜はある?流れや注意点・通夜なしの葬儀形式やマナーを解説
寝ずの番の過ごし方とは?寝てしまった場合の対処法や注意点も解説
お通夜をする時間帯
お通夜は通常、故人が亡くなった翌日の午後6時前後から始まることが多くなっています。
これは参列者が、仕事を終えてからでも駆けつけられるように配慮された時間帯でもあるのです。
所要時間は1〜2時間程度で、僧侶による読経や参列者による焼香が行われます。
その後に、遺族から感謝の意を込めて参列者に食事を振る舞う「通夜振る舞い」が実施される場合もあるでしょう。
宗教や地域ごとに差はありますが、一連の流れは以上のようになっています。
仮通夜・本通夜
「仮通夜」とは、故人が亡くなった当日に近親者のみで行う簡易な通夜のことで「本通夜」は翌日に正式に行う通夜を指します。
仮通夜は、遺族や近親者が故人と向き合い、心の整理をするための時間として位置付けられているものです。
一方、本通夜は僧侶の読経や焼香などを含む正式な儀式で、故人と関わりのあった多くの参列者が集まる場となります。
地域や宗派によって異なりますが、近年では仮通夜を省略し、死後翌日の通夜を本通夜として執り行うケースも少なくありません。
お通夜と葬式の違いは何?
お通夜は通常夜間に行われ、近親者や親しい友人が集まり故人との最後の時間を過ごす場です。
一方で葬儀は日中に執り行われる正式な宗教儀式で、故人の冥福を祈ることが主な目的となっています。
「お通夜は別れを惜しむ場であり、葬儀は宗教的な儀式を重視する場」といった点が大きな違いと言えるでしょう。
これらの役割の違いを理解して、適切な振る舞いやマナーを心がけることが大切です。
【関連記事】
通夜と葬式の違いは?葬儀・告別式との違いや流れ・マナーも紹介
告別式とは何をする?葬儀やお通夜との違い・マナー・流れを解説
お通夜と葬式の日程は?
お通夜と葬儀の日程には厳密な決まりはありませんが、故人が亡くなった翌日にお通夜、さらにその翌日に葬儀が行われるのが一般的です。
ただし、夜間に亡くなられた場合・火葬場の予約状況・親族の都合・風習などにより、日程が調整されることもあります。
そのため、具体的な日程は葬儀社や関係者と十分に相談し、地域の慣習を考慮しながら柔軟に決定することが重要です。
お通夜の流れは?
お通夜は、一般的な流れが決まっています。
宗派や地域の風習で異なる場合もありますが、ここでは基本的な通夜式の流れを見ていきましょう。
通夜の準備をする
お通夜の準備は、遺族と葬儀社が協力しながら進めます。
祭壇の設営・遺影や位牌の準備・供花や供物の手配などが主な内容で、他には参列者を迎えるための会場設営や、流れの確認も重要な作業となります。
心穏やかにお別れするためにも、故人が希望していたことや、遺族の意向にも配慮して準備を進めていくことが大切です。
受付の準備をする
受付は、参列者の出迎えとともに氏名や連絡先を正確に記録し、香典の管理を行う重要な役割です。
芳名帳や香典を受け取るための準備、受付係の配置、返礼品の用意などスムーズな進行のため、しっかりと準備しておきましょう。
また、人数が多かったり大きな会場で行ったりする場合は、参列者が迷わないように案内表示やスタッフの配置も整えると安心です。
遺族・親族・僧侶が入場する
式が始まると、まず遺族や親族、僧侶が入場して開式となります。
遺族や親族は祭壇に向かって右側の席に着席し、僧侶は左側に座るのが一般的です。
この際、喪主や遺族代表が参列者に挨拶を行うこともあります。
入場の順序や座席配置は、宗派や地域の習慣によって異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
また、会場全体の進行をスムーズにするため、葬儀社のスタッフが案内を担当する場合もあります。
読経・焼香を行う
僧侶による読経が始まり、参列者は静かに手を合わせ心を込めて祈りを捧げ、その後に喪主や遺族・参列者の順に焼香を行います。
焼香は、仏前に香を捧げることで故人への敬意を表す重要な儀式です。
焼香の作法は宗派によって異なるため、事前に確認し適切な方法で行いましょう。
また、焼香の順番は遺族か葬儀社が案内してくれる場合が多いため、参加する際は指示に従い落ち着いて行動してください。
通夜振る舞いをする
式が終わると、遺族は参列者に感謝の意を込めて食事を提供する「通夜振る舞い」を行います。
これは、故人を偲びながら参列者同士が語らい、さまざまな思い出を共有する時間です。
地域や宗派によっては、通夜振る舞いを省略する場合もありますが、一般的には軽食などの料理が提供されます。
通夜振る舞いは、遺族が弔問客に直接感謝を伝えられる貴重な機会でもあるため、できるだけ参加するのが望ましいです。
お通夜で守るべきマナーや服装は?
お通夜は、故人と遺族に哀悼の意を表す重要な場です。
参列する際には、適切なマナーや服装を心がけることを意識しましょう。
ここでは、一般的にお通夜でのマナーとされていることを解説します。
お悔やみの言葉に気を付ける
お悔やみの言葉は、遺族への思いやりが伝わるよう慎重に選ぶことが大切です。
言葉の使い方や適切な表現は、宗教や状況によって異なるため注意しましょう。
とくによく使われる「ご冥福をお祈りいたします」は、浄土真宗や神道では避けるべき表現です。
以下に、一般的に使われるお悔やみの言葉とその使い方をまとめましたので参考にしてください。
【一般的なお悔やみの言葉】
| 言葉 | シチュエーション |
| お悔やみ申し上げます | ・口頭と文章どちらでも使用可能 ・どんな状況でも使いやすい |
| ご冥福をお祈りいたします | ・文章でのみ使用可能 ・故人に向けた言葉 ・浄土真宗や神道、キリスト教では使えない |
| ご愁傷さまです | ・口頭でのみ使用可能 ・皮肉やからかいで使われるイメージがあるため使うときは表情や声色に注意 |
| 残念でなりません | ・口頭・文章どちらでも使用可能 ・他のお悔やみの言葉と合わせて使うと丁寧 |
| 哀悼の意を表します | ・文章でのみ使用可能 ・故人に向けた言葉 |
【関連記事】
お悔やみの言葉の例文集|友人・親戚へのメールやLINEのマナーとは?
お悔やみ申し上げます・ご冥福をお祈りしますはどっちを使う?メールでの例文も紹介
「謹んでお悔やみ申し上げます」の意味は?メールやLINEで伝える時の例文も紹介
忌み言葉や重ね言葉を避ける
お通夜の場では、不幸を連想させる「忌み言葉」や、不幸が重なることを連想させる「重ね言葉」はマナー違反とされています。
遺族の心情を考え、不適切な表現は避けるように気を付けてください。
また、宗教的に配慮が必要な場面もあります。
以下では避けるべき具体的な言葉を一覧にしているので、参考にしてください。
| 重ね言葉 | くれぐれも、重ね重ね 色々、段々、引き続き …など |
| 忌み言葉 | 苦しい、終わる 辛い、消える …など |
| 生死を連想する言葉 | 死ぬ、急死 生きていたころ …など |
焼香の作法を覚えておく
焼香は故人への敬意を示す大切な儀式で、正しい作法を知っておくことが重要です。
宗派によって回数や手順は異なりますが、焼香の一連の流れは、以下のとおりとなります。
葬儀場の案内に従うことを前提に、基本的な作法として参考にしてください。
【焼香の流れ】
- 数珠を左手に持ち、祭壇に行く
- 遺影→喪主・遺族→参列者全体の順に一礼する
- 故人に合掌する
- 右手で抹香をつまみ、頭を下げながら右手を額の高さに掲げてからくべる
※くべる回数は宗派によって異なります - 遺影→喪主→参列者全体の順に一礼する
※こちらは一例です。実際の焼香の流れは葬儀場のスタッフの案内に従ってください。
喪服を着て参列する
お通夜に参列する際の服装は、正式な喪服を着用することが一般的です。
男性は黒のスーツに白いシャツ、黒のネクタイと靴を、女性は黒のワンピースやスーツに控えめなアクセサリーを選びましょう。
子供の場合も、黒や紺の落ち着いた服装が望ましいです。
急で喪服がない場合は黒やダークグレーなどの平服でも構いませんが、派手な差し色やデザインは避け、全体的に控えめな装いを心がけましょう。
【関連記事】
葬儀で女性が着るべき服装とは?喪服の種類やお葬式の身だしなみマナーを解説
お通夜における香典のマナーは?
お通夜に参列する際、香典を持参するのが一般的です。
ただし、香典の表書きや金額、渡すタイミングには注意が必要になります。
宗教や地域の慣習を理解し、故人と遺族に敬意を示すためにも、次のようなマナーを心がけましょう。
お通夜か葬儀のどちらか一回のみ渡す
香典は、お通夜か葬儀のどちらか一方に参列する際に渡すのが一般的です。
両方に参列する場合でも一度渡せば十分とされており、家族に負担をかけないためにも再び香典を用意する必要はありません。
渡す際は、受付で「このたびはお悔やみ申し上げます」など一言添えながら丁寧に手渡しましょう。
受付で香典を受け付けていない場合は、遺族が落ち着いている時間を見計らい、失礼のないように渡してください。
表書きは宗派に合わせる
【香典の表書き(上書き)】
| 仏教全般 | ・四十九日前|御霊前 ・四十九日後|御仏前 |
| 浄土真宗 | ・御仏前 |
| 神道 | ・御霊前 ・御榊(おさかき)料 ・御玉串(おたまぐし)料 |
| キリスト教 (カトリック) |
・御ミサ料 ・御花料 ・献花料 |
| キリスト教 (プロテスタント) |
・忌慰(きい)料 ・御花料 ・献花料 |
| 宗教・宗派が不明な場合 | ・御香料 ・御香資(ごこうし) ・御香典(ごこうでん) |
参考:碑文谷創「葬儀概論 四訂」,葬祭ディレクター技能審査協会,2020年4月,171・172ページ
香典の表書きは宗教や宗派によって異なります。
たとえば、仏教では浄土真宗のみ「御霊前」を使わず「御仏前」とし、キリスト教では「御花料」「献花料」などが一般的です。
宗教や宗派が分からない場合は、「御香典」や「御香料」を選ぶといいでしょう。
表書きは黒の薄墨で、丁寧に書いてください。
相場に合った金額を包む
香典の金額は、故人との関係性や地域の習慣によって異なります。
近親者の場合は1万円〜5万円、友人や知人の場合は5千円〜1万円程度が一般的な目安です。
包む金額は偶数を避けるのが好ましいとされていますが、最近では許容される場合も多くなっているので奇数にするのが難しい場合は偶数でも問題ありません。
また、香典には古札を入れるのがマナーのため、新札しかない場合は軽く折り目をつけて使用しましょう。
相場に合った金額で香典を準備し、故人と遺族への思いやりを示すことが大切です。
【関連記事】
50代の香典の相場一覧!友人や親戚など関係性別に書き方とあわせて解説
60代の香典相場とは?友人・兄弟・いとこなどの関係性別の金額を解説
お通夜とは故人と最期の夜を過ごす儀式。現代では夜通しではない本通夜が主流
お通夜は故人を弔うとともに、最後のお別れをする大切な儀式です。
現在では夜通し行う形式は少なく、1~3時間程度で済ませる本通夜が主流となっていますが、形式に関わらず故人を偲び心を込めて過ごしましょう。
葬儀に関するお悩みがあれば「家族葬のゲートハウス」へ
家族葬のゲートハウスは、和歌山市の家族葬施行件数No.1の葬儀社です。
経験豊富なスタッフが、丁寧に対応いたしますので葬儀に関することはどんなことでもお任せください。

監修者
木村 聡太
・家族葬のゲートハウススタッフ
・一級葬祭ディレクター
「家族の絆を確かめ合えるような温かいお葬式」をモットーに、10年以上に渡って多くのご葬儀に携わっている。
![家族葬のゲートハウス [公式] 和歌山 大阪 兵庫のお葬式・ご葬儀](https://gate-house.jp/wordpress/wp-content/themes/toneya2021/assets/img/cmn/logo_001.svg)









 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ 3つの特徴
3つの特徴 供花のご注文
供花のご注文 会社概要
会社概要